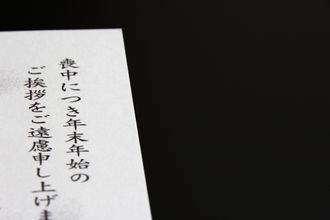 イベント・行事・お祝い事
イベント・行事・お祝い事 喪中の初詣のルール!神社はダメでもお寺ならOKって本当?
大切な家族がお亡くなりになって、次第に寂しさが募る毎日。そんな毎日ですが、月日が経つのは早いもので、気がつけばもう年末です。「来年の初詣は、やっぱり喪中なのでお参りすることはダメなんじゃないかな~?」と思われている人も多いんじゃないでしょう...
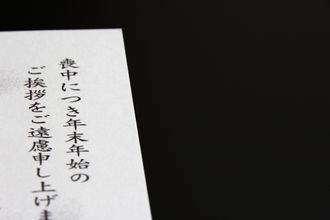 イベント・行事・お祝い事
イベント・行事・お祝い事  子育て
子育て