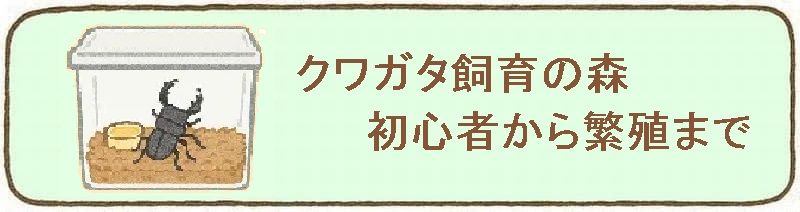クワガタがエサを食べてくれない。。。そんなとき、
心の中に「どうしよう」「まさか病気?」という不安が、じわじわ広がってきますよね。
わたしも、初めて飼ったノコギリクワガタが、ゼリーに見向きもしない姿を見て、胸がギュッとなった経験があります。
毎日観察しても、ゼリーの角がまったく減ってなくて、「このまま弱ってしまうんじゃないか…」と夜も気になってしまいました。
クワガタって、とっても強そうに見えるけど、意外とデリケートな生き物なんですよね。
エサを食べないのには、ちゃんと理由があることがほとんど。
むしろ、「気温がちょっと低いだけ」とか「夜にこっそり食べてるだけ」なんてこともよくあるんです。
この記事では、「エサを食べない」というサインをどう読みとるか、その原因と対策をわかりやすくお話ししていきます。
焦らず、あきらめず、大切なクワガタの気持ちにちょっとだけ寄りそってみませんか?
そのやさしさが、きっとクワガタに届くはずです。
クワガタがエサを食べないとき、まず確認すべきこと
そもそもエサの時間帯はいつ?
「朝にゼリーを置いたけど、夕方見ても減ってない」
「一口も食べてないみたい」
そんなふうに心配になる方、多いと思います。
わたしも同じでした。
でも実は、クワガタは夜行性の生き物です。
人間が眠っているあいだに、ひっそりと活動するのがふつうなんです。
つまり、昼間にエサを食べていなくても、まったく問題ないことも多いんですね。
うちの子も、昼はまったく動かないのに、朝になったらゼリーがぐちゃっとなっていて「あ、ちゃんと食べてたんだ」とほっとした経験があります。
クワガタの生活リズムは私たちとはまったく違うということを、まずは知っておくことが大切です。
昼間は食べないのが普通?夜行性の習性を理解しよう
クワガタは本能的に、敵に見つかりにくい夜に活動します。
とくに野生では昼間に動くと鳥や天敵に狙われるリスクがあるため、暗くなってから動き出す性質が身についているんです。
だから、昼間はずっと木のかげやマットの下でじっとしていて、「まったく動いてないけど大丈夫かな?」と思うくらい静かでも心配いりません。
エサも夜のあいだに食べ終えてしまうことが多く、朝まで残っていたとしても「なんとなくなめた」くらいでは見た目に変化がないこともあります。
人間のリズムで判断してしまうと、必要以上に心配になってしまうんですね。
そっと観察してる?食べてるけど気づかないケースも
これはわたしの失敗談なんですが、「全然食べてない!」と思い込んで違うゼリーに何度も変えたり、エサ皿をあちこち移動させたりしてしまったことがありました。
でも、よく見るとゼリーのふちがほんの少しだけ削れていたんです。
そう、食べてはいるけど気づきにくいだけというケースもあるんです。
クワガタはお皿の上で豪快に食べるわけではありません。
ちょっとずつなめたり、ほんの少しずつかじったりするため、ゼリーの減り方が目立たないこともよくあります。
また、食べたあとにマットの中に隠れてしまうことも多いため「まったく動いてないように見える=何もしていない」とは限らないんですね。
ときには夜中にそっとのぞいてみたり、ゼリーの表面に残ったかじった跡を見つけたり、そんな“ささやかな証拠”を見逃さないことも大切です。
クワガタがエサを食べない主な原因とその見分け方
【原因1】環境の温度・湿度が合っていない
クワガタは気温や湿度の変化にとても敏感です。
私たちがちょっと暑い、ちょっと寒いと感じるだけでも、クワガタにとっては「もう動きたくない」と思ってしまうほど不快な環境かもしれません。
とくに夏の暑すぎる室内や、冬場の冷え込みは要注意です。
クワガタが快適にすごせる温度はだいたい20~28度前後。
30度を超えるとバテてしまいやすくなり、15度を下回ると活動が鈍くなってエサを食べなくなります。
また、乾燥した環境も大敵です。
ケース内のマットがカラカラに乾いていると、湿度が足りずにクワガタが落ち着かなくなることもあります。
そんなときは霧吹きで軽く湿らせるだけでも、ぐっと動きがよくなることがあります。
【原因2】エサの種類や鮮度が合っていない
人間と同じように、クワガタにも食の好みがあります。
「このゼリー、まったく食べてくれない…」というときは、エサの種類や鮮度が合っていないだけという可能性も。
とくに安価な昆虫ゼリーは、香りが弱くて興味を持たれにくいことがあります。
また、一度開封して時間がたったものや、気温の高い部屋で数日置いてしまったゼリーは、風味が落ちて食いつきが悪くなることがあります。
個体によっては、果物の方がよく食べることもあります。
ただし、果物はすぐに腐ってしまうため、毎日こまめに取り替えないと逆に不衛生になってしまうので注意が必要です。
【原因3】成虫の寿命が近い、または弱っている
クワガタの寿命は、種類や育て方にもよりますが、だいたい半年から1年程度です。
エサを食べなくなった、動かない、反応が鈍いなどの様子が見られたときは、もしかすると寿命が近づいているのかもしれません。
わたしも、以前飼っていたミヤマクワガタが、ある日を境に急にゼリーに手をつけなくなり、静かにマットの下に潜ったまま数日をすごしました。
そのときは悲しかったですが、「よくがんばったね」とやさしく声をかけて、見守ることができたのが救いでした。
もちろん、ただの一時的な休息ということもあるので、あわてずに見きわめることが大切です。
【原因4】脱皮直後や冬眠・休眠前の一時的な状態
クワガタは羽化(うか)してすぐの時期や、寒さが近づく季節になると、活動が一時的に鈍くなることがあります。
これは体がまだ完全に整っていなかったり、冬眠や休眠の準備に入っていたりするためで、まったく珍しいことではありません。
とくに秋口になると、クワガタ自身が「もう冬だな」と感じて、自然に食事量が減っていくことがあります。
この時期は、あえて静かにすごさせてあげることで、体力を温存できるんです。
無理に起こしたり、刺激をあたえると逆効果になる場合もあるので、「いまはおやすみの時期かな」と受け止めてあげるのが大切です。
【原因5】ケンカやストレスで元気がない可能性も
複数のクワガタを同じケースに入れていると、テリトリー争いやケンカが原因でストレスがたまることがあります。
とくにオス同士や、気性の荒い種類の組み合わせでは、エサの取り合いや威嚇(いかく)でエサ場に近づけない個体も出てきます。
以前わたしが同居させていた2匹のクワガタも、片方はいつも元気でゼリーを占領していたのですが、もう片方は近づくことすらできずにマットの中にこもってしまっていました。
そういうときは別々のケースに分けるだけで劇的に改善することがあります。
クワガタも、静かで落ち着ける場所を求めているんですね。
クワガタにエサを食べさせるための対策ガイド
与える時間帯と置き場所を工夫しよう
クワガタがエサを食べてくれないとき、意外と見落とされがちなのが「置くタイミング」と「場所」です。
クワガタは夜行性なので、朝や昼にエサを出しても、食事の時間ではなかった…ということも多いんです。
いちばんおすすめなのは、日が沈む頃にゼリーをセットすることです。
部屋の明かりを落として静かな環境を作ってあげると、クワガタが安心して動き出しやすくなります。
また、エサの置き場所も重要です。
ケースのすみや、通気口の近くなど、風が直接あたる位置は避けてあげてください。
できればマットの上にエサ皿をしっかり固定して、動かないようにしておくと安心です。
ひんやりしすぎる場所や、明るすぎる位置も苦手なので、「暗くて落ち着けるエリア」に置くのがコツです。
昆虫ゼリーと果物の選び方と注意点
「どのエサが正解なの?」と迷う方も多いと思いますが、クワガタの好みは個体によっても違います。
基本的には市販の昆虫ゼリーがおすすめですが、ゼリーにもグレードがあります。
わたしが失敗したのは、安さ重視で買ったゼリーを与え続けていたときでした。
全然食べてくれなくて、「もしかして嫌いなのかも…」と、試しに高たんぱくタイプに変えたら、それまでの静けさがウソのようにガツガツ食べ始めたんです。
ゼリーはなるべくにおいが強く、成分がしっかりしたものを選ぶのがコツです。
「プロ仕様」
「熟成樹液風」
と書かれているものは食いつきが良い傾向があります。
果物を使うときは、必ず毎日取り替えるようにしましょう。
バナナやリンゴは人気ですが、すぐに腐ったり虫がわいたりするため、取り扱いには注意が必要です。
他の個体と分けて飼育するのもひとつの手
クワガタをペアやグループで飼っている場合、エサを食べないのは「争いを避けている」だけかもしれません。
特にオス同士は、力関係がはっきりしていて、気の強い個体に遠慮してエサに近づけなくなることがあります。
以前わたしが飼っていたノコギリクワガタは、同居していたもう一匹に毎晩おされぎみで、ゼリーを一切口にしていませんでした。
そこでケースを分けてみたところ、次の日からぺろりとゼリーを完食してくれたんです。
ほんの小さなきっかけでストレスがたまり、食欲が落ちることはよくあります。
個別飼育は、トラブルを減らすいちばんシンプルで効果的な方法なので、もし同居させているなら、いちど試してみてください。
強制給餌はしてもいいの?注意すべき点
「どうしても食べてくれない…。もうこのままじゃ心配で仕方ない」
そんなとき、最後の手段として考えるのが強制給餌です。
これは、ゼリーをほんの少しだけ綿棒やスプーンの先にとって、クワガタの口元にそっとあてる方法です。
うまくいけば、自分からペロッとなめてくれることもあります。
ただし、これは本当に「最終手段」だと思っておいてください。
クワガタは非常にデリケートな生き物です。
口のまわりを強く押したり、無理に口をこじ開けたりすると、かえって体力を消耗させたり、けがをさせてしまうおそれもあります。
「食べないからって、あせらないで大丈夫だよ」そんな気持ちで見守ることが、いちばんの栄養になると私は思います。
それでも食べないときはどうする?プロの判断ポイント
弱っている個体の見分け方と自然な見送り方
一通りの対策を試しても、どうしてもエサを食べないとき。
「これはもうダメなのかな…」と、心がざわつく瞬間がありますよね。
わたしも何度も経験があります。
まず確認してほしいのは、足に力があるかどうかです。
ケースのふちや木にしっかりつかまれていれば、まだ元気が残っている証拠です。
ですが、手足がだらんと力なく伸びていたり、ひっくり返っても起き上がれなかったりする場合は、体力が限界に近いかもしれません。
そんなときは、「なんとかして助けなきゃ」とがんばりすぎずに、そっと見守ることも大切です。
生き物を飼うって、楽しいことばかりじゃなくて、こうしたお別れの瞬間もふくまれています。
以前、うちのクワガタがマットの下にもぐったまま出てこなくなったことがありました。
数日後にそっと確認すると、静かに、まるで眠るように息を引き取っていました。
悲しかったけど、「この場所で、安心して過ごしてくれていたんだな」と思うと、不思議とあたたかい気持ちになれたのを覚えています。
動物病院に連れていくべき?判断基準とは
「どうしても原因がわからない」「なんとか回復させたい」そう思ったときに浮かぶのが「病院につれていくべきかどうか」ですよね。
ただ、昆虫を専門に診てくれる動物病院というのは、正直とても少ないです。
ふつうの犬猫クリニックでは対応してもらえないことがほとんどで、「診察対象外です」と断られることもあります。
そこでおすすめしたいのが、爬虫類や昆虫を扱っている専門のペットショップへの相談です。
販売経験のあるスタッフさんは、クワガタの状態を見て
「これは寿命ですね」
「このゼリーが合ってないかもしれませんよ」
といったアドバイスをくれることもあります。
もちろん、すべてのショップで対応してもらえるわけではありませんが、「どうしても不安なときの相談先」として覚えておいて損はありません。
無理に食べさせようとしないことも大切
これは、わたし自身に言い聞かせていた言葉でもあります。
「食べてくれないのは、わたしの育て方が悪いのかもしれない」
「もっと何かできたんじゃないか」
そんなふうに自分を責めてしまうことって、ありますよね。
でも、クワガタはとても静かで、繊細で、マイペースな生き物です。
人間のように「食べないと死んじゃうから無理にでも口にしよう」とは思いません。
だからこそ、こちらもあわてず、追い詰めず、そっと寄り添ってあげることが大切なんだと思います。
わたしが最後にたどりついた答えは、「いま、この子が静かに過ごせているかどうか」それを大事にすることでした。
エサを食べない理由がどうであれ、大切なのはその子らしい時間を、安心して過ごせるように整えてあげること。
それが、飼い主としてできる最高のケアなのかもしれません。
まとめ|エサを食べないときも慌てず、原因をひとつずつチェックしよう
クワガタがエサを食べてくれないとき、最初に感じるのはきっと「不安」だと思います。
「おなかがすいているはずなのに」
「ゼリーに近づこうともしない」
「もしかして弱ってる?」
そんな思いが頭の中をぐるぐるめぐって、つい焦った行動をしてしまいがちです。
でも実際には、クワガタがエサを食べない理由には、夜行性という習性や、温度・湿度・エサの好みといった、ちょっとした環境のズレが原因になっていることもたくさんあります。
中には、ストレスや同居している個体との相性、あるいは寿命や休眠のサインといった、生き物として自然なタイミングによる場合もあります。
私たちにできるのは、クワガタの様子をよく観察し、小さな変化を見逃さず、そっと寄り添ってあげることです。
食べないからといって無理に手を出すよりも、
「いま、この子はどんな気持ちかな?」
「安心して過ごせているかな?」
と想像してみることが、いちばんの思いやりになるのではないでしょうか。
あなたのそのやさしい気持ちが、きっとクワガタにも伝わっています。
焦らず、見守りながら、一歩ずつ一緒に歩んでいきましょう。