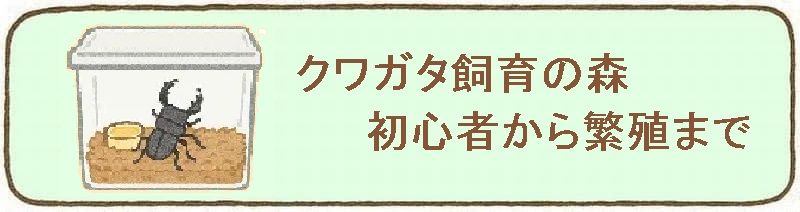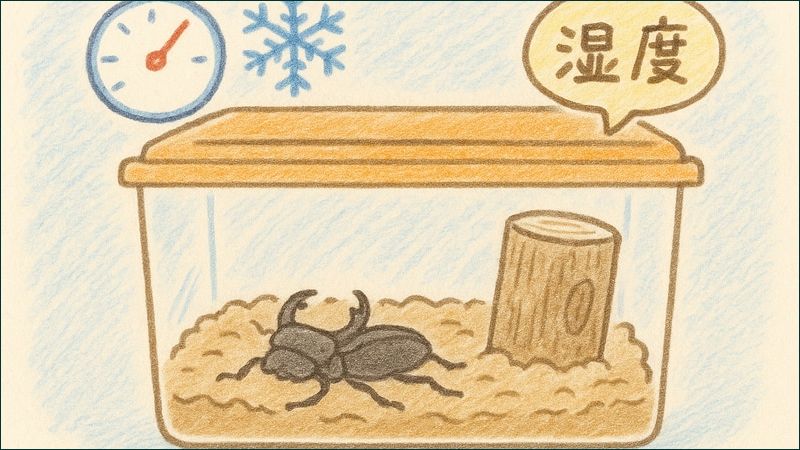
寒くなってくると、わたしたち人間(にんげん)だけでなく、小さなクワガタたちにも“冬支度(ふゆじたく)”が必要になります。
「冬のあいだ、どうやって過ごすの?」「そのままにしておいていいの?」
クワガタを飼(か)い始めたばかりのころの私は、そんな不安でいっぱいでした。
とくに初めての冬は、夜な夜なケースをのぞいては「大丈夫かな…」と心配になってしまって。
温度計を見てはうろうろ、マットを軽くさわってはビクビク。
まるで子どもの初めてのおつかいを見守る親のようでした。
でも…
ちゃんと準備して、ちょっとしたポイントに気をつければ、クワガタはちゃんと静かに、たくましく冬を乗りこえてくれます。
この記事では、そんな「冬がこわい初心者さん」のために、温度(おんど)や湿度(しつど)、マットの選び方や注意点まで、やさしくくわしくお伝えしていきます。
春にまた「元気な姿(すがた)」に会えるように。
あなたとクワガタの冬が、あたたかく、やさしいものになりますように――。
クワガタの越冬って本当に必要なの?
クワガタを飼(か)い始めて最初にびっくりするのが、「冬のあいだって、どうすればいいの?」という素朴(そぼく)な疑問じゃないでしょうか。
夏の間は元気に動きまわっていたのに、秋が深まってくると、だんだん動きがにぶくなって、エサも減って…。
最初の冬をむかえるとき、私は正直あわてました。
「このまま放っておいていいの?」「冬眠(とうみん)させた方がいいの?」
ネットで調べれば調べるほど情報はバラバラで、よけいに混乱してしまって…。
でも、実際に何匹ものクワガタと冬を越してきて感じたのは、
**「越冬が必要かどうかは、種類(しゅるい)や寿命(じゅみょう)、その子の状態によって違う」**ということでした。
しっかり知っておくと、その子にとってベストな冬の過ごし方が見えてきます。
冬眠する種類としない種類の見分け方
クワガタとひとことで言っても、じつはいろんな種類がいます。
その中でも「冬眠をするタイプ」と「寿命が夏で終わるタイプ」がいることを、まずは知っておいてください。
たとえば…
ノコギリクワガタやミヤマクワガタは、成虫になってからの寿命が短く、たいていは冬まで生きのこることはありません。
夏の間にじゅうぶん活動して、秋には命をまっとうする子たちです。
一方で、オオクワガタやコクワガタは、冬の寒さをじっと耐(た)え、春にまた活動を再開する「越冬型(えっとうがた)」の種類。
何年も生きることがあるので、しっかりと冬越しの準備が必要です。
この見分けができるだけでも、冬の対応はガラッと変わってきます。
もし「種類がよくわからない…」というときは、購入(こうにゅう)したショップに確認したり、体の特徴から調べてみるのもおすすめですよ。
越冬に入るタイミングと前兆とは?
越冬のサインは、とてもわかりやすくあらわれます。
まず、クワガタの動きがにぶくなります。
私のコクワくんも、ある日突然、登り木に登らなくなって、マットのすみにじーっとたたずむようになりました。
次に、エサへの反応が鈍(にぶ)くなります。
大好物だった昆虫ゼリーを入れても、まったく口をつけない日がつづくようになったら、そろそろ「眠りたい」合図。
そしてなにより、マットの中にもぐりはじめたら、いよいよ越冬モードです。
私はこのタイミングで、声には出さずそっとつぶやきます。
「おやすみ、また春にね」って。
大切なのは、無理に引っぱり出したり、心配だからとマットをめくったりしないこと。
クワガタのリズムを信じて、やさしく見守ってあげてくださいね。
クワガタが冬を越すための温度と湿度管理
クワガタの越冬をうまく成功させるためには、
- 温度(おんど)
- 湿度(しつど)
これ、私も最初はぜんぜん分かってなくて…。
なんとなく寒そうだからと、こたつの近くにケースを置いたことがあったんです。
すると数日後、なんとケースの中がびっしょり。
マットがカビだらけになってしまって…。
クワガタって、想像以上に「静かな環境」と「一定の温度・湿度」を好むんです。
冬は人間(にんげん)にとっても乾燥が気になる季節。
でもクワガタにとっては「湿気(しっけ)がこもる」のも問題。
ここでは、私のちょっとした失敗や試行錯誤(しこうさくご)もまじえながら、クワガタが快適に眠れる越冬環境づくりについてお話していきます。
最適な温度は何度?加温は必要?
まず気になるのが、クワガタにとってベストな「越冬中の温度」。
目安としては、10℃前後が理想とされています。
人間が「ちょっと肌寒いな」と感じるくらいの気温ですね。
私の家では、北向きの廊下の収納スペースがちょうどそのくらい。
ただ、寒波が来ると一気に5℃を下回ることもあるので、発泡(はっぽう)スチロールの箱にケースごと入れるようにしています。
加温ヒーターを使う人もいますが、私はあまりおすすめしません。
ヒーターを使うと、どうしても温度の上下が激(はげ)しくなってしまうんです。
それよりも「安定した温度」を意識した方が、クワガタにとっては安心です。
湿度が高すぎるとどうなる?カビやダニの注意点
次に大切なのが「湿度(しつど)」です。
冬は乾燥しがち…と思いきや、ケースの中って、意外と湿気がたまりやすいんです。
とくにふたがぴったり閉まっていると、内部の水分がこもってカビやダニの原因に。
うちでは、ケースのふたに小さな空気穴(くうきあな)を開けて、換気できるようにしています。
それでも湿度が高いときは、ふたのすき間にティッシュをはさんで少しだけ通気(つうき)を良くすることも。
ちなみに一度、マットの上に白いふわふわのカビが出たときは、私、本気で泣きました…。
クワガタが眠っているあいだも、空気がよどまないように、でも乾燥しすぎないように。
このバランスが、越冬のカギです。
室内飼育と屋外飼育、どっちがいい?
「外に出しておけば自然に冬眠してくれるでしょ?」と、昔の私は思っていました。
でも、屋外は意外と危険がいっぱいです。
たとえばベランダや物置は、夜になると温度が一気に氷点下(ひょうてんか)近くまで下がることがあります。
そんな極端な寒さは、クワガタにとっては命取り。
私は一度、屋外で越冬させようとして、春に目覚めなかった子がいました…。
あれは本当に悲しかった…。
だから今は、室内で温度が安定していて、かつ静かな場所を選んでいます。
たとえば、北側の押し入れ、廊下のすみ、靴箱の下段など。
暖房の風が直接あたらず、昼と夜の気温差も少ない場所
クワガタにとっては、そんな「ひっそり落ちつける冬の寝床(ねどこ)」がぴったりなんです。
越冬マットの選び方と設置のコツ
「冬用のマットって、何でもいいのかな?」
「どれくらいの量を入れればいいの?」
越冬の準備をしようとしたときに、私がいちばん迷ったのがこの“マット問題”でした。
お店に行けばたくさん種類があるし、「発酵(はっこう)マット」だの「針葉樹(しんようじゅ)マット」だの…もう混乱!
でも試行錯誤(しこうさくご)して分かったのは、
クワガタにとってマットは、冬のふとんみたいなものなんですよね。
どんなふとんを使うか、どんなふうに敷(し)くかで、眠りの質(しつ)も安心感も変わってきます。
ここでは、私が実際に使ってよかったマットや設置の工夫を、ぜんぶお伝えしますね。
おすすめのマットの種類と特徴
「どのマットを選べばいいの?」
この疑問には、今の私なら迷わずこう答えます。
「微粒子タイプの発酵マット」がおすすめ!
理由は3つ。
まず、粒子が細かくてふんわりしているので、クワガタがもぐりやすい。
次に、ほどよい水分が保たれているため、湿度調整がしやすい。
そして最後に、発酵済みのものはカビや雑菌(ざっきん)が発生しにくいという安心感があります。
私が以前、未発酵の安いマットを使ったときは、1週間ほどで白カビが発生してしまって…。
あのときは本当にショックでした。
以来、「発酵済み・無添加・クワガタ用」と明記されているマットを選ぶようにしています。
マットの厚みと詰め方の目安
さて、マットの「量」もとっても大切です。
目安は10cm前後。
けっこうたっぷり使うんですよね。
私も最初は「こんなに入れるの?」と思いましたが、クワガタがもぐるスペースを確保するためには、最低でもケースの1/3~半分くらいは必要です。
詰(つ)め方にもコツがあって、ふんわりと、でも空気が通るように軽く押さえるのが理想。
あまりギュッと押し込んでしまうと、空気の通り道がなくなってしまって、
冬のあいだに酸欠(さんけつ)になってしまうおそれもあります。
私の場合は、手のひらでトントンと数回、表面をならすようにして整えています。
あとは、クワガタが自分の落ち着ける場所を見つけてくれるのを待つだけです。
ケースの選び方と通気性の工夫
最後に、マットを入れる「ケース」の選び方についても触れておきますね。
基本はふた付きの昆虫ケースでOKです。
ただし、完全密閉タイプはNG! これはほんとに要注意。
湿度がこもってしまうと、カビや結露(けつろ)が出やすくなります。
私は過去に、密閉したケースで越冬させたとき、内側に水滴がビッシリついてしまったことがありました。
案の定(あんのじょう)、マットにはカビが…泣きました…。
いまは通気穴つきのケース+紙やティッシュで通気量を調節するやり方に落ち着いています。
あと、ケースの底にスノコ状の板や厚紙を敷(し)くと、通気もよくなって湿気対策にもなりますよ。
越冬中は目立った変化がないぶん、「静かな管理」が求められます。
だからこそ、最初のマットとケースの選びがとても大事なんです。
越冬中の注意点とNG行動
クワガタが静かに眠りについたら、「これでもう安心!」…と油断したくなりますよね。
でも実は、越冬中こそ“そっと見守る力”が試される時期でもあります。
私も最初の冬は、気になりすぎて毎日のようにマットをのぞき込んだり、そーっとケースを持ち上げたりしていました。
そのたびに「ごめんね…」ってつぶやきながら後悔してたんですよね。
越冬中のクワガタは、まるで“薄い膜(まく)の中にいる小さな命”。
ちょっとした環境の変化や人の手のぬくもりさえ、ストレスになることもあるんです。
このセクションでは、そんな繊細(せんさい)な冬眠期に「やってしまいがちなNG行動」と「そっとしておくべき理由」、そして「本当に必要なケア」についてお伝えします。
途中で動き出してしまったらどうする?
冬のある日、ふとケースの中をのぞいたら
あれ?マットの上にクワガタがいる!?動いてる!?
…そんな経験、私も一度だけありました。
あれは2月下旬の暖かい日で、リビングの暖房(だんぼう)がケースに直接当たっていたせいでした。
クワガタはとっても敏感(びんかん)です。
ちょっとした温度の変化で「春が来た」と勘違いして、越冬から目覚めてしまうことがあります。
そんなときは、あわてず騒がずが大切です。
すぐにケースを静かな場所に移し、暖房のない少しひんやりした空間に戻してあげましょう。
そして、ゼリーなどのエサはこの時点では与えないこと。
半覚醒(はんかくせい)の状態で食べ物が入ってくると、消化できずに体調をくずしてしまう可能性があるんです。
また眠りにつけるように、暗く静かな環境を整えてあげてくださいね。
乾燥・結露・カビの予防方法
クワガタの冬眠を見守るうえで、実は「最大の敵(てき)」は温度よりも湿気かもしれません。
うちでは以前、ケースのふたを完全に閉めたまま放置していたら、数日後に内側に水滴が…。
マットもじっとり重くなっていて、鼻を近づけると、ちょっとイヤなにおいが…。
これは、湿度が高すぎて“結露(けつろ)”が発生していたサイン。
そのままにしておくと、マットにカビが生えたり、ダニが繁殖してしまうこともあります。
対策としては、
- ケースのふたに小さな空気穴をつくる
- ふたのすき間にティッシュを軽くはさむ
- ケースの下にすのこや新聞紙を敷いて通気性をよくする
特に気温差が大きい日や、日が差しこむ場所に置いている場合は、
ケースの内側の水滴(すいてき)チェックを忘れずに。
冬の間、目立った動きがないぶん、環境トラブルには本当に気をつけたいところです。
越冬中でも点検は必要?様子の確認方法
「越冬中って、本当に放っておいて大丈夫なの?」
これ、私もずっと悩んでいました。
結論から言うと――基本的にはそっとしておくが正解です。
でも、やっぱり気になりますよね。
生きてるかな?大丈夫かな?って。
そんなときは、ケースの表面をそーっと観察するだけでOKです。
私は月に一度くらい、マットの表面やケースのにおい、湿り具合をチェックしています。
でも絶対に、マットをめくったり、クワガタを直接見ようとしたりはしません。
冬のクワガタは、まるでおふとんにくるまっている赤ちゃんのよう。
「そっと見守る勇気」こそが、いちばんの優しさなんだなぁと今では思います。
越冬から春の目覚めまでの流れ
長い冬を越えて、ついに春――。
この季節が来ると、私は毎年、ほんの少しドキドキしながらクワガタのケースをのぞきこみます。
「元気に目覚めてくれるかな?」
「ちゃんと冬を乗りこえられたかな?」って。
クワガタが越冬から目覚めるタイミングは、まるで春の息吹(いぶき)を感じるような、あたたかな出来事です。
でも実はこの時期、クワガタにとっても、飼い主にとっても“意外と難しい”ステージだったりするんです。
一気に活動モードに戻すのではなく、ゆっくり、やさしく、目覚めをサポートすることが大切なんですよね。
ではここから、春の訪れとともに始まる「越冬明けの過ごし方」を一緒に見ていきましょう。
冬眠明けのサインと対応の仕方
春が近づくと、日差しがやわらかくなって、室内の温度も少しずつ上がってきます。
すると、越冬していたクワガタが、ゆっくりと動き出します。
マットの中から、ちょこんと頭をのぞかせたり、ケースのすみに姿を見せたり…。
私のオオクワくんも、3月上旬にふと姿を見せてくれたとき、ほんとうに涙が出そうになりました。
「あぁ、生きていてくれた…また会えた」って。
冬眠明けのサインには、
- マットの表面に出てくる
- ゆっくりと歩きまわる
- マットの中でもぞもぞと動く音がする
このとき、急に照明をあてたり、大きな音を立てたりするのはNG。
起きたばかりのクワガタにとっては、刺激が強すぎるんです。
そっと見守りながら、「おかえり」と心の中で声をかけてあげましょう。
目覚めたあとのエサや温度の管理
越冬から目覚めたクワガタは、すぐにエサを食べるとは限りません。
特に、まだ体力が戻っていない子は、しばらくマットの上でじっとしていることも。
私はゼリーをそっと置いて、「食べてもいいよ」と思いながら見守っています。
最初のひとくちは、ほんとうに感動的です。
小さな命がまた動き出した実感(じっかん)に、胸が熱くなります。
温度も大事なポイント。
急にあたたかい場所に移すのではなく、15℃→18℃→20℃…と、数日~1週間くらいかけて段階的に上げていくのが理想的。
温度計をこまめにチェックしながら、「春のはじまり」をゆっくり一緒に感じていきましょう。
弱っているときのケア方法
中には、冬眠から目覚めても、すぐに元気になれない子もいます。
私も経験があるんですが。。。
4月になってもマットの中でじっとしていて、「もうダメかも…」と心配していたクワガタが、5月に入ってから少しずつ動き出したんです。
こういうときは、
- ゼリーを複数置いてみる(置く位置を変えてみる)
- 湿度が下がりすぎていないかチェック
- 強い光や騒音から遠ざける
心配になる気持ちはすごく分かります。
でも、「大丈夫、ゆっくりでいいよ」っていう気持ちで見守ってあげることが、いちばんのエネルギーになります。
そしてもしも、春になっても動かない、反応がないときは、静かにやさしく見送ってあげてください。
命はいつか終わるものだけれど、その冬を一緒に過ごした時間は、たしかに心に残っている。
そう思うことで、私はクワガタとの別れを何度も乗りこえてきました。
まとめ
クワガタの越冬(えっとう)は、一見(いっけん)むずかしく見えるかもしれません。
でも…
大切なのは、高価な道具や完ぺきな準備ではなく、「ちゃんと生きてほしい」と願う気持ちなんですよね。
私自身、最初の冬は分からないことだらけで、不安や後悔(こうかい)もたくさんありました。
でも経験を重ねるうちに、クワガタが静かに眠り、ゆっくり春を迎える姿に、なんとも言えない“いとおしさ”を感じるようになりました。
越冬のポイントは、温度(おんど)・湿度(しつど)・マットの環境をととのえて、静かに見守ること。
途中で心配になっても、ぐっとこらえてそっとしておく勇気が、命をつなぐ支えになります。
春になって、マットの中からひょっこり顔を出してくれたとき。
その瞬間のよろこびは、きっとあなたの心に残る宝物になります。
どうかこの冬、あなたのクワガタも安心して眠り、また元気な姿で春を迎えられますように。
そしてこの記事が、その小さな命を守るお手伝いになれたなら、まいつきんとしてこれ以上うれしいことはありません