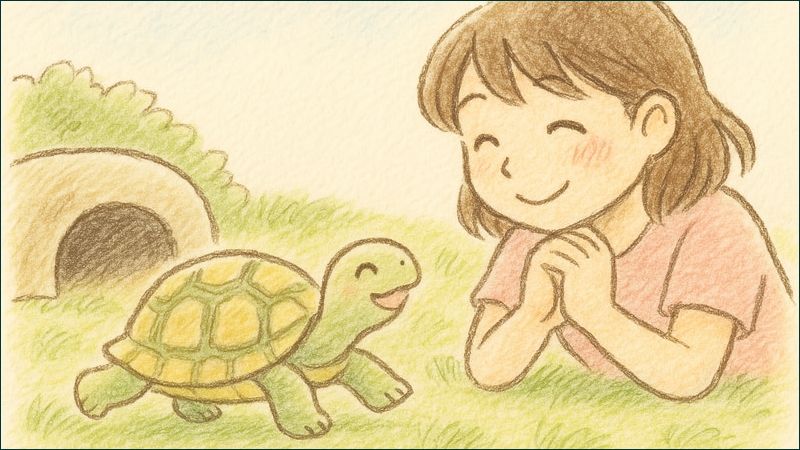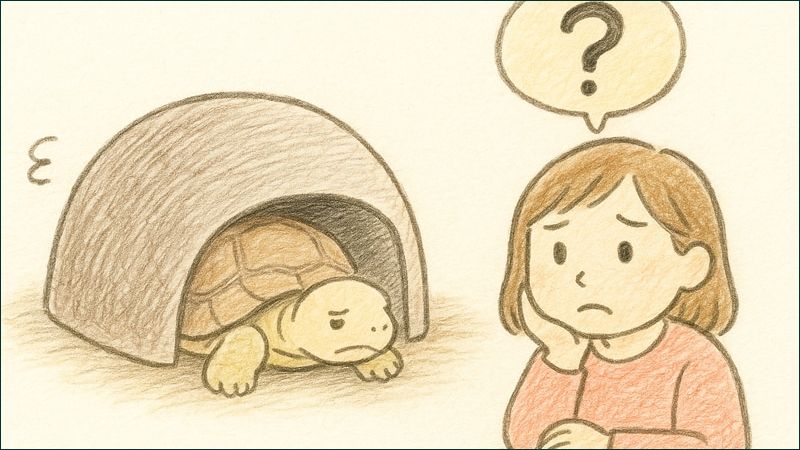
リクガメをじっと見ていたら、「あれ?今日もずっとシェルターにこもったままだな…」なんてこと、ありませんか?
せっかくかわいがろうと思って覗いてみても、甲羅の端っこしか見えず、名前を呼んでも出てこない。
ごはんの時間になってもまるで動く気配なし。
なんだか寂しいし、心配にもなってしまいますよね。
「昨日までは元気に歩いてたのに…」
「お気に入りのごはんも残してる…」
「もしかして、病気?それとも何か嫌なことがあった?」
そんなふうに、飼い主としてはどんどん考えが深みにハマっていきます。
わたしも最初はそうでした。
何をどうしていいかもわからず、ただひたすら「出てきてくれないかなぁ」と、ケージの前で何時間も待っていたことがあります。
でも、リクガメがシェルターにこもるのには、ちゃんと理由があるんです。
その理由を知らずに「出ておいで~」なんて無理に引っ張り出そうとすると、かえってリクガメにストレスを与えてしまうことも…。
この記事では、リクガメがシェルターにこもって出てこない理由と、そのときに見直したい飼育環境や、シェルターの正しい設置方法。
そんな、わたし自身が実践して効果のあった工夫について、わかりやすく丁寧にお話ししていきます。
ちょっとした変化に気づけること。
それが、リクガメと心を通わせていく第一歩になるはずです。
この記事が、あなたとリクガメの距離を少しでも縮めるきっかけになれば嬉しいです。
リクガメがシェルターから出てこない主な原因とは?
温度や湿度など飼育環境に問題がある
まず一番にチェックしたいのが「室温」と「湿度」。
この2つはリクガメの健康に直結する非常に大切な要素です。
特にリクガメは変温動物であるため、気温や湿度の変化にとても敏感。
室温が下がると体温も一緒に下がってしまい、動きが鈍くなるどころか、食欲や代謝にも大きく影響を及ぼします。
気温が下がりすぎれば、まるでスイッチが切れたかのようにじっと動かなくなりますし、ジメジメしすぎる環境では皮膚病のリスクも高まります。
特に冬場や梅雨の時期は注意が必要で、ケージ内の温度が想像以上に下がっていたり、湿度が高くなりすぎていたりするケースも少なくありません。
わたしの家でも、朝方の室温が18度を切っていたとき、リクガメがまったく動かず心配になりました。
そこで温度計と湿度計を導入してみたところ、夜間の冷え込みがかなり厳しかったことが判明し、ヒーターの設置と床材の見直しを行いました。
結果として、数日後にはリクガメがゆっくりとシェルターから出てきて、日光浴をするようになったんです。
これだけでも、温度と湿度がいかに重要かがよくわかります。
加湿器や保温球を使うだけでなく、ケージ内に直接測定器を設置し、常に環境を見える化しておくことが大切です。
シェルターの形状や設置場所が不適切
次に見直したいのが、シェルターの形と置き場所です。
一見、「シェルターがある=安心できる場所」と思いがちですが、実はその中身や位置が適切でないと、逆にストレスの原因になってしまうんです。
たとえば出入り口が狭すぎて、リクガメが体を回転できないほどだったり、中が真っ暗で常に陰鬱な雰囲気になっていたり。
こういったシェルターだと、リクガメは入りづらさを感じながらも「ここにいるしかない」と思ってこもってしまうことも。
また、設置場所も重要です。
ケージの最も寒い隅や、空気がよどむような角に置いてしまうと、リクガメはそこから出る気になれません。
「出た先が寒い」「出ても落ち着かない」と感じていると、シェルターにこもりっぱなしになるのも当然です。
わたしも以前、観葉植物の陰で日光が入りにくい場所にシェルターを設置していたのですが、そのときは全然出てきてくれませんでした。
思いきって陽当たりのよい場所に移動し、中に干し草を足してあげたら、次の日から少しずつ顔を出してくれるように。
この経験から、シェルターはただの“箱”ではなく、“暮らしの中心”だと痛感しました。
リクガメが「また戻りたいな」と思えるような快適な空間づくりが、実は一番の引きこもり防止策になるんですよ。
警戒心やストレスによるもの
リクガメもとても繊細で、感受性の強い生きものです。
私たちが「このくらい平気でしょ」と思うような環境音や気配も、彼らにとっては大きなストレスになることがあります。
人の気配が常にそばにあったり、テレビの音が大きく流れていたり、日々の生活音が予想以上に響いていたりすると、リクガメは「今は外に出ないほうが安全」と感じてしまいます。
また、急に何かが動いたり、家族がバタバタと通ったりするだけでも、リクガメには大きな刺激。
ましてや犬や猫が近づいてきたら、それはもう“天敵が来た”くらいの警戒モードに突入することも。
うちの子も、掃除機をかけた直後にはほぼ100%シェルターに引きこもります。
掃除が終わって静かになってもしばらくは顔すら出さず、そ~っと様子を伺っている様子。
人間からすると「もう音しないよ、大丈夫だよ~」なんて思ってしまうのですが、リクガメにとっては「本当にもう安全なのか?」と慎重に判断しているんですね。
ある日、家具の配置を少し変えただけで、急に行動パターンが変わってしまったこともありました。
それまでは朝日が当たる場所まで出てきていたのに、その日を境にシェルターの奥に引きこもってしまって…。
結局その原因は、家具の影になって陽が入らなくなったからでした。
このように、ちょっとした環境の変化が、リクガメにとっては大きな出来事であることを忘れてはいけません。
彼らのペースや感覚を尊重して、なるべく静かで安心できる空間を保ってあげること。
それが、リクガメが「外に出ても大丈夫」と思える第一歩になります。
体調不良や病気のサインである可能性も
何日も連続して出てこない、ごはんも食べない、水も飲まない…。
そんなときは、単に怖がっているだけではなく、身体に何か異変が起きている可能性も考えるべきです。
特に注目したいのは排泄の様子や動きの鈍さ。
便が出ていない、逆に下痢が続いている、うんちが極端に臭うなどのサインがあれば、消化器系のトラブルが疑われます。
また、目に力がなかったり、目ヤニやくもりが出ている場合は目の病気や感染症の兆候かもしれません。
わたし自身、リクガメが食欲をなくして数日間こもっていたとき、「冬眠の準備なのかな?」と勝手に思って様子を見ていたことがあります。
でも、ある日ふと胸のあたりの呼吸が速いことに気づき、不安になって病院へ連れて行ったところ、軽度の肺炎との診断。
早期発見だったため大事には至りませんでしたが、「もっと早く気づいていれば」と自分を責めたのを覚えています。
さらに怖いのは、見た目にはまったく変わりないけれど、内臓疾患や寄生虫による不調が進行しているケース。
これらは見逃しやすく、気づいたときにはかなり悪化していた…なんてことも。
だからこそ、「いつもと違うな」という小さな違和感を見過ごさないことがとても大事。
食べ方、歩き方、息の仕方、目つき…。
ほんの少しでも「なんかおかしいかも」と思ったら、その直感を信じて、一度環境を見直し、それでも改善しないなら病院へ。
リクガメは自分から「つらい」とは言えませんから、気づいてあげられるのは飼い主だけなのです。
シェルターは必要?それとも無くした方がいい?
シェルターは「安心できる居場所」として大切な存在
「じゃあ、シェルターをなくせばいいの?」と思ってしまいそうですが、実は逆。
シェルターはリクガメにとって、ストレスを避けるための大切な避難場所です。
まるで私たちにとっての布団やお気に入りの椅子のように、そこにいるとホッとできる。
そんな場所があるかないかで、日々の安心感が大きく変わってくるんですよね。
野生下のリクガメも、木の陰や岩のすき間などに身を潜めて休んでいます。
これは単に身を隠すためだけでなく、外敵から身を守ったり、気温や日差しを避けたりするための行動でもあります。
つまり、隠れられる空間は本能的に求めている“必要不可欠な場所”なのです。
実際にうちのリクガメも、掃除機をかけたあとや、ちょっとした家具の移動などがあった日は、いつもより長くシェルターにこもって過ごしています。
その姿を見て、「ここが安心できる場所なんだな」と思えたとき、シェルターの重要性をあらためて実感しました。
ただし間違った設置が「引きこもり」の原因になることも
とはいえ、ただ置いてあればいいというものではないのが難しいところ。
問題なのは「シェルターがあること」ではなく、「使い方」や「設置環境」にあります。
例えば、ケージの中で一番寒い場所にシェルターを置いてしまっていたり、風通しが悪く湿気がこもるような場所に設置していたりすると。
リクガメにとってはそこが「避難場所」どころか「出たくなくなる場所」になってしまうことも。
また、シェルターの材質が湿気を吸い込みやすい布製だったり、底に隙間がなく空気がこもるような構造だったりする場合。
居心地が悪くて逆に引きこもってしまう原因になることもあります。
さらに、サイズが小さすぎて体の向きを変えられなかったり、逆に広すぎて暗すぎたりする場合も要注意。
リクガメがリラックスして休めるちょうど良い「安心感のある空間」が必要なんです。
わたしも最初は「とりあえず隠れられればいいかな」と思って、小さめの木の箱を入れていたのですが、中が暗すぎたのか、ずっと出てこなくなってしまったことがありました。
後から開口部を広くしたり、中に明るめの干し草を敷いたりと工夫することで、ようやく安心して出入りするようになったんです。
理想的なシェルターの選び方と設置場所のポイント
理想的なのは、「リクガメが自由に出入りできて、のびのびと体を伸ばせる広さ」。
これはとても大切なポイントで、動きやすさが確保されていないと、シェルターそのものが「窮屈な箱」になってしまいます。
材質は通気性のよい木製やプラスチック製が◎。
プラスチック製であれば湿度の管理がしやすいですし、木製は見た目も自然に馴染んで落ち着いた印象になります。
中が真っ暗にならないように、光を少しだけ取り入れる小窓がついているものもおすすめです。
また、床材との相性も考えて、底に適度なすき間がある構造にすると湿気もこもりにくくなります。
中に干し草やヤシガラを敷くことで、より自然に近い環境に近づけることができます。
設置場所はケージ内の暖かいエリアにして、あえて少し開けた場所に置いてみるのもポイントです。
壁際にぴったりくっつけすぎると空気がこもりがちなので、通気性の良さも意識して配置しましょう。
うちでは、朝日が入るケージの手前側にシェルターを配置しています。
すると、朝の光を感じてゆっくり顔を出し、そのまま日光浴エリアに向かうという自然な行動パターンができてきました。
設置のちょっとした工夫ひとつで、リクガメの1日がこんなに変わるんだと驚かされた経験です。
環境に合わせた「快適な隠れ家」をつくってあげること。
それが、リクガメが安心して過ごせる毎日への第一歩になるのかもしれません。
シェルターの数を増やすのもひとつの手段
実は、シェルターは1つだけでは不十分なことがあります。
リクガメにもその日の気分や体調、気温によって「こっちのほうが落ち着くな」と感じる場所があるようで。
明るめの開放的なシェルターと、暗めで狭い落ち着けるタイプのシェルターを両方用意しておくと、自分で選んで移動する姿が見られるようになります。
例えば、昼間は陽が差し込むシェルターでうとうと過ごし、夕方には暗くて静かな方へ移動していく…
そんな行動を見ていると、「この子なりに過ごし方を考えてるんだなあ」と感心させられます。
また、気温差があるときなども、暖かい側のシェルターと涼しい側のシェルターを選んで使い分けている様子が見られることがあります。
こうした「選べる余地」があることで、リクガメの行動範囲が自然と広がり、運動不足やストレスの軽減にもつながっていくのです。
うちでは、最初はひとつだけだったシェルターを2つに増やしてから、リクガメの動きが明らかに活発になりました。
「今日はどっちにいるかな?」と探す楽しみも増えて、飼い主としてもうれしくなりますよ。
シェルターのない飼育はNG?そのデメリットとは
「隠れられない環境」というのは、リクガメにとって想像以上に大きなストレスになります。
野生の世界では、常に周囲を警戒しながら生活しているリクガメにとって、身を隠せる場所がないというのは「常に外敵にさらされている」ようなもの。
そんな環境では、安心して眠ることもできませんし、餌を食べる気力もなくなってしまうことすらあります。
リクガメは感情を大きく表に出す生きものではないからこそ、「元気がないな…」と気づいたときには、実は相当なストレスがたまっていることも。
飼い主としては「姿をもっと見たい」「かわいい顔をちゃんと見ていたい」と思ってしまう気持ちもよくわかります。
でも、それは人間側の都合であって、リクガメにとっては「見られている状態=落ち着けない状態」。
シェルターがないことで、見た目には活発そうに見えても、内心ではびくびくしながら動いている…なんてこともありえます。
だからこそ、安心して身をゆだねられる空間=シェルターの存在は欠かせません。
「隠れる場所があるからこそ、外に出る勇気も持てる」
そんなふうに考えて、リクガメの居場所づくりを見直してみるのもおすすめですよ。
まとめ
リクガメがシェルターにこもって出てこないとき、「また引きこもってる…」とただ心配するだけで終わらせてしまうのは、ちょっともったいないかもしれません。
その行動の裏には、必ず何かしらの“理由”や“気持ち”が隠れているものです。
たとえば、環境が合っていないのかもしれない。
気温が低すぎる、湿度が高すぎる、明るさが強すぎる…そんな小さな違和感が、リクガメにとっては「出たくない」と感じる大きな理由になります。
もしかしたら、ストレスを感じているのかもしれません。
人の声、物音、他のペットの気配、レイアウトの変化…人間が気にしないことでも、彼らにとっては重大なことも多いのです。
そしてなにより怖いのは、体調不良のサインを見逃してしまうこと。
元気がない、食べない、水を飲まないというのは、単なる“気まぐれ”ではなく、何か不調があるというメッセージかもしれません。
「今、この子は何を感じているのかな?」「なにか困っていることはないかな?」そんなふうに想像することが、リクガメとの距離を縮める第一歩。
目に見える行動だけでなく、そこに込められた“気持ち”に目を向けることが、信頼関係を築くうえでとても大切です。
出てこないからといって、「嫌われた」と思う必要はまったくありません。
むしろあなたを信頼しているからこそ、「ここなら安心して隠れていられる」と感じているのかもしれません。
だからこそ、無理に引っぱり出すのではなく、そっと見守ってあげてください。
そして、温度や湿度、明るさ、音の環境を見直したり、シェルターの位置を変えてみたり、リクガメが「外に出たくなる環境」をじっくり整えていくことが大切です。
リクガメの「ちょっとしたサイン」に気づける飼い主さんって、本当に素敵です。
そういう優しさや観察力が、リクガメの安心につながり、やがて“信頼して顔を出してくれる”瞬間を生んでくれるのだと思います。