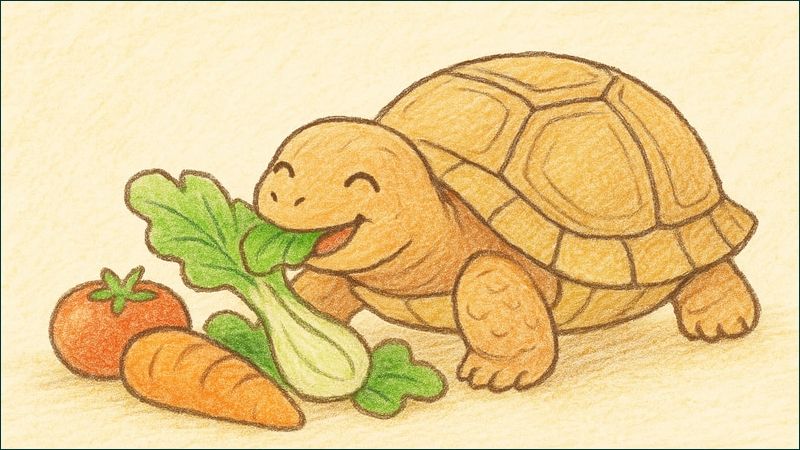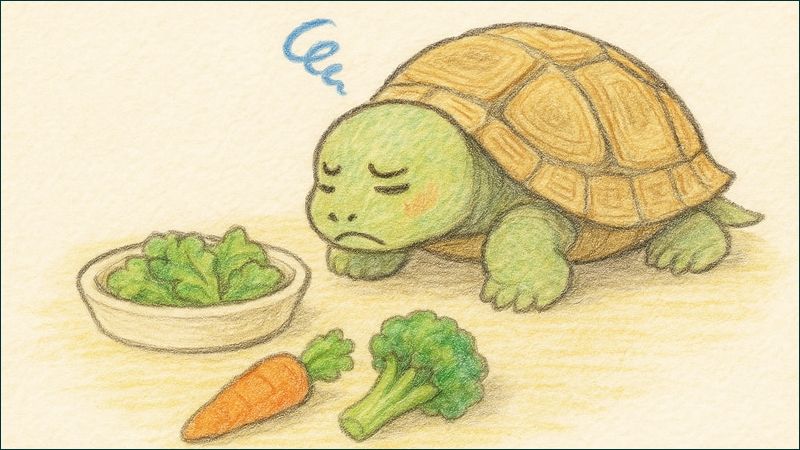
リクガメって、見ているだけで癒される存在ですよね。
そののんびりした姿や、ちょこちょことした歩き方、ゆっくりと野菜をかじる仕草……
もう、見てるだけでこっちまで心がほぐれてきます。
まるで「時間なんて気にしなくていいよ」って言われているような、そんな穏やかな空気をまとった小さな生き物です。
でも、そんな愛らしいリクガメが、ある日突然ごはんを食べなくなったとしたら?
最初は「お腹空いてないのかな?」くらいに思うかもしれません。
でも、1日、2日と続くと、急に不安が押し寄せてきますよね。
「え?何か変なもの食べさせちゃった?」
「体調悪い?」
「もしかして病気?」
「このまま一生食べなかったらどうしよう……」
と、心配で気が気じゃなくなります。
私も、かつて同じように何度も何度もケージの前で立ち尽くしていたことがあります。
「ただの気まぐれでしょ」と言われたこともありました。
でも、飼い主としては、ちょっとした変化がものすごく気になるんですよね。
だって、話せない子だからこそ、こちらが気づいてあげるしかないんです。
この記事では、そんな「ごはんを食べない」リクガメの異変にどう向き合えばいいのか?
考えられる原因から、今すぐ試せる対処法までを、できるだけわかりやすくお届けします。
必要以上に慌てず、でも「大丈夫」と決めつけず、今この子が何を伝えようとしているのか、一緒に考えるヒントになればうれしいです。
リクガメが食欲をなくす「よくある原因」とは?
「昨日まであんなにムシャムシャ食べてたのに、今日突然ぷいっ!」
そんなとき、まずは“何が変わったか”を思い出してみてください。
ほんの小さな変化でも、リクガメにとっては大きなストレスになることがあります。
季節の変化(特に夏バテ・冬の寒さ)
特に温度変化が激しい季節の変わり目は要注意です。
人間も季節の変わり目に体調を崩しやすいですが、リクガメも同じ。
夏の蒸し暑さや、冬のじんわりとした冷え込みに影響されて、食欲がガクンと落ちる子もいます。
私の子も、夏の終わりに一気に食が細くなって、慌てて温度管理を見直した経験があります。
ストレス(環境の変化・引っ越し・ケージの模様替え)
「ちょっと模様替えしてみようかな♪」と飼い主が気軽にケージの位置を変えたつもりでも、リクガメにとってはそれが「世界が変わった」くらいの衝撃になることも。
家族の声が届く場所に変えただけで、一気にシェルターにこもるようになってしまったという話もよく聞きます。
食事内容のマンネリや飽き
リクガメは基本的に草食性で、そこまでグルメではないと思われがちですが、意外と好みや「飽き」がある子も。
たとえば、ずっとチンゲン菜ばかりを与えていたら急に食べなくなった…なんてこともあります。
ほんの少し種類を変えたり、切り方を工夫するだけでも反応が変わったりするんです。
温度・湿度が合っていない
飼育書に書かれている理想温度を守っているつもりでも、実は床面が冷たかったり、日中と夜間で大きな寒暖差があったりすることも。
リクガメは変温動物なので、自分で体温調整ができないぶん、ちょっとした環境のズレが体調や食欲に直結します。
湿度も同じで、乾燥しすぎると呼吸が浅くなったり、飲水量が減って消化に影響が出たりするんです。
病気や体調不良のサインかも?
一見元気そうに見えても、実は体の中で異変が起きていることもあります。
目を閉じてばかり、動きが鈍い、いつものお気に入りスペースにも行かない……
そんな「なんとなくおかしい」サインがあれば、食欲不振は体調不良の表れかもしれません。
私のリクガメも、一度便秘が続いたときに、いつものごはんを見ても顔を背けるようになりました。
飼い主の勘、けっこう当たるんです。
まず試してほしい5つのチェックポイント
「なんとなく不調っぽい?」と思ったら、まずはこの5つのポイントをじっくりチェックしてみてください。
日常の中で見落としがちな小さな変化が、実は大きな原因につながっていることがあります。
温度・湿度が適切か再確認
昼間と夜で温度が大きく変化していないか確認してみましょう。
特に春や秋は日中は暖かくても、夜間に急激に冷え込むことがあります。
保温球の位置が高すぎたり、ケージの隅まで熱が届いていなかったりすると、体温をうまく保てず食欲が落ちることも。
湿度も同様で、乾燥しすぎは脱水や皮膚トラブルのもと。
温湿度計を置いて、目に見えるかたちで管理するのがおすすめです。
餌の鮮度や与え方を見直す
葉野菜がしなびていたり、変色していたりすると、リクガメは敏感に反応して口をつけなくなります。
スーパーで買ったばかりでも、保存状態によっては風味が変わってしまうことも。
与える直前に霧吹きで湿らせてみたり、常温に戻してから出すだけでも印象が変わることがあります。
また、餌皿の高さが合っていなかったり、餌が地面に散らかっていたりすると、食べづらくて諦めてしまうこともあるんです。
排泄物の状態を確認(便秘・下痢)
うんちの有無だけでなく、色・におい・かたさ・量も重要なサイン。
数日間まったく排泄がない場合は便秘の可能性がありますし、反対に、いつもより水っぽくてにおいが強い場合は腸の不調が疑われます。
私は以前、便秘かな?と思っていたら、じつは温度不足で代謝が落ちていたという経験がありました。
温浴や食事内容の見直しで改善するケースも多いです。
シェルターにこもりすぎていないか
普段は活発に動いていたのに、ここ最近はずっとシェルターに引きこもっている…
そんな様子が見られたら、何らかの不安や不快感を抱えているサインかもしれません。
部屋のレイアウト変更や、テレビの音量、掃除機の振動など、思わぬところが原因になっていることもあります。
私のリクガメは、床材を変えた翌日から全く出てこなくなり、元に戻したらすぐにケロッとして出てきたことがありました。
最近の生活環境に変化がなかったか
新しい家具を置いた、カーテンを変えた、子どもが夏休みに入って部屋にいる時間が増えた…
そうした些細な変化も、リクガメにとっては“環境の揺れ”に感じられることがあります。
- 音
- におい
- 光
- 気配
食欲がないときの対処法と工夫
「どうにかして食べてほしい!」そんなときに試してみたい、やさしい工夫を紹介します。
水分補給も忘れずに!温浴でリラックス
ぬるめのお湯での温浴は、代謝を上げて腸の動きを活発にしてくれる、リクガメにとっての“お風呂タイム”。
水分補給が苦手な子にも、温浴で皮膚からの吸収や、排泄の促進が期待できます。
温浴中にうんちをすることもよくあり、それだけでスッキリして食欲が戻ることも。
私はお風呂中にウトウトしている様子を見て「この子も癒されてるんだな」と、思わずほっこりしてしまった経験があります。
少量ずつ好物を混ぜてみる(例:チンゲン菜・タンポポ)
人間と同じで「好きなものがちょっとだけある」と、それだけで気分が上がることってありますよね。
リクガメも同じで、苦手な野菜の中にひとつだけ好物が混ざっているだけで、つられて口をつけてくれることがあります。
チンゲン菜やタンポポ、モロヘイヤなど、少量ずつ、彩りや香りも意識して工夫してみましょう。
「今日は食べてくれた!」そんな日は、飼い主までガッツポーズしちゃうんです。
サプリメントやカルシウムの量を調整
「健康のために」と思ってカルシウムをたっぷり振りかけすぎていませんか?実はこの“やりすぎ”が、かえって食欲低下につながることもあります。
粉っぽくて匂いが変わってしまった餌には、リクガメも敏感に反応します。
使う頻度や量、混ぜ方を見直すことで、驚くほど食べっぷりが変わることもありますよ。
いつもの餌を刻んだり茹でたりして食べやすく
葉っぱが大きすぎたり、茎が硬すぎたりするだけで、「食べづらいな」と感じてしまうことも。
とくに子ガメや食が細い子は、ちょっとした配慮で食べる量がグンと増えます。
私は、いつもは丸ごと与えていた葉を小さく刻んでみたら、パクパクと食べてくれるようになったことがありました。
また、冷蔵庫から出してすぐの冷たい野菜は避け、常温に戻してから与えるのも効果的です。
照明の点灯時間・位置を見直す
照明の当たり方ひとつで、行動範囲や餌場に立ち寄る頻度が大きく変わることもあります。
特に餌皿が暗い場所にあると、そもそも見えていなかったり、冷えや湿気で敬遠されるケースも。
逆に、強すぎる光が直接目に入る位置だと、それがストレスになって食事どころではなくなることも。
照明の位置や角度、点灯時間も「食事しやすい環境づくり」のひとつとして考えてみてください。
病気の可能性があるときの見分け方と動物病院の目安
「食べないだけ」と思ってしまいがちですが、リクガメの場合、それが病気のサインであることも多いんです。
特に口をきけない生き物だからこそ、飼い主の観察力が頼りになります。
「なんとなく元気がない」「ちょっと変かも」と感じたら、その“直感”を大事にしてあげてください。
2日以上まったく食べない場合は要注意
リクガメは代謝がとても低いので、1日くらい食べなくてもあまり問題ないことも多いです。
ただ、2日以上完全に何も食べないとなると話は別。
内臓の機能が低下していたり、消化器系にトラブルがある可能性があります。
特に、若齢の個体や老齢のカメは、体力も落ちやすいため、早めの対応が大切です。
私の子も、最初は「今日も食べないなぁ」くらいにしか思っていなかったのですが、3日目には完全に動きが鈍くなってしまって……。
もっと早く気づいていればと、後悔したことがあります。
便が極端に少ない・やわらかすぎる・色が異常
うんちの状態は、リクガメの健康を知る重要な手がかり。
便がコロコロしていても出ていればまだ良いのですが、数日まったく出ないのは便秘の可能性があります。
逆に、ゆるすぎたり異様なにおいがする場合は、腸の炎症や寄生虫の可能性も。
色が緑や黒に変わっていたり、粘液が混ざっていたりしたら、迷わず動物病院へ。
目を閉じてばかり・動かない・元気がない
リクガメがじっと動かず、目を閉じたままの時間が長くなってきたら、それは「疲れてるだけ」ではなく、体調不良のサインかもしれません。
目ヤニが出ていたり、前足に力が入っていなかったり、頭を引っ込めっぱなしだったり。
こうした変化は、すべて見逃してはいけないSOSです。
私自身、目を閉じて動かない様子を見たときの心臓のバクバクは、今でも忘れられません。
病院に行く前に用意するチェックリスト
いざ病院へ行こうと思ったとき、「何を聞かれるかな?」と不安になりますよね。
そんなときのために、以下の項目を記録しておくと診察がスムーズです。
- 直近1週間の食事内容(量・種類・与えた時間)
- 排泄の頻度と状態(写真があればベスト)
- 温度・湿度の記録(昼夜の変化も)
- 行動パターンの変化(いつもと違う様子)
- 照明・保温器具の設置状況
リクガメの「食べる意欲」を取り戻すコツ
リクガメの食欲が落ちているとき、つい「栄養が足りなくなるんじゃ…」と焦ってしまいますよね。
でも、身体の健康だけでなく、心のコンディションも整えてあげることが、また元気に食べる第一歩になります。
ここでは、リクガメの“気持ち”を支える工夫をいくつかご紹介します。
飼い主とのふれあい時間で安心感をアップ
「生き物は飼い主の気配を感じてる」とよく言われますが、リクガメも例外ではありません。
声をかけたり、そっとケージのそばで静かに過ごすだけでも、そのぬくもりや安心感は伝わります。
私のリクガメも、落ち込んだようにシェルターから出てこなかった日が続いていたのですが、声をかけてじっと見守るだけで、ある日ふっと出てきてくれました。
まるで「見ててくれた?」とでも言うような顔で。
そんな瞬間に、リクガメとの絆を深く感じられるんです。
毎日の観察ノートで体調変化を記録
「昨日と違う」「先週より元気がないかも」といった変化は、意外と記憶だけでは曖昧になります。
だからこそ、ちょっとしたことでもメモしておくと後で大きなヒントになります。
食べた量、食いつきの様子、排泄の状態、日中の動きなど、毎日の記録を続けることで「なんか変だな」の“なんか”が見える化されるんです。
数日後に見返して、「あ、気温が下がってから食欲が落ちたんだ」と気づけたこともありました。
無理に食べさせない「待つ勇気」も大切
心配すぎて、「お願いだから食べて」とエサを無理に口元に持っていきたくなりますよね。
私もやりました。
でも、それが逆にプレッシャーになってしまって、「もう近づかないで」と言わんばかりに逃げていったことがありました。
そういうときは、そっとお皿に好物を置いて、距離をとって静かに見守るのが一番です。
リクガメにはリクガメのペースがある。
信じて、待つことも、愛情のひとつなんだなと実感しました。
食事環境の「静かさ」と「安心感」を見直して
リクガメはとても敏感な生き物。
周囲の音や振動、光の加減ひとつでも「落ち着かない」と感じてしまうことがあります。
餌場の近くにテレビやスピーカーがあったり、人通りが多かったりすると、食事どころじゃなくなってしまうんです。
私の家では、ケージの場所をほんの1メートル移動しただけで、食欲が戻ったことがありました。
静かで落ち着ける空間、そして外敵が来ない安心感。
それが“食べる気持ち”を呼び起こしてくれるのかもしれません。
まとめ
リクガメが食べないとき、焦る気持ちはすごくわかります。
頭の中では「少し様子を見よう」と思っていても、心のほうが先にざわざわしてきて、
「このまま食べなかったらどうしよう」
「もしかして大きな病気かも」
と悪い想像が止まらなくなるんですよね。
私もかつて、心配で
- 何度も温浴させたり
- 餌の種類を毎日変えてみたり
- 照明の角度まで調整して
でも、そんな時こそ立ち止まって深呼吸。
大切なのは、慌てすぎず、冷静に「今のこの子に何が起きているのか?」を見てあげることなんだなと、何度も実感しました。
リクガメはおしゃべりこそしませんが、仕草や表情、目の動きひとつひとつに
「今こんな気持ちだよ」
「ちょっとしんどいんだよ」
と、サインを出してくれているんです。
それに気づけたとき、飼い主としての自信も少しずつ芽生えてきます。
季節の変わり目でなんとなく体がだるかったり、知らない音にびっくりして食欲がなくなったり、ほんの小さな変化でリクガメは食べなくなることがあります。
けれど、多くの場合は時間をかけて見守っていくうちに、また自然と元気に食べてくれるようになります。
焦らず、でも見逃さず。
大事なのはその「ちょうどいい距離感」なのかもしれません。
この記事が、あなたとリクガメの「食べる楽しみ」をまた取り戻すきっかけになりますように。
そして、この記事を読んでいるあなた自身の気持ちも、少しでも軽くなりますように。