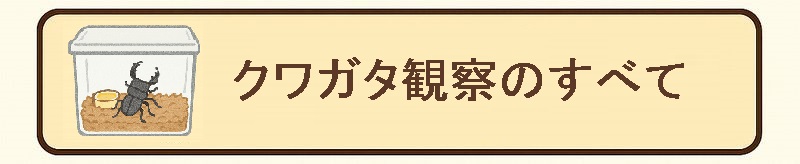「飼育グッズって高いし、できれば節約したいなぁ…」と、私がクワガタ飼育を始めたばかりの頃、ふと感じたのが始まりでした。
何もかも揃えるのにお金がかかるなぁ、と戸惑いながらホームセンターをウロウロしていたのを今でも覚えています。
実際、エサ皿や登り木って、市販品でもけっこういいお値段しますよね。
しかも「これ、見た目はいいけど使い勝手はどうなんだろう?」と悩むものも多くて。
でも、クワガタたちが元気に過ごせるなら、見た目やブランドにこだわらず、愛情たっぷりの手作りでもいいんじゃない?
そんなふうに考えるようになったんです。
そう思って始めた“手作りグッズ生活”。
これが意外と楽しくて、材料を探しているときからワクワクするし、作っているうちに夢中になってしまう。
そして何より、手作りしたものにクワガタがちょこんと乗ってくれた瞬間の喜びといったら…!
市販品にはない、なんとも言えない愛着が湧いてくるんですよね。
この記事では、私が実際に作ってみて「これはよかった!」と思った手作りエサ皿や登り木の作り方を、写真やちょっとしたエピソードも交えてご紹介していきます。
親子で工作気分で楽しむもよし、自分だけのオリジナル飼育グッズを極めるもよし。
自由研究のテーマにもぴったりなので、夏休み中の子どもたちにもおすすめです。
世界に一つだけのクワガタグッズ、あなたも作ってみませんか?クワガタもあなたも、もっと楽しく、もっと近づけるヒントがきっと見つかりますよ。
クワガタ用グッズは手作りできる?
市販と手作りの違い
クワガタ用のエサ皿や登り木は、もちろん市販品もあります。
見た目が整っていて、サイズも規格通りで安心感があるし、機能性も高いものが多いです。
特に初心者向けに作られているものは、使いやすさや清掃のしやすさなど、細かい配慮がされていて、「これさえ買えばOK!」という安心感があります。
ただその分、お値段もちょっと高め。
ひとつひとつは数百円でも、何種類も揃えようとすると意外と出費がかさみます。
一方で手作りの良さは、「コストを抑えつつ、自分の飼育スタイルに合わせられる」ところにあります。
何より、作る過程も楽しい!
子どもと一緒に「どんなのにしようか?」なんて話しながらあれこれ試行錯誤する時間も、実は宝物だったりするんです。
我が家では、子どもが「これクワちゃんのおうちにどうかな?」と空き箱を持ってきたり、「この枝いい感じじゃない?」と道端で拾ってきたものを見せてきたりして、ちょっとした遊び心と想像力がどんどん広がっていきました。
そうやってできた飼育グッズには、自然と愛着も湧くんですよね。
また、手作りならではのアレンジも楽しめます。
例えば、ゼリーが動かないようにピッタリの穴を開けたり、登り木を複数組み合わせて“ジャングルジム”みたいにしたり。
飼育スペースやクワガタの個体に合わせて微調整できるのも、手作りの醍醐味です。
どんな素材で作れる?
素材は本当に身近なものでOK!「これ、こんなふうに使えるかも?」という発想が大事です。
たとえば…
紙皿・牛乳パック
加工がしやすく、小さい子どもでも扱いやすい。
カラフルな紙皿なら見た目も楽しくなります。
木の枝
拾ってきた自然素材が一番クワガタにやさしい!
形がいびつなほど登りやすかったりもします。
小皿・フタ
ジャムやヨーグルトのフタなど、家にあるものが意外とちょうどいいサイズだったりするんです。
園芸グッズ
ウッドバーやコルク材など、園芸コーナーは宝の山!
虫かごコーナーより安い場合も多いです。
空き容器やペットボトルの底
カットしてフチを丸くすれば、安全でしっかりしたエサ皿になります。
工夫次第で、おしゃれで機能的なグッズに変身しますし、何より「自分で作った」達成感はひとしお。
少しのひらめきと手間が、クワガタとの距離をぐっと縮めてくれますよ。
クワガタ用エサ皿の作り方
紙皿・牛乳パックで作る方法
わが家の最初のエサ皿は、なんと牛乳パックでした。
1リットルの空きパックをよく洗って乾かし、底の部分を切り取って、低めの皿にしてみたんです。
最初は「えっ、こんなので大丈夫かな?」と不安だったけれど、意外や意外。
水分が染みないように内側にアルミホイルを貼ったら、これがなかなか優秀。
ゼリーをぴったり置けるし、汚れたら気軽に交換できる。
おまけに軽くて扱いやすい。
手軽さと機能性を両立できる優秀素材だと気づいた瞬間でした。
紙皿もおすすめです。
はさみで簡単に形を整えられるので、小さな子どもが一緒に作るときにもぴったり。
「ここに星のシール貼ろう!」なんて言いながら一緒に飾りつけをして、気がつけば“うちの子専用モデル”の完成。
名前を書いてあげると、「これボクの!」と愛着も倍増です。
さらに進化系として、紙皿にスポンジを貼り付けて、ゼリーが滑らないようにする工夫もあり。
こういうちょっとしたアレンジができるのも、手作りならではの楽しみですよね。
木の枝・小皿を使った本格派エサ皿
より自然な雰囲気を大切にしたい人には、小さめの木の皿や、木片をくり抜いたタイプがおすすめです。
私は庭で落ちていた丸太の端材を拾い、ヤスリで表面を丸く滑らかに整えて、エサ皿として使ってみました。
これが見た目にもよくて、自然のレイアウトにしっくり馴染むんです。
クワガタがその上にちょこんと乗っていると、まるで森の中のワンシーンのようで癒されます。
木の素材は湿度にも強く、適度な重みもあるのでひっくり返りにくいのがメリット。
ちょっとひと手間かかるけれど、そのぶん完成したときの満足感もひとしおです。
ちなみに最近では、100均でも小さな木皿が手に入るようになってきているので、加工が難しいときはそういった市販品をアレンジするのもおすすめですよ。
使いやすくする工夫ポイント
エサ皿を手作りするときに忘れてはいけないのが、使いやすさの工夫。
どんなに見た目がよくても、ひっくり返ってしまったり、ゼリーが転がってしまったら意味がありません。
我が家で実践しているポイントとしては、まず「底を広くする」こと。
安定感がぐっと増して、クワガタが上に乗っても傾きません。
次に、「ゼリーがちょうど入るくぼみ」をあらかじめ作っておくと、動いてもずれないし、見た目もスッキリします。
また、皿の一部に小さな穴を開けておくことで、水分や湿気が溜まりにくくなり、カビの発生も予防できます。
さらには「掃除のしやすさ」も大事なポイント。
木材で作る場合は、表面をニスなどでコーティングしておくと、汚れても拭き取りやすくなりますし、長持ちします。
こうして自分で工夫を重ねることで、クワガタにとっても、飼育する私たちにとっても、心地よいグッズが完成するんです。
クワガタ用登り木の作り方
拾った枝を登り木にする方法
「近所の公園で拾ってきた枝」で十分なんです。
わざわざ買わなくても、自然の中にはちょうどいい太さや形の枝がたくさん落ちていて、それだけでちょっとした宝探し気分。
でも、拾ってきたままだと雑菌や虫が心配なので、下処理が必要です。
まずは 熱湯で煮沸(5~10分)。
大きな鍋に入れてしっかり茹でることで、表面に潜んでいる雑菌やカビの胞子、虫の卵などをしっかり取り除くことができます。
煮沸後は 天日干しで完全に乾燥。
このとき、直射日光が当たる場所で半日~1日程度干しておくと、より安心して使えます。
さらに、表面をヤスリで丁寧になめらかにしておくと、クワガタの足もひっかかりにくく、ケガの心配も減ります。
角ばっている部分やささくれもこの段階で取り除いておきましょう。
ちなみに我が家では、拾った枝を「うちのクワちゃんのアスレチックにしよう!」と子どもが楽しみながらレイアウトを考えていました。
S字に曲がった枝を吊るしたり、小さな枝を渡したりと、遊園地感覚で組み合わせてみると、それだけで飼育ケースの中がぐっと楽しくなりますよ♪
100均アイテムで作る登り木アイデア
最近は100円ショップにも便利なアイテムがいっぱい。
特に園芸コーナーにある「ウッドバー」「小型のコルクボード」「流木風の飾り」は、実は登り木としてのポテンシャル大!
私が試してみた中で一番のお気に入りは、麻紐を巻きつけた“登れる壁”。
ウッドボードにぐるぐる麻紐を巻きつけて、立てかけるだけ。
するとクワガタがまるでロッククライミングのように上っていくんです。
その姿があまりにかわいくて、子どもと一緒に「がんばれー!」と声をかけながら見守ってしまいました(笑)
ほかにも、小さなスノコを立てて階段風にしたり、コルクのコースターを重ねてステージにしたりと、アイデア次第でいろんな遊び方ができます。
木工用ボンドで固定したり、グルーガンで組み合わせると、安定感も出て安心です。
クワガタが喜ぶ形状とは?
登り木の形で大切なのは、クワガタの本能に合った構造を意識すること。
まず、足がしっかりかかる太さがあること。
直径2~4cm程度が理想的で、極端に細すぎると落下のリスクもあります。
適度な太さの枝は、踏ん張りやすくてストレスも少ないようです。
そして、横枝やでっぱりなどがあると、クワガタの行動がとっても豊かに!高いところから降りたり、登り直したりと、見ていて飽きません。
自然界では木を登ったり下りたりして生活しているので、それに近い環境を再現してあげると生き生きしてくれます。
さらに、表面に凹凸があることも重要。
ツルツルした表面よりも、少しザラザラしていたり、樹皮が残っているほうが、クワガタの足がひっかかりやすく安心して動けるんです。
市販品のように見た目が完璧でなくても、「登ってみたい!」と思わせる魅力があればそれで充分。
手作りだからこそ、その子に合わせた“お気に入りスポット”を作ってあげられるのが嬉しいところです。
手作りグッズの注意点と長持ちさせるコツ
カビ・湿気対策は必須!
特に木材を使うときに気をつけたいのが湿気とカビ。
私も初めて使った登り木がカビだらけになってびっくりした経験があります。
「あれ?白いふわふわが…」と気づいたときには、すでにケースの中が湿っぽくなっていて、思わずゾッとしました。
カビは見た目が悪いだけでなく、クワガタの健康にも影響を及ぼします。
空気中のカビ胞子が体についたり、呼吸器に入り込んでしまったりすると、弱ってしまうこともあるんです。
だからこそ、予防がなにより大事。
完全に乾燥させてから使用する:拾ってきた枝や木材は、内部にまで水分を含んでいる場合があります。
しっかりと天日干しするだけでなく、場合によっては電子レンジなどで軽く乾燥させるのも手です(※焦げに注意)。
定期的に天日干しする:使い始めてからも、週に一度は風通しの良い場所で日光に当てる習慣を。
湿気が抜け、殺菌効果も期待できます。
ケース内の湿度をチェック:湿度計を設置しておくと安心。
理想は60%前後。
保湿しすぎるとカビが発生しやすくなるので、加湿と通気のバランスが大切です。
ちょっとした手間ですが、この3つを意識するだけで、手作りグッズの寿命がぐっと延び、クワガタも快適に過ごしてくれます。
安全面にも配慮しよう
クワガタは力強い見た目に反して、とても繊細な生き物。
登り木やエサ皿のちょっとした尖りが足に引っかかったり、ケガをする原因になることも。
我が家でも、初めて作った登り木の角が少し鋭くなっていて、クワガタがそこを避けて登らなくなったことがありました。
見ていて「あっ、怖がってる…」と感じた瞬間に、やっぱり気をつけないとと反省したものです。
安全に使うためのポイントをご紹介しておきますね。
ヤスリで角を丸くする
見た目ではわからなくても、クワガタの足にとっては小さな出っ張りも危険。
紙やすりやスポンジヤスリで丁寧に丸めましょう。
ボンドや接着剤はしっかり乾かす
固まる前に使うと、クワガタの体にくっついてしまうことがあります。
完全に乾燥してからケースに入れるのが鉄則です。
洗剤などの匂い残りにも注意
加工前の素材を洗うときは、できるだけ無香料の石けんや重曹など、自然素材を使うのがおすすめ。
クワガタは匂いに敏感です。
そして一番大事なのは、「人の赤ちゃんと同じくらい丁寧に扱う」くらいの気持ちで、やさしく安全な環境を目指すこと。
グッズを通じて、クワガタにとっての“安心できるおうち”を作ってあげましょう。
まとめ|手作りで楽しむクワガタ飼育
手作りって、最初は「面倒そう」「うまく作れるかな?」なんて心配になってしまうもの。
でも、いざ始めてみると、そのイメージは良い意味で裏切られます。
実際に手を動かして作ってみると、ただの作業じゃなくて「小さな発見の連続」なんですよね。
「この枝の曲がり具合、ちょうどよく登りやすそうだな」とか、「このスポンジ、ゼリーが滑らなくていいかも!」とか。
そういう“ひらめき”や“工夫”がどんどん湧いてきて、気づけば夢中に。
しかも、完成したグッズを使ってくれるクワガタの姿を見ると、それまでの苦労がすべて報われる気がします。
「おぉ、登ってくれた!」「そこでエサ食べてる~!」なんて、ちょっとした行動が嬉しくてたまらなくなるんです。
エサ皿も、登り木も、ほんの少しの手間と気配りで、クワガタにとって居心地のいい空間に変わります。
しかもそれが自分の手で作ったものなら、愛着もひとしお。
我が家では、子どもが「これはボクが作ったやつ!」と自慢げに話すこともしばしば。
クワガタとのふれあいだけじゃなく、家族との絆も自然と深まっていくんですよね。
「うちのクワちゃん、登り木気に入ってるっぽい!」なんて、日常の中に生まれるちょっとした喜びが、毎日をほんの少し明るくしてくれます。
あなたのクワガタライフが、もっと楽しく、もっと愛おしいものになりますように。
そして、世界に一つだけの“わが家オリジナル飼育セット”が、たくさんの笑顔を生み出しますように。