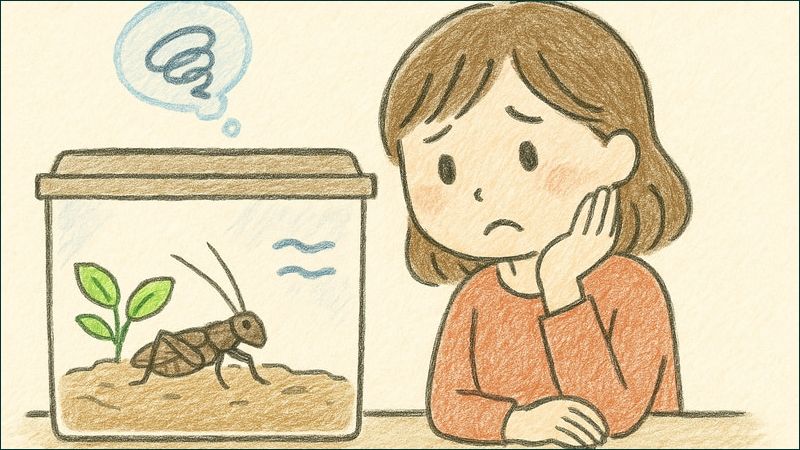
「楽しみにしていた鈴虫の鳴き声が、聞こえない……」そんな違和感から始まったのが、私の鈴虫との本気の向き合いでした。
ケースをのぞけば、元気そうに動いているし、エサも減っている。
でも、あの“チリチリ…”と響く癒しの音が、どこにもない。
最初は「まだ夜じゃないからかな?」と軽く流していたものの、次の日も、そのまた次の日も沈黙が続き、不安がじわじわと広がっていきました。
鈴虫って、こんなに鳴かないものなの?それとも私の育て方が間違ってた?そんなふうに自分を責めそうになったこと。
今ではちょっと笑える思い出だけれど、当時は本気で心配でした。
でも調べてみると、「鳴かない=異常」ではないケースが意外と多くて、むしろ“よくあること”だったんです。
この記事では、鈴虫が鳴かないときに考えられる原因や、その対処法をできるだけわかりやすく、そしてちょっぴり寄り添う気持ちも込めてまとめました。
鈴虫の声が聞こえないことでモヤモヤしたあなたの心が、この記事を読み終えた頃には少しでも晴れて、もう一度“チリチリ…”という小さな音に耳を澄ませたくなる。
そんな気持ちになってもらえたら嬉しいです。
鈴虫が鳴かないのはよくあること?
鈴虫が鳴かない。
そう聞くと「え?うちの子だけ?何か悪いことしちゃった?」って焦ってしまう方、実はかなり多いんです。
私も最初はその一人でした。
だって、あの鳴き声を楽しみに飼いはじめたのに、しーんとしてるとちょっと拍子抜けしちゃいますよね。
けれど実はこれ、決して珍しいことではないんです。
むしろ鈴虫と暮らしていれば誰もが一度はぶつかる“静けさの時間”なんじゃないかと思います。
鳴く・鳴かないにはいろんな理由があって、そのどれもが鈴虫にとっての「今の気分」や「ちょっとした事情」だったりします。
体調が悪いわけでもなく、環境が大きく乱れているわけでもない、ただ単に「今は鳴きたくないだけ」なんてことも。
本当に、生き物って奥が深いですよね。
だから、「鳴かない=失敗した」なんて思わないでくださいね。
むしろそれは、鈴虫との暮らしの中でしか味わえない、静かな観察タイムのはじまりかもしれません。
音がなくても、ちゃんと命はそこにあって、じっと息づいている。
私はそんな時間も、今では大切に感じられるようになりました。
オスだけが鳴くって知ってた?
「えっ、メスって鳴かないの?」
この事実を初めて知ったとき、私はちょっとした衝撃を受けました。
だって、鈴虫を飼う=鳴き声を楽しむものだと思っていたから。
だけど、実は鳴き声を出すのは“オスだけ”なんですよね。
これは恋のアピール。
メスに自分の存在を知ってもらって、「こっちにいるよ」「どう?素敵でしょ?」って、一生懸命に羽を震わせて音を奏でているんです。
その姿を想像したら、なんだかちょっと切なくて、愛おしくなってきませんか?
でも、そんな大事な仕組みを知らずに、うっかり
- メスだけのペア
- まだ羽化したばかりの子たち
私も最初の年は、オスメスを選ばずに数匹まとめて買ってきて、ずっとシーンとしたまま……。
数日後にようやく気づいたときには、軽く肩を落としました(笑)
だからこそ、まずは性別を確認することが大事。
羽の先が交差しているのがオス、丸く収まっているのがメス、という見分け方もありますが、慣れるまではちょっと難しく感じるかもしれません。
でも大丈夫。
焦らずじっくり観察していると、少しずつ違いが見えてきます。
鳴き声を聞きたいなら、元気なオスをお迎えすることが第一歩。
そして、彼らがその声を響かせたくなるような環境を、そっと整えてあげることが飼い主の愛なのかもしれません。
時期によっては鳴かないこともある
鈴虫って、あの風流な鳴き声で「秋の音」を届けてくれる存在だと思っていたのに、いざ飼い始めてみたら
「……まだ鳴かない」
「なんで?」
と戸惑ってしまうことがあります。
でもそれ、実は“まだその時期じゃないだけ”なのかもしれません。
鈴虫が本格的に鳴きはじめるのは、だいたい7月後半から8月中旬以降。
気温が落ち着き始めて、昼と夜の長さに少し差が出てくるころです。
涼しい夜に、静かに響くあの音色。
彼らは本能的に“季節の変わり目”を感じて、そこではじめて「そろそろ鳴こうかな」とスイッチが入るんです。
それに、羽化してすぐの子は、羽がまだ柔らかくてうまく音を出せないことも多いです。
私が初めて飼った鈴虫も、羽がしっかり乾いて固まるまで1週間くらいはじっとしていて、気づけば音がして「えっ、今のって鈴虫!?」とびっくりした記憶があります。
つまり、「今はまだその時じゃない」というだけで、何か問題があるわけじゃないこともたくさんあるんです。
焦らず、見守ってあげてくださいね。
鳴き声が聞こえない“静けさ”の時間もまた、鈴虫のリズムの一部。
その時間も含めて楽しめたら、きっともっと深く、鈴虫との暮らしを味わえるようになるはずです。
鳴かない=病気や異常ではないケースも
「こんなに静かで大丈夫なのかな……」
鈴虫が鳴かない日が続くと、だんだん不安が胸に広がってきますよね。
- エサは食べてる。
- 元気に動いてる。
- でも鳴かない。
だけど、安心してください。
鳴かない=病気や異常とは限らないんです。
鈴虫だって生き物。
いつでも100%の力でアピールするわけじゃないし、日によって気分や体調に波があるのは当然です。
私たち人間だって、毎日ずっと喋っているわけではないですよね。
たまには黙って、じっと周りを見ていたい日だってある。
それと同じように、鈴虫にも「今日はちょっと静かに過ごしたいな」っていうタイミングがあるんです。
私が以前飼っていた子も、ある日突然ぴたっと鳴き止んでしまって、心配になってケースの中をずっと観察していました。
でも、動きはスムーズで、エサにもちゃんと口をつけていて、水も飲んでいる。
なのに鳴かない。
数日間、ずっとそんな状態が続いたあと、ふいに夜更けに「チリ……チリ……」と音が鳴ったときの安心感といったら、言葉にならないものでした。
だからこそ、鳴き声だけに頼らず、全体の様子を見て判断することがとても大切です。
焦らず、慌てず、音のない時間にこそ目を向けてみてください。
静かなその時間も、きっと鈴虫があなたに何かを語りかけているサインなのかもしれません。
鳴かないときの主な原因とは?
「元気そうなのに、なんで鳴かないんだろう?」
鈴虫と暮らし始めると、こんなふうに不安になる瞬間が何度かやってきます。
私もそうでした。
姿は見えているし、動いているし、エサも食べてる。
でもあの癒しのチリチリという音が、いくら待っても聞こえてこない。
静けさが続くほどに、「何かおかしいのかな」「自分の育て方が悪かったのかな」と責めそうになってしまう。
でも、そんなふうに思わなくていいんです。
鈴虫が鳴かない理由は一つじゃなくて、本当にいろんな可能性があって、それが複雑に重なり合っていることもあるから。
環境が合っていない(温度・湿度)
鈴虫にとって、温度と湿度は「快適さ」のバロメーターそのもの。
エアコンの風が直接当たっていたり、逆に部屋が蒸し暑すぎたり乾燥しすぎたりしていると、鳴くどころじゃなくなります。
理想は25~28℃くらいで、湿度は60%前後。
これより外れると、体力を温存するためか、警戒心を強めるためか、まったく鳴かなくなることもあります。
私がある晩に「まったく鳴かない」と悩んだとき、湿度が40%台まで下がっていて、慌てて霧吹きや加湿器を使ったことがありました。
ほんの数時間後、「チリ……」と鳴いた瞬間、胸にふっと風が吹いたような安心感があったのを今でも覚えています。
照明や音、振動のストレス
鈴虫って、思った以上にデリケート。
人が「たいしたことない」と感じる光や音、振動も、彼らにとっては大きなストレスになるんです。
たとえば、テレビの音や家族の会話、洗濯機の振動、スマホの通知音。
そういう日常の中の刺激にさらされていると、「今は鳴かないほうが安全かも」と判断して、鳴かない時間が長くなることがあります。
私の飼っていた鈴虫も、リビングでは一切鳴かなかったのに、静かな和室に移したとたん夜通し鳴きはじめたんです。
それだけ環境が鳴き声に直結しているということ。
もし鳴かない日が続いたら、まずは「うるさすぎないか」「明るすぎないか」と、鈴虫の目線になって部屋の空気を見直してみるのもひとつの方法です。
オスがいない、もしくは高齢になった
基本中の基本ですが、鳴くのはオスだけ。
そしてそのオスも、ずっと鳴き続けられるわけじゃなくて、年齢とともに鳴き声は減っていきます。
初めて飼うときに性別を気にせず購入すると、気づかぬうちにメスだけの状態になっていて「どうして鳴かないの?」と悩んでしまう人、けっこう多いんです。
私もその一人でした。
さらに、羽化してからしばらくは元気でも、9月を過ぎたころから急に静かになることもあります。
鈴虫の寿命は短く、成虫でいられるのは1~2ヶ月程度。
だからこそ、あの音が聞ける時間はとても貴重で、たとえ静かになっても「ありがとう」と声をかけたくなるような、そんな気持ちになるのです。
脱皮前や羽が未成熟な可能性
羽化したばかりのオスは、まだ体も羽も未熟で、うまく音を鳴らすことができません。
羽が完全に乾いて固まり、鳴くための筋肉がしっかり動くようになるまでは、しばらく“準備期間”が必要なんです。
だから、見た目が成虫に近づいたからといって、すぐに鳴くとは限らないんですね。
私が一度だけ経験したのは、あるオスが羽化してからまる4日間ずっと沈黙していたけれど、5日目の夜、そっと羽を震わせるようにして初めての音を鳴らしたときのこと。
それはもう、拍手を送りたくなるような感動でした。
焦らず待つこと、これも飼い主としての大事な役割だと感じた瞬間です。
共食いや個体同士の相性も影響することも
これも見落としがちですが、ケースの中での“人間関係”、いや“虫間関係”も、鳴かない原因になり得ます。
鈴虫は意外と縄張り意識が強くて、オス同士の相性が悪いと、どちらかが萎縮して鳴かなくなってしまうことがあります。
場合によってはエサ不足やストレスから共食いが起きてしまい、そのショックで他の個体も鳴かなくなることも……。
私の鈴虫も、ある年に突然一匹が脱落してしまって、それ以降鳴き声がぴたっと止まったことがありました。
それをきっかけに、仕切りをつけたり、ケースを分けたり、隠れ家になる木の皮を入れたりして、ようやくまた鳴き声が戻ってきたんです。
小さなケースの中にも“空気感”があって、それが鳴き声に如実にあらわれる。
そんな繊細さもまた、鈴虫という生きものの魅力なのかもしれません。
今すぐできる対処法
鈴虫が鳴かないときって、どうしても不安になりますよね。
でも、原因がわかってきたら、次は「じゃあ何をしてあげればいいの?」というところが気になると思います。
実は、鳴かないときの対処法って、特別な道具や知識が必要なわけじゃなくて、“ほんのちょっとの気づかい”と“生活の中でできる工夫”で大きく変わることが多いんです。
私も最初のころは不安でいっぱいでしたが、環境をちょっと見直すだけで、鈴虫たちの声がふわっと戻ってきたときの感動は今でも忘れられません。
ここでは、今日からすぐに試せる具体的な対処法をお伝えしていきますね。
最適な温度・湿度を保つコツ
温度と湿度は、鈴虫にとっての“心地よさ”を決める鍵のようなものです。
エアコンの風が直接当たる場所にいたり、部屋が乾燥していたりすると、それだけで「ここは鳴くにはちょっと…」と感じてしまうようです。
私が一度試したのは、ケースの近くに霧吹きで水をシュッと吹いて湿度を上げること。
それだけで鈴虫の羽が軽やかに動きはじめて、音が戻ってきたことがありました。
また、温度が低くなりすぎる夜は、小さな保温シートや段ボールでケースを囲ってあげるだけでも安心感が変わってきます。
難しいことはしなくても、室温と湿度を気にかけてあげるだけで、鳴き声のリズムは驚くほど変わるんです。
静かで暗めの落ち着いた場所に置く
これは本当に効果絶大でした。
私は最初、リビングに鈴虫のケースを置いていたんですが、テレビの音、子どもたちの笑い声、食器のカチャカチャという音……日常の何気ない音たちが、彼らにとってはとても落ち着かない空間になっていたんだと思います。
思い切って、誰も使っていない和室の隅にケースを移して、夜は間接照明だけにしてみたんです。
するとその日の夜、まるで安心したかのように「チリ…チリ…」と鳴き声が返ってきて、それを聞いた瞬間、胸がじんわり温かくなりました。
鈴虫にとって“暗くて静か”は、自分をさらけ出せる空間。
それを意識してあげるだけで、彼らはちゃんと応えてくれるんです。
他の昆虫や動物から距離をとる
これ、意外と気づかれにくいのですが、鈴虫って他の生き物の存在にもかなり敏感です。
うちでは金魚の水槽の近くに鈴虫を置いていたことがあるのですが。
ブクブクというエアレーションの音や、水槽の光の反射が気になったのか、まったく鳴かなくなってしまったことがありました。
その後、場所を移してから少しずつ鳴くようになって「まさか原因はそこだったのか…」と驚いた経験があります。
ハムスターや犬猫など他のペットがいるお家では、なるべく物理的な距離をとってあげるのが安心です。
鈴虫にとって“自分だけの空間”を用意してあげることが、落ち着いて鳴くためにはとても大切なんですね。
エサと水分を見直してみよう
鳴かない原因が“空腹”ということもあります。
私も最初のころ、エサがまだ残っているように見えていたので気にしていなかったのですが。
実は乾燥してカピカピになったキュウリを前に、鈴虫たちが見向きもしない状態だったんです。
新鮮なエサに替えたとたん、もぞもぞと集まってきて、その夜にはチリチリと音が戻ってきたとき、「ああ、ごめんね…」と心の中で何度も謝りました。
水分も、野菜の水分だけでは足りないこともあります。
濡らした脱脂綿を小皿に置いてあげたり、こまめに水を入れ替えることで、鈴虫の体調はずいぶん変わってくるんです。
彼らの“食”に対する小さな変化にも、気づけるようになりたいなと、そのとき強く思いました。
ケースを大きめに変えるのも有効
狭い空間にギュウギュウに詰め込まれている状態では、鈴虫は安心して鳴くことができません。
オス同士が距離をとれず、鳴きたいのに鳴けないという空気感がケースの中に漂ってしまうことも。
私がケースをひと回り大きなものに変えて、仕切りや隠れ家になる小枝を入れてあげたとき。
最初は静かだった空間が、数日後にはまるで“森の夜”のようににぎやかになったことがありました。
空間に余裕があることで、彼らの“自分らしさ”が戻ってくるような感覚。
スペースの広さって、鳴く・鳴かないにすごく影響してくるんですね。
鳴き声を楽しむための工夫とポイント
鈴虫の鳴き声って、ただ“音”として聴くものじゃないと思うんです。
耳に届いた瞬間、心の奥がじんわりとほぐれて、なんとも言えない穏やかな気持ちになれる。
それが、鈴虫と暮らすことの醍醐味なんじゃないかなって、私は思っています。
でも、せっかく飼っているのに「思ったより鳴かないな」「もっとたくさん鳴き声が聴きたいな」って感じる日もありますよね。
ここでは、鈴虫が自然と鳴きたくなるような工夫や、鳴き声をもっと楽しむためのちょっとしたポイントをお伝えしていきます。
鳴きやすい時間帯を知ろう(夜~朝)
鈴虫は夜行性。
つまり、昼間は静かにじっとしていて、夜になるとようやく活動を始め、羽を震わせて音を奏でるようになります。
私も最初のころ、日中に「全然鳴かないなあ…」と不安になっていたのですが。
夜11時を過ぎたころ、電気を消して静かにしていたら突然「チリ…チリ…」と小さな音が鳴りはじめたんです。
その瞬間、「この子、ちゃんとここにいたんだ…」って、胸がぎゅっとなりました。
だから、鳴き声を楽しみたいなら、夜~明け方の時間帯にそっと耳をすませるのがおすすめです。
テレビもスマホも消して、静かな部屋でただ“音を聴く”ことに集中する。
その時間そのものが、まるで小さな瞑想のように心を整えてくれます。
複数のオスを入れると鳴きやすくなる?
ちょっとした裏ワザのように感じられるかもしれませんが、オスを複数飼うと、まるで“俺のほうがいい声だぞ!”と張り合うように鳴きはじめることがあります。
これは私も実際に体験していて、1匹だけだとおとなしかった子が、もう1匹オスを入れたとたんに、見違えるほど元気に鳴くようになったんです。
ただし、ここで注意したいのは“スペース”。
オス同士は縄張り意識が強いので、距離が近すぎるとケンカになったり、かえって萎縮してしまうこともあります。
ケースはなるべく広めにして、間に隠れ家になる小石や葉っぱなどを置いてあげると、互いに程よく意識しながらも、安心して自分らしい声を響かせてくれるようになります。
鳴き声を引き出すための“静けさ”の重要性
鈴虫が鳴くには、なにより“安心できる空間”が必要です。
そしてその安心感を作るいちばんの近道が、“静けさ”だと私は思っています。
私自身、鈴虫を和室の隅に移して、照明を落とし、物音もできるだけ立てないように気を配ったとき。
その夜からまるで何かが溶けたかのように、やさしい音がふわっと部屋に広がりました。
その“音のない時間”をつくることって、私たちの日常では意外と難しいけれど。
鈴虫のために少しだけ静けさを整えてあげることで、その空間が自分自身にとっても癒しの場所になっていったんです。
鈴虫の鳴き声って聞こうとしないと聞こえないほど繊細だからこそ、音を“聴く”という時間を意識して持つことで、暮らしの中の感覚がぐっと研ぎ澄まされていくような気がします。
それでも鳴かない…そんなときは?
ここまでいろんな工夫をしてみても、それでも鳴かない。
夜になっても静かなまま。
そんな日が続くと、がんばってお世話しているぶんだけ、「どうして…?」という思いがこみ上げてきますよね。
私もそうでした。
温度も湿度もばっちり。
静かな場所に移して、エサも新鮮なものを用意して、それでも音がしない。
正直「もうどうしていいかわからない…」って、ため息まじりにケースを見つめていた夜もありました。
でも、そんなときこそ“無理に音を求めないこと”が大切なんだと、後になって思うんです。
ここからは、鈴虫が“鳴かないまま”でも、心を整えて向き合っていくためのヒントをご紹介します。
そっと見守ってみるのもひとつの方法
鈴虫にも、その子なりのリズムがあります。
調子が出るのに時間がかかる子もいれば、環境に慣れるまで鳴かない子もいます。
あれこれ試してみたあとは、いったん“手放して見守る”というのも立派な選択肢。
人間だって、がんばれない日があるように、鈴虫にだって「今日は静かにしてたい」って日があって当然なんですよね。
私も、何もしないでそっと寄り添ってみたら、2日後の夜にぽつん…と鳴き始めたことがありました。
その音は、それまでよりもずっと大きく、私の心に響きました。
“待っててよかった”と思えたその瞬間が、すべてを報われたように感じたんです。
新しいオスに入れ替えてみる選択も
どうしても鳴き声を聴きたい、子どもが楽しみにしてるから…そんなときは、新しいオスを迎え入れるという選択もあります。
ただし、そのときに大切なのは、“今いる子”のこともきちんと見送ること。
もしもすでに寿命が近づいているようなら、最後まで大切にお世話してあげてから、新しい出会いを迎えてあげてほしいんです。
命のバトンをそっとつなぐような気持ちで。
うちは一度だけ、静かになったケースをそっと片付けて、数日後に新しいオスをお迎えしたことがありました。
そのときの最初の鳴き声は、どこか“前の子”を思い出させるような響きで、私は思わずケースの前で手を合わせてしまいました。
命って、つながってるんだなぁ…そんなふうに感じた夜でした。
自然にまかせて、焦らず向き合おう
すべての鈴虫が、必ず元気に鳴いてくれるとは限りません。
でも、だからこそ“鳴かない時間”をどう感じて過ごすかが、飼育の本当の醍醐味だと思うんです。
音がなくても、そこには確かに命があって、呼吸があって、生きている。
ケースの中で羽を震わせる前の“静けさの時間”だって、ちゃんと意味のある大切なひとときなんですよね。
私はそう信じています。
鳴かなくてもいい。
焦らなくてもいい。
大切なのは「鳴かせること」じゃなくて、「その子のペースに寄り添うこと」。
そう思えるようになったとき、鈴虫との距離はぐんと縮まって、心の中に優しい静けさが広がっていく気がします。
まとめ
鈴虫が鳴かないとき、私たちはつい「なにか間違えたのかな」「ちゃんと育てられてないのかも」と自分を責めてしまいがちです。
でも実際には、鳴かないのには理由があり、それは多くの場合ほんの些細な環境のズレや、その子自身のタイミングだったりします。
静けさの中にも命はあって、鳴き声がしない日々にも意味がある。
そう思えるようになったとき、鈴虫との暮らしはぐっと豊かなものに変わっていきます。
温度や湿度、エサや住まいの見直し、そして何より“そっと見守る時間”。
それらすべてが、音では測れない大切な“対話”なのだと思うんです。
鳴いても鳴かなくても、そこにいる鈴虫と一緒に過ごす毎日は、かけがえのない時間。
焦らず、無理せず、寄り添いながら育てていけば、きっとある日ふいにチリチリと音が響いて、その瞬間の喜びが心に残るはずです。
鳴くことだけをゴールにしなくてもいい。
ただ、生きているその存在と向き合うこと。
それが、鈴虫との暮らしのいちばんの醍醐味なのかもしれませんね。
今日もあなたと鈴虫に、静かでやさしい夜が訪れますように。
