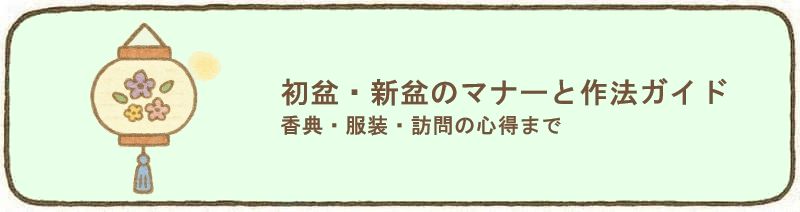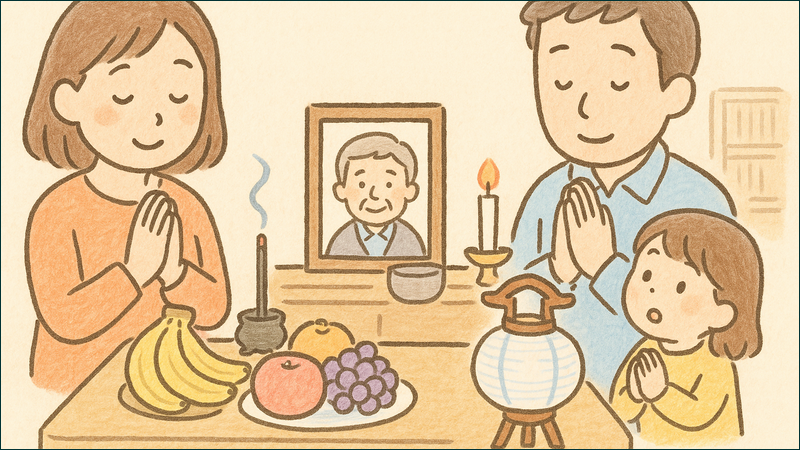
身近な人を見送ったあとの日々は、何かをするたびにふと故人の姿が思い浮かんだり、ふとした瞬間に涙が出そうになったりして、時間が止まったような気がすることがあります。
そしてそんな気持ちがようやく落ち着きかけた頃に訪れるのが「初盆」ですよね。
お盆の時期は誰にとっても特別な意味を持ちますが、故人が旅立って初めて迎えるお盆は、なおさら感慨深くなります。
きちんと供養してあげたい、でも形式ばったことや親戚付き合いには気が重い、そんな心の板挟みになる方も多いのではないでしょうか。
私自身もそうでした。
「家族だけで静かにやりたい」と思ったものの、どこまでが常識なのかが分からず、不安ばかりが募ってしまって。
親戚の目も気になるし、もしも誰かに「非常識だ」と思われたらどうしようって、頭の中がぐるぐるして眠れなかったこともありました。
でも、家族の形が多様化している今、供養のあり方も少しずつ変わってきていると感じます。
誰かに見せるための法要ではなく、心から故人を想う気持ちこそが一番大切なのだと、今なら胸を張って言えます。
この記事では、初盆を家族だけで行いたいと考えている方が、不安や後悔なくその日を迎えられるように、マナーや案内の仕方、気をつけたい点などを、実体験を交えて丁寧にお伝えしていきます。
どうかこの記事が、あなたの迷いをそっとほどいてくれる一助になりますように。
初盆を家族だけで行うことを知らせるはがきの例文!なにか決まりごとはあるの?
大切な人を亡くして、心の整理がつかないまま月日が過ぎていき、ふとカレンダーに目をやったときに
「あ、もうすぐお盆だ」と気づく瞬間って、胸がキュッと締めつけられるような感覚がありますよね。
特に初盆となると、その重みはなおさらで、心の中でいろんな思いが交錯します。
ちゃんと供養してあげたい。
でも今の生活の中でできることには限界があるし、無理をしてまで大々的にやるのはちょっと違う気もする。
だからこそ、最近では「家族だけで静かに初盆を迎えたい」と考える方も増えてきています。
でも、そう決めたとしても次に迷うのが「親戚や関係のある方にどう伝えたらいいのか」ということ。
声をかけるべきなのか、何も言わずに済ませてもいいのか、逆に伝え方を間違えると失礼になるんじゃないかと心配になる気持ち、とてもよく分かります。
なぜ案内状を出すのか?その目的を明確に
そもそも案内状とは、本来「参列してもらう」ことを前提に送るもの。
だから「呼ばないけれど知らせたい」という場合には、送り方にも少し配慮が必要です。
ただ、これは形式的なものではなく、こちらの気持ちを伝えるための“心の橋渡し”なんですよね。
私は過去に「何も言わずに家族だけで初盆を済ませたら、あとから親戚に『何も聞いてなかった』とちょっとした誤解を招いたこと」がありました。
悪気はなかったのに、それが相手にとっては「除け者にされた」と感じさせてしまったようで、すごく後悔しました。
だからこそ、家族だけで行うにしても、事前に「今回はこのようにさせていただきます」とお伝えしておくのは、相手のためでもあり。
そして、自分たちの気持ちを守ることにもつながると思います。
案内状を出すときに気をつけたい表現のニュアンス
案内状の文面は、少しの言葉の選び方で印象が大きく変わってしまいます。
「今回はご遠慮ください」と書かれると、どうしても断られたような冷たさを感じてしまう人もいます。
なので、表現としては
「ご足労をおかけするのも申し訳なく」
「家族で静かに行うことにいたしました」
というように、相手を思いやっていることが伝わる言い回しが大切です。
また、親戚によっては伝統を重んじる方もいるかもしれません。
その場合は「ご理解いただければ幸いです」といった柔らかい表現で締めくくると、角が立ちにくくなります。
案内状を出さないという選択肢もある
実は、最近では初盆を家族だけで行う家庭も多くなってきていて、特に案内状を出さないケースも増えています。
特にごく近しい親戚以外には、電話やLINEなどで簡単に伝えるだけで済ませるという方も多く、「わざわざはがきでお知らせしなくても自然と察してくれる」と考える人もいます。
それでも、もし故人と深い付き合いがあった方や、気にしてくださっている親戚がいれば、最低限一言お伝えしておくことで、気まずさを避けることができます。
「知らせてくれてありがとうね」と言われたときに、伝えてよかったなと思える瞬間がきっとあるはずです。
案内状に書き添えるおすすめの一文
はがきを送る場合、もっとも気をつけたいのが「お供え物や香典などはご辞退する」という意思をきちんと伝えること。
これを明記しておかないと、「知らせてきたということは何か送ったほうがいいのかしら」と勘違いさせてしまうこともあります。
人によってはそのことで「催促されたように感じた」と受け取ってしまうこともあるので注意が必要です。
そんなときには、以下のような一文を追記しておくと安心です。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
はがきの文例(家族だけで初盆を行う場合)
このたび ○月○日に 故 ○○○○ の初盆法要を予定しておりますが
誠に勝手ながら ご足労をおかけするのも恐縮に存じ
家族のみで静かに執り行うことといたしました
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
なお 御香典・御供花・御供物等はご辞退させていただきたく存じます
略儀ながら書中をもちましてご報告申し上げます
謹白
令和○年○月
相手のことを想う気持ちと、故人を大切にしたい気持ち。
その両方を言葉に込めて伝えることで、初盆が“心のこもった時間”になると、私は思っています。
大事なのは形式よりも心。
その軸を忘れずにいれば、どんな形の初盆でも、きっと故人に届くのではないでしょうか。
初盆へのお供えをお断りするのは失礼?うまく断る方法はないの?
「香典やお供えはご遠慮ください」と伝えることに、ちょっと躊躇してしまう気持ち、すごくよく分かります。
相手の気持ちを思えば思うほど、そんな風に断ってもいいのだろうか、自分だけ常識外れなことをしているのではないかと、不安になることがありますよね。
私自身も最初は迷いました。
家族だけで静かに送りたいという想いがあった反面、生前お世話になった方々の気持ちを無視するような気がして、罪悪感のようなものを感じていました。
でも、あるとき葬儀社の方に言われたんです。
「最近は、いただかないという選択も珍しくありませんよ。大切なのは、きちんと気持ちを伝えることです」と。
そうなんです。
お供えや香典を断ること自体が失礼なのではなく、それをどう伝えるかが一番大事なんですよね。
香典やお供えをいただくということの意味
香典やお供えには、故人を偲ぶ気持ちと、残された家族への思いやりが込められています。
それはとてもありがたいことですし、決して軽んじてはいけないものだと思います。
でも一方で、受け取る側にも「お返しを準備しなければ」「誰に何を送ったか管理しなければ」といった負担があるのも事実です。
特に高齢の家族や、遠方に住む親戚が多い場合などは、その負担が大きくのしかかることもあります。
だからこそ、最近ではあらかじめ「ご辞退させていただきます」と伝えておくことで、お互いに気を遣わずに済むという考え方が広まりつつあるんです。
辞退を伝えるときは「理由」を添えるとやわらかくなる
断るときって、どうしても言葉が固くなりがちなんですが、ほんの少しだけ気持ちを添えると、相手の受け取り方が全然違ってきます。
たとえば、
「辞退します」ときっぱり言うのではなく、「今回はお気遣いなさいませんよう、お願いいたします」と、お願い口調で伝えるのが、角が立ちにくくておすすめです。
案内状に書き添える丁寧な一文の例
お供え辞退の文言は、案内状の中にさらっと添えるだけで十分です。
強く断る必要はありませんが、「受け取りません」とも書かずに、やさしく包むように伝えることで、相手への敬意も伝わります。
以下のような表現が参考になります。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
「生前故人に賜りましたご厚情に心より御礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げます。」
といった言葉も添えると、形式的ではなく、本当に相手を思っている気持ちが伝わると思います。
辞退しても受け取ってしまったときの対応は?
「辞退していたのに、香典が届いてしまった」「お供えが郵送されてきた」ということもありますよね。
でも、そんなときに「困ったな」「断ったのに」とネガティブに捉える必要はありません。
むしろ、それは故人のことを想ってくれていた証です。
受け取った際には、感謝の気持ちを込めたお礼状と、心ばかりのお返しを送れば大丈夫です。
形式にとらわれすぎず、「ありがたく受け取りました」と素直に伝えることが何よりの礼儀です。
お断り=冷たい ではなく、お断り=心遣い の形もある
「お断りするのは冷たく感じられるかもしれない」そう思う方も多いと思います。
けれど実際には、相手に負担をかけたくないという思いやりが込められている場合がほとんどなんですよね。
私はこの経験を通じて、「お断りすることも、やさしさのひとつなんだな」と思えるようになりました。
もちろん、どのご家庭にも事情がありますし、正解はひとつではありません。
でも、故人を想う気持ちが根っこにあれば、どんな形でもそれはきちんと届くと、私は信じています。
初盆にご仏前だけいただいたとき!失礼のない対応4つのポイント
「今回は家族だけで初盆を行います」と丁寧にお伝えしていたとしても、やはり関係の深かった方や故人を大切に思ってくれた方から、ご仏前をいただくことがあります。
そのとき、戸惑ってしまう方はとても多いと思います。
「断ったのに、どう対応したらいいの?」
「返さなきゃダメ?」
「そもそも受け取っていいの?」
と、心の中が一瞬フリーズしてしまうんですよね。
私も実際そうでした。
案内状で香典辞退の旨を添えていたにもかかわらず、親戚の一人が「気持ちだけでも」と現金書留で送ってくださって。
そのお気持ちが本当にありがたくて、うれしくて、それと同時に「どうしよう、どう返せば失礼じゃないのか」と慌ててしまったんです。
でも結論から言うと、いただいたお気持ちは素直にありがたく受け取って大丈夫です。
そして、受け取ったら「失礼のないかたちで感謝を伝える」ことを意識すれば、それで充分なんです。
① お返しはなるべく早めに!できれば8月中に
ご仏前へのお返しは、法要が終わったあと、できれば8月中に済ませるのが丁寧とされています。
あまり時期を外してしまうと、相手も「あれ、届いてない?」と気にされる場合がありますし、何より早めの対応はあなたの誠意そのものです。
私の場合、お盆が終わって2~3日でお返しの手配を済ませました。
郵送で届いていたものだったので、送り状に記載されていた住所を確認し、礼状と一緒にお返しを送りました。
少し慌ただしかったけれど、「ちゃんとお返しできた」と思えることが、何より自分の心の整理にもつながった気がしています。
② お返しの品は“軽くて日持ちのするもの”を選ぶ
真夏の時期ということもあり、食品などを選ぶときは常温保存ができるものや、相手が好きなタイミングで使えるものを選ぶと安心です。
そうめんやお茶、海苔などの詰め合わせは定番ですが、最近は洗剤セットや入浴剤、タオルギフトなども人気です。
高額なご仏前をいただいた場合には、カタログギフトを選ぶというのもひとつの方法です。
相手に好きなものを選んでもらえるので、気を遣わせすぎず、ちょうどいい距離感で感謝を伝えられます。
大事なのは「無理をしすぎないこと」。
あなたが背伸びせずに贈れる範囲の中で、「気持ち」を込められるものを選ぶことが、いちばんのポイントです。
③ お返しには必ず“お礼状”を添えること
たとえ品物を贈ったとしても、言葉がなければ気持ちは半分しか伝わりません。
だからこそ、お礼状は必須だと思っています。
大げさなものでなくていいので、「無事に法要を終えましたこと」「あたたかいお気持ちに感謝していること」をしっかり伝えることが大切です。
以下のような一文を添えると、温かさが伝わります。
無事に家族での法要を執り行うことができましたことをご報告申し上げます。
皆様のご厚意に心より感謝申し上げます。
④ のしや水引の種類は地域によって異なるため要確認
ご仏前へのお返しには“のし紙”をかけるのが一般的ですが、表書きや水引の色は地域によって微妙に違うため、そこは慎重に確認しましょう。
関東方面では
- 志
- 新盆志
- 初盆供養
水引も、関東では白黒、関西や京都では黄白が使われることがあります。
これを知ったとき、正直「なんでそんなに違うの…」と混乱しました。
でも、こうした違いこそが、それぞれの土地の文化であり、大切にしてきた想いの積み重ねなんですよね。
分からないときは、無理せず近くの葬儀社や仏具店に相談すると、親身になって教えてくれることが多いです。
初盆を家族だけでするとき何と挨拶すればいい?
親戚を呼ばず、家族だけで初盆を行うことを決めたとしても、やっぱり気になるのが「当日の挨拶、何て言えばいいんだろう?」ということ。
形式ばったものが必要なのか、それともカジュアルすぎるとよくないのか、そのさじ加減が分からなくて戸惑ってしまう方も多いと思います。
私も最初は、「せっかく来てくれた家族に何か言わなきゃ」「でも、かしこまった言葉が思いつかない」と、前日の夜に一人でノートを開いて何度も書いては消してを繰り返しました。
でもそのときふと思ったんです。
「故人に向き合う時間を大切にしたいだけなのに、なんでこんなに“正解”を探してるんだろう」って。
そうなんです。
家族だけの初盆なら、何よりも大事なのは“言葉の正しさ”より“想いのこもったやさしさ”だと、私は今なら思えるんです。
家族だけなら挨拶も“シンプル”でいい
堅苦しい挨拶は必要ありません。
相手は気心の知れた家族だからこそ、飾らない言葉で十分です。
たとえば、
「今日はお父さんの初盆だから、みんなで心を込めてお参りしようね。」
それだけでも、ちゃんと“供養の気持ち”は伝わります。
むしろ、無理に背伸びしてしまうより、こうした自然体の言葉のほうが、場の空気もあたたかくなります。
私の家では、こんな風に始めました。
「じゃあ、お線香つけようか。おばあちゃん、帰ってきてるかな。」
それだけで子どもたちも真剣な表情になって、自然と手を合わせる時間が生まれました。
“いつも通り”のようでいて、でもちょっとだけ気持ちを込める。
それが、家族だけで行う初盆のやさしいスタイルなんだと思います。
子どもがいるなら「初盆の意味」を一緒に伝えて
家族に小さなお子さんがいる場合は、初盆の意味をかんたんに伝えてあげるのも素敵です。
子どもにとっては「なぜ今日はおじいちゃんにお線香をあげるの?」と疑問を持つかもしれませんよね。
そんなときは、
「お盆の間は、あの世からおじいちゃんが帰ってくるんだよ。だから一緒に“おかえり”ってしてあげようね。」
こんな感じで伝えてあげると、子どもなりにしっかりと手を合わせてくれます。
そしてそれが、家族全員にとっての“心の節目”になる瞬間になるのです。
形式にとらわれすぎなくて大丈夫です
世の中には、喪主の挨拶の例文や正しい言い回しがたくさん紹介されています。
もちろん、そういうものに頼るのも悪いことではありません。
でも、家族だけで行う初盆ならば、自分たちの気持ちに正直な言葉こそが、いちばん大事だと私は思っています。
何を話してもいい。
何も話さなくてもいい。
ただそこに、故人を想う静かな時間があれば、それが何よりの供養になるはずです。
「立派な言葉が言えないから不安」「何を言えばいいか分からない」と悩むあなたへ。
どうか、正しい言葉を探すよりも、“いま、誰と、どんな想いでここにいるか”を大切にしてみてください。
きっと、あなたらしい初盆の時間が、ゆっくりと流れていきます。
初盆を家族だけでするときには盆提灯や供物は必要なの?
「初盆は家族だけで静かに行いたい」と決めたとき、ふと湧いてくる疑問のひとつが「提灯って必要?お供えってどこまで用意すればいいの?」ということだと思います。
私も、最初はまったく分かりませんでした。
お寺の人も呼ばないし、親戚も来ない。
じゃあ、お飾りや供物まで用意するのって、なんだか大げさすぎる気がする…。
正直、そんなふうに思っていたんです。
でもその一方で、「せっかくあの世から帰ってきてくれるのに、何も用意してなかったら寂しくないかな?」と、ぽつんとした気持ちにもなって。
そう考えているうちに、これは「誰に見せるため」でも「形式を守るため」でもなく、“故人を迎える自分たちの気持ちをどう形にするか”なんだなって気づいたんです。
家族だけでも提灯や供物は準備したほうがいい?
結論から言えば、家族だけで行う初盆でも、できる範囲で提灯や供物を準備するのが望ましいです。
なぜならそれは、故人への「おかえりなさい」のサインでもあり、家族の心の準備にもなるからです。
もちろん「絶対にこうしなければならない」という決まりがあるわけではありません。
でも、
- お線香だけでは少し寂しい気がする
- 仏壇に明かりが灯っていたほうがあたたかい気がする
私の家では、小さな卓上の白提灯と、季節の果物やお菓子をお供えして迎えました。
それだけでも十分に「おばあちゃん、帰ってきてね」という気持ちが伝わった気がしています。
提灯がないとダメ?住宅事情に合わせた選び方でOK
「うちはマンションだから、玄関に吊るすのは難しい」「近所に目立つのがちょっと…」という声も多いですよね。
実際、白提灯を外に飾るのが一般的とされていますが、最近は室内用のコンパクトな提灯やLEDタイプなど、現代の住宅事情に合わせたスタイルのものがたくさん出ています。
室内の窓辺にさりげなく置くだけでも、そこに灯るやさしい光が、まるで「おかえり」を伝えてくれているようで、心がじんわりあたたまります。
形にこだわらなくてもいい。
大事なのは、「帰ってきてね」「ここにいてね」という想いを灯すことなのだと思います。
供物はどこまで?「できる範囲で」で大丈夫
お供え物についても、基本的には通常のお盆と同じように考えれば大丈夫です。
果物やお菓子、ご飯やお茶など、故人が好きだったものを用意してあげると、それだけで供養の気持ちはしっかり伝わります。
「これは必ず準備しなければいけない」と決まっているものはないので、できる範囲で、できる形で、心を込めて準備してあげてください。
我が家では、子どもたちが「おじいちゃん、プリン好きだったよね」と言ってくれて、一緒にコンビニで選んできたプリンを仏壇にお供えしました。
そういう時間も、家族の絆や故人とのつながりを感じる、かけがえのないひとときだったと思います。
初盆をどう迎えるかに、正解も不正解もありません。
人目を気にするのではなく、自分たちの気持ちをどう形にして届けるか、それだけでいいんだと思います。
形式に縛られすぎず、でも“心のこもった準備”ができたとき、きっと故人も「ただいま」と静かに笑ってくれているような、そんな気がします。
まとめ
初盆という節目を迎えるとき、家族だけで静かに過ごしたいという気持ちと、周囲の目やマナーへの不安が入り混じって、心の中が揺れ動くのは自然なことだと思います。
故人を大切に想うからこそ、「失礼になっていないか」「ちゃんと供養になっているか」と悩んでしまうのですよね。
でも本当は、形よりも気持ちが何より大切だということを、私自身も経験を通して実感しました。
家族だけで迎える初盆だからこそ、無理のない範囲で、でもできるだけ丁寧に故人をお迎えすること。
その想いがあれば、十分に立派な供養になりますし、何よりご先祖様も安心して帰ってきてくださるはずです。
また、親戚やお世話になった方々へのご挨拶や心配りも、形式にとらわれることなく、誠実な気持ちを込めて伝えることで、きっと思いは通じると信じています。
これからの人間関係を円滑に保つためにも、必要に応じて事前の連絡やお礼の一言を忘れずに。
そして、なによりも大切なのは、故人との思い出を心に描きながら家族とともに過ごす時間。
そのひとときが、初盆を“あたたかな記憶”として刻んでくれるのだと思います。
どんな形であっても、あなたのやさしい気持ちがしっかり届きますように。