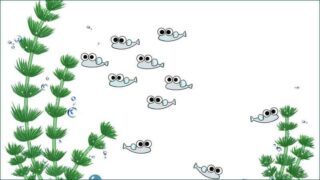 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学 メダカと間違えやすい魚の見分け方と特徴を徹底解説
メダカと似た魚には、オイカワ、カダヤシ、モツゴなどがいます。これらの魚は一見するとメダカにそっくりですが、体の大きさ、ヒレの形、泳ぎ方、生息環境などに違いがあります。例えば、オイカワは成長すると体が大きくなり、オスは繁殖期に鮮やかな色に変化...
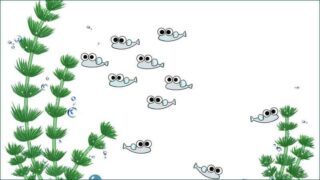 言葉の意味・雑学
言葉の意味・雑学  ペット・生き物
ペット・生き物 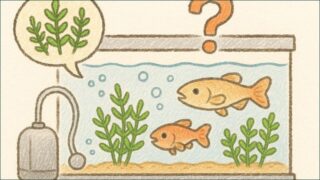 ペット・生き物
ペット・生き物  ペット・生き物
ペット・生き物  ペット・生き物
ペット・生き物 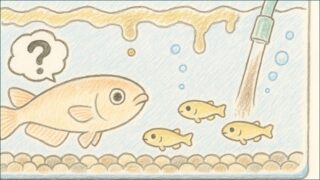 ペット・生き物
ペット・生き物  ペット・生き物
ペット・生き物  仕事
仕事  ペット・生き物
ペット・生き物  ペット・生き物
ペット・生き物