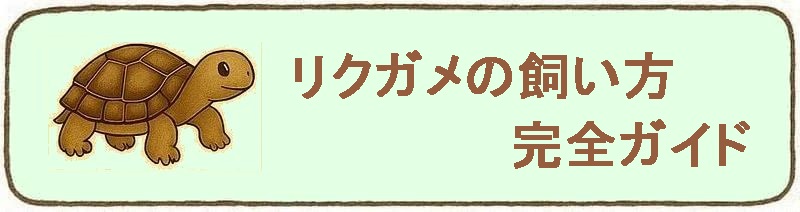リクガメって、本当に不思議な魅力を持っていますよね。
のんびりとした動き、ちょこんとした顔、気ままに日向ぼっこを楽しむ姿。
見ているだけで気持ちがふっと和らいで、「今日もがんばろう」って思えてくる存在です。
そんな癒し系のリクガメですが、一緒に暮らしていると
「この子の体、ちゃんと健康に育ってるのかな?」
「この甲羅、少しやわらかくない?」
「カルシウムってどれくらい必要なの?」
と、ふと不安になることってありませんか?
実は、カルシウムはリクガメの健康を支えるうえで欠かせない栄養素のひとつ。
でもね、これがちょっと繊細で、「あげすぎてもダメ」「少なすぎてもダメ」というなかなか悩ましい存在なんです。
まさに、ちょうどいいバランスが必要な“気まぐれなパズル”みたいなもの。
私も最初は全然わかりませんでした。
「カルシウム=とりあえず多めに!」くらいの感覚でいたら、思ったより体調に変化が出てしまって…。
そこから色々調べたり、先輩飼い主さんたちの声を聞いたり、動物病院の先生に相談したりして、ようやく「なるほど、そういうことか」と腑に落ちたんです。
この記事では、そんな私の失敗談やリアルな学びをぎゅっと詰め込んで。
リクガメにとってのカルシウムの重要性や、正しい与え方・頻度について、やさしく、でもちょっと熱を込めてお話ししていきます。
「この子にずっと元気でいてほしい」そんな思いに寄り添える記事になれたら嬉しいです。
リクガメにカルシウムはなぜ必要?
カルシウムは甲羅と骨をつくる大事な栄養素
リクガメにとってのカルシウムは、人間でいうと「骨の基礎」。
体の骨格だけでなく、あの特徴的な甲羅もカルシウムが材料となって形成されます。
だからこそ、しっかりとしたカルシウム補給がないと、見た目だけではなく内部から健康を損なってしまうんです。
私も以前、カルシウム不足が原因で、甲羅の表面が少し波打ってしまった子を育てた経験があります。
写真で見るとわかりづらいけれど、触ってみると「あれ?なんだか柔らかいような…?」という違和感。
それを感じた瞬間、「これはマズいかも」と焦ったのを今でも覚えています。
その子はすぐに食事の見直しと環境改善をして、なんとか持ち直してくれました。
ですが、「ちゃんとした知識を持っていたら、あんな思いをさせなくてすんだのに…」という後悔が、今でも私の中に残っています。
カルシウム不足が引き起こす「くる病」とは?
カルシウムが足りないと、リクガメは「くる病」と呼ばれる状態になる可能性があります。
これは、骨や甲羅の形成不良を起こし、見た目にも体内的にも深刻なダメージが出る怖い病気です。
くる病になると、甲羅が柔らかくなる、骨が変形する、体のバランスが悪くなって歩き方がおかしくなる…など、様々な症状が現れます。
特に成長期のベビーリクガメは、体のあらゆる部分が急激に成長するタイミング。
栄養が足りなければ、ダイレクトに健康を損ねてしまうんです。
人間の赤ちゃんが栄養不足で骨が脆くなるのと、まったく同じようなイメージです。
「小さいから大丈夫」ではなく、「小さいからこそ大事」なんですね。
成長期のリクガメには特に重要!
カルシウムの重要性は、成長期のリクガメにとっては生命線のようなもの。
ベビーやヤングサイズのうちは骨格も甲羅もまだ未完成で、これからしっかりと育てていく時期。
その時に栄養が足りていないと、大人になってからもその影響を引きずることになってしまいます。
私が信頼している獣医さんが言っていました。
「成長期にどんな栄養を与えるかで、リクガメの将来が変わる」って。
本当にその通りだと思います。
カルシウムパウダーを与えることは、単なる栄養補助ではなく「この子の将来の土台をつくる」行為。
今あげる一匙が、未来の健康を支えると考えると、なんだか胸が熱くなりませんか?
未来の元気な姿を思い浮かべながら、今できることを一つずつしていきたいですね。
カルシウムパウダーの与え方と頻度は?
基本は「週2~3回」が目安!年齢や種類で変わる
カルシウムパウダーの与え方、気になりますよね。
これはリクガメの健康を左右する大切なポイントなので、飼い主としてはしっかり押さえておきたいところです。
基本的な目安としては、以下のように考えられています。
ベビー~ヤング
週2~3回が理想的。
体が成長していく大事な時期なので、こまめな補給が必要です。
アダルト
週1~2回でOK。
成長が落ち着いてくる分、過剰にならないように抑えめにします。
ただし、この頻度はあくまで目安であり、万能な正解ではありません。
リクガメの種類(ヘルマン、ギリシャ、ホルスなど)
- 飼育環境
- 紫外線の当たり具合
- 食べている野菜の種類
たとえば、うちの子はUVBライトをしっかり使っていたこともあって吸収効率が良く、成長がかなり早かったタイプ。
そのため、週3回きっちり与えることで甲羅の硬さや体調の安定が保てていました。
逆に、知人のリクガメはあまり食が進まない子だったので、少しずつ調整しながら週2回ペースで落ち着いたそうです。
大切なのは、「回数だけに頼らず、リクガメの反応を見ながら調整する」こと。
飼い主さんの観察力が一番の目安になると、私は思っています。
毎日あげてもいい?与えすぎによる悪影響
「心配だから毎日あげたほうがいいかな?」という気持ち、すっごくよくわかります。
私も飼い始めの頃は、「ちょっとでも不足していたら大変かも」と不安で、ついつい毎日のようにふりかけてしまっていました。
でも、実はそれが“やさしさの落とし穴”になってしまうんです。
というのも、カルシウムの与えすぎは腎臓にかなりの負担をかける可能性があるからです。
体の中で使われなかったカルシウムは、血液中に残りやすくなり、結果として結石(尿路結石など)の原因になったり、内臓に負担をかけたりしてしまいます。
実際に、毎日カルシウムをあげていた飼い主さんが
「おしっこの色が濃くなった」
「尿の回数が減った」
と異変に気づき、病院で診てもらったら腎臓に炎症が出ていた…という話を聞いたこともあります。
もちろんすべてがカルシウムのせいとは限りませんが、「健康のため」が「健康を損なうきっかけ」になるなんて、切ないですよね。
「よかれと思ってやっていたことが裏目に出る」って、すごくつらい。
だからこそ、適切な頻度で、必要な量だけを与えることが一番の愛情なんだと思います。
迷ったときは、あげる前に一呼吸おいて、「本当に今日も必要かな?」と自分に問いかけてみるといいかもしれません。
焦らず、過不足なく、コツコツ続けていくのが、リクガメとの長いおつきあいでは何より大切な姿勢です。
与えるタイミングと注意点(エサの直前が効果的)
カルシウムパウダーは、エサにまぶしてすぐ与えるのがベストです。
時間が経つと、パウダーが野菜から浮いてしまって粉が飛び散ったり、見た目が変わってリクガメが警戒して食べてくれなかったりすることがあります。
特に匂いに敏感な子は、ちょっとした違いに気づいて食欲をなくしてしまうこともあるんです。
私が以前飼っていた子もそうでした。
最初は先に餌にふりかけてからしばらく他の準備をしていたのですが、時間が経つとパウダーが乾いてしまって、まるで粉雪のように舞い上がってしまうんです。
そのせいか、食べるのをためらってしまうことが何度かありました。
それ以来、エサ皿に野菜をセットしたら、最後の仕上げにパウダーをさっと振りかけて、すぐにケージに入れるようにしています。
まるで料理の盛り付けのような感覚ですが、このちょっとした“ひと手間”が、リクガメの食いつきを全然変えてくれるんですよね。
また、粉が舞わないようにするために、野菜を少し湿らせてからふりかけるという方法もあります。
霧吹きで軽く湿らせてから使うと、パウダーがしっかり絡んでくれて、リクガメも違和感なく食べてくれます。
もちろん、水っぽくしすぎないように注意してくださいね。
そしてもうひとつ大事なポイントは、ふりかけすぎないこと。
白くコーティングされるほどたっぷりまぶしてしまうと、逆にエサそのものの香りが隠れてしまって、リクガメが食べるのを嫌がることもあります。
あくまで“うっすら”がベスト。
軽くまぶす程度に留めて、リクガメにとって自然な食事になるよう意識してみましょう。
カルシウムパウダーはどんな種類を選べばいい?
リンとのバランスが大事(Ca:P比)
カルシウムを与えるうえで、まず最初に気をつけたいのがカルシウムとリンのバランスです。
理想的な比率は2:1、つまりカルシウム2に対してリンが1。
これが崩れると、いくらカルシウムを与えても、うまく体内に吸収されなかったり、逆にカルシウムが骨に沈着せず排出されてしまったりします。
特にリンが多いと、カルシウムの吸収を邪魔するどころか、骨からカルシウムが溶け出してしまうこともあるんです。
怖いですよね。
実際に、野菜だけで育てているリクガメでは、リンが多めになりがちで、気づかないうちにCa:Pバランスが崩れてしまうことがあります。
だからこそ、パウダーの選び方が大切なんです。
市販のカルシウムパウダーには、このCa:P比を意識して調整されているものが多くあります。
購入する際は、成分表示や商品説明をしっかり確認して、適切なバランスの商品を選ぶようにしましょう。
D3入りかどうかだけでなく、リンの量もしっかり見てあげると安心です。
紫外線ライトとセットで使おう(ビタミンD3との関係)
カルシウムの吸収に欠かせないもの、それがビタミンD3。
この栄養素が体内にあることで、カルシウムはきちんと骨や甲羅に取り込まれるのですが。
リクガメ自身はビタミンD3を紫外線(UVB)を浴びることで合成する仕組みになっています。
つまり、どんなに高品質なカルシウムパウダーを与えても、紫外線ライトがないとその効果は半減してしまうというわけです。
特に屋内飼育では、太陽光が直接当たらないため、UVBライトは必須アイテム。
昼間の時間帯にしっかり照射して、D3が体内で合成されるようにしてあげましょう。
また、UVBライトを使用している場合は、D3入りのカルシウムパウダーを毎回使う必要はありません。
逆にD3の摂りすぎも体に悪影響を及ぼすため、D3入りとD3なしを交互に使う、あるいは週1だけD3入りにするなど、使い分けるのもおすすめです。
こうした知識を持っていると、飼育の安心感もぐんと増しますよ。
おすすめのカルシウムパウダー商品3選
私が使ってよかったものを、特徴と一緒にもう少し詳しく紹介しますね。
どれも初心者さんからベテランさんまで幅広く支持されている商品です。
Repti Calcium(ビタミンD3入り)
白くてきめ細かい粉状で、エサにふりかけてもなじみやすく、リクガメも違和感なく食べてくれます。
特にビタミンD3が入っているので、UVBライトをあまり使えていない環境や、まだ飼育環境が整いきっていない初心者さんには心強い味方になります。
![]() 「Repti Calcium(ビタミンD3入り)」の詳細を見てみる【楽天市場】
「Repti Calcium(ビタミンD3入り)」の詳細を見てみる【楽天市場】
Zoo Med カルシウムパウダー(D3なし)
天然素材にこだわっていて、無添加・無着色。
食材に混ぜたときのにおいも控えめで、リクガメの食欲を邪魔しにくいのが特長です。
日常的に紫外線ライトをしっかり使っている飼育スタイルの方におすすめです。
![]() 「Zoo Med カルシウムパウダー」の詳細を見てみる【楽天市場】
「Zoo Med カルシウムパウダー」の詳細を見てみる【楽天市場】
マルベリーカルシウム
桑の葉(マルベリー)パウダーをたっぷり使用していて、カルシウムに加えて
- 鉄
- ナトリウム
- カリウム
- 天然β?カロテン
- ビタミンA・B群・C・E・K?
- ニコチン酸
- クエン酸
- クロレラ
- 食物繊維
- トレハロース
日本国内で製造されているため、品質や安全性にこだわる飼い主さんにも安心ですね。
ちなみに我が家では、このマルベリーカルシウムを愛用しています♪
D3入り・なしの両方タイプがあるので、環境に合わせて使い分けしやすいのも魅力です。
どの商品も「D3あり/なし」のバリエーションが用意されているので、紫外線ライトの設置状況やリクガメの体調、年齢に合わせて選ぶことがポイントです。
また、どれか一つに絞るのではなく、飼育環境やリクガメの様子を見ながら、D3ありとなしを状況に応じて併用するスタイルもおすすめ。
上手に使い分けることで、リクガメの健康維持にしっかりと役立ってくれますよ。
カルシウムが足りているかの見極め方は?
甲羅の硬さ・ツヤ・成長具合をチェック
カルシウムが足りているかどうかは、甲羅の状態を見ればだいたいわかります。
観察すべきポイントは、
- ツヤがあるか(くすんでいないか)
- 凹みや変形がないか(特に背中の中央や周囲)
- 手で軽く押しても硬いか(柔らかく沈むようなら要注意)
よく見ると表面に少しザラつきがあって、「あれ?前はもうちょっとツヤがあったような…?」と気になり、カルシウムの量を見直してみたんです。
すると、数週間後にはだんだんツヤが戻ってきて、見た目も手触りも改善しました。
特に成長期の子ガメは、変化が早いぶんちょっとした違和感が「見逃したサイン」になりがち。
定期的に写真を撮っておいて、以前との比較をしてみるのもおすすめです。
視覚的に変化がわかると、判断材料になりますよ。
うんちや食欲の変化もヒントになる
「最近うんちが小さめかも…」「なんだか食が細い?」という時は、カルシウム不足のサインである可能性も。
特に便の量や形状の変化、そして食欲の有無は体内バランスを反映しやすい指標です。
カルシウムが不足すると、筋肉の収縮や消化活動にも影響を及ぼし、結果として便秘気味になったり、食べる量が落ちてしまうこともあります。
実際に「なんとなく元気がないなあ…」と感じた子が、カルシウムを補うことで徐々に食欲が戻ってきたというケースもあります。
カメって本当に我慢強い生き物なので、こちらが思っているよりもずっと静かに、じっと不調に耐えていることがあります。
だからこそ、小さな変化にも敏感に気づいてあげられる飼い主の観察力が重要なんです。
心配なときは動物病院で血液検査も視野に
「なんとなく元気がない」「成長が止まっている気がする」「甲羅が柔らかいような…」そんな時は、迷わず動物病院に相談しましょう。
特に、定期的な健康診断や血液検査は、見た目だけではわからないカルシウムの血中濃度や、腎臓・肝臓の状態を把握する手がかりになります。
私も一度、「念のため」で受けた血液検査でカルシウム値がぎりぎりのラインだったことがありました。
まだ明確な症状が出ていないうちに気づけたことで、生活環境を見直したり、与える頻度を調整したりといった対策ができました。
病院というと構えてしまいがちですが、「未然に防ぐ」ことこそが本当のケア。
ちょっとした不安の積み重ねこそが、プロに聞くべきサインかもしれません。
失敗しないためのQ&A|飼い主のよくある疑問に回答!
Q. 毎日あげたら甲羅がゴツゴツに?
はい、これは実際によくあるケースです。
カルシウムの与えすぎによって、甲羅が不自然に盛り上がってしまったり、全体がゴツゴツとした質感になってしまうこともあるんです。
過剰なカルシウム摂取は「代謝性骨疾患(MBD)」の一因になることもあり、決して安全とは言えません。
だからこそ、「健康のために」と思って多めにあげるのではなく、あくまで“適量”を守ることがポイントです。
控えめがちょうどいい。
それが、リクガメとの信頼関係にもつながっていくんですよ。
Q. 野菜だけの餌でもカルシウムは足りる?
実は、これも非常に多い勘違いのひとつ。
私たちが「健康的」と思ってあげている野菜ですが、実際にはカルシウム含有量が不十分なものが多いんです。
特にキュウリやレタスなど水分の多い野菜は、栄養価が低く、カルシウムもほんのわずかしか含まれていません。
さらに、リンを多く含む野菜(例:トマト、キャベツなど)ばかりを与えていると、体内のCa:Pバランスが崩れ、カルシウム不足を引き起こしやすくなります。
だからこそ、カルシウムパウダーによる補助がとても大切なんです。
野菜はあくまで“土台”。
そこに、カルシウムパウダーという“サポート役”をうまく組み合わせることで、初めてバランスのとれた食事になりますよ。
Q. パウダーをかけても食べてくれません…
これ、実は多くの飼い主さんが直面する問題なんです。
せっかく健康のためにふりかけたのに、そっぽを向かれてしまったら、ちょっと切なくなりますよね。
そんな時は、エサの選び方やパウダーのまぶし方を少し変えてみると効果的です。
たとえば、葉野菜を軽く湿らせてからパウダーをふりかけると、粉がしっかり絡んで落ちにくくなりますし、リクガメも違和感なく口にしてくれることが増えます。
また、うちでは果物(バナナやリンゴ)にごく少量ふりかけて与えたところ、最初は抵抗があった子でも自然と食べてくれるようになりました。
ただし、果物は糖分が多いので与えすぎ注意。
あくまで“カルシウム導入のきっかけ”として、少量をたまに使う程度にしましょう。
リクガメにも好みがあります。
試行錯誤を重ねながら、「この子にはこれが合う」という方法を見つけられたときの喜びは、何ものにも代えがたいですよ。
まとめ|リクガメに必要なカルシウム、焦らずコツコツ補おう
カルシウムパウダーは、リクガメの健康と成長を支える「縁の下の力持ち」みたいな存在。
だけど、やりすぎは禁物です。
どんなに体に良いものでも、バランスが崩れるとリスクに変わる。
だからこそ、与える頻度や使い方をしっかり守って、毎日の食事にほんのちょっとの愛情とひと工夫を添えてあげることが、何よりも大切なんです。
「これで本当に大丈夫かな…」「ちゃんと吸収されているのかな?」と心配になることもあるかもしれません。
でも、そんなふうに悩みながらも、丁寧に向き合おうとしている時点で、もうあなたは立派なリクガメのパートナーです。
知識を得ようとしていること。
食べる様子を観察して工夫しようとしていること。
それって、リクガメにとっては本当に幸せなことなんだと思います。
焦らず、コツコツ。
迷ったときはこの記事を読み返して、「今できること」を少しずつ重ねていけば大丈夫。
小さな命に寄り添うこの時間は、リクガメだけでなく、あなた自身の心も優しく整えてくれる時間になるはずです。
これからも、リクガメとの暮らしをのんびり楽しみながら、ゆっくり一緒に歩んでいけますように。