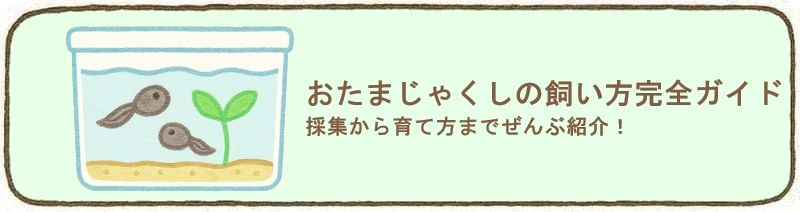春の終わりから夏の初めにかけて、田んぼや池などでよく見かける「おたまじゃくし」。
ふよふよと泳ぐ姿が可愛らしく、比較的簡単に捕まえられる事から、捕まえて遊ぶ子供も多いですね。
そんな「おたまじゃくし」ですが、飼育すときには”ブクブク”こと「エアレーション」って、必要なんでしょうか?
おたまじゃくしって基本、水の中で暮らしているから必要そうでああるけれど、足が生えてきたら水の外に出てくるイメージもあるし。
まず、おたまじゃくしはエラ呼吸と肺呼吸、両方することができるんです!
ということは、ブクブクがなくても、水の中の酸素量が少なくなってきたら、水の外に出てきてから肺呼吸をする回数が増えるだけのことなんです。
なので、オタマジャクシを飼うときには「ブクブクは無くても大丈夫」ですよ。
もちろんブクブクがあっても大丈夫だけど、おたまじゃくしの負担にならないようにブクブクは弱めにしてしておくようにしましょう。
オタマジャクシは、キッチンで使う「おたま」、じゃなくて「玉杓子(たまじゃくし)」に似ていることから名前が付いたと言われています。
ご存知の通り、おたまじゃくしはカエルの子供です。
カエルの種類や孵化してからの期間によって、5ミリ程度のものから5センチ以上の大きなものもいます。
カエルは両生類ですが、オタマジャクシでいる時期は魚類かと思えるくらいカエルの形を想像させません。
やがて足が生え、尻尾が体に吸収されて無くなってゆき、陸に上がります。
このように生体の変化が目に見えて分かる事から、自由研究の題材にするケースも多いようです。
今回は、そんな「おたまじゃくし」を家で買うための環境や飼育方法について、そのポイントをお伝えしていきますね!
おたまじゃくしの飼育環境!水槽・ケース選びのコツ
おたまじゃくしの飼い方は、実はとてもシンプルで、誰にでも取り組みやすいものです。
特別な設備や高価な道具を揃える必要もなく、身近なもので十分に飼育をスタートできます。
もちろん、生き物を育てる以上、最低限のポイントを押さえておくことは大切ですが、それさえ理解すれば、あとは楽しみながらお世話を続けられますよ。
初心者の方でも失敗しにくく、成長の様子を観察できる楽しみもあるので、子供の自由研究や家庭での小さな生き物飼育にぴったりです。
気になるポイントごとに、わかりやすくまとめてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
おたまじゃくし飼育ケースの選び方|タライや虫かごでもOK
水槽でも虫かごでも、なんだったらタライでも問題ありません。
プラスチック製のケースやガラス製の水槽、または身近な家庭用品を活用しても十分に飼育できます。
特別に高価な飼育セットを用意する必要はありませんし、むしろシンプルな容器のほうが管理がしやすいです。
広さはおたまじゃくしの数にもよりますが、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。
おたまじゃくし同士がぎゅうぎゅう詰めにならない程度の広さがあれば十分で、多少狭くても問題なく育ってくれます。
数が多い場合は、ケースを分けて複数にするのもおすすめです。
100円ショップで手に入るような、虫かごやタッパーなどでも飼育可能です。
むしろ軽くて取り扱いやすいため、水替えや掃除が楽にできるというメリットもあります。
透明な容器なら観察もしやすく、成長の様子をじっくり楽しむことができますよ。
おたまじゃくし飼育にフタは必要?注意点を解説
おたまじゃくしのうちは、基本的にフタがなくても大丈夫です。
おたまじゃくしは水中で過ごすため、飛び出してしまう心配もほとんどありません。
風通しもよくなり、空気の流れがスムーズになるので、むしろフタがない方が快適に過ごせることもあります。
ただし、おたまじゃくしが成長してカエルに変態し始めると、状況は一変します。
カエルは活発に動き回るため、容器から脱走してしまう可能性が高まります。
そのため、カエルになったときのために、フタ付きの虫かごや水槽を用意しておくのが安心です。
タライなどで飼育している場合は、ホームセンターなどで売っている網や、適度な通気性のあるカバーをかぶせると良いでしょう。
しっかりと脱走防止対策をして、安心して飼育を続けられるように準備しておきましょう。
おたまじゃくしに適した水の深さとは?
水位は、そんなに高くなくてOKです。
むしろ浅めにしておく方が、おたまじゃくしにとって安心できる環境になります。
深すぎると水圧の影響で体に負担がかかったり、底に沈んで動きにくくなったりすることもあるため注意が必要です。
目安としては3センチもあれば十分でしょう。
特にまだ小さいおたまじゃくしの場合は、浅い水深のほうが泳ぎやすく、餌にもすぐにアクセスできるため、成長にも好影響を与えます。
おたまじゃくしが泳いでいるような「田んぼの水位」をイメージしてみると分かりやすいですね。
自然界では浅い水たまりや田んぼで生活しているため、それに近い環境を作ってあげるのが理想的です。
おたまじゃくし飼育容器に石を置く理由とは?
容器内には、水面からはみ出るくらいの、ちょっと大きめの石などを置きましょう。
これは、カエルになったときに簡単にのぼれる場所を確保してあげるためです。
カエルは変態後、水中だけでなく陸地にも上がって生活するようになります。
そのため、自然に近い環境を作ることがとても大切です。
また、砂利や土などを使って傾斜をつけて陸地を作ってあげると、より自然な移動ができるようになり、成長にも好影響を与えます。
石だけでなく、木の枝や流木などを配置してあげても良いでしょう。
これにより、隠れ家になったり、休憩する場所にもなります。
陸地部分はしっかり固定しておくと、おたまじゃくしやカエルが動いても倒れにくく、安心して使用できますよ。
水草を使ったおたまじゃくし飼育のメリット
水草や流木を入れておくと、なお良いですね。
見た目が自然な雰囲気になるだけでなく、おたまじゃくしにとっても過ごしやすい環境を作ることができます。
水草は水中の酸素を供給してくれるため、水質が安定しやすくなります。
また、流木も水に溶け出す成分によって水質を緩やかに調整する役割を果たします。
こうした自然のアイテムを取り入れることで、人工的な環境よりも生き物にとって負担が少ない、快適な住みかになります。
さらに、おたまじゃくしが水草を食べることで、栄養補給にもなり、健康的な成長を促すことができます。
隠れ場所にもなるため、ストレスの軽減にもつながりますよ。
できれば複数種類の水草を用意すると、よりバランスのとれた環境を作ることができておすすめです。
おたまじゃくしの水替え頻度とやり方のコツ
水替えは、最低でも4~5日に1回は行うようにしましょう。
水の汚れ具合やおたまじゃくしの数によっては、さらに頻度を増やしてあげると、より快適な環境を保てます。
水替えの際は、すべてを一気に入れ替えるのではなく、全体の半分程度を目安に新しい水を注ぎ足していきます。
この方法なら、水質の急激な変化を防ぐことができ、おたまじゃくしにも優しいです。
また、新たに使用する水については、必ず水道水の塩素を抜いてから使いましょう。
バケツや容器に水を汲み置きし、最低でも1日以上は放置して塩素を飛ばします。
可能であれば2~3日置いておくと、さらに安心です。
塩素を含んだ水はおたまじゃくしにとって有害なので、ちょっとした手間ですがとても大切なポイントです。
おたまじゃくしの飼育場所は日陰がベスト
直射日光は避けて飼育しましょう。
特に夏場は、強い日差しによって水温が急激に上昇しやすく、おたまじゃくしにとって過酷な環境になってしまう恐れがあります。
水温の急変は体調不良や命にかかわるリスクにもつながるため、日陰や風通しの良い涼しい場所に置くことが大切です。
また、室内で飼育する場合も、窓辺の直射日光が当たる位置は避けて、カーテン越しの柔らかい光が当たるくらいの場所を選ぶと安心です。
さらに、必要に応じて遮光ネットやすだれなどを活用し、日差しをコントロールしてあげると良いでしょう。
おたまじゃくしにエアレーションは必要ない?
最初にお話ししたように、「エアレーション」、つまり酸素補給用のブクブクは、基本的に無くても問題ありません。
おたまじゃくしはエラ呼吸と肺呼吸の両方を使えるため、水中の酸素が多少少なくなっても、自力で環境に適応することができるからです。
自然界の田んぼや小川のような場所にもエアレーション装置はありませんが、おたまじゃくしは元気に育っていますよね。
このため、家庭で飼う際にも、エアレーションは必須ではないと考えてOKです。
とはいえ、水槽の水量が多かったり、気温が高くて酸素が水中に溶け込みにくい場合には、軽くエアレーションを加えると安心です。
ただし注意したいのは、エアレーションを強くしすぎると水流ができ、おたまじゃくしが体力を消耗してしまう点です。
そのため、もし取り付ける場合でも、泡がほんのりポコポコと上がる程度の、弱め設定にしておくのが理想的です。
必要に応じて使い分けることで、より快適な飼育環境を整えられますよ。
おたまじゃくし飼育にろ過装置を使ってはいけない理由
ろ過装置や水流はつけないでください。
おたまじゃくしは非常に体が小さく、泳ぐ力もあまり強くありません。
そのため、ろ過装置によって生まれる水流に常に逆らって泳ぎ続ける必要があると、短時間で体力を消耗してしまいます。
結果として、弱ってしまったり、最悪の場合命に関わることもあるのです。
さらに、水流が強いと餌が流されやすくなり、十分に餌を食べられなくなってしまう恐れもあります。
これは栄養不足や成長不良につながる大きなリスクです。
自然界のおたまじゃくしは、流れのない池や田んぼなど、穏やかな水場で育っています。
家庭で飼う場合も、できるだけ自然に近い静かな水環境を作ってあげることが重要です。
そのため、ろ過装置は使わず、こまめな水替えで水質を維持する方法が最も安全でおたまじゃくしに優しい飼育スタイルといえますよ。
おたまじゃくしの餌は何でもOK?雑食の特徴
下記でご紹介しますが、おたまじゃくしは雑食です。
野菜や動物性の餌など、幅広い種類のものを食べるため、餌の用意もそこまで難しくありません。
成長に合わせた適切な餌を与えることで、健康的に育てることができます。
文章にすると長くなりますが、実際にやってみると驚くほど簡単です。
特別なテクニックや技術は必要なく、誰でもすぐに取り組める飼育方法ですよ。
通常、水中で生きるほとんどの生き物には
- エアレーション(酸素供給装置)
- ろ過装置(水質浄化装置)
- ヒーター(水温調整器)
浅い水とちょっとした工夫さえあれば、快適な飼育環境を整えることができます。
色々な生き物をこれまでに飼ってきた性分の私にとっても、おたまじゃくしの飼育は本当に楽で、これ以上ないくらい気軽な楽しみ方だと感じています。
初心者にもぜひおすすめしたい生き物です。
おたまじゃくしの餌やり方法|おすすめの食べ物とは?
先ほど記述した通り、おたまじゃくしは雑食です。
基本的になんでも食べるため、餌の準備にそこまで神経質になる必要はありません。
例えば、小松菜をちぎって入れたり、煮干しを小さく砕いて与えたりするだけで、いつの間にかかじって食べてくれます。
さらに、ごはん粒やパンくずなども好んで食べるので、家庭にある食材で簡単に対応できるのが嬉しいポイントです。
試しにレタスやほうれん草などの葉物野菜を少しだけ与えてみるのもおすすめです。
季節や体調によって好みが変わることもあるので、様子を見ながら餌を調整してみましょう。
これらの餌を準備するのが難しいときには、市販の金魚の餌でも十分対応できます。
特に、溶けて柔らかくなりやすいものや、小さな粒のタイプを選んであげると食べやすくて安心です。
水に少しふやかして与えると、おたまじゃくしにも優しいですよ。
おたまじゃくしは一度にたくさんの餌を食べることができないため、1日に2回、朝と夕方に少量ずつ与えるのが理想的です。
様子を見て、元気に餌を食べているようなら、少し量を増やしても構いません。
ただし、餌を入れすぎるとすぐに水が汚れてしまい、病気の原因になるので要注意です。
餌の食べ残しがあれば早めに取り除き、常に清潔な環境を保つことを意識しましょう。
こうしてお世話していると、1~2ヵ月ほどでおたまじゃくしは成長し、やがてカエルへと変態していきます。
毎日少しずつ変わっていく姿を観察できるのは、本当に楽しく貴重な経験になりますよ!
カエルへの成長後も安心!おたまじゃくし飼育まとめ
カエルになったら飼い方や餌の種類も大きく変わってきます。
水中生活をしていたおたまじゃくし時代とは異なり、カエルは基本的に陸上で過ごす時間が長くなります。
そのため、飼育環境も水場中心から陸地を多く含むものへと整える必要が出てきます。
さらに、餌も水中で食べやすいものから、昆虫類などの動く獲物を中心としたものへとシフトしていきます。
なので、カエルになっても飼育を続ける場合は、しっかりとカエル用の飼い方や餌について情報を集めておきましょう。
成長段階に合わせた適切な環境作りと食事管理を行うことで、カエルも元気に長生きできるようになります。
これまでとは違う新しい飼育の楽しみが始まりますよ!