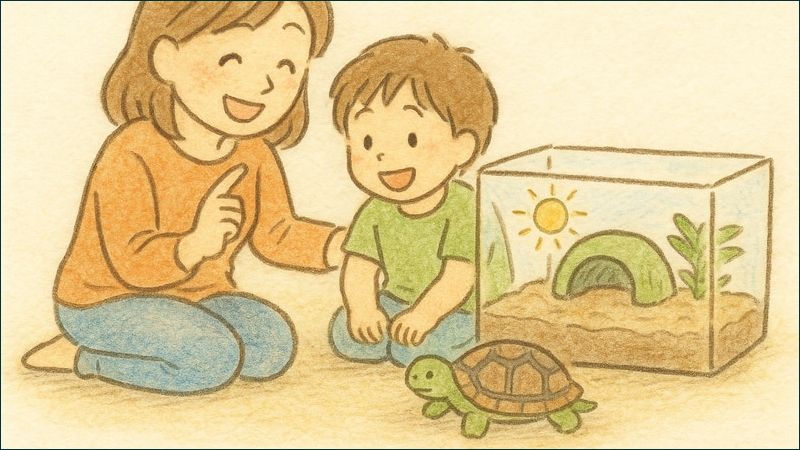「ねえママ、カメさんって一緒に暮らせるのかな?」
そんな息子の一言がきっかけで、私たち家族の新しい暮らしが始まりました。
正直、最初はびっくりしましたし、「カメって家で飼えるの?」「お世話って大変なんじゃないの?」という不安もたくさんありました。
でも、少しずつ調べていくうちに、リクガメという存在が、思っていた以上に穏やかで、家庭でも無理なくお世話できることを知ったんです。
子どもが小さいうちは、生き物との距離感や安全面もとても気になりますよね。
だからこそ、リクガメの性格や習性、どんなふうに関わっていけるかを、しっかり知った上で迎えることが大切なんだと感じました。
この記事では、リクガメ初心者の私が実際に体験したことをもとに、子育て家庭で安心して飼える種類や、安全に楽しむための工夫。
そして命と向き合う時間のあたたかさまで、やさしくていねいにお伝えしていきますね。
子どもとリクガメは相性がいい?家庭で迎える前に知りたいこと
子どもとリクガメの暮らしって、実際どうなんだろうと最初は不安もありました。
でも、一緒に過ごしていくうちに「ゆっくり動くこの子たちだからこそ、子どもの成長に寄り添ってくれるんだな」と感じる場面がいくつもありました。
とはいえ、生き物との暮らしには安心して向き合うための知識も必要で、親がしっかり理解しておくことで子どもちもリクガメも心地よく過ごせる環境が作れていくんですね。
ここでは、迎える前に知っておくと安心できるポイントを丁寧にまとめていきます。
リクガメの性格はとても穏やかで“子どもが怖がりにくい”
リクガメの最大の特徴は、その穏やかで落ち着いた性格です。
基本的にはゆっくり歩き、突然跳びかかったりせず、鳴いたり吠えたりもしません。
動きが予想しやすいので、小さな子でも安心して観察できるんですね。
生き物が少し苦手な子でも、「あ、動いた」「こっち見たかも」と少しずつ距離を縮められるのもリクガメならではです。
私の子どもも最初は遠巻きに眺めるだけでしたが、この落ち着いた動きのおかげで自然と近づけるようになりました。
子どもの好奇心は止められないからこそ“大人の見守り”が大事
一方で、幼児期の子どもはどうしても触ってみたくなるものです。
甲羅を触りたくなったり、持ち上げようとしたりと本人は遊んでいるつもりでも、リクガメにとっては驚く行動になってしまうことがあります。
我が家でも何度かヒヤッとする瞬間があって、そのたびに「今のびっくりしちゃったね」「どう触ったら優しいかな」と声をかけて一緒に考える時間を作っていました。
こうした“見守り”は、子どもを守るためだけでなく、リクガメのストレスを減らし、安心して暮らせる環境づくりにもつながるんですね。
年齢別に見る“どこまでできるか”の目安
リクガメのお世話を子どもと一緒に楽しめるようになるのは、目安として3~4歳頃からです。
この頃になると、目の前の生き物が「おもちゃではなく命なんだ」という感覚が少しずつ育っていきます。
「これ触ってもいい?」「お水あげてもいい?」と、自分で確認する姿が出てくると、こちらも任せやすくなっていきます。
もちろんエサやりや掃除などのメインのお世話はまだ大人の役目になりますが、観察したり、声をかけたり、簡単なお手伝いをするだけでも立派な関わりになります。
その“できること”が少しずつ増えていく過程を見ると、生き物との暮らしが子どもの成長にも寄り添っていることを実感できます。
家族で暮らすためには“安全と衛生”を最初に整えておこう
子どもとリクガメの暮らしを安心して楽しむためには、日常の衛生面や安全面を整えることがとても大切です。
リクガメは穏やかでも、指先をエサと勘違いして軽く噛んでしまうこともありますし、爬虫類には特有の衛生リスクもあります。
だからこそ、
「触ったら手を洗う」
「エサはトングを使う」
「勝手に持ち上げない」
など、家庭でのルールを先に決めておくと安心です。
こうしたルール作りは、子どもが命を大切に扱う姿勢を身につけるきっかけにもなります。
子育て家庭に向いているリクガメの種類と選び方
リクガメを飼うことに興味はあっても、「どの種類を選べばいいの?」というのは多くの人が最初に感じる悩みだと思います。
特に子どもと一緒に暮らす家庭では、性格や大きさ、飼いやすさといった観点から慎重に選ぶことが大切です。
ここでは、初心者でも安心して迎えられて、子どもとの日々にも寄り添ってくれるリクガメたちの特徴をわかりやすく紹介していきますね。
ヘルマンリクガメ|人懐っこくて家族になじみやすい
「えっ、カメってこんなに懐くの?」と驚かされたのがヘルマンリクガメでした。
リクガメというと無口でマイペースな印象がありますが、この子たちは人の気配に敏感で、足音がすればトコトコと寄ってくることもあります。
特にエサの時間には、首を伸ばしてこちらをじーっと見上げてくれる姿に、我が家の子どももすっかり夢中に。
見た目の可愛らしさも抜群で、くっきりとした甲羅の模様は見ていて飽きません。
成長しても20cm前後と比較的小型なので、限られたスペースでも飼育しやすく、マンション暮らしの家庭にもぴったりです。
性格も明るく、まさに「初めてのリクガメ」としておすすめしたい存在です。
ギリシャリクガメ|落ち着いた性格で観察が楽しい
ヘルマンよりもややおっとりとした印象のギリシャリクガメは、リクガメらしい「のんびり感」が際立つ存在です。
じっと同じ場所にとどまっていることも多く、子どもが観察しやすいという点でも魅力的。
刺激に対して過剰に反応せず、そっとそばにいてくれるような安心感があるんですね。
大きさも25cmほどまでと中型で、比較的丈夫な体質から「初心者にも育てやすい」と評判の種類です。
うちでは、毎日の変化を子どもがノートに記録していて、「昨日は小松菜だったけど、今日はレタスのほうが食べてたね」など、小さな気づきが日々の会話になっていました。
ホシガメ|見た目は魅力的でも慎重な管理が必要
「とにかく美しいカメがいい!」という方には、ホシガメが目を引くかもしれません。
放射状の星のような模様が入った甲羅はまるで芸術品のようで、インテリアとしても存在感抜群です。
来客があると「本物?すごくきれい!」と注目を集めるほど。
ただし、ホシガメは他の種類と比べてデリケート。
特に乾燥に弱く、温度と湿度のコントロールがシビアになります。
慣れないうちは飼育の難しさを感じるかもしれませんが、適切な環境を整えてあげれば、人にもよく慣れて立派な家族の一員になります。
飼育に余裕のあるご家庭や、すでにある程度の経験がある場合には選択肢として検討しても良いでしょう。
ケヅメ・ヒョウモン|子育て家庭には不向きな大型種
「ベビーの頃は手のひらサイズで可愛かったのに、気づいたらケージがはみ出してる!」という声が後を絶たないのが、ケヅメリクガメやヒョウモンリクガメなどの大型種です。
これらは成長が早く、数年で30~60cmほどになることも珍しくありません。
力も非常に強くなり、ケージを破壊したり家具を押し倒したりする例もあるので、住宅環境や子どもの安全を考えると、日常的に管理するのはなかなか大変です。
広い屋外スペースがあり、将来的な屋外飼育への移行を見据えられる家庭でない限り、小型~中型でおとなしい種類を選ぶのが安心ですね。
“かわいい”だけで選ばないことが大切
ペットショップで小さなカメと目が合ってしまうと、「この子がいい!」となってしまうのはよくあること。
でも、その場の“かわいい”だけで選ぶのは、後々のトラブルや後悔にもつながりかねません。
命を迎えるということは、これから10年、20年と一緒に生きていく覚悟を持つことでもあります。
「子どもの年齢」
「家族の生活スタイル」
「住環境」
「その子自身の性格や飼育のしやすさ」
などをふまえて、「この子となら長く暮らせそう」と思える相性を大切にしてみてください。
リクガメは静かでも、確かにその場に“いてくれる”存在です。
だからこそ、家族の一員として迎えるには、慎重に選びたいですね。
子どもと安心して暮らすためのリクガメ飼育の安全ポイント
リクガメは穏やかで静かな性格とはいえ、やはり「生き物」として迎える以上、子どもとの生活の中で気をつけたいことはいくつかあります。
特に小さな子どもは好奇心が旺盛で、まだ“加減”がうまくできない時期だからこそ、リクガメも子どもも安全に過ごせるような環境づくりがとても大切です。
ここでは、実際にわたしたち家族が気をつけてきたポイントを中心に、家庭でできる対策をまとめてみました。
触れ合いルールは“最初に話す”のがカギ
リクガメは基本的におとなしい性格ですが、エサと間違えて指を軽く噛んでしまうこともあります。
「うちの子に限って大丈夫」と思いたくなりますが、実際は「かわいい~!」とテンションが上がって指を伸ばしてしまう瞬間って、どの子にもあるものです。
そこで大切なのが、家族全体で「触るときのルール」を事前に共有しておくこと。
「持ち上げない」
「エサは手であげずにトングで」
「おやすみ中はそっとしておく」
など、子どもにもわかりやすい形で決めておくとトラブルを防げます。
うちでは、最初のうちは何度も
「今びっくりしちゃったかもね」
「カメさんの気持ちになってみようか」
と繰り返し声をかけていました。
そうするうちに、子ども自身が「優しくしなきゃ」と自分で気づくようになってくれたんです。
“見せるけど触らせない”レイアウトでストレスを減らす
子どもにとって、生き物がすぐ目の前にいたら触りたくなるのは当然です。
だからこそ、ケージの位置や高さを調整して「観察はできるけど、むやみに手を出せない」レイアウトを工夫するのがおすすめです。
我が家では、リビングの棚の上にケージを置き、踏み台がないと手が届かない高さにしています。
すると自然と「今日は動いてるね」「あ、レタス食べたよ!」と“見ること”に意識が向くようになり、子ども自身がスケッチや観察ノートをつける習慣にもつながっていきました。
「触らせない」は一見ネガティブなように聞こえるかもしれませんが、実は“観察する楽しさ”を引き出すための大事なきっかけになるんですね。
サルモネラ菌などの衛生対策は“習慣化”が大切
リクガメを含む爬虫類は、体表やフンにサルモネラ菌を持っていることがあります。
健康な大人では問題にならないことが多いですが、免疫力がまだ弱い小さな子どもにとっては、感染のリスクがゼロではありません。
とはいえ、怖がりすぎる必要はありません。
大事なのは「正しく知って、毎日の習慣にしてしまうこと」。
我が家で実践しているのは、以下のような基本ルールです。
- カメに触ったあとは必ず石けんで丁寧に手洗い
- お風呂用のタライやスポンジは人用と完全に分ける
- ケージ掃除の後は大人も子どもも着替える
- エサの準備をした手で他の作業をしない
誤飲や転倒を防ぐ“ちょっとした気配り”も忘れずに
意外と盲点なのが、ケージのまわりや飼育スペースの整理整頓です。
子どもが使ったおもちゃや紙くずがケージの隙間に入ってしまうと、リクガメが口にしてしまうおそれも。
観葉植物やコード類なども、子どもの手の届く場所にはできるだけ置かないようにすると安心です。
また、リクガメが自由に動き回るスペースを確保する際も、すべったりつまずいたりしないように、床材や段差に注意を払うようにしています。
ほんのちょっとの気配りが、毎日をより安心して過ごすための大きな土台になります。
親子で楽しむリクガメとの関わり方と育ちゆく“思いやり”
リクガメとの暮らしは、お世話をするだけでなく、家族の中にあたたかくて静かな時間を運んできてくれる不思議な存在です。
特に子どもにとっては、「命と向き合う」ことを自然な形で経験できる貴重なパートナー。
ここでは、リクガメとの関わりの中で生まれる“親子の時間”と、“思いやり”が育っていくプロセスを、具体的な例を交えてご紹介しますね。
子どもができる“ちょっとしたお手伝い”が毎日の喜びに
我が家では、エサの準備を子どもが担当しています。
といっても、難しいことではなく、「葉っぱをちぎって、お皿にのせる」だけ。
最初はおそるおそるだったのが、少しずつ慣れてくると
「これくらいのサイズが食べやすいかな」
「今日はレタスじゃなくて小松菜にしよう」
と、自分なりの工夫が出てくるようになりました。
エサの時間になると、リクガメがのそのそ近づいてきて、その様子を見た子どもが「来た来た~!」と大喜び。
そのリアクションに親の私までほっこりして、「ちゃんと食べてくれるってうれしいね」と自然に会話が生まれるんです。
温浴のときも「お湯ぬるめにしてね」「そーっと入れてね」と一緒に声をかけ合いながら、親子で“リクガメのスパタイム”を楽しむのが、ちょっとした癒しの時間になっています。
毎日の観察が“気づく力”と“関わる力”を育ててくれる
リクガメは、派手に動いたり感情を表現したりしません。
でも、じっくり見ていると「あ、今日はあくびした!」「寝る前って、あんなふうに首をしまうんだね」と、小さな発見の連続なんです。
うちの子は、「今日はずっと同じ場所にいるね」とぽつりと言ったことがありました。
よく見ると、その日はケージの温度がいつもより低く、ライトの位置を調整したら再び元気に動き出してくれて。
その瞬間、子どもが「見てあげてよかったね」と嬉しそうに言ったのを、今でも覚えています。
ただ見るだけでなく、“気づいてあげること”が関わりの始まりになる。
その経験が、子どもの観察力や思いやりを少しずつ育ててくれるんですね。
“命って当たり前じゃない”を感じる日々の中で
ある日、エサをあまり食べなくなったリクガメを見て、子どもが「元気ないのかな」と不安そうに言ったことがありました。
家族で原因を探して、温度や湿度を調整しながら数日間見守ったあの時間は、まるで小さな家族会議のようでした。
リクガメが元気を取り戻したとき、子どもは「よかったね」と心からほっとした表情を見せてくれて、その姿に私も胸がいっぱいになりました。
「生きているって、簡単なことじゃないんだよね」ということを、体で覚えていくような経験だったと思います。
命をそばで感じること。
手をかけ、心をかけること。
それは特別なことじゃなくて、日々の中で少しずつ積み重なっていく“思いやりの練習”なのかもしれません。
リクガメ飼育でよくある悩みと家庭でできる対処法
リクガメは比較的飼いやすいといわれる爬虫類ですが、いざ一緒に暮らしはじめると
「これって大丈夫なのかな?」
「どうしたらいいの?」
という小さな不安やつまずきに出会うことが出てきます。
そんなときに、あらかじめ知っておくと心がラクになる“よくある悩み”と“家庭でできる対処法”を、わたし自身の体験もふまえてご紹介していきますね。
食欲が落ちた?動かない?まず見直してほしい環境のこと
リクガメの元気がないように見えたとき、最初にチェックしたいのは「環境」です。
私も最初のころ、エサの減りが明らかに少なくなって「あれ、どうしたんだろう…」と焦ったことがありました。
実はその日は室内の気温が前日よりも低く、ケージ内の温度も23℃を下回っていたんです。
リクガメは変温動物なので、体温が下がると動きが鈍くなり、食欲も落ちやすくなります。
温度・湿度・照明の状態を日々記録しておくと、こうした変化に早く気づけて、対処もしやすくなりますよ。
子どもが触りすぎてしまうときの“やさしいブレーキのかけ方”
「かわいい」が止まらなくて、つい触りすぎてしまう子ども。
うちでも何度も「やめようね」と言う場面がありました。
でも、ただ「ダメ!」と強く止めると、今度はリクガメに対してネガティブな気持ちを持ってしまう可能性もあるんですよね。
だからこそ、「カメさん、今休憩中かもしれないね」「ちょっと恥ずかしがってるかもよ」と、“気持ちを代弁する声かけ”で子どもの行動をやんわり調整するようにしています。
そうすると、子どもも「そっか、じゃあ見るだけにしようかな」と納得して距離を取れるようになるんです。
ケージ内のトラブルは“日々の観察と点検”で防げる
ケージの中で意外と起きやすいのが、
「床材が湿りすぎていた」
「ライトがいつのまにか切れていた」
「水入れがこぼれていた」
などの“ちょっとした変化”です。
けれど、この“ちょっとした”が積もると、リクガメにとっては大きなストレスや体調不良につながってしまうことも。
わが家では、朝と夜に「温度・湿度・照明・水・エサ」のチェックを親子で一緒にするようにして、ちょっとした“点検タイム”を日課にしています。
点検表を紙に書いて貼っておくと、子どもも積極的に参加してくれるようになって、「今日はボウルきれいだったよ!」と嬉しそうに教えてくれるんですよ。
体調が不安なときは“早めの相談”が安心につながる
どうしても「素人の自分が判断していいのかな」と迷う場面も出てきますよね。
エサを数日食べない、水をあまり飲まない、糞が出ない、急に動かなくなった…など。
気になることがあれば、早めに爬虫類に詳しい動物病院や飼育経験のあるショップに相談することをおすすめします。
わたしも一度、心配になってメールで相談したことがあります。
「すぐ病気ってわけではなさそうだけど、湿度をもう少し高めて様子を見てね」とアドバイスをもらってホッとしたことがありました。
ひとりで抱え込まず、「ちょっと不安です」と伝えるだけでも、心がぐっと軽くなるんですよね。
まとめ|家族でリクガメを迎えるということは“日々を育てる”こと
リクガメとの暮らしって、始める前は「ちゃんとお世話できるかな」「子どもにとって危なくないかな」と不安がつきものなんですよね。
私自身も最初はそうでした。
でも、ケージの中でのんびりと日向ぼっこしている姿や、エサを食べるたびに少しだけ近づいてくれるあの表情を見ていると、不思議とこちらの心まで整っていくんです。
子どもも、最初は「見るだけ」が精一杯だったのに、いつのまにか「ごはんあげていい?」「今日は元気そうだね」と自分から関わろうとするようになっていきました。
そんな小さな変化の積み重ねが、思いやりや責任感を少しずつ育ててくれているような気がしています。
もちろん、生き物だからこその大変さもあります。
温度や湿度の管理、掃除、病気の心配…。
でもそれも全部、親子で「命と向き合う」経験のひとつになってくれるんですよね。
リクガメは言葉を話しません。
だけど、確かに“そこにいてくれる”という存在感が、家の中にあたたかくて静かなつながりを作ってくれます。
もし今、少しでも「飼ってみようかな」と思っているのなら、その気持ちを大切にしてみてください。
子どもと一緒に育てていく毎日の中に、想像以上の優しさや気づきがきっと見つかりますよ。