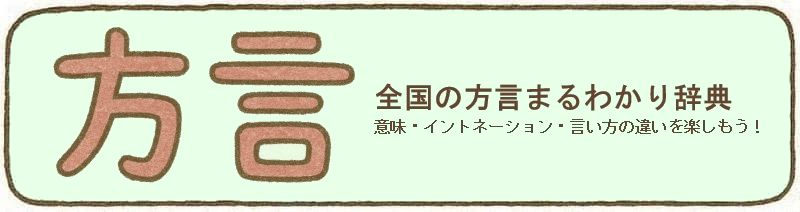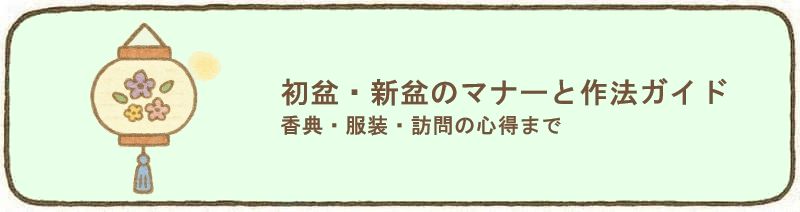「新盆(にいぼん)」と「初盆(はつぼん)」、どちらも故人が亡くなって初めて迎えるお盆という意味では同じですが、地域によって呼び方や読み方に違いがあります。
たとえば、関東では「新盆」、関西では「初盆」と呼ばれることが多く、さらに「ういぼん」や「あらぼん」といった別の呼び方をする地域もあるんです。
こうした呼び方の違いは、地域の歴史や文化、言葉の成り立ちが関係しています。
昔からその土地で使われてきた言い回しや風習が今も根づいているため、同じ行事でも呼び方にバリエーションが生まれているんですね。
特に、お盆のように家族や親戚が集まる大切な行事では、地元のやり方に合わせることがマナーとしても大切です。
意味は変わらなくても、地域の習慣や言い回しがちょっとずつ違うと、「これで合ってるのかな?」と不安になることもありますよね。
初めて経験する立場だったり、他の地域から嫁いできた場合などは、なおさら戸惑うこともあるかもしれません。
この記事では、そんな呼び方の違いや、それぞれの背景、風習についてわかりやすくご紹介していきます。
「新盆」と「初盆」の違いをしっかり知っておくことで、失礼のないように準備ができたり、親族との関係もよりスムーズになるはずです。
大切な方を偲ぶお盆だからこそ、心を込めて丁寧に迎えたいですね。
新盆と初盆!地域によって読み方以外にも違いはあるの?
新盆と初盆、この2つは大きく地域によって使い分けられています。
基本的には、関東地方では“新盆”と呼ぶことが多く、関西地方では“初盆”と呼ぶことが多いようです。
でもこの地域による呼び方の差は、東と西などのようにざっくりとした別れ方ではなく、それぞれの地域や市などによって細かく呼び分けられているのです。
関西地方では“初盆(はつぼん)”とご説明しましたが、関西でも場所によって違います。
または四国・九州地方などでは、同じ「初盆」と書いて「ういぼん」と呼ぶ地域が多いようです。
関東地方では、東京は「新盆(にいぼん)」と呼ばれていますが、関東の中でも千葉や茨木では同じ「新盆」と書いて「しんぼん」と呼んでいる方が多いようです。
さらに、茨城地方では、「入盆(にゅうぼん)」だとか「新盆(あらぼん)」と呼ぶ方もいるそうです。
少し調べただけでも、5種類の呼び方がでてきました。
同じ意味の言葉なのに、地域で色々差があって面白いですよね(^^)
新盆と初盆の違いは?どちらも初めて迎えるお盆のことじゃないの?
地域によって色々な呼び方があるとわかった初盆ですが、呼び方以外に違いはあるのでしょうか?
それぞれの意味などを調べてみました。
「初盆」とは、人が亡くなってから四十九日を過ぎた後、初めて迎えるお盆のことをいいます。
通常のお盆では「年に一度、故人が家族のもとに帰ってくる」とされている日です。
そして初盆は「故人が亡くなってから、初めて迎えるお盆」ということで、通常のお盆よりも供養の行事なども大切におこなわれるものです。
そして新盆とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆・・・
これは全く同じ意味ですね。笑
どうやら「初盆」と「新盆」では呼び方や読み方に違いがあるだけで、その意味や内容には違いはないようです。
では「どうして呼び方に違いがあるのか?」について調べてみましたが、これについては残念ながらわかりませんでした(><)
初盆や新盆は具体的になにをするものなの?
「初盆」と「新盆」。
この2つに意味などの違いないということがわかりましたが、具体的には何をするものなのでしょうか?
一般的に、8月13日(東京・神奈川・静岡などは7月13日)がお盆の初日(盆の入り)となります。
この日は「迎え火」を焚いてご先祖の霊を自宅に招き入れます。
そして、自宅で盆棚の準備を整えた後、お墓参りをしてきれいに掃除をします。
夕方になったら素焼きの土鍋やお皿を準備して、その上でおがらという皮をむいた麻の茎を焚いて、白提灯に火を灯します。
14日・15日になると、遺族が集まってお墓参りをします。
その後、自宅に親族や故人と親しかった知人・友人を呼び、僧侶を招いて法要をし、その後会食をおこないます。
僧侶がお帰りになる際はお盆の上にお布施を乗せてお渡しします。
16日は盆明けです。
なるべく遅い時間に送り火を焚き、先祖の霊を見送ります。
これが一連の“初盆・新盆”の流れになります。
地域や宗派によって違う場合もありますので、一例として参考にしてみてくださいね。
東京などの地域はお盆の日にが違うのはなぜ?
一つ気になったのが、なぜ東京など関東の一部では、一般的にお盆といわれる8月15日ではなく、7月15日が初盆となるのでしょうか?
もともとお盆とは、旧暦7月15日の「中元節」に行われていました。
それが明治時代になると、新暦が採用されたため、対応がわかれてしまったというわけです。
- 新暦の8月15日におこなう「月遅れのお盆」
- 旧暦の7月15日におこなう「旧盆」
- 新暦の7月15日
一般的には8月15日(月遅れのお盆)を中心としておこなわれています。
一方東京などの関東圏の一部では、7月15日を中心におこなわれています。
どうして東京などの関東圏でこのような対応になったかは所説ありますが。
大きな理由として「東京と地方の時期をずらすことで、縁者一同が集まりやすくなり、皆でゆっくりと先祖の供養をするため」といわれています。
また、農作業が忙しい時期を避けるために、お盆の時期がずれているという説もあります。
新盆の読み方は地域によって違うって本当?のまとめ
「新盆」と「初盆」は、どちらも故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことを指していて、意味としてはまったく同じです。
ただし、地域によって使われる言葉が異なり、たとえば
・関東では「新盆(にいぼん)」
・関西では「初盆(はつぼん)」と呼ばれることが多く。
・四国や九州の一部では「ういぼん」
さらに茨城県などでは「あらぼん」といった呼び方も使われています。
これらの違いは地域の歴史や文化、そして方言や風習に根ざしたもので、どれが正しい・間違っているというものではありません。
こうした呼び方の違いを知っておくことで、親族やご近所とのやり取りもスムーズになりますし、失礼のない形で供養を行うことにもつながります。
たとえば、親戚が集まる場で「初盆」と言うべきか「新盆」と言うべきか迷ったときも、相手の地域や慣習を思い出せば安心して対応できますよね。
慣れない言葉であっても、意味を理解していれば自然と対応できるものです。
大切なのは、形式や呼び方よりも、故人を偲ぶ気持ちや供養の心を持つことです。
相手や地域の風習に寄り添いながら、できる範囲で心を込めて準備を整え、家族や親戚とともに穏やかであたたかなお盆のひとときを過ごしてくださいね。