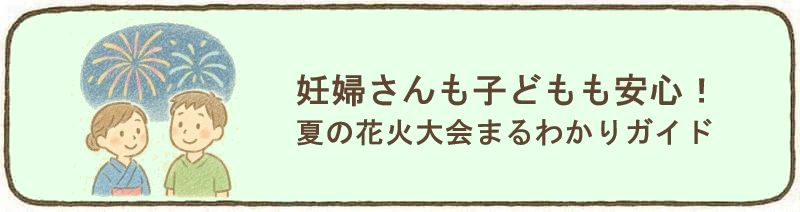夏といえば、やっぱり花火大会。
毎年この季節が来ると、私はついワクワクしてしまいます。
夜空に咲くあの大きな花火の音と色、浴衣の人たち、屋台のにおい。
どれもこれも「日本の夏」がぎゅっと詰まっていて、子どもの頃の思い出とも重なって、心がふわっと浮き立つんです。
でもそんな私も、娘が生まれて初めての夏を迎えた年、いつものように素直に楽しめなくなっていました。
「赤ちゃんを連れて花火大会に行っても大丈夫なのかな?」という不安が、頭の片隅から離れなくなっていたんです。
特に気になったのが、あの花火の「ドーン」という音。
大人でもお腹に響くような、地面が揺れるようなあの爆音を、まだ生まれて間もない赤ちゃんが聞いたら、どうなってしまうんだろう。
泣くだけならまだしも、耳に悪影響があったりしないのかなと、どんどん心配がふくらんでしまいました。
それでもやっぱり、夏の思い出を子どもと一緒に楽しみたいという気持ちもあって、私は実際に耳鼻科の先生に相談してみることにしました。
すると返ってきたのは、ちょっと意外で、でもホッとする答えでした。
赤ちゃんの鼓膜は花火の音で破れる?先生の見解
音で鼓膜が破れることってあるの?
「もしかして、花火の“ドーン”って音で赤ちゃんの耳がダメになっちゃったりするのかな?」
娘が生まれて初めての夏、そんな不安がふと胸に浮かんで、なぜかその日から頭の中でずっとグルグルしていました。
夜中の授乳のときも、赤ちゃんの小さな耳を見るたびに、「この耳にあの爆音はキツすぎるよね…」と、なんとも言えないモヤモヤが消えませんでした。
心配が募って、いてもたってもいられず、ある日、定期検診で訪れた耳鼻科の先生に、思い切って聞いてみたんです。
「先生、花火大会の音で赤ちゃんの鼓膜が破れたりって、ないですよね…?」
なんとなく恥ずかしくて、ちょっと笑いながら聞いたんですが、先生は真剣な顔で、でもやさしい口調でこう答えてくれました。
「赤ちゃんの耳だからって、特別に鼓膜が弱いわけじゃないですよ。
むしろ、大人と同じくらいしっかりしています。
ですから、通常の花火大会の音で鼓膜が破れる心配はほとんどありません。
ただ、大きな音には敏感なので、びっくりして泣いてしまうことはありますけどね」
その瞬間、肩の力がすっと抜けたような気がしました。
「大丈夫」という言葉を聞けたことで、漠然とした不安がやっと形を持って消えてくれた気がしたんです。
鼓膜が破れるレベルの音って?
そもそも、どれくらいの音で鼓膜って破れてしまうものなんだろう。
そんなこと、考えたこともなかったけれど、私は帰宅してからすぐに調べてみました。
専門サイトや医療機関のページによると、鼓膜が物理的に破れてしまうのは、「120~150デシベル以上」の非常に強い音を、耳のすぐそばで聞いたときとされています。
たとえば飛行機のエンジン音を至近距離で浴びるような状況や、爆発の直後に近くにいた場合など、日常生活ではまず起こり得ないような音の衝撃が必要だそうです。
一方で、花火大会の音は場所にもよりますが、一般的にはだいたい70~100デシベルほど。
しかもそれは空中で破裂して響いてくる音であって、耳元で直接鳴っているわけではありません。
つまり、「花火の音=爆音」と思いがちですが、鼓膜を破るようなレベルではないということなんですね。
もちろん、赤ちゃんの耳が未熟というわけではないけれど、だからといって油断していいという話でもありません。
大人が「花火の音は楽しい」と感じるのは、その大きさや振動に慣れているからであって、赤ちゃんにとっては「これまで経験したことのない、びっくりするほどの衝撃」なんです。
それを思うと、やっぱり慎重になるに越したことはないなと、私は改めて感じました。
私の中での花火大会に赤ちゃんを連れていく事への結論
「音は大丈夫」でも安心できない現実
「鼓膜は破れない」と聞いて安心したのも束の間、私の頭にはすぐに別の不安が浮かび上がりました。
それは、“音”ではなく、“人混みの中で赤ちゃんを守れるかどうか”という現実的な心配です。
花火大会のあの混雑を思い出すたび、赤ちゃんを連れていくことがどれほど無謀かがリアルに想像できてしまいました。
泣き出しても逃げられない人混み
赤ちゃんは、びっくりしたら泣いてしまうもの。
だけど、その泣き声を聞いてすぐに移動できるとは限りません。
まるで波のように押し寄せてくる人波の中で、抱っこした赤ちゃんをあやしながら耐え続けるなんて、考えただけで怖くなりました。
冷たい視線や迷惑そうな顔が向けられたときの、あの孤独感も想像してしまったんです。
夏の夜の“蒸し暑さ”はあなどれない
「夜なら涼しいはず」と思いがちですが、最近の夏は夜でも気温が下がらない日が多く、抱っこ紐の中の赤ちゃんは蒸れやすくなります。
大人の私でさえ汗だくになるのに、小さな体で同じ環境に耐えるのはかなりしんどいはず。
熱中症や脱水も十分にあり得ると考え、私は自然と“行かない選択”をとるようになりました。
無理に連れて行かなくてもいいと気づけた
赤ちゃんが「花火を楽しい」と思えるようになるまで、無理に人混みに連れて行かなくてもいい。
それよりも、遠くから安心して見られる環境で、親子一緒に穏やかに過ごすほうが、きっと素敵な思い出になる。
そう気づけたことで、私は無理に“夏のイベント”に合わせようとする心の焦りからも解放されたような気がしました。
花火大会に赤ちゃんを連れて行くと泣いてしまうのはなぜ?
泣くのは「うるさいから」だけじゃなかった
赤ちゃんを花火大会に連れて行くと泣いてしまう──これ、実際に経験した方なら「やっぱりそうなるよね」と思われるかもしれません。
でも、その理由を「音が大きいから」「うるさいから」だけで片づけてしまうのは、少しもったいない気がするんです。
私自身も、娘を2歳くらいのときに人混みの少ない地方の花火大会に連れて行ったことがありました。
そのとき、彼女は花火を見上げながら「きれい~!」と嬉しそうに言ってくれたんです。
だけど、同時に耳はずっとふさいだままでした。
笑顔で見ているのに、耳はふさぐ
その姿に、私はなんとも言えない気持ちになったのを覚えています。
「キレイ」と「こわい」が、彼女の中で同時に存在していたんだなって。
赤ちゃんの聴覚はまだ発達途中
これは後から知ったことなのですが、赤ちゃんの「鼓膜」は大人とほとんど同じ構造なんだそうです。
だから、構造上は簡単に破れるようなことはないのですが、「聴覚」という面では、まだ発達の途中にあります。
つまり、聞こえる範囲や音の刺激に対する敏感さが、大人とはまったく違うということ。
赤ちゃんや小さな子どもにとっては、大きな音は「情報量が多すぎる」状態なんですね。
処理しきれないから、脳も体もストレスを感じてしまう。
だからこそ、花火のような爆発音は「驚き」では済まなくて、「怖い」「イヤ」といった強い反応につながりやすいんです。
専門家によると、子どもの聴覚がある程度安定するのは、個人差はありますがだいたい4~7歳ごろだと言われています。
「泣く」ことは赤ちゃんのSOSかもしれない
うちの娘も、4歳になるまでは花火の音があまり得意ではありませんでした。
3歳のときなんて、始まった瞬間に「おうちかえる」と泣いてしまって、せっかく場所取りしていたのに一瞬で撤退したこともあります。
でも、5歳の夏を過ぎたころから、驚くほど平気になってきたんです。
音も怖くなくなって、むしろ「もっと近くで見たい!」と前のめり。
そのとき私は「あぁ、こうやって心と身体って少しずつ育っていくんだな」と感じました。
もし今、赤ちゃんが花火の音で泣いてしまっても、それは「今の環境はまだつらいよ」「今はちょっと怖いよ」という、体と心の素直な声なのかもしれません。
親としてできることは、その声を責めずに、受けとめてあげることなんだと思います。
赤ちゃんにとっての花火大会ってどんな感じなの?
親が「楽しい」と思うことが、赤ちゃんには苦痛のことも
私たち大人は、花火大会というとワクワクするものですよね。
夜空に大輪の花が咲いて、ふわっと胸が高鳴るようなあの感覚。
でもふと立ち止まって考えてみたんです。
赤ちゃんにとっては、果たしてあの場所は「楽しい」空間になっているんだろうかって。
私は娘を連れて花火大会を“遠くから”眺めた年のことを思い出しました。
人のざわめき、会場に響く音楽、アナウンス、大勢の声、そして突然の大きな打ち上げ音。
大人の私ですら、「ちょっとうるさいな」と思う瞬間があったほどです。
それを、まだ言葉もわからない小さな赤ちゃんが、どう感じているかを想像すると…胸がギュッとなりました。
赤ちゃんの視界に見えるのは、花火じゃなく“人の足”
ベビーカーに乗った赤ちゃんの視線って、とても低いんですよね。
親の私たちは「ほら、見てごらん!きれいだよ~」と花火を指さすけれど、
赤ちゃんの目に映るのは前の人の背中やお尻、すれ違う人の脚、地面ばかり。
花火が見えるどころか、むしろ息苦しさや圧迫感ばかり感じていたかもしれません。
私自身も、初めてベビーカーで人混みに入ったとき、
「これ、赤ちゃんにとってはすごく怖い世界なのかも」と気づいてハッとしたことがありました。
赤ちゃんは“暑さ”と“情報の多さ”に疲れやすい
花火大会って、始まる何時間も前から場所取りがあったり、混雑で予定通りに進まなかったりしますよね。
その間ずっと外にいて、暑さや湿気、人の熱気にさらされることになる赤ちゃん。
しかも
- 聞いたこともない大きな音
- 光の点滅
- 話し声
- 足音
- 屋台の匂い
まるで五感をフルに使ったサバイバル状態。
大人でもヘトヘトになるのに、赤ちゃんの小さな体と心では、到底処理しきれない情報量なのは当然のことなんですよね。
だからこそ、「泣く」「ぐずる」「抱っこから離れたがらない」という反応が出るのは、決してワガママではなく、むしろ自然なSOSなんだと思います。
スヤスヤ寝ている赤ちゃん、本当に安心してる?
ときどき、花火大会の会場でベビーカーに乗ってぐっすり眠っている赤ちゃんを見かけることがありますよね。
「すごいな~、こんな爆音の中で寝られるなんて」と思いがちなんですが、最近になって私は別の視点を持つようになりました。
赤ちゃんって、自分の感情や状況をうまく整理できなくなると、
“脳がシャットダウン”するようにして眠りに入ることがあるんだそうです。
つまり、「眠っている=安心している」ではなく、「もう限界、なかったことにしよう」と、体が強制的に休もうとしている可能性もあるんですよね。
もちろん、本当に安心して寝ている子もいるかもしれません。
でも、もし親の私が「なんとなく心配だな」と思っているなら、その感覚を信じていいんだと思います。
赤ちゃんとの花火大会では音以外でもまだある!気を付けたい注意点は?
人混みで赤ちゃんを守るのは想像以上に難しい
赤ちゃん連れの外出で、真っ先に不安になるのが“人混み”ですよね。
とくに花火大会のような大規模イベントでは、想像以上に人の波が激しく、まさに“押し合いへし合い”状態になることも珍しくありません。
私も何度か身動きが取れないほどの混雑を経験したことがありますが、そのときはまだ自分ひとり。
でも、もしそこに赤ちゃんがいたら?と思った瞬間、ゾッとしました。
ベビーカーなんてとても押せない。
抱っこ紐ですら、周りの人の荷物や腕がぶつかってしまいそう。
そのたびに赤ちゃんがビクッとする姿を想像して、「うちの子を連れてここに来るのはムリだ…」と直感的に思いました。
お酒・煙草・大声…トラブルの要素もいっぱい
花火大会の会場には、さまざまな人が集まります。
楽しい雰囲気の中だからこそ開放的になりすぎて、時にはお酒が入ってテンションの高い人や、喫煙マナーの悪い人と鉢合わせることも。
赤ちゃんを連れていると、こうした小さな“リスク”がすべて拡大して感じられます。
例えば、近くでタバコの煙が漂ってきたり、酔っ払って大声で騒ぐグループがいたりすると、赤ちゃんは不安そうに眉をしかめて、親の私もハラハラしてしまうんです。
大人同士なら「まぁ仕方ないか」とやりすごせることも、赤ちゃんと一緒だとそうはいきません。
花火が終わっても“帰れない”が待っている
花火が終わって「さあ帰ろう」と思ったときに、地獄のような“退場ラッシュ”が始まるのも、花火大会あるあるですよね。
一斉に帰路につく何万人もの人。
まったく動かない駅の改札。
照明の少ない暗い道を、疲れ切った状態でベビーカーを押して歩く姿は、想像するだけで不安が膨らみます。
しかも、赤ちゃんがそのタイミングで眠くなってぐずったり、おむつを替えたくなったり、泣き出したりしたら…その場で対処できる余裕なんて残っていないかもしれません。
トイレ・授乳・おむつ替え…どこでする?
意外と見落としがちなのが、“授乳・おむつ替えのスペース”です。
花火大会の会場に「赤ちゃんスペース」が完備されていることは、まだ少ないのが現状。
仮設トイレがズラーッと並んでいる場所を見ても、赤ちゃん連れにはとても使える環境ではないですよね。
私も実際に、「どこで授乳しよう…」と焦った経験がありました。
そうならないためにも、事前に授乳ケープを準備したり、レジャーシートで少し人の少ない場所を確保しておくなど、できる範囲の工夫がとても大事です。
「備えあれば憂いなし」とはまさにこのこと。
赤ちゃんの快適さを保つには、親がひと足先にいろいろとシミュレーションしておく必要があるんですよね。
まとめ
花火大会の大きな音で、赤ちゃんの鼓膜が破れてしまうんじゃないか──そう思って不安になる気持ち、私にはとてもよくわかります。
大人でもドキッとするあの爆発音を、まだ生まれて間もない子が受け止められるのか、心配して当然です。
でも、耳鼻科の先生のお話や専門的な情報を調べてみると、赤ちゃんの鼓膜は思っていたよりも丈夫で、遠くから聞く花火の音で傷つくことはほとんどないことがわかりました。
けれどそれは、あくまで「鼓膜が破れるリスクは少ない」というだけの話。
赤ちゃんは聴覚が未熟で、音に敏感な時期です。
花火の音に驚いたり、泣き出したりすることは十分にありえます。
そしてそれ以上に、会場の人混み、熱気、騒音、慣れない環境が赤ちゃんにとってはとても大きなストレスになってしまうんです。
だからこそ、無理に連れて行く必要はありません。
遠くからでも花火は楽しめるし、「安心できる場所で親と一緒にいる時間」こそが、赤ちゃんにとっての一番の思い出になります。
焦らずに、今のわが子に合った形で、やさしい夏の夜を過ごしてくださいね。