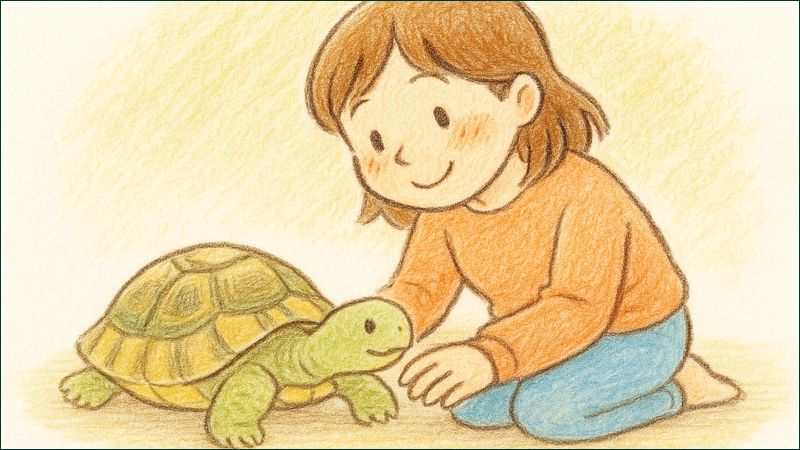
「リクガメって飼いやすいんでしょ?」そう思って、何の準備もせずにお迎えした私。
小さな甲羅のリクガメを見て「癒される~」と胸キュンしながらも、どこかで“カメ=手がかからない”という先入観があったんだと思います。
でも、実際には「えっ、こんなに手がかかるの!?」と驚くことの連続でした。
ケージの準備も甘かったし、ライトの種類もよくわからず、餌も自己流。
気がつけば、リクガメの元気がないような気がして、慌てて調べる日々……。
はじめてのリクガメ飼育は、知らないことだらけ。
飼い方だけじゃなく、季節ごとのケア、性格の個体差、ちょっとした仕草の意味…
知れば知るほど「こんな奥深い世界があったのか」と驚きました。
それゆえに、ちょっとした勘違いや準備不足が“命に関わる失敗”につながることもあるという現実も、しっかり感じました。
この記事では、初心者の私が経験した失敗談や、他の飼育者さんたちのリアルな声をもとに、
「どうすれば失敗を回避できるか?」をわかりやすくお伝えしていきます。
「こんなことなら最初に知っておきたかった…!」という内容をギュッと詰め込んで、
これからリクガメを迎えるあなたの参考になるように心を込めて書きました。
“かわいいリクガメとずっと一緒に暮らしていくために”
あなたの飼育生活が、優しくてあたたかいものになるように、ささやかなエールを込めてお届けします。
よくあるリクガメ飼育の失敗談とは?
「思ったより大きくなる」と知らずに買って後悔
ショップで小さなリクガメを見て「これなら棚の上に置けそう」と軽い気持ちで購入。
そのときは手のひらにちょこんと乗る可愛らしさに、すっかり心を奪われてしまったんです。
でも数年後、甲羅が弁当箱サイズに成長して、あんなに余裕だったケージがみるみる狭くなり、
設置していた棚も耐えられずに傾きはじめ…ついには床置きに変更する羽目に。
思わず「こんなに大きくなるなんて聞いてない!」と嘆いたのは私だけではないはず。
成長後のサイズ感や必要なスペースを事前にイメージしておくことって、本当に大事なんだと身に沁みました。
ケージや設備を後から買い足す羽目に…
「最低限でいいよね」と思っていたら、温度計・紫外線ライト・シェルター・床材…次々必要に。
最初はダンボール箱で代用しようとしたり、普通のデスクライトで代用してみたり。
けれど当然ながらうまくいかず、リクガメは体調を崩すし、私の財布もどんどん軽くなるしで散々な目に。
気づけば、想定していた金額の2倍以上の出費に。
それでも「ちゃんと揃えていればこんなに不安にならずに済んだのに…」と後悔。
飼い始めてから慌てて揃えるより、最初から必要なものを知っておくべきでした。
餌の選び方を間違えて体調を崩した
「キャベツあげとけば大丈夫でしょ」なんて安易な考えで与えていたら、下痢が止まらなくなったリクガメ。
しかも「よく食べてるし大丈夫か」とそのまま放置してしまい、結果的に動きが鈍くなって心配に。
動物病院で「栄養バランスが崩れていますね」と言われて青ざめました。
草食性でも、与える野菜の種類や栄養バランスには注意が必要なんです。
「緑の野菜ならなんでもOK」ではなく、カルシウムとリンの比率、繊維の量、水分量まで気にする必要があります。
寒さ・暑さで弱らせてしまった実例
冬の夜にヒーターの電源が切れていたことに朝気づき、カメがぐったり。
そのときの絶望感といったら…呼びかけてもほとんど反応がなく、真っ先に「死んじゃった?」と頭によぎりました。
幸い、しばらく温めることで回復してくれましたが、それ以来電源チェックは寝る前のルーティンに。
逆に夏はケージ内がサウナ状態に…。
窓際に置いていたことで直射日光が差し込み、ケージ内が40度超えに。
気づいたときには、リクガメがバテて呼吸も浅くなっていて、こちらも冷や汗だらだら。
リクガメは変温動物なので、温度管理のミスは命取りになります。
本当に。
放し飼いで家具や床がボロボロに…
「自由に動けた方が幸せかな」と放し飼いにしたら、壁紙はボロボロ、コードはかじる、床にフン…。
思っていた以上にあちこち動き回り、家具の隙間に入り込んで出てこなくなることも。
掃除も追いつかないし、リクガメ本人も落ち着かなそうで、結局ケージ飼いに切り替えました。
人間側の管理体制が整っていないと、お互いにストレスになります。
「自由=幸せ」ではないんだなと気づかされたエピソードです。
初心者が失敗しやすい原因はどこにある?
「カメ=手がかからない」は大間違い
「動かないし、静かだし、世話も楽そう」と思いがちなカメ。
私も最初は、魚の次くらいにお世話が簡単なのでは?と思っていたのですが、まったくの思い違いでした。
リクガメは、飼育環境を細かく整えなければすぐに体調を崩してしまう繊細な生き物です。
温度・湿度・餌の内容…どれもこだわる必要がありますし、特に温度差には敏感。
「今日はちょっと寒いかな?」という感覚が、命に関わる大問題になることもあります。
また、日々の観察と気づきがとても大切。
「昨日より動きが少ない」
「餌の食いつきが悪い」
そんな「ほんのわずかな変化」に気づけるかどうかで、その後の健康状態が大きく左右されるのです。
ネット情報だけを信じて準備不足に
私自身もそうでしたが、SNSやブログの断片的な情報を鵜呑みにしてしまいがち。
「リクガメ飼育って意外と簡単らしいよ」「これだけあれば大丈夫!」なんて言葉を見て、安心してしまったことがあります。
でも、実際は種類によって必要な環境や注意点はまったく違います。
特に、ケヅメリクガメとヘルマンリクガメでは大きさも生活リズムもまるで違うので、同じように扱っていてはトラブルの元。
表面的な情報だけで判断せず、リクガメ専門書や獣医師、実際に飼っている人のリアルな声に耳を傾けるのがとても大切です。
一度、専門家が書いた書籍を読んだときに「今まで自分がどれだけ間違った知識で育てていたか」を思い知って、ショックと同時に感謝の気持ちがこみ上げたのを覚えています。
ペットショップでの勢い購入がトラブルの元
「かわいい!この子にする!」と、予定も準備もないままお迎え。
そのときの私は、まさに一目惚れでした。
店員さんに「餌と水入れとケージがあれば大丈夫ですよ~」なんて言われて、すぐに連れて帰ってしまったのですが…。
結果、帰宅後に慌ててケージや餌を買いに走ることに。
しかも、後から「紫外線ライトが必要」「保温球がないと冬越しできない」と次々情報が出てきて、完全にパニック状態に。
お迎えは、事前準備を整えてからが鉄則です。
せっかく迎える命だからこそ、焦らず、しっかり環境を整えてから家族に迎え入れてあげたいですよね。
勢いで決めると、リクガメも自分もお互いにとって大変なスタートになってしまいます。
リクガメ飼育で失敗しないための事前準備
成長後のサイズをイメージしておく
リクガメの成長速度と最終サイズは種類によって大きく異なります。
「今は手のひらサイズでかわいいから、ちょっとしたケージで十分」と思いがちですが、数年後には予想外のサイズになっていることも珍しくありません。
例えば、ケヅメリクガメのような大型種は、成長すれば60cm以上に達することもあります。
一方で、ヘルマンリクガメやギリシャリクガメのような中型種でも、最終的にはスペースに余裕のあるケージや室内環境が必要です。
ケージのサイズだけでなく、温度や湿度を適切に管理できる空間、シェルターやバスキングスペースを確保する余裕も大切です。
さらに、部屋の模様替えや配置の見直しが必要になる可能性もあるので、「今の生活環境にそのスペースが確保できるか?」もよく考えておきましょう。
温度・湿度管理グッズを揃えておく
- サーモスタット
- 保温球
- 紫外線ライト
- 温湿度計
リクガメは変温動物であり、外部環境に体温が左右されます。
冬場の保温が甘いと風邪や消化不良を起こし、夏場の過剰な高温も命取りになります。
サーモスタットは一定の温度を保つための自動調節装置で、ケージ内を安全な温度にキープしてくれます。
紫外線ライトはカルシウムの吸収に関わるビタミンD3の生成に必要で、特に室内飼育では欠かせません。
湿度管理も見落とされがちですが、床材の乾燥や通気性によってリクガメの脱皮不全や皮膚病を招くこともあるため、湿度計や加湿・除湿対策も取り入れておきましょう。
餌やライトの正しい選び方をチェック
「この餌で大丈夫かな?」
「紫外線ライトはこれでいいの?」
実際に買い物をしようとすると、選択肢が多すぎて迷ってしまいます。
リクガメ専用の餌といってもメーカーや種類によって栄養バランスは大きく異なりますし、乾燥タイプかフレッシュタイプかでも与え方が変わってきます。
また、紫外線ライトにはUV-AとUV-Bの2種類があり、リクガメに必要なのは主にUV-Bです。
しかも、その照射距離や寿命にも注意が必要で、「ライトはついてるけど効果ゼロ」なんてことも。
購入前に一度、リクガメに詳しい店員さんや飼育経験者に相談するのがおすすめです。
できれば、信頼できる爬虫類専門店や獣医さんのアドバイスを参考にすると、安心して道具を選べます。
最初に正しい知識で選べば、あとからの買い直しも少なく、リクガメにとっても安心できる環境が作れますよ。
実体験から学ぶ「やってよかった対策」
飼う前に実際に飼っている人の話を聞いた
インスタで仲良くなったリクガメ飼い主さんに話を聞いて、リアルな体験談が超参考になりました。
「こんな時どうする?」「この行動って大丈夫?」といった小さな疑問も、経験者の声を聞くと一気に安心できます。
本やサイトには載ってない「ちょっとしたコツ」が満載なんですよね。
たとえば「床材に隠れたうんちの見つけ方」とか「電球の交換時期を逃さないチェック方法」など、実際に飼っていないとわからない実践知がたくさん。
ネットだけでは得られない、日々の“暮らし”に寄り添ったアドバイスに何度も助けられました。
最初から放し飼いにせずケージ飼育からスタート
かわいさに負けて広々空間を与えたくなりますが、初心者はまずはケージ飼育からスタートするのが断然おすすめです。
私も最初は「ケージってかわいそうかな?」と思っていたのですが、実際にやってみると、リクガメ自身も落ち着いて過ごしてくれることに気づきました。
温度管理がしやすく、掃除もラクになりますし、何より“安心できる居場所”があることでリクガメのストレスも減るんです。
放し飼いにするにしても、まずはケージの中でお互いのリズムをつかむのが先。
結果的にそれが信頼関係を築く第一歩にもなりました。
温浴や爪切りなどケアの習慣をつけた
毎週の温浴タイムが楽しみな子も多いんです。
「今日は気持ちよさそうにしてるな~」なんて表情を見られるのも、飼い主の特権。
温浴を通じてリクガメとのコミュニケーションも深まっていきます。
また、爪や甲羅もこまめにチェックすることで、病気の早期発見につながります。
私の場合、甲羅に小さなひび割れを見つけたことで、早めに病院に行けた経験があります。
ケアの時間は、リクガメの健康を守る「日々の点検タイム」でもあるんですね。
最初はちょっと緊張するかもしれませんが、慣れてくるとそれすら楽しくなってきますよ。
まとめ|リクガメ飼育は「知らないと損」が多い!
小さな失敗が命に関わることも
リクガメは静かで我慢強い生き物だからこそ、異変に気づきにくい。
具合が悪くても声を出して教えてくれるわけではなく、じっとそのままの姿勢で耐えてしまうこともあります。
だからこそ、「ちょっと失敗したかも…」が、命の危機になることもあるんです。
ほんの数度の温度差、ちょっとした餌の偏り、些細な湿度の変化が体調不良の原因になることもあります。
私自身も、「たまたま元気がないだけかな」と見過ごしかけたことが何度もありました。
ですが、経験を重ねることで「あ、これは注意サインかも」と感じ取れるようになってきます。
気づけるようになるまでが大変だからこそ、最初からの準備が命を守る鍵になるんですよね。
楽しいリクガメライフのために、準備と情報収集がカギ
しっかり準備して、リクガメの気持ちに寄り添って飼えば、
何十年も一緒に過ごせる最高のパートナーになります。
リクガメはせかせかした生き物ではありません。
ゆっくり、じっくり時間をかけて絆を育んでいく存在。
その穏やかな時間に、自分の生活も整えられていくような感覚があります。
忙しい日々の中でも、リクガメを見てふっと肩の力が抜ける。
そんな癒しの存在に育ってくれるのは、飼い主のあなたが“正しく知ろうとする姿勢”を持っているからこそです。
「失敗しちゃったなあ」も、次への学びに。
どんなにベテランでも、最初はみんな初心者。
少しずつ知識を積み重ねながら、あなたとリクガメの間に温かな時間が流れますように。
このガイドが、ほんの少しでもそのお手伝いになれば嬉しいです。

