
育児中のママにとって、頭をなやませることの一つが「睡眠について」だと思います。
赤ちゃんがしっかり昼寝をしてくれると、ママも日中少し休むことができますよね(^^)
つかの間の休息タイムは、ママにとって大切な時間です。
そこで今回は、1歳くらいの子供がお昼寝で泣くときの、よくある原因とその対策についてについて、見ていきましょう!
知っておきたい!一歳の子が昼寝で休むための寝かしつけの方法を紹介!

通常、2歳くらいまでの幼児は、1~2時間くらいのお昼寝をするといわれています。
でもこれはあくまで目安で、もっと沢山寝る子もいれば、全く寝ない子もいます。
子供の育ち方は千差万別ですね(#^^#)
(1)1歳の子供にお昼寝は必要なの??
そもそも、1歳くらいの赤ちゃんの昼寝はどうしてしたほうがいいのでしょうか??
赤ちゃんは、昼寝によって脳を休ませています。
赤ちゃんにとって、大人にとっては何気ない「普段の外からの刺激」はとっても強いものです。
脳をきちんと休ませないと、情報の処理が追いつかなかったり、疲れすぎたりしてしまうのです。
日中にちゃんと寝られる子は、夜もしっかり寝てくれる子が多いようです。
我が家は三姉妹なのですが、長女は一歳半頃から全然お昼寝をしない子でした。
次女と三女は昼寝をしっかりする子たちで、昼寝をあまりしない長女よりも夜泣きも少なかったですね。
(2)お昼寝させるために効果的な方法は??
赤ちゃんにとって、とっても大切なお昼寝。
どうしたら、しっかりお昼寝してくれるのでしょうか??
いくつかご紹介します☆
- 朝を早起きにする・・・朝カーテンを開けて、太陽の光をいれるのも効果的です。
- 運動する・・・体を動かして疲れさせれば眠たくなります。
- お散歩をする・・・抱っこや抱っこ紐にいれてお散歩するのも効果的です。
朝は6時ころまでに起床して、午前中は公園に行ったり支援センターで遊ばせたり、、、
とにかく体を疲れさせて、11:30頃にはお昼寝の体制をとっていましたzzz
遊びに付き合う午前中は大変でしたが、お昼寝してくれるとやっと自分の時間が出来てほっとしていましたね(*^-^*)
一歳の子供の昼寝にオススメ!快眠できる子供用の布団を紹介!

お昼寝する時に「お昼寝用の布団」を使っているお家も多いのではないでしょうか??
そこでここでは、赤ちゃんが快適に眠ることのできるお昼寝布団の中でも、オススメのポイントをご紹介します。
(1)どんな布団を選べばいいの??
お昼寝布団を選ぶポイントとしてあげられるのが、
- お洗濯しやすい
- コンパクトで収納しやすい
- 肌触りがよい
赤ちゃんは汗をかきやすく、吐き戻しなどで布団を汚すことが多いですよね。
なので「お洗濯しやすい」というのは必須条件ですよね!
あとは、少しでも赤ちゃんが眠りやすい環境を整えてあげるためにも、布団の素材や肌触りにもこだわりたいものですね(^^)
(2)赤ちゃんの快適な睡眠のため!オススメ布団5選!!
布団の中綿にはテイジンの洗えるウォッシャブルを使用しているので、全部じゃぶじゃぶ洗うことができるのも嬉しいポイントです(#^^#)
![]() 「HashkuDe オーガニックダブルガーゼ 洗えるベビー布団11点セット」を楽天市場で見てみる
「HashkuDe オーガニックダブルガーゼ 洗えるベビー布団11点セット」を楽天市場で見てみる
もちろん、すべて自宅の洗濯機でお洗濯可能です!
二重ガーゼを使用しているので、肌触りもとっても良いですよ(^^)
このまま保育園用にすることができちゃいます。
自宅の洗濯機で丸洗い可能です!
個人的には、きのこの柄がとっても可愛くて、デザイン一押しです(*^-^*)
![]() 「Hoppetta お昼寝ふとんセット」を楽天市場で見てみる
「Hoppetta お昼寝ふとんセット」を楽天市場で見てみる
10点がセットになっているので、オールシーズンこのセットで大丈夫!
おねしょシーツがついているのも嬉しいポイントですね(^^)
![]() 「西川リビング ベビー組ふとん10点セット」を楽天市場で見てみる
「西川リビング ベビー組ふとん10点セット」を楽天市場で見てみる
ブランケットや枕などもまとめて持ち運びができるので、外出さきでも使用可能です。
お布団バッグは簡易ベットに早変わりしちゃいます(*^-^*)
1歳の子が昼寝で泣く!のまとめ
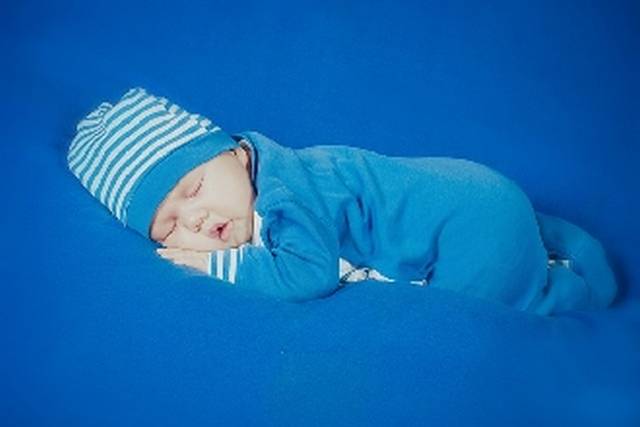
お昼寝布団ひとつ見てみても、とても沢山の種類があるので、迷っちゃいますよね(><)
その子によって、お昼寝しやすい環境も入眠儀式も様々です。
色々な方法を試しながら、赤ちゃんとママにとって一番負担にならない方法を見つけられるといいですね(^^)
素敵なお昼寝タイムになることをお祈りしております(*^^*)