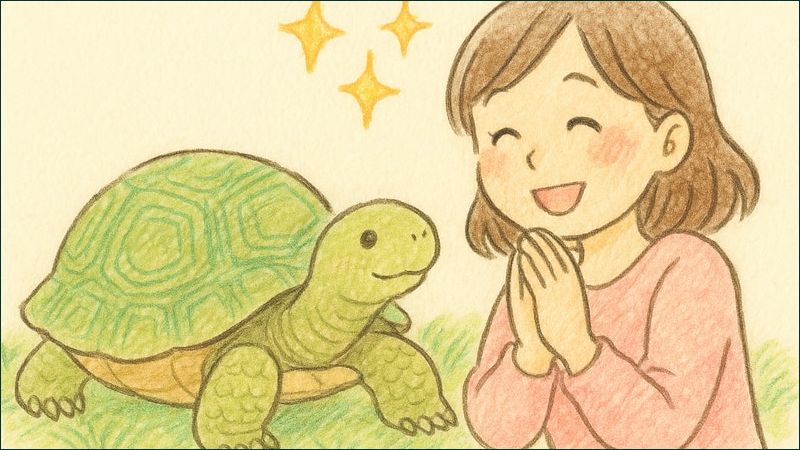リクガメってのんびりしてて癒し系で…
でも、「大きくなりすぎたら飼えなくなるかも?」ってちょっと不安になったこと、ありませんか?
「小さいままでいてくれたらいいのに」
「うちの子、なんか成長が止まってる気がする…」
そんなふうに感じているあなたへ。
実際、リクガメって種類によって成長速度や大きさが全然違うんですよね。
うちの子も、最初はてのひらサイズで「ずっとこのままかも!」とウキウキしてたんですが、半年後には手のひらからあふれるほどに成長してて「え、どこまで大きくなるの…?」と内心ドキドキした経験があります(笑)
この記事では、リクガメが大きくならない原因と、小型で飼いやすい種類、そしてゆるやかな成長を保つためのポイントまで、ぜんぶまとめてお届けします。
もちろん「大きくならない=何かおかしい?」と心配している方にも、「これからリクガメを飼いたいけどスペースが不安…」という方にも、役立つ内容になっています。
ちなみに筆者も「ちっちゃいカメのままでいてくれ…!」って何度祈ったことか(笑)
でもね、ただ小さいってだけじゃなくて、「ちゃんと健康でいてくれてるか?」が本当はもっと大事なんですよね。
リクガメって、見た目はマイペースに見えるけど、意外と環境の変化に敏感な繊細ちゃん。
だからこそ、飼い主側のちょっとした配慮や理解が、とっても大きな差を生むんです。
それでは一緒に、リクガメとのちょうどいい距離感を探っていきましょう。
「小さくてかわいい」だけじゃなく、「元気で幸せそう」に暮らしてもらうために。
リクガメはどれくらい大きくなるの?
よく見かけるリクガメのサイズ比較
リクガメって聞くと、手のひらサイズを想像する人もいるかもしれません。
でも種類によっては、最終的に体長40~50cm以上になることも。
代表的なホシガメやケヅメリクガメは大きくなるタイプで、飼育スペースの確保が必要です。
ホシガメは見た目も美しく、人気のある品種ではありますが。
でも成体になると、想像以上に場所を取るようになり、「思ったより広いケージが必要だった…」という声もよく耳にします。
特にケヅメリクガメは成長すると体重30kg以上になることもあり、庭や屋外飼育が前提になる場合もあります。
ケヅメの場合、ただ“飼う”というより、“共に暮らす”レベルの覚悟が必要になることも。
小さなうちはかわいくても、いずれ「置き場所がない…!」と困ってしまう飼い主さんもいるんです。
「ケヅメを玄関で放し飼いにしてたら家族より先にお迎えに来るようになった」なんて笑い話もあるくらい(笑)
でも本当に、スペース問題は真剣に考えたいポイントなんですよね。
「小型種」と「大型種」の違いを知ろう
小型種は20cm前後に収まることが多く、ギリシャリクガメやヘルマンリクガメが人気。
成長スピードもおだやかなので、初心者にはうれしい存在です。
中には「成体でも15cm台」で収まる個体もいて、狭いスペースでも無理なく飼えます。
こうした小型種は、室内飼育にも向いており、シンプルなケージや衣装ケースでも十分な空間を確保できるのが魅力です。
しかも温和な性格の子が多いので、初めて爬虫類を飼う方にもおすすめです。
一方で、ケヅメやアルダブラゾウガメといった大型種は成長が早く、数年で劇的にサイズアップすることもめずらしくありません。
毎年見るたびに「え、また大きくなってない?」と思うくらいの成長スピードなんです。
大型種を選ぶときは「今の自分の生活スタイルと5年後のリクガメのサイズ」を天秤にかけて考えるのがポイントです。
家族のライフスタイルの変化(引っ越し、結婚、子育てなど)に合わせて柔軟に対応できるかも含めて、「飼える環境」と「続けられる環境」は別物だという意識が必要ですね。
大きくならないリクガメのおすすめ種類
成体でも20cm以下の小型リクガメとは
小型種の代表格は、ヘルマンリクガメ・ニシヘルマン・ギリシャリクガメなど。
これらの種類は、成長しても体長が15~20cm前後で止まることが多く、室内でも比較的飼育しやすいのが特徴です。
中でもギリシャリクガメは飼いやすさと丈夫さでファンが多く、長寿な種類としても知られています。
気性も比較的穏やかで、よく食べ、よく歩く元気な子が多いのも魅力です。
好奇心旺盛で、人の手からエサを食べたり、近づくと寄ってくるような子もいるので、リクガメとの距離が近く感じられるのもポイントです。
また、ロシアリクガメ(ヨツユビリクガメ)も体長20cm前後で止まる個体が多く、根強い人気があります。
乾燥地帯に生息するため湿度の管理が比較的しやすく、日本の気候にもなじみやすいと言われています。
ただし、輸入個体も多いため、健康チェックや寄生虫対策などは慎重に行いたいところです。
近年ではレア種として、マルギナータリクガメ(フチゾリリクガメ)も注目されています。
やや大きめに育つこともありますが、個体によっては20cm未満でおさまるものもあり、見た目の美しさとおだやかな性格が魅力です。
飼いやすさで選ぶならこの品種
初心者向けなら、気性が穏やかで丈夫なヘルマンリクガメがおすすめです。
ヘルマンリクガメは比較的流通量も多く、飼育情報や飼育経験者のブログ・動画などもたくさんあるので、調べればすぐに情報が得られる点も心強いです。
さらに、ヘルマンリクガメは気温の変化にも強く、丈夫でストレス耐性が高く、病気にもなりにくい傾向があります。
少し荒めの床材でも平気で歩き回れるたくましさがあり、活発に行動する姿は見ていて飽きません。
また、ニシヘルマンリクガメはヘルマンの中でもさらに小型で、飼育スペースをコンパクトに抑えたい人にはぴったりです。
性格もおだやかで、慣れると手から餌を受け取ったり、飼い主の存在をしっかり覚える個体も多く、「カメなのに懐いてくれる!」と驚く飼い主さんも少なくありません。
「小さめサイズで、丈夫で、のんびり飼える子がいいな…」という方には、まさにこれらの品種がぴったりのパートナーになってくれるでしょう。
飼っているリクガメが成長しないときの原因
成長不良の可能性とそのサイン
元気がなくてエサも食べない、甲羅がやわらかい、目が腫れてる…そんなときは成長不良かもしれません。
成長が止まっているように見えると、飼い主としてはとても不安になりますよね。
毎日お世話をしていて、「昨日と比べて何も変わっていない気がする…」そんな風に感じることが続くと、「このままで大丈夫なの?」と心配になってしまいます。
実は、リクガメの成長にはとても繊細なバランスが関わっていて、そのバランスが崩れてしまうと、体の中でさまざまな影響が出てしまうんです。
特にカルシウムやビタミンD3が足りないと、骨や甲羅の成長が滞り、**くる病(骨の発達障害)**と呼ばれる状態になってしまうこともあります。
このくる病になると、甲羅が変形したり、足が曲がったままになったりといった深刻な状態になることがあるため、なるべく早めに対処してあげる必要があります。
さらに、甲羅がふにゃっと柔らかくなっている場合や、食欲が落ちているようであれば、それは体の中で「ちょっと助けて!」というサインかもしれません。
目が腫れているのもよくあるサインのひとつで、これはビタミンAの不足や、環境の乾燥が影響していることも。
リクガメの目元って意外と感情が出るというか、パッチリ開いていたり、じっと閉じていたりするだけで、体調のバロメーターになっていたりするんですよね。
エサ・紫外線・温度など環境要因のチェック
カルシウム・ビタミンD3の不足、紫外線不足、温度管理の不備──どれもリクガメの成長には深く関わっています。
「エサは与えてるし…」ではなく、**何を・どれだけ・どうやって与えているか?**まで見直してみましょう。
野菜の種類に偏りがあったり、乾燥野菜ばかりになっていたりしませんか?
リクガメは、チンゲン菜や小松菜のような緑黄色野菜をメインにしつつ、ときには野草やハーブも混ぜてあげるとバランスが良くなります。
そこにカルシウムのパウダーをふりかけて、週に何度かはビタミンD3のサプリも加えてみてください。
栄養面の底上げができるだけで、リクガメの元気さがぐっと変わることも多いです。
また、紫外線ライトの照射距離が近すぎる/遠すぎることもよくあるトラブル。
適切な距離はライトの種類によって異なるので、説明書を必ず読みましょう。
新品のときと、数カ月後とでは紫外線の出方が変わってくるので、「ちゃんと光ってるから大丈夫」ではなく、「ちゃんと紫外線が出ているか?」を意識することが大事です。
さらに、温度が低すぎたり、湿度が足りなかったりすると、代謝が落ちてエサを食べなくなることもあります。
ケージの温度や湿度はこまめに確認し、必要に応じてヒーターや加湿器を活用して、リクガメにとって心地よい環境を保ってあげてくださいね。
ちょっとしたことが原因で、成長が止まってしまうこともあるからこそ、毎日の観察と気づきがとても大切なんです。
成長をゆるやかに保つ飼育のポイント
早く大きくしすぎないための注意点
「成長しないように」と思っていても、リクガメが本来持っているポテンシャルまで押さえ込むのは不自然。
“健康的にゆっくり育つ”を目指しましょう。
急激に大きくなると、内臓や骨に負担がかかってしまい、健康トラブルのリスクも高くなります。
特に幼体期に急速に成長させようとして、毎日たくさん食べさせたり、高カロリーなフードを多用してしまうと。。。
体の成長に甲羅の成長が追いつかず、見た目もガタガタな形になってしまうことがあります。
これは「ピラミディング」と呼ばれる状態で、一度そうなると元に戻すのが難しくなるため、未然に防ぐことがとても重要なんです。
人工飼料は便利ですが、そればかりに頼ると栄養バランスが偏りがちになります。
自然に近い野草や野菜を中心にし、フードは“補助”として使う感覚がベストです。
また、与える頻度も工夫しましょう。
毎日同じ量を与えるより、日によって「控えめの日」を作ることで、野生に近いリズムを取り戻せることがあります。
人間だって食べすぎた翌日は自然と食が細くなるように、リクガメにも緩急あるリズムが必要です。
小さいままで健康を保つコツ
基本は、野草中心のバランスの取れた食事と、適度な日光浴。
自然に近い環境づくりが、健康な成長と“ちょうどいいサイズ”につながります。
焦らず、のんびり育てることが一番の近道です。
野草にはさまざまな栄養素が含まれていて、リクガメにとっては理想のごちそう。
タンポポ、オオバコ、ノゲシなど、身近にある安全な野草を取り入れることで、自然な食事サイクルが整いやすくなります。
もし手に入らない場合でも、冷凍保存できる市販の野草ミックスなどを上手に取り入れると良いでしょう。
さらに、日光浴も欠かせません。
室内飼育ではUVBライトに頼ることになりますが、可能であれば週に数回は短時間でも直射日光を浴びさせてあげることで、体の調子がグンと整います。
日光には紫外線だけでなく、心理的なリフレッシュ効果もあると言われており、動きが活発になったり、食欲が戻ることもあるんですよ。
また、週に1回ほどの体重測定もおすすめです。
少しずつでも増えていれば、成長は順調。
数値として記録を取っていくことで、日々の変化に気づきやすくなり、早期対応が可能になります。
逆に、変化がない・減っている場合は、環境の見直しが必要かもしれません。
湿度や気温、食事の内容や光の当たり方…「今のこの子にとって本当に快適かな?」という視点で、もう一度全体を見直してみてください。
そして何より、リクガメは個体差が大きい動物です。
「他の子より小さいからダメ」ではなく、「うちの子はうちの子のペースで成長している」と思えるようになると、飼育の時間そのものがもっと豊かに、楽しく感じられるようになりますよ。
大きくならない種類を選ぶときの注意点
流通が少ないリクガメは高価なことも
小型種は人気がある反面、流通数が限られている種類も多く、価格が高めになる傾向があります。
「かわいいから」で飛びつく前に、きちんと飼育環境やコストも検討してから選びましょう。
人気の小型種ほど需要が高く、ペットショップやブリーダーでもすぐに売り切れてしまうことが多くなっています。
そのため、どうしても欲しい種類がある場合は、事前に入荷時期を問い合わせたり、予約を入れたりするなど、準備が必要になることもあります。
特にCB(ブリードされた国内繁殖個体)を選ぶと、健康面でも安心ですが価格はさらに高くなります。
CB個体は、野生からの輸入に比べてストレスが少なく、寄生虫などのリスクも少ないため、初心者にとっても扱いやすいメリットがあります。
一見すると高額に感じられるかもしれませんが、実際には後々の医療費や飼育トラブルのリスクを考えると、むしろ“安い買い物”と感じる飼い主さんも多いです。
長い目で見たときに、「健康な子を選ぶ」という視点はとても大切な判断材料になります。
飼育環境の準備はサイズだけでは決まらない
「小さい=簡単」とは限りません。
リクガメはとても繊細な生き物。
サイズだけで判断せず、日々の温湿度管理や紫外線ライトなどの飼育設備も見据えて準備を整えることが大切です。
小さなリクガメだからといって、簡易なケージや設備で済ませてしまうと、ストレスを感じたり体調を崩したりすることがあります。
たとえば、風通しの悪い場所に置いたり、温度が安定しない環境に長く置いてしまったりすると、免疫力が下がってしまうんです。
例えば、たとえ20cm以下のカメでも、毎日湿度60%以上を保たないと調子を崩す子もいます。
乾燥しやすい冬場には、加湿器や霧吹きでの調整も欠かせませんし、紫外線ライトは半年~1年で照射効果が落ちてしまうため、定期的な交換が必要です。
さらに、シェルターや隠れ家の設置、床材の選び方ひとつでもカメのストレスレベルは大きく変わります。
「なんとなく」で決めてしまうのではなく、「この子にとってどんな環境が落ち着くのか?」を意識して準備していくことが、リクガメと長く穏やかに暮らしていくための第一歩になります。
サイズだけで安心せず、「その子に合った暮らし方」を第一に考えましょう。
大きくなってしまったときの対処法はある?
飼育スペースの拡張アイデア
もし想定より大きく育ってしまったら──まずは焦らず、飼育スペースを広げる工夫を考えてみましょう。
市販のケージでは手狭なら、衣装ケースや自作ケージを活用するのも一つの手です。
木材やアクリル板を使った自作ケージは、サイズや形状も自由に調整でき、意外とコストを抑えて作ることができます。
また、天気の良い日には庭やベランダで過ごす「日中だけ屋外飼育」も視野に入れると、カメもリフレッシュできます。
脱走対策と紫外線の当たり方には十分注意してあげましょう。
とくに夏場は直射日光が強すぎて熱中症になるリスクがあるため、日陰を作れる場所や水場の確保が欠かせません。
さらに、家の中でも床を一部囲って“室内放し飼いエリア”を作るのも選択肢のひとつです。
その際には、電気コードや小物をかじられないよう工夫をし、事故のないよう配慮することが大切です。
それでも飼えない場合の相談先とは
どうしても飼い続けるのが難しくなった場合、信頼できるブリーダーや保護施設に相談するのも選択肢のひとつ。
最後まで責任を持つために、事前の下調べが大切です。
受け入れてくれる施設は限られており、事前の連絡や条件の確認が必要な場合が多いので、早めに動くことがポイントです。
SNSやブログで「里親募集」をかける際も、必ず相手の飼育環境や過去の飼育実績を確認しましょう。
できれば実際に連絡を取り合い、写真やビデオ通話で相手の飼育環境を見せてもらうと安心です。
また、無責任な引き渡しを避けるために、譲渡契約書を交わしておくのもひとつの方法です。
カメの命をつなぐ、最後まで“思いやり”を忘れずに。
どんな事情があっても、「命を預かった責任」は最後まで持ち続ける姿勢が大切です。
まとめ
リクガメがなかなか大きくならない──それはもしかしたら、「その子なりのペースでゆっくり育ってるだけ」かもしれません。
リクガメは個体差がとても大きく、早く成長する子もいれば、じっくり時間をかけて育っていく子もいます。
だから、他のリクガメと比べて「うちの子は小さいかも…」と不安になってしまうのはよくあること。
でも、比べることよりも“その子自身の調子”を見つめてあげることが大切です。
だけど、もし「全然食べない」「ずっと動かない」といった様子が見られるなら、
- 栄養バランス(特にカルシウム・ビタミンD3)
- 紫外線や温湿度などの飼育環境
- 種類に合った成長スピード
ちょっとした気づきや工夫が、ぐんと成長の手助けになることもあります。
温度計や紫外線測定器を使って環境を見直したり、食事に粉末カルシウムを加えるだけでも、意外な変化が見られるかもしれません。
リクガメの成長は“急成長”より“じっくりコツコツ”がちょうどいい。
その子のペースに寄り添いながら、「小さくても、元気に生きてる」そんな毎日を大事にしていきましょう。
元気なまなざし、食べるときの表情、ゆっくり歩くその姿
どれもが愛おしい成長の証です。
焦らなくていい。
その子なりの“成長の物語”を、今日もあなたと一緒に紡いでいけますように。
たとえ小さな一歩でも、あなたがそばにいる限り、その一歩は確かに“前進”しています。