
発達障害という言葉は最近とてもよく耳にするようになりましたが、「一次障害」と「二次障害」の違いまできちんと知っている人は少ないかもしれません。
私も家族に発達障害があるとわかったとき、何から理解していいのかまったくわからず、どう接していいのか悩んで戸惑うばかりでした。
それでも少しずつ調べる中で、一次障害と二次障害の意味や違いが見えてくると、本人に対する声かけや環境の整え方が変わり、表情がやわらいでいったのを今でも覚えています。
違いを知ることで家族の支え方が前向きに変わるんですね。
この記事では、私自身の体験談も交えながら、一次障害と二次障害の特徴や原因、周りができるサポートの具体的な工夫まで、できるだけわかりやすくたっぷりとお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
一次障害と二次障害とは?基本の考え方
発達障害における「一次障害」とは
一次障害は、生まれつきの脳の特性によって現れる発達障害そのものを指します。
具体的には、
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
例えば授業中にじっとしていられなかったり、友達との会話の意図が読み取れずに誤解されたりすることがあります。
私の家族も幼い頃から「落ち着きがない」「空気が読めない」と言われていましたが、それが一次障害の特性なんだと後から知りました。
今思えば、そのころに周りの理解や支援があれば、もっと本人の自信を守れたかもしれないと思うこともあります。
「二次障害」とは何を指すのか
一方で二次障害は、一次障害による生きづらさや周囲の理解不足によって後から心に傷がつき、うつや不安障害などの精神的な症状が出てくる状態です。
周囲に責められたり孤立したりすることで、本人は自分を責めてしまうんですね。
家族の中でも「どうしてうまくできないんだろう」と悩んでしまい、学校に行けなくなったり気力を失ったりする姿を見て、胸が痛くなったのを覚えています。
そのときに私が感じたのは、二次障害の背景には深い悲しみや諦めが隠れているということでした。
一次と二次はどちらが「重い」という意味ではない
大切なのは、どちらが重いという話ではなく、それぞれに必要な支え方が違うということです。
一次障害は特性を理解して環境を調整することが大切ですし、二次障害は心のケアが重要です。
一次と二次を区別して理解してあげることが、本人の負担を減らす第一歩なんですよね。
こうした視点を持つだけで、本人の安心感はずいぶん変わってくると私は感じています。
一次障害と二次障害の違い
原因の違い
一次障害は先天的な脳の発達の特性が原因です。
それに対して二次障害は、一次障害による失敗体験やいじめ、周囲からのプレッシャーなど、いろいろな外的なストレスが積み重なることで引き起こされます。
さらに、本人の性格やそのときの環境の影響も大きく関わっていて、ストレスに弱い状況に置かれた場合に二次障害は強く出やすいです。
私が実感したのは、ほんの小さな失敗の積み重ねが、思った以上に心に深い傷を残してしまうということでした。
しかも一度自信を失うと、なかなか立ち直れず負のスパイラルに陥りがちです。
周囲のサポートや理解がないと、本人は「自分が悪いんだ」「何をしてもダメだ」と感じてしまい、心を閉ざしてしまうこともあります。
その姿を見るのは本当に辛いものです。
現れるタイミングの違い
一次障害は幼少期から現れやすく、親や先生が比較的早い段階で気づけることも多いですが、二次障害は思春期以降や大人になってから症状がはっきり出ることも少なくありません。
私の家族も、小学生のころは「変わってる子」程度で周りからも軽く見られていましたが、中学に入ってからは二次障害が強く出てしまい、学校に行けなくなり不登校や引きこもりが続き、さらには心身のバランスを崩して体調まで悪くしてしまいました。
思春期以降は周囲からの期待や社会のルールがどんどん増えていくので、耐えきれずに心が壊れてしまうケースが多いのだと痛感しました。
親としては気づいてあげたい気持ちがあっても、なかなか言葉にしてくれず見過ごしがちなので、普段の様子をよく見ておくことが大切なんですね。
症状や影響の違い
一次障害は特性として行動や認知の違いが見られるのに対し、二次障害は心の病としての苦しみが強く出ます。
例えば、社会的な孤立感や無力感、自分には価値がないと思い込んでしまうなど、本人の自己否定が強くなっていくのが特徴です。
さらに、周囲に支えがない場合は不安感が増し、恐怖やパニックを伴うこともあります。
本人も「なぜこんなに苦しいのかわからない」と混乱してしまい、周囲が声をかけても届かないような感覚を持ってしまうこともあります。
その姿を見るのは本当に切なく、こちらもどうしていいかわからず悩みました。
私自身も何度も涙を流しながら試行錯誤して支え続けましたが、それでも小さな変化が見えたときの喜びは大きいものでした。
治療やサポートの違い
一次障害は療育や環境調整による支援が中心ですが、二次障害は心療内科やカウンセリングによる治療が必要になります。
特に、本人が安心できる環境を整えながら、医師やカウンセラーと一緒に少しずつ症状に向き合うことが大切です。
本人の気持ちを否定せず、焦らずにゆっくりと回復を待つ姿勢が大切ですし、家族としても学びながら支える気持ちが必要です。
私たち家族も、早めに医療や福祉の力を借りて、どう支えればいいかを一緒に考えられたことで、少しずつ前を向けるようになりました。
専門家との連携が重要だと強く感じますし、決して一人で抱え込まないことが何よりも大切だと今は思います。
二次障害が起きる理由
周囲の理解不足やストレス
「変わり者」「怠けてる」と誤解されることが何より本人を苦しめます。
周囲からの心ない言葉が積み重なると、本人はますます自分を責めるようになり、周りとの距離を感じてしまいます。
私も、学校の先生に「もっと頑張れ」と言われていた家族を見て、胸が締め付けられるように悔しくてたまりませんでした。
そして、その後も長くその言葉に苦しめられていた姿が忘れられません。
自己肯定感の低下
できることよりも「できないこと」ばかり指摘されると、自信を失い自己評価がどんどん下がってしまうんです。
特に、周囲から褒められる機会が少ないと「どうせ自分なんて」と諦めの気持ちが強くなり、何かに挑戦する意欲さえ失われてしまうようになります。
それが二次障害を悪化させる大きな原因のひとつだと感じます。
環境調整の不十分さ
無理を強いられる環境で過ごし続けると、限界を迎えて心身の調子を崩しやすくなります。
例えば学校や職場で本人に合わないやり方を押し付けられたり、人間関係のトラブルを放置されたりすると、そのストレスが少しずつ積み重なり、耐えきれなくなるんですね。
本人に合った環境作りが本当に大切だと実感しましたし、少しでも居心地のいい空間があるだけで、心が落ち着くのを何度も見てきました。
家族や周囲の人が少し気を配るだけでも大きく変わるんですよ。
一次障害と二次障害を区別するメリット
適切な支援の第一歩になる
違いを知っていると、必要な支援の方向性が見えやすくなります。
「何に困っているのか」がわかると、本人も安心できますし、周りも動きやすくなりますよ。
それに、支援の優先順位やどこに焦点を当てるべきかが見えてくるので、サポートが的確になります。
私も実際に、何が一次の特性で何が二次の苦しみなのかが分かった瞬間に、「じゃあこうしてみよう」という行動に移せるようになり、前向きに動けるようになりました。
本人と家族が安心できる
二次障害の原因が理解できると「甘えじゃなかったんだ」と納得でき、支える側も少し心が軽くなりました。
さらに、周囲の人たちに説明するときも「こういう背景があるんです」と伝えられるので、誤解が減るのも大きなメリットです。
何より、本人が「自分が悪いわけじゃない」と気づけるのが本当に大きいと思います。
私の家族も、自分を責めるのをやめて少しずつ表情が和らいでいったのを見て、家族としてもホッとしましたし、その後の接し方にも余裕が生まれました。
区別する知識が、安心感や希望につながるんですね。
—
二次障害を防ぐ・軽減するための工夫
本人への配慮と声かけ
「頑張らなくてもいいよ」「そばにいるよ」という言葉だけでも、安心感につながります。
私もそれを繰り返し伝えてきましたし、調子が悪そうな日は無理に励まさずそっと寄り添うようにしています。
本人にとっては「見守ってくれている」というだけで気が楽になるものです。
時には一緒に散歩したり、好きなものの話をして気を紛らわせるなど、小さな関わりも大きな意味を持ちます。
学校や職場の環境調整
無理をしなくていい環境を作ることが、二次障害の予防に役立ちます。
具体的には、席の位置を変えたり、仕事内容を調整したりといったちょっとした工夫で本人の負担が減ります。
例えば音が気になりにくい席や、プレッシャーの少ない作業を任せるだけでも、安心して過ごせるようになるのを実感しました。
周りの人への理解を広めるために話し合いの場を設けるのもおすすめです。
柔軟に対応していく姿勢が大切です。
専門機関の利用やカウンセリング
一人で抱え込まずに、専門家の力を借りるのも大切です。
実際、私の家族もカウンセラーさんと話したことで表情がやわらかくなっていきました。
定期的に通うことで気持ちが整理され、自分でも対処法を見つけられるようになります。
医師や支援機関との連携を取ることで、本人も家族も安心して生活できる基盤が整っていきます。
時には福祉サービスや支援グループに参加するのも心強いですよ。
まとめ
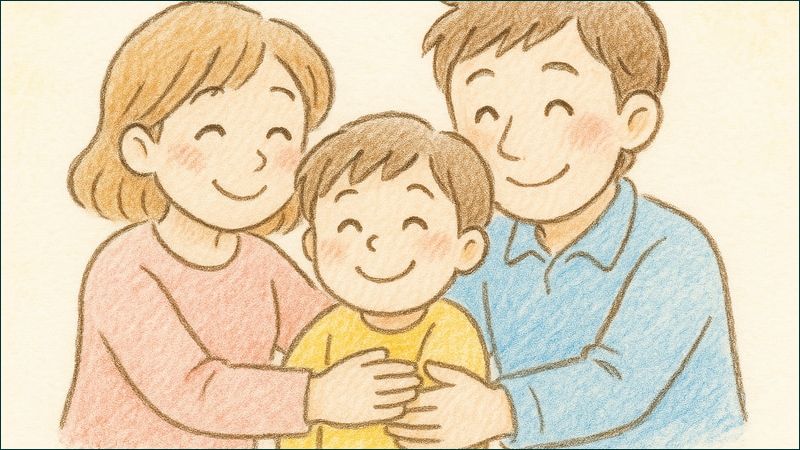
一次障害と二次障害の違いを知ると、今まで見えなかった苦しみや小さな希望が少しずつ見えてきます。
それによって本人が安心して過ごせるように、周りが知ること、寄り添うことが本当に大切なんだと、私も強く感じています。
違いを理解した上で行動することで、本人の表情や日々の生活が少しずつ前向きに変わっていくのを何度も目の当たりにしてきました。
あなたや、あなたの大事な人が少しでも楽に生きられるように、そして支える側も無理しすぎず一緒に歩んでいけるように、この記事が少しでもお役に立てばうれしいです。
焦らずに、ゆっくりと一歩ずつ、時には立ち止まりながらでも前を向いていきましょうね。