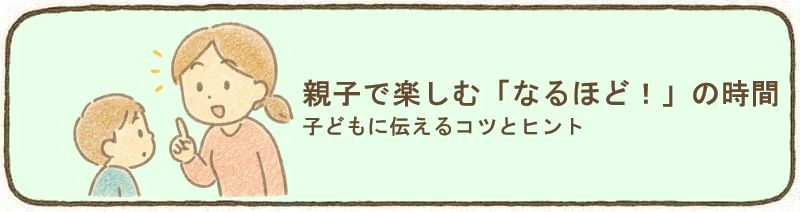「ねぇママ、なんで豆まくの?」「鬼って本当にいるの?」そんな素朴でまっすぐな質問が飛んできたのは、節分が近づいたある日の夕方でした。
保育園から帰ってきた娘が、園で読んでもらった絵本の影響もあってか、目をキラキラさせながら聞いてきたんです。
私は「よしきた、これはしっかり説明してあげよう」と思ったものの、いざ口を開こうとしたら言葉に詰まってしまって。
「うーん…節分っていうのはね、えーと…」とごまかしていたら、娘は早々に興味を失ったのか「ふーん、そうなんや」と一言だけ残して、おやつの方に夢中になってしまいました。
あのときの“置いていかれた感”が妙にくやしくて、ちゃんとわかりやすく伝えたいという気持ちがじわじわ湧いてきたんです。
子どもに説明するときって、大人が知っていることをそのまま伝えればいいわけじゃないんですよね。
どんな言葉なら伝わるか、どこがわからないポイントなのか、そこをちゃんと想像して、子ども目線で話してあげることって本当に大事なんだなと実感しました。
この記事では、私自身がつまずいた体験もふまえて、幼稚園児に“ふーん”で終わらせない節分の伝え方をお届けします。
幼稚園児に節分を説明するときに大切なこと
節分の意味や豆まきの由来は、私たち大人にとっては「まあなんとなく知ってるよ」という感覚かもしれません。
でも、それをそのまま子どもに伝えたところで、必ずしも理解してくれるとは限らないんですよね。
実際、私はかつて「季節の変わり目でね…」なんて一生懸命説明したのに、我が子から返ってきたのは「ふーん、そうなんや」の一言だけでした。
正直ちょっと切なかったです。
子どもにとって、“わかる”ってどういうことなのかを、もう一度こっちがちゃんと考え直す必要があるのだと痛感しました。
知識を詰め込むような説明じゃなく、子どもが「それ、なんかいいね!」って感じられるような言葉の選び方と伝え方がとても大切なんです。
言葉の意味が通じても、世界観がまだ育ちきっていない
年長さんくらいになると、言葉の意味そのものはだいぶ理解できるようになります。
「節分って季節の変わり目の行事なんだよ」って言えば、「ふーん」とは返ってきます。
でもその「ふーん」の裏には、「それってどういうこと?」という疑問が潜んでいることもあるんです。
子どもは、言葉の意味は表面上なぞれても、それが自分の世界にどう関係しているのかまでは、まだうまくつなげて考えられないことも多いんですよね。
1年や季節の概念はまだ“ふんわりした雲”のようなもの
カレンダーを見て、「今日は2月だね」とは言えるけれど、それが
「1年の中でどのへんに位置しているのか」
「季節の節目にあたる」
みたいなことまでは、幼稚園児にはまだピンとこないのが自然です。
まだまだ数えることに一生懸命な時期ですから、「春の前に悪いものを追い払うんだよ」というのも、抽象的すぎると届かないんですよね。
“知識”よりも“感覚”に落とし込むことが大切
だからこそ、大人が意識したいのは「教える」のではなく「感じさせてあげる」こと。
たとえば
「春になるとお花が咲くよね」
「ポカポカして上着いらなくなってくるね」
といった、子ども自身の体験とつなげて話すことで、「ああ、そういうことか!」と納得してくれることがあります。
「鬼ってね、風邪をひいちゃったりケンカしちゃったり、そういうイヤなことを運んでくるんだって」と伝えれば。
子どもは「それやだ!豆でやっつけよう!」とワクワクしながら理解してくれたりするんです。
知識の正確さも大事だけど、それ以上に子どもが“心で感じられる説明”をしてあげるほうが、ずっと深く伝わるんだなと、私自身も節分を通して実感しました。
子どもに伝えるために、まず大人が「寄り添う視点」を持つ
親として「ちゃんと説明してあげたい」「わかってもらいたい」と思うからこそ、難しい言葉や歴史的な背景をつい真面目に並べてしまいがちなんですよね。
でも子どもは、その温度差を敏感に感じ取ります。
「自分に関係のあることだ」って思えるかどうかが、理解のカギになるんです。
だから、大人が知っていることを押し付けるのではなく、子どもの今の世界に合わせて“言葉を選んであげること”が、何より大切なんだと思います。
「この子にはどう言ったら伝わるかな?」と、一歩引いて相手の目線に立つこと。
それが、節分を通して伝えたい“心の育て方”にもつながっていく気がしています。
そもそも節分ってなに?大人も知っておきたい基本の意味
「節分ってどういう意味?」と聞かれて、即答できる大人ってどれくらいいるんでしょうか。
私もつい最近までは、「豆まきの日」くらいのざっくりした認識しかありませんでした。
でも子どもに聞かれたとき、しどろもどろになるのって、ちょっと悔しいし恥ずかしいんですよね。
だからこそまずは、私たち自身が節分について改めてきちんと知っておくことが大切です。
きちんと理解できていれば、それを子どもに合わせた言葉で、やさしく伝えてあげることができるようになります。
「節分=季節の変わり目」という考え方
節分という言葉は、「季節を分ける」と書きます。
つまり、季節の変わり目のことを指しているんですね。
春・夏・秋・冬という四季があるように、昔の日本ではそれぞれの季節の始まりには特別な意味があったんです。
そして、季節が変わる前日が「節分」と呼ばれていました。
だから、実は昔は年に4回、節分があったんですよ。
今の節分が「春だけ」になった理由
じゃあ、なぜ今は「春の節分」だけが残っているんだろう?実は、昔のカレンダー(旧暦)では、立春が“1年のはじまり”だったからなんです。
つまり、春はお正月と同じくらい特別なスタートの日だったんですね。
その前日にあたる節分は、“大晦日”的な存在として、大切にされていたんです。
新しい年を迎える前に、悪いものを追い払って、心も空気もすっきり整える。
それが節分の本来の役割だったんですね。
節分は“心の切り替えスイッチ”でもあった
節分って、実はただの「豆まきイベント」ではなく、“新しい季節に向けて自分を整える儀式”でもあったんです。
寒さが続く時期に、春が来ることを感じながら、「さあ、ここから新しい流れが始まるんだな」と意識を切り替えるきっかけ。
そう思うと、大人にとっても心がしゃんとするような行事だったんだろうなと想像できます。
“鬼”の正体を子どもにも伝えやすく解説
節分といえば「鬼は~そと、福は~うち!」の掛け声でおなじみですが、そもそもこの“鬼”って何者なんでしょうか。
子どもに聞かれて、「うーん、怖いもの…?」なんて答えたら、「じゃあどこにいるの?なんで豆で追い払えるの?」とさらにツッコまれてしまうかもしれません。
でもこの“鬼”という存在、実はとても奥が深いんです。
きちんと背景を知っておけば、子どもにもわかりやすく、そしてちょっと面白く伝えることができますよ。
“鬼”は見えない不安や悪いものの象徴だった
昔の人にとって“鬼”は、ただの怖い存在ではなく、病気や災い、争いごとや心の乱れなど、「目には見えないけど、良くないこと」の象徴でした。
現代で言うなら、
「風邪をひいたり」
「お友達とケンカしちゃったり」
「朝起きられなかったり」
そういう“困ったこと”や“イヤな気持ち”も、全部“鬼”のしわざと考えていたんです。
だから豆をまくことで「もう来ないで!」と、そうした悪い流れをお家の外に追い払っていたんですね。
子どもに伝えるなら「鬼=困ったこと」のイメージで
子どもにとって、鬼は絵本やアニメの中の“怖いキャラクター”という印象が強いかもしれません。
でもそこに、“今の自分の困っていること”を重ねると、ぐっと身近に感じられるようになります。
「寝坊しちゃう鬼」
「風邪をひかせる鬼」
「おこりんぼうにさせる鬼」
など、子どもが想像しやすい“自分の中の鬼”に置きかえて話してあげると、豆まきの意味がスッと入っていくようになりますよ。
“鬼”の語源には、実は深い説がある
ちなみに“鬼”という言葉には、昔の日本語で「隠れていて見えないもの」という意味が込められていたと言われています。
「陰(おん)」という言葉が「おに」に変化した説や、「隠人(おんにん)」という、怖くて見えない存在を指す言葉が変化したという説などがありました。
もちろん小さな子どもに難しく語る必要はありませんが、「昔の人は、見えない怖いことを“鬼”って呼んでいたんだって」と、ふわっと伝えるだけでも、興味を持ってくれる子は多いですよ。
どうして豆をまくの?の理由をやさしく言いかえる
節分といえば“豆まき”。
でも、なぜ「豆」なんでしょう?子どもにとっては、「どうしてお菓子じゃなくて豆なの?」とか「おにぎりじゃダメなの?」なんて疑問が自然とわいてきますよね。
実はこの“豆”には、昔の人たちの「願い」や「おまじない」がたくさん詰まっているんです。
だからこそ、大人がちゃんと意味を知って、子どもにも伝えやすい言葉で話してあげたいところです。
豆には“悪いものを追い払う力”があると考えられていた
昔の人たちは、穀物や果物に“特別な力”があると信じていました。
お米や栗なども、邪気を追い払うためにまかれていた時代もあったようです。
でもお米は粒が小さくてまきにくいし、果物は大きくて痛そうですよね。
だから手頃でたくさんあって投げやすい「豆」が選ばれていったのだと言われています。
「この豆には、悪いものを外に出す力があるんだよ」と伝えるだけでも、子どもたちは「よし!やっつけよう!」と楽しんで豆まきしてくれるようになります。
“魔を滅する”という語呂合わせにも意味がある
もうひとつ有名なのが、「豆=魔を滅する」という語呂合わせ。
「魔(ま)を滅(め)する=まめ」という、ちょっとした言葉遊びが込められているんです。
「鬼に豆をぶつけることで、悪い魔法がとけるんだよ」と伝えてあげると、子どもは目を輝かせてくれます。
うちの子も、「豆が魔法を消すんだ!強いね!」と嬉しそうに豆を握ってました。
こういうちょっとした“ファンタジー感”があると、子どもの興味スイッチが一気に入るんですよね。
炒った豆を使う理由もちゃんと意味がある
実は、節分に使う豆は「炒った豆」でなければいけないという話もあります。
それは、まいた豆が土に落ちて芽を出してしまうと、そこから“悪いものがまた育ってしまう”と考えられていたからなんです。
炒った豆なら芽が出ることもないし、清めの意味でも安全なんですね。
「魔法を吸い取った豆から芽が出ちゃうと、また悪いことが起きるかもしれないから、火でカラッと炒めてあるんだよ」と伝えてあげると、子どもも納得しやすくなります。
豆を年の数だけ食べるのはなぜ?
節分の日、豆まきのあとに「自分の年の数だけ豆を食べようね」って言われたこと、あなたにもありませんでしたか?
子どもも大人も一緒になって豆をポリポリ食べるあの時間、なんだかほっこりしますよね。
でも実は、この「年の数だけ豆を食べる」風習にも、ちゃんと意味があるんです。
ただのお楽しみではなく、昔の人たちの“願い”がこもった、大切な習わしなんですよ。
“福豆”を食べることで、福を自分の中に取り込む
豆まきに使われた豆は、「福豆(ふくまめ)」と呼ばれています。
これは、鬼を追い払った後に残った、清められた特別な豆なんです。
「外の悪いものを追い払って、家の中には幸せを呼び込もう」という想いが込められているからこそ、その福豆を食べることで「福を体の中に取り込む」と信じられてきました。
だからこそ、「今年も元気に過ごせますように」という願いを込めながら、年の数だけ豆を食べるんですね。
“年の数+1個”には「来年も元気で」という意味もある
地域や家庭によっては、「年の数+1個」豆を食べるというところもあります。
それは「今年の分」だけでなく、「来年も健康に迎えられるように」という意味が込められているから。
ちょっとした違いかもしれませんが、こういう心づかいがある日本の行事って素敵だなぁと改めて感じます。
子どもにも、「来年も元気でいられますようにって意味があるんだよ」と伝えてあげると、大事そうに一粒一粒かみしめながら食べてくれるかもしれません。
小さな子には「福茶」やアレンジで安全に楽しんで
ただ、小さい子どもは硬い豆を食べるのが難しいこともありますよね。
そんなときは、無理をせず“福茶”という形で楽しむのもおすすめです。
福豆に梅干しや塩昆布を加えて、あたたかいお湯を注ぐと、ほんのり優しい味わいのお茶ができます。
「豆は飲みにくいから、今日はこの“福のお茶”で福をいただこうね」と声をかけてあげれば、子どもも安心して節分の習わしに触れられますよ。
幼稚園児に節分を説明するときのわかりやすい伝え方実例
子どもが節分に興味を持ってくれたとき、それをチャンスにして“ちゃんと伝えたい”という気持ちになりますよね。
でも、いざ話そうとすると意外と難しくて、伝わったようで伝わっていないことってよくあります。
ここでは、私が実際に子どもと話す中で見えてきた、「伝わる言い方」「響く説明」のコツをご紹介しますね。
ちょっとした工夫だけで、子どもの目がぱっと輝く瞬間が生まれますよ。
“1年のはじまり”や“季節の節目”は使わない方がいい理由
「立春の前日で、昔はここが1年の切り替わりで…」なんて説明、実はほとんどの幼稚園児には難しすぎるんです。
大人からするとちゃんと説明したつもりでも、子どもは「なんか話が長い」「よくわからない」と感じてしまって、気持ちが離れていってしまうこともあります。
だからあえて、そういった時間や季節の概念を使わずに、「寒い冬から、あったかい春にかわるころのお祭りなんだよ」くらいの表現のほうが、子どもの頭にも心にもすっと届くんです。
子どもの“今”に寄り添った言葉選びがカギになる
説明をするときは、子どもが今感じていること、知っていることをベースにしてあげると伝わりやすくなります。
「最近寒い日が続いてるでしょ?でも、もうすぐポカポカして、お花が咲く季節がくるんだよ。
節分は、その“春をむかえる準備の日”なの」と話してあげると、子どもの顔が「あ、それ知ってる!」という表情になるんですよね。
実感のある言葉は、子どもの理解を助けてくれます。
“鬼=悪いこと”を子ども自身に考えさせてみる
「鬼って何だと思う?」と聞いてみると、子どもなりの答えが返ってきます。
「泣き虫鬼!」「おこりんぼう鬼!」とか、時には「ゲームやめられない鬼…」なんて言葉も飛び出すことがあるんです。
大人が一方的に教えるより、こうして“自分の中の鬼”を子ども自身に見つけてもらうと、豆まきの意味も自分ごととして感じられるようになります。
「じゃあその鬼を、お外にバイバイしようね」とつなげれば、楽しみながら自然に行事の意味が伝わるんです。
“豆まきをするとどうなるのか”までイメージさせてあげる
ただ豆をまくだけじゃなくて、「豆まきすると、どうなるの?」という“その先”を伝えることも大切です。
「豆まきをすると、みんなが元気に過ごせるようになるんだよ」と教えると、「じゃあママが風邪ひかないように、ママの鬼も追い出す!」なんて優しい言葉が返ってくることも。
行事の意味を“自分と家族の幸せにつながるもの”として伝えていくと、子どもはもっと興味を持ってくれますよ。
子どもが“ふーん”で終わらないための声かけのコツ
どれだけ丁寧に説明しても、子どもから返ってくるのが「ふーん…」のひとことだったとき、正直なところちょっとしょんぼりしてしまいますよね。
でもそれって、こちらの話し方が悪いというより、子どもがまだ自分の世界とつながっていないだけなのかもしれません。
大切なのは、“話すこと”よりも“対話すること”。
少しの工夫で、子どもの心がパッと開く瞬間が訪れるんです。
「伝える」より「一緒に考える」スタイルが効果的
大人はつい「説明しなきゃ」と構えてしまいがちですが、子どもにとっては、聞かされるだけよりも“自分で考える時間”の方が印象に残ることが多いんです。
「鬼ってどんなことすると思う?」「豆をまいたら何が起きるかな?」といった問いかけを混ぜることで、子どもは“自分の言葉”で節分を受け止めようとしてくれます。
こうしたやりとりの中にこそ、理解や納得が育っていくんですね。
“どんな鬼を追い払いたい?”で想像力を引き出す
我が家で大ヒットだったのがこの質問。
「○○ちゃんの中にいる鬼って、どんなのだと思う?」って聞いたら、
「泣き虫鬼!」
「怒りんぼう鬼!」
「寝るのやだやだ鬼!」
と大盛り上がり。
自分の中の“ちょっと困ったところ”を鬼として表現できたことで、豆まきがただの遊びではなく、自分と向き合う時間になっていたのが印象的でした。
想像力は子どもの最大の武器。
そこに火をつける声かけを大切にしたいですね。
準備も一緒にやることで“自分ごと”になる
豆を袋に分けたり、豆を入れる箱を手作りしたり、鬼のお面を作ったり。
行事の準備段階から子どもと一緒に関わると、節分そのものが“自分のイベント”になります。
作業をしながら、「この鬼さん、○○ちゃんの○○鬼だね~」なんて笑いながら話すと、それだけで自然と行事の意味が子どもの中に浸透していくんです。
子どもって、“手を動かす”ことで心も動くんですね。
怖がりな子には“安心できる表現”を選ぶ
「鬼が来るよ~!」と強く脅すような言い方は、敏感な子には逆効果になることもあります。
泣き出してしまったり、「節分=怖い日」と記憶されてしまったらもったいないですよね。
だから、
「悪い気持ちをやっつける魔法の豆をまこうね」
「元気で過ごせるおまじないなんだよ」
といった、安心できる優しい言葉に言い換えて伝えてあげるといいですよ。
行事は“楽しさ”の中にこそ、心の栄養があると思うんです。
まとめ:節分は“家族が元気で過ごせますように”の願いを伝える行事
節分って、豆をまいたり鬼のお面をつけて遊ぶだけのイベントのように思いがちだけど。
でも、ちゃんとその奥には「家族みんなが健康で過ごせますように」という、昔から受け継がれてきた温かい願いが込められているんですよね。
私も正直、子どもに聞かれるまでは「なんで豆?なんで鬼?」とあまり深く考えたことがありませんでした。
でも、ひとつひとつの意味を調べていくうちに、ただの行事じゃなくて、季節の変わり目に気持ちを整える“心の行事”なんだなと感じるようになりました。
そしてその想いを、子どもにもちゃんと届けたいって思ったんです。
ただ伝えるだけじゃなくて、子どもが「それ知りたい!」って思ってくれるような話し方をしたり、「こうかな?ああかな?」って一緒に考えていけるような時間を持つこと。
節分って、行事を通して親子の距離をぐっと縮めてくれるチャンスなんですよね。
「豆まきってなに?」から始まった何気ない会話が、気づけば“鬼ってなに?”“どうして豆なの?”とどんどん深まっていって。
最後には「みんな元気でいられますように」って言いながら豆を投げる姿を見て、私の方がなんだか泣きそうになりました。
小さな行事の中に、大きな思いや愛情が詰まっている。
そんなことを、あらためて感じさせてくれるのが節分なのかもしれません。
どうか今年の節分が、あなたとお子さんにとって、ただのイベントではなくて、心があったかくなるような、かけがえのない時間になりますように。