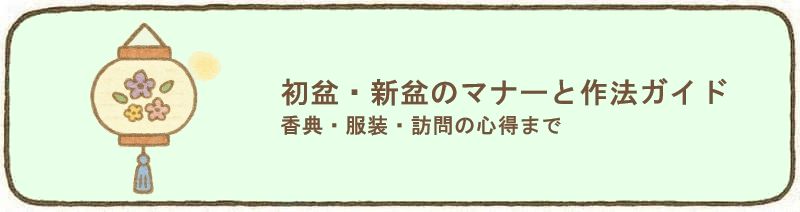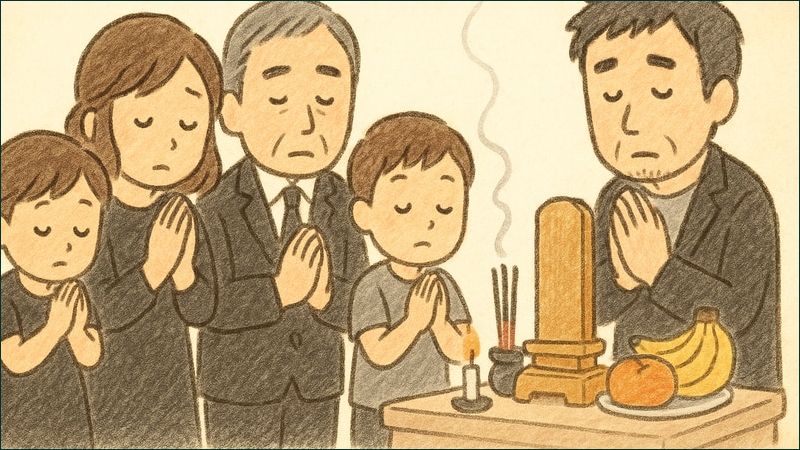
仕事でうっかりミスをしてしまったり、思いがけないトラブルに巻き込まれたとき、会社から「始末書」や「顛末書」の提出をお願いされることってありますよね。
そんなとき、
「えっ?始末書ってなに?顛末書ってどう違うの?」
「どっちのほうが立場的に重いの?」
と、慌てたり不安になったりした経験がある方も少なくないと思います。
特に社会人になりたての方や、これまで大きなミスを経験したことがなかった人にとっては、こういった文書は少し構えてしまう存在かもしれません。
「書いた内容が人事評価に影響するのでは?」「変なことを書いて処分が重くなったらどうしよう…」など、いろんな不安が頭をよぎりますよね。
そこでこの記事では、そんな疑問や不安をやさしく解消しながら、「始末書」と「顛末書」の違いをはっきりと説明していきます。
それぞれの文書の意味、どんなときに使われるのか、どんな内容を書けばよいのかなどを、実際の事例も交えながらわかりやすくまとめました。
この記事を読むことで、「いざというときに焦らず対応できるようにしておきたい」という方の不安が少しでも和らぎ、前向きな気持ちで書類に向き合えるようになればうれしいです。
始末書と顛末書、どっちが重い?結論からお伝えします
重いのは「始末書」|処分につながる文書
まず結論からお伝えすると、「始末書」の方が顛末書よりも重い意味を持っているんです。
始末書は、自分自身の非をはっきりと認め、そのうえで深く反省し、さらに今後の改善策までしっかりと記載する文書になります。
単に「こういうことが起きました」と報告するだけではなく、
「自分の責任でした」
「もう二度と繰り返さないように、こうしていきます」
と自分の言葉で誠意をもって示す必要があるんですね。
このため、始末書は懲戒処分と一緒に提出を求められることも多く、内容によっては減給や降格など、直接的に評価や処分に影響する可能性もあります。
会社としても「一個人の反省文」というだけでなく、「今後の再発防止の意思を確認する証拠」として使うため、取り扱いには非常に慎重になります。
書く側もプレッシャーが大きい文書といえるでしょう。
顛末書はあくまで報告用の書類
一方で「顛末書」は、発生した出来事について、事実関係や経緯、原因などをできるだけ客観的にまとめた報告書という位置づけになります。
「いつ、どこで、何が起きたのか」「なぜそれが起きたのか」を明確に書き出していくのが目的です。
顛末書の大きな特徴は、そこに「謝罪の言葉」や「自分の感情」が入らない点です。
あくまで事実報告に徹するもので、責任の所在を問われるわけではありません。
なので、顛末書を提出したからといって、それが処分に直結するということは基本的にはありません。
ただし、内容次第では後に責任の所在を判断するための資料になることもあるので、事実を正確に書くことが大切です。
このように、両者の性質には明確な違いがあり、
- 始末書=謝罪と改善策を含む責任文書
- 顛末書=経緯や背景を説明する報告書
そもそも顛末書と始末書ってどう違うの?
顛末書は「何が起こったか」を報告する書類
顛末書というのは、仕事の現場で何かトラブルやミスが起きたときに、その出来事の流れや背景、原因などを時系列に沿って客観的に説明するための文書です。
たとえば、
「本来5個発注する予定の商品を、誤って50個発注してしまった」
「確認作業を怠ったために請求書の金額が間違っていた」
「パソコンの設定ミスで作業が中断された」
など、実際に何があったのかを記録して報告します。
この文書のポイントは、あくまで“事実を正確に書く”という点です。
謝罪の言葉や自分の気持ちを書く必要はなく、主観を交えず冷静に説明することが求められます。
つまり、感情を入れずに
- 起きたこと
- なぜそうなったのか
- 誰が関係していたのか
上司や関係者が状況を把握するための参考資料となるため、過剰に自分を責めたり、逆に責任逃れのような表現にならないよう、淡々と事実を記すことが大切です。
始末書は「反省と改善策」まで求められる
始末書は、顛末書と違って「自分に責任があることを認め、そのうえで謝罪と改善の意志を示す」ための文書です。
ですから、顛末書に書く内容に加えて、
「自分の不注意が原因でした」
「申し訳ありませんでした」
といった謝罪の気持ちを言葉にし、さらに「今後は〇〇を徹底して、再発を防ぎます」といった改善策まで求められます。
たとえば、「50個も発注してしまったのは、自分が入力を確認せずに確定ボタンを押してしまったからです。
今後は必ず上司にダブルチェックを依頼してから確定するようにします」といった具合に、自分のミスを認めたうえで、どう防止するかを具体的に書く必要があるんですね。
このように、始末書は単なる報告ではなく
「自分の責任を自覚し、反省していることを社内に明示する文書」
なので、どうしても内容が重くなりますし、精神的にも少し負担に感じるかもしれません。
どちらも大事だけど、責任の度合いが違う
どちらの書類も会社で働いていくうえでは必要になることがありますが、書く側が負う責任の重さには違いがあります。
顛末書は、会社側が「状況を把握するため」に指示して提出させるもので、業務の一環としての位置づけです。
ミスの報告や原因の説明が目的であって、書いたことで直ちに処分につながるということは少ないでしょう。
それに対して始末書は、本人の反省と謝罪の気持ちを文書として形にし、場合によっては懲戒処分に結びつくこともあります。
会社によっては、この書類の提出が「減給」や「査定への影響」などにつながる可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。
つまり、
「顛末書は事実の報告」
「始末書は責任の表明と反省の文書」
という大きな違いがあるということですね。
始末書が「重い」と言われる理由
懲戒処分の一種とされることもある
始末書は、会社によっては「懲戒処分の一環」として正式に扱われるケースも少なくありません。
これは、単なる反省文としてではなく、「処分に付随する公式な記録」として意味を持つからです。
たとえば、勤務態度やミスの内容が重かった場合、始末書を提出することが減給や昇格見送り、降格といった処分とセットで実施されることがあります。
始末書の提出そのものが、「今回の件について会社として正式に対応した」という証明になるため、人事や労務記録として保管される場合もあります。
実際に、
「ミスをしてしまい、始末書を提出したあとで賞与査定が下がった」
「降格処分とあわせて始末書の提出が求められた」
などの経験談も見聞きします。
つまり始末書は、ただの“反省”だけで終わらず、会社側にとっても“懲戒記録”として扱われる可能性があることを意識しておく必要があるんですね。
法的な意味合いを含むケースも
さらに、始末書には“法的な意味合い”を持つケースもあります。
なぜなら、始末書は自分自身の過失やミスを認める内容が明確に書かれているからです。
つまり、書き方や表現によっては「自分で自分の責任を認めた証拠」として残ることになります。
こういった特性があるため、始末書は会社側が強制的に書かせることができるものではありません。
本来、始末書というのは“本人の意思で提出される文書”という建前があり、本人が納得の上で記入することが原則とされています。
もし、会社が無理に書かせた場合は、後々の労使トラブルの火種になることもあるため、慎重な対応が求められるのです。
本人の「謝罪の意思」が前提になる書類
始末書という文書には、「私はこの件について自分の非を認め、反省しています」という謝罪の気持ちがこもっていることが前提になります。
なので、もし本人に「自分には落ち度がない」と感じている部分がある場合、無理に書かせるのは好ましくありません。
実際、始末書には「今後はこのようなことがないよう改善します」といった改善策まで盛り込まれることが多く、単なるミスの報告を超えた“反省と約束”の意味を持ちます。
こうした文書を納得せずに書くと、気持ちの面でも整理がつかず、あとで「書きたくなかったのに無理やり書かされた」といった不満やトラブルにつながる可能性もあるんです。
だからこそ、始末書を書くときは
「謝る理由を自分の中でしっかり理解していること」
「どう改善していくかが明確になっていること」
が大切になります。
本人の意思がきちんと反映された始末書でなければ、形式だけの反省になってしまい、かえって信頼回復につながらないこともあるんですね。
顛末書や始末書を求められたときの対処法
まずは冷静に内容を確認しよう
突然「書いてください」と言われると、誰でもドキッとして焦ってしまいますよね。
何を書けばいいのか、どう書いたら変に受け取られないか、いろいろ不安になるものです。
でも、まずは落ち着いて、何が起きたのかを整理することが大切です。
ミスが起きた場面をできるだけ冷静に思い出して、
- どこで
- 何が
- なぜ起きたのか
上司に聞かれたときに正しく説明できるよう、自分の頭の中で時系列をはっきりさせておくことがポイントです。
たとえば、
「この日、〇〇の作業をしていたときに、確認作業を飛ばしてしまった」
「〇〇さんからの連絡を見落としていた」
といったように、具体的に自分の行動を洗い出すと、文章にも説得力が生まれます。
また、自分の中で「あれは本当に自分の責任だったのか?」と疑問に思うことがあれば、無理に一人で抱え込まず、先に信頼できる同僚や上司に相談してみるのもひとつの方法です。
内容を誤解されたまま文書にしてしまうと、あとで誤解が広がってしまうこともあるので、まずは事実確認をしっかりしておきましょう。
顛末書は業務命令、始末書は気持ちも大切
顛末書は会社からの業務命令として出されることが多く、「出してください」と言われたら基本的に拒否はできない書類です。
これはあくまで報告文書なので、起きた出来事の内容を淡々と整理して書けばOK。
気持ちをこめる必要はなく、「事実の記録」としての役割を果たすことが目的です。
一方で始末書は、「反省と謝罪」が求められる書類です。
本人の気持ちが大切になるため、会社側としても「絶対に書いてください」と強制するのは本来できません。
ただ、現実的には上司から強めに言われたり、職場の空気的に「書かないとまずいな…」と感じてしまうこともあるでしょう。
そんなときは、「強制されて書かされる」のではなく、自分の中で「納得して書く」ことが大事です。
ミスに対する気持ちを整理し、自分の言葉で表現するように意識してみると、書く作業が少しだけ楽になりますよ。
謝罪文や改善策の書き方ポイント
謝罪文を書くときは、形式ばった言い回しにこだわりすぎず、「自分の言葉で謝る」ことを意識してみてくださいね。
「申し訳ありませんでした」だけでなく、
「〇〇という点で配慮が足りませんでした」
「自分の確認不足が原因でした」
といったように、どこに反省しているのかが伝わる文章にすると、より誠実さが伝わります。
改善策を書くときは、抽象的な言い回しではなく、
「今後は必ずダブルチェックを行います」
「定期的にマニュアルを読み返すようにします」
など、具体的な行動に落とし込んだほうが信頼感がアップします。
上司も「この人は本気で改善しようとしているな」と受け取ってくれるはずです。
謝罪と改善策はセットで伝えるのがポイント。
「申し訳ありませんでした。
今後は~します」といった形で、自然な流れを意識して書いてみてください。
まとめ:違いを知って、落ち着いて対応を
書類に込める意味と心構えを大切に
顛末書も始末書も、「ただの書類」として片付けてしまうのはもったいないかもしれません。
確かに形式的に見えるかもしれませんが、これらの文書には、その人の責任感や誠意、仕事への姿勢がにじみ出るものです。
だからこそ、書くときには「とりあえず出せばいいや」と思わずに、自分の言葉で丁寧に向き合うことがとても大切です。
書類にどんな思いを込めるかで、上司や会社からの印象も変わってきます。
「この人は真剣に考えているな」
「しっかり反省して、次に活かそうとしているな」
と受け止めてもらえるように、自分なりにしっかり振り返り、気持ちを込めて文章を書いてみてくださいね。
ちょっとした表現の工夫や、丁寧な言い回し一つで、印象が大きく変わることもあります。
「誤字脱字に気をつける」「読みやすい文になるように心がける」といった細かいところも含めて、自分の姿勢を表すチャンスだと思って取り組むといいですよ。
ミスをチャンスに変える気持ちも忘れずに
人間である以上、どれだけ気をつけていてもミスをゼロにすることは難しいものです。
だからこそ、ミスをしたときにどう行動するかが、その人の評価や信頼に直結してきます。
もちろん、落ち込んでしまうのは仕方ありません。
でも、その気持ちのままで終わらせず、「この経験をどう活かすか?」と前向きに考えてみてください。
たとえば、
「次は確認を2回するようにしよう」
「相談を早めにするように気をつけよう」
といったように、小さな一歩でも改善に向けた行動を意識することで、自分自身も少しずつ成長できます。
また、反省する姿勢を見せることで、周囲の信頼を取り戻すきっかけにもなります。
誰にでもミスはあるという前提で、誠実に向き合い、同じことを繰り返さないための努力を続けていけば、むしろ「成長する力がある人」として良い印象を持たれることも多いんですよ。
なので、書類の提出を求められたときこそ、自分の姿勢を見直すチャンス。
落ち込むだけで終わらせず、「次はもっと良くなるために」と前を向く気持ちを大切にしてみてくださいね。