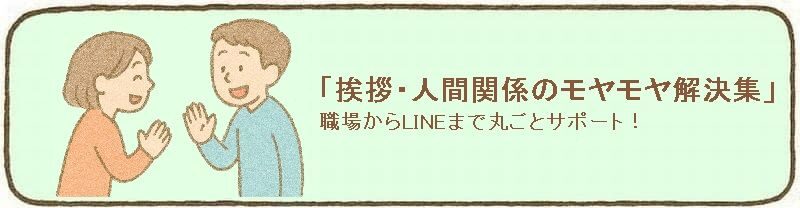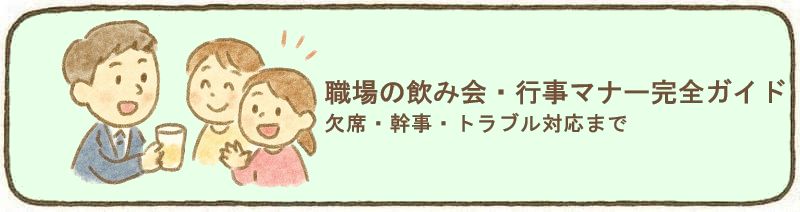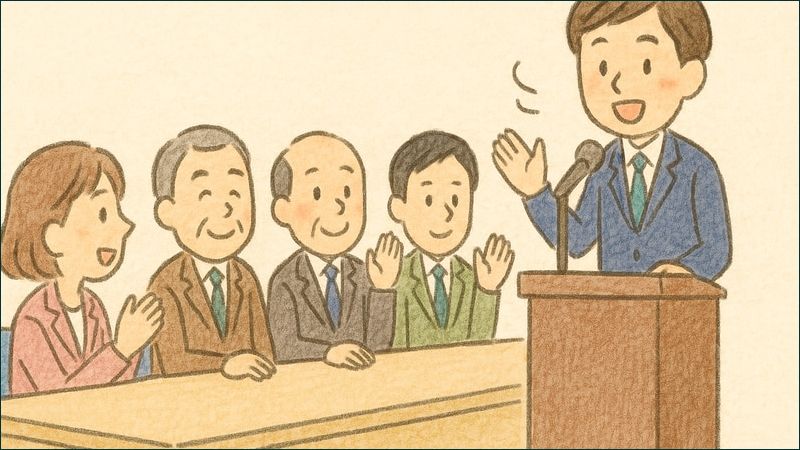
初めて会社の宴会幹事を任されると、「何から手をつけていいかわからない!」と戸惑ってしまいますよね。
お店の予約や出欠確認、案内状の作成といった準備ももちろん大切ですが、それらと同じくらい、いやもしかするとそれ以上に悩みやすいのが「挨拶の順番」です。
「偉い人から順番にお願いすればなんとかなるでしょ?」と考えたくなりますが、実はそれだけではうまくいかないこともあるんです。
会社によっては役職順だけでなく、慣例やその場の雰囲気を重視する場合もあり、「思ってたのと違った…」と後から困ってしまうことも。
この記事では、宴会で必要な挨拶の基本的な流れや、それぞれの挨拶を誰にどのタイミングで頼めばよいのか?
さらにマナーや進行のコツまで、幹事としてぜひ押さえておきたいポイントを丁寧にご紹介していきます。
初めての幹事で不安いっぱい…という方も、この記事を読むことで少しずつイメージがつかめてくるはずです。
楽しい宴会のスタートを切るためにも、しっかり準備してのぞんでみてくださいね。
会社の宴会で必要な挨拶の流れと順番とは?
一般的な宴会の挨拶順はこの5つ
会社の宴会では、基本的に以下の5つの挨拶が必要になることが多いです。
- 開宴の挨拶(幹事または司会)
- はじめの挨拶(最上位の役職者)
- 乾杯の挨拶
- 締めの挨拶
- 閉宴の挨拶(幹事または司会)
たとえば、開宴の挨拶がしっかりしていれば、その後の流れもスムーズに始められますし、締めの挨拶がきちんとしていれば、参加者も気持ちよく宴を終えることができます。
特に「はじめの挨拶」や「乾杯の挨拶」は、参加者全体のテンションを高めたり、和やかな雰囲気をつくる大切な役割を担っています。
逆に、タイミングや内容を間違えてしまうと、「ちょっとグダグダだったね…」という印象を持たれてしまうこともあるので要注意です。
どれも宴会の空気づくりに直結する大事なパートなので、形式的にこなすのではなく、丁寧に準備し、誰にどの挨拶をお願いするのかをしっかりと計画しておくことが大切ですよ。
幹事が担当するのは「開宴」と「閉宴」の挨拶
幹事の役割として特に大切なのが、宴会の最初と最後をしっかり締める「開宴」と「閉宴」の挨拶です。
この2つの挨拶は、宴会全体の雰囲気を左右する重要な場面となります。
まず開宴の挨拶では、参加者が全員そろったことを確認してから、大きな声ではっきりと「それでは始めさせていただきます」と声をかけましょう。
このとき、幹事または司会としての簡単な自己紹介を添えつつ、宴会の進行に関する案内(例:飲み放題は2時間、途中で新入社員の紹介があります など)を簡潔に伝えると親切です。
挨拶のポイントは、テンポよく、そして明るく伝えること。
あまり長く話しすぎず、30秒~1分程度でまとめると、参加者も気持ちよくスタートを迎えられます。
一方で、宴会の終盤に行う閉宴の挨拶も見逃せません。
締めの挨拶が終わった直後は、参加者がざわついて席を立ち始めるタイミング。
だからこそ、間髪入れずに「本日はご参加ありがとうございました」とお礼の言葉を述べることで、参加者全体の注意を集めることができます。
また、もし二次会の予定がある場合は、案内をこの場でしっかり伝えることも大事です。
お店の場所や集合時間など、必要な情報を簡単に伝えて誘導しましょう。
開宴と閉宴の挨拶は、幹事の段取り力と気配りが試されるシーンでもあります。
事前に流れをイメージしながらリハーサルしておくと、より安心して当日を迎えられますよ。
社内イベント特有の挨拶タイミングにも注意
会社の宴会では、通常の挨拶以外に、新入社員の紹介や異動・昇進者のあいさつなど、追加の挨拶タイムが入ることがあります。
これらは事前に把握しておかないと、進行がバタついてしまう原因になりがちです。
特に新年度や年末の忘年会では、新しい顔ぶれを紹介するタイミングとして活用されることもあるので、幹事は上司や先輩に「例年どんな進行でしたか?」と確認しておくのが安心です。
こうした社内特有の要素をうまく盛り込むことで、より気配りのあるスムーズな宴会運営ができますよ。
役職順でいいの?挨拶を頼む順番の考え方
はじめの挨拶は最上位役職者にお願いするのが基本
「はじめの挨拶」は、宴会の中でも特にフォーマルな意味合いが強いタイミングです。
まだお酒が入っていない状態での挨拶となるため、その場の空気をピシッと整える大事なスタートポイントになります。
そのため、はじめの挨拶は、その場に出席しているメンバーの中で一番役職が高い方。
たとえば社長・専務・部長クラスなどの最上位役職者にお願いするのが基本的なマナーとされています。
この挨拶がしっかりしていると、全体の流れも引き締まり、参加者も自然と耳を傾けてくれる雰囲気が生まれます。
ただし、同じような役職の方が複数人参加している場合、誰にお願いするべきか迷うこともあるかもしれません。
そういったときは、役職だけではなく年齢の高い方や勤続年数が長い方、または会社内での影響力や立場などを考慮して判断するケースが多いです。
たとえば、部長が複数人いる場合であれば、「本社の部長」と「支店の部長」のどちらが全体の挨拶にふさわしいかといったことも、社内の空気を見ながら決めていく必要があります。
慣例やその場の雰囲気に従うのがベストですが、判断が難しい場合は、自己判断せず、あらかじめ直属の上司や幹事経験者に相談するようにすると安心です。
「この人にお願いして大丈夫かな…?」と悩んだときには、事前に一声かけて意向を確認しておくのもトラブル回避のポイントです。
丁寧な対応を心がけましょう。
乾杯は3番目、締めは2番目の役職者が目安
乾杯の挨拶は、はじめの挨拶に続く大事なタイミングではありますが、少しカジュアルな雰囲気も含まれる場面です。
参加者もグラスを手にしてワクワクしている状態なので、短く気持ちよく場を盛り上げる役割を担っています。
そのため、乾杯の挨拶は役職的に3番目くらいの方にお願いするのが一般的です。
たとえば、はじめの挨拶を社長が担当した場合、乾杯は本部長や部長クラスに依頼するイメージですね。
また、会社によっては「はじめの挨拶」と「乾杯の挨拶」を同じ方がまとめて担当する場合もあります。
どちらが良いかは、社内の慣例やこれまでの進行例にあわせて柔軟に決めていきましょう。
一方、宴会の締めの挨拶は、最後をきちんと締めくくる重要なシーンです。
参加者全員がしっかり耳を傾け、気持ちよくその場を終えられるように、比較的落ち着きと貫禄のある2番目に偉い役職の方にお願いするのがベターとされています。
ただし、これも例外があって、「毎年締めは〇〇さん」と決まっているケースや、一本締め・三本締めが恒例となっている会社もあります。
そうしたルールや流れがある場合は、それに従ったほうが安心ですね。
いずれにしても、事前に先輩や過去の幹事経験者に「例年は誰がどの挨拶をしていますか?」と確認しておくことで、当日の段取りがぐっとラクになりますよ。
役職が同じときの判断は「年齢」or「在籍年数」
係長や課長が複数人いる場合、「どちらにお願いしたらいいのか分からない…」と迷ってしまうこともありますよね。
そんなときには、年齢が上の人や、在籍年数が長い人を優先するというのがひとつの目安になります。
特に日本の職場文化では、年功序列がまだ根強く残っていることも多く、自然とそういった順番での依頼がスムーズに受け入れられる傾向があります。
ただし、この判断基準もあくまで一例。
社風や部署によっては、若くても仕事の成果や実績を重視する会社もありますし、在籍年数よりも役割の大きさで選ばれることもあります。
たとえば、「社歴は浅くてもプロジェクトのリーダーを任されている」「役職は同じでも会社の中心的な立場にある」といったケースでは、そうした点も配慮する必要が出てきます。
また、職場によっては「去年は○○さんが挨拶したから、今年は△△さんに」といったように、持ち回りになっていたり、内々の慣例がある場合も少なくありません。
なので、挨拶の順番を決める際には、自分だけで判断せず、周囲の人の意見を聞きながら進めていくのが安心です。
判断に迷ったら上司に相談が安心!
挨拶の順番でトラブルが起きてしまうと、その後の宴会がなんとなく気まずい空気になってしまうこともあります。
誰にお願いするかを間違えると「なんで自分じゃなかったの?」といった不満が出てしまう可能性もあるんですね。
そんな事態を避けるためにも、判断に自信が持てないときは、無理に独断で決めてしまわずに、素直に上司に相談してみるのが一番です。
「どなたにお願いするのがよさそうでしょうか?」と軽く聞いてみるだけでも、納得感のある進行になりますし、自分自身も安心して段取りができます。
上司も、幹事が丁寧に気を配っていることに好印象を持ってくれるはずです。
遠慮せず、積極的に相談してみてくださいね。
挨拶のお願いはいつ・どう伝える?
事前に先輩や上司に相談して慣例をチェック
挨拶をお願いする前に、まず確認しておきたいのが「過去の流れ」。
毎年の宴会でどんな人がどの挨拶をしていたか、慣例的な順番や持ち回りがないかを、先輩や上司にしっかり聞いておきましょう。
会社の文化や部署ごとの決まりが反映されている場合もあるので、事前の情報収集がとても大切です。
また、以前に挨拶をお願いされた人の反応や、どんな雰囲気で行われていたかなども聞いておくと、よりスムーズな進行の参考になります。
もし可能であれば、過去の進行表や台本が残っている場合は見せてもらえると、かなり助かりますよ。
挨拶の内容だけでなく、「乾杯のあとに社長から一言」「最後は必ず一本締め」など、暗黙の流れがあることも多いので、そうした細かい部分も確認しておくと安心です。
準備の早い段階で慣例を把握しておくことで、余計な迷いやミスを防ぐことができます。
挨拶を依頼するタイミングは1週間前がベスト
挨拶のお願いは、なるべく早めにしておくのが鉄則です。
宴会当日になって急にお願いすると、相手にとっても心の準備ができておらず、負担になってしまうことがあります。
最悪の場合、「そんなの聞いてないよ」とトラブルになることも。
理想的なのは、宴会の1週間前くらいに依頼すること。
このタイミングなら、相手も自分のスケジュールを確認しやすく、内容を考える余裕もあります。
幹事としても、もし断られた場合に他の人にお願いする時間が確保できるので安心です。
また、タイミングだけでなく、お願いするタイミングの雰囲気も大切。
忙しい時や慌ただしいときに切り出すよりも、落ち着いたタイミングで「お願いがあって…」と切り出すことで、相手も快く引き受けてくれやすくなります。
口頭+メールなど、丁寧な伝え方が好印象に
挨拶を依頼するときは、まずは対面や電話などの口頭でお願いするのが基本ですが、それだけで終わらせずに、後日あらためてメールやメッセージで詳細を伝えるようにすると丁寧です。
「いつ・どんな内容で・どんな順番で」などを簡潔にまとめて送ると、相手も安心して準備できます。
また、メールでは「お忙しいところ恐縮ですが」「無理のない範囲で結構ですので」など、やわらかい言葉を添えると好印象です。
挨拶を頼む相手が上司や目上の方の場合は、特に失礼のないよう、敬語や言い回しにも気を配るようにしましょう。
こうした丁寧なやり取りは、幹事としての信頼感にもつながります。
挨拶のお願いを通して、相手に「しっかり準備しているな」と思ってもらえるような配慮を意識してみてくださいね。
幹事がスムーズに進行するための工夫
当日は大きな声で注目を集めるのがコツ
宴会当日は、会場のざわざわした雰囲気や参加者同士の会話で、こちらの声が通りにくくなってしまうことがあります。
特に居酒屋や大きなホールなどでは、騒音やBGMの影響で、話しかけても聞き取ってもらえないこともあるんですね。
だからこそ、幹事として開宴や閉宴の挨拶をするときには、しっかりとした大きな声で参加者の注意を引くことが大切です。
まずは「皆さん、すみません!」や「お静かにお願いします!」といった一言をはっきり伝えてから、挨拶に入るようにすると、場が自然と整いやすくなります。
また、声のボリュームだけでなく、話すスピードや抑揚も意識すると効果的です。
ゆっくり、はっきりと、語尾までしっかり伝えるよう心がけてみてくださいね。
長すぎる挨拶はNG!簡潔な段取りでOK
宴会の場では、挨拶が長引くと参加者の集中力も途切れてしまいます。
せっかく用意しても「長いな…」と思われてしまうのはもったいないですよね。
そのため、挨拶をお願いする相手には、あらかじめ「1分くらいでお願いできると助かります」と伝えておくと、負担をかけずに済みますし、進行もテンポよく進みます。
幹事自身が話す場面でも、挨拶の構成を「お礼・案内・締めの一言」などに絞って、簡潔にまとめることを意識しましょう。
たとえば、「本日はご参加ありがとうございます。
飲み放題は2時間ですので、お楽しみください!」といったシンプルなメッセージで十分です。
必要であれば、あらかじめ台本やメモを用意しておくと安心ですよ。
一本締めや社長からの差し入れ紹介も忘れずに
宴の最後には、一本締めや三本締めなどで会をしっかりと締めるのが定番となっている会社も多いです。
これは参加者に「宴が終わった」というけじめを感じてもらう大切な演出でもあります。
一本締めのときは、事前にお願いする人を決めておくとスムーズです。
また「○○さんに一本締めをお願いしております。
よろしくお願いします」と幹事がアナウンスすると、場の注目も集めやすくなります。
さらに、社長などから酒肴料(差し入れ)をいただいている場合は、乾杯後などに「ちなみに本日は社長より酒肴料をいただいております。
この場を借りてお礼申し上げます」といった形で紹介すると丁寧です。
このような小さな気配りが、幹事としての印象をグッと良くしてくれるので、忘れずに伝えるようにしてみてくださいね。
まとめ:挨拶順は基本+柔軟な判断がカギ
「基本は役職順+状況に応じて調整」が正解
宴会の挨拶順は基本的には役職順で問題ありません。
たとえば、はじめの挨拶は一番偉い方に、乾杯の挨拶は3番手、締めの挨拶は2番手というように、役職を基準に考えると基本的な流れが組み立てやすくなります。
ただし、現実にはその通りにいかないことも少なくありません。
たとえば、役職は上でも当日は途中参加だったり、過去に挨拶をしているため今回は別の方に回したいというケースもあります。
また、形式にとらわれすぎず、雰囲気やその人のキャラクターを重視してお願いした方が場が和むこともあるんです。
さらに、社内の慣例や空気感を無視すると「え?あの人じゃないの?」と違和感を与えてしまうこともあります。
だからこそ、役職順をベースにしつつ、柔軟に調整していくことが大切なんですね。
迷ったときは周囲に相談したり、前年の進行例を確認したりして、臨機応変に対応してみてください。
正解は1つではありません。
状況やメンバーの顔ぶれに応じて、その場に合った挨拶順を組み立てていくのが、できる幹事の工夫です。
幹事の事前準備が宴会の成功を左右する!
宴会は事前の準備がすべてと言っても過言ではありません。
幹事の計画性や段取り力によって、宴の流れがスムーズにもなれば、バタバタして慌ただしいものにもなってしまいます。
特に挨拶のタイミングや順番、誰に何をいつお願いするかを明確にしておくことは、成功のカギとなるポイント。
お願いのタイミングを誤ると、相手に準備の余裕がなかったり、当日混乱してしまうリスクもあります。
加えて、進行表を簡単に作っておくと、自分自身の安心材料にもなりますし、他のスタッフや先輩と共有することで「今ここだよ」と確認しながら進められて心強いですよ。
初めての幹事で不安もあると思いますが、この記事で紹介したようなポイントをおさえておけば、きっとスムーズに対応できます。
「準備はしっかり・本番は笑顔で」をモットーに、ぜひ自信を持ってチャレンジしてみてくださいね!