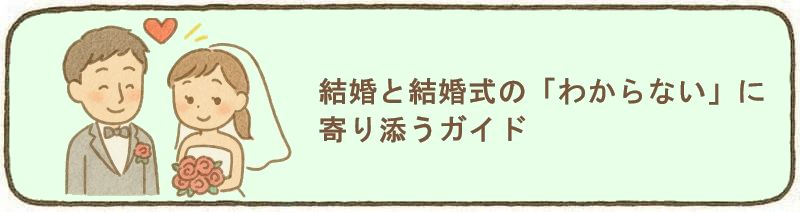「結婚してください」
そのひと言が聞こえた瞬間、胸の奥がじんわり熱くなって、まるで夢の中みたいだった。
これまでの交際の日々、笑い合ったことやすれ違った夜のことが一気に押し寄せてきて、「この人と一緒に未来を歩くんだ」と思ったら、自然と涙が出てきました。
でも、プロポーズを受けたあとに待っていたのは、思っていたより現実的で、ちょっとややこしい「結婚準備」という名の段取りの山でした。
両家の顔合わせ、入籍に必要な書類の確認、式をするかしないかの話し合い、住まいのこと、仕事との兼ね合い……
ひとつひとつが初めてのことばかりで、嬉しい気持ちと同時に不安もたくさん湧いてきたのを覚えています。
私はつい後回しにしてしまって、顔合わせの日程が決まったのが入籍のギリギリになってしまったこともありました。
親に心配をかけたくない気持ちと、自分の都合との板挟みで悩んだ末、勇気を出して相談したら「何でもっと早く言ってくれなかったの」と優しく怒られました。
結婚はふたりだけで完結するものじゃない。
そう実感したからこそ、このページでは
「プロポーズから入籍までにやるべきこと」
「顔合わせのタイミング」
「ギリギリになってしまったときの対応法」
まで、わたし自身の経験を交えながら丁寧にお伝えしていきます。
大丈夫、完璧じゃなくてもふたりで決めて、ふたりで進めていけば、ちゃんとあなたたちらしい形にたどり着けますから。
プロポーズのあとにすぐ始めたいこととは?
プロポーズを受けて、幸せな気持ちが胸いっぱいに広がるあの瞬間。
その余韻に浸っていたい気持ちは痛いほどわかります。
私もそうでした。
彼の顔を見るたびにニヤニヤが止まらなくて、ふたりでいる時間がまるで別世界のように感じられました。
けれどその一方で、現実の時間は容赦なく流れていきます。
プロポーズを受けたその日から、結婚に向けた準備はもう始まっているんです。
中でも「すぐに動き出したほうがいいこと」がいくつかあります。
タイミングを逃すと、後々バタバタしてしまう原因にもなるので、まずは気持ちを落ち着けて、順を追って始めていきましょう。
最初の一歩は「両家の親への結婚報告」
結婚はふたりの気持ちだけで完結するものではありません。
まずやるべきことは、お互いのご両親に結婚の意思を伝えること。
いわゆる「親への結婚報告」です。
このタイミングを後回しにすると、後で顔合わせや日程調整が難航するだけでなく、親にとっても「聞かされていなかった」という不信感につながることがあります。
私自身、彼の両親への報告をちょっと遅らせてしまったことで、顔合わせの日程がなかなか合わず、結果的に入籍の直前ギリギリに開催することになってしまいました。
親に気を遣わせてしまったことを、今でも申し訳なく思っています。
できれば、プロポーズから1ヶ月以内を目安に、それぞれの親へ順番に報告するのが理想です。
「順番ってどっちが先?」と迷う方もいますが、一般的には女性の親→男性の親の順に挨拶することが多いとされています。
ただ、家庭の事情や距離などもあるので、絶対的なルールではありません。
大切なのは、誠意をもってきちんと気持ちを伝えることです。
報告のときに気をつけたい3つのこと
結婚報告は、単に「結婚します」と伝えればいいだけではありません。
ふたりの意思の強さや今後の予定、親への配慮をきちんと表現することが、信頼につながります。
まずひとつ目は、「あらかじめ日程を調整してから訪問する」こと。
いきなり押しかけてしまうと、心の準備ができていない親御さんにとっては戸惑いを与える可能性があります。
ふたつ目は、「服装や言葉遣いに気をつける」こと。
改まった挨拶の場面では、カジュアルすぎる格好やラフな態度は避けましょう。
スーツや清潔感のある服装で、言葉遣いも丁寧に。
そして三つ目は、「手土産を忘れない」こと。
高価なものではなくても構いません。
季節の和菓子や地元の名産など、気持ちのこもったものを準備するだけで、相手への敬意がしっかり伝わります。
こうした小さな気配りが、のちの顔合わせや親族との関係づくりを円滑にしてくれるのです。
親への報告が遅れることで起きやすいトラブル
「忙しくてタイミングが合わなくて」
「まだ準備が整ってないから」
そうやって、報告を先延ばしにしてしまうカップルは少なくありません。
でもその結果、
- 顔合わせの予定が立たない
- 入籍までに親と会う時間が取れない
- 式や新居の話が進められない
さらに、親世代にとっては「子どもが人生の大きな決断をするのに、なぜ事前に話してくれなかったのか」と、寂しさや戸惑いを感じることもあります。
特に結婚というのは、親にとっても節目の出来事。
その瞬間を一緒に迎えたいという気持ちが強いからこそ、できるだけ早めに伝えてあげてほしいのです。
ふたりで共有しておきたい「気持ち」と「優先順位」
結婚準備の中でも、最初に親へ報告するというのは、とても重要なステップ。
でも、ひとりで抱え込まず、ふたりで話し合って進めていくことが何より大切です。
「いつ報告する?」
「どういう順番で?」
「どんな言葉で伝える?」
「手土産は何にしよう?」
こういった話し合いを早い段階でしておくことで、パートナーの価値観や家庭環境、考え方も見えてきます。
そして何より、「これからの人生を一緒に築いていく実感」が少しずつ湧いてくるはずです。
結婚はスタート地点。
親への報告という最初のステップを、ふたりで丁寧に踏み出すことが、これからの未来を支える土台になっていくのです。
顔合わせはいつ?タイミングと注意点
プロポーズのあとは、できるだけ早めに親へ結婚の報告をして、その流れで「両家の顔合わせ」の段取りに進むことになります。
でも、この“顔合わせ”が意外とハードルが高いんですよね。
日程を合わせるのも一苦労だし、
- どこで何を話すのか
- どこまで準備すればいいのか
私もまさにその一人でした。
結婚を決めたあと、仕事の繁忙期と彼の転勤のタイミングが重なってしまい、顔合わせができたのは入籍の3週間前というギリギリのスケジュール。
心配する親たちの前で、お腹がキリキリするくらい緊張したのを今でも覚えています。
だからこそ、これから準備を始める方に向けて、顔合わせの最適なタイミングと注意点を丁寧にお伝えしていきたいと思います。
顔合わせの理想的な時期とは?
顔合わせのタイミングとして理想的なのは、親への結婚報告から1~3ヶ月以内、そして入籍の少なくとも1~2ヶ月前。
式を挙げる予定がある場合は、式の約10ヶ月前には済ませておくと、全体の準備がスムーズに進みます。
この時期を目安にしておけば、両家の親のスケジュールも調整しやすくなり、会場の予約や手配にも余裕が持てます。
顔合わせがバタバタになってしまうと、準備に追われて当日の空気がギクシャクしてしまうこともあるので、できるだけ余裕をもって計画するのがポイントです。
結納と顔合わせってどう違うの?
最近では「結納を省略して顔合わせ食事会だけをする」というスタイルが主流になっていますが、この2つの違いがよくわからないという方も多いはず。
結納は、昔ながらの正式な婚約儀式で、男性側の家が女性側に結納金や結納品を贈るという流れがあります。
一方、顔合わせはもう少しカジュアルで、両家が一堂に会して挨拶を交わし、これから親族としてのお付き合いが始まることを確認する食事会のようなもの。
私たちも「結納は堅苦しいからやめよう」という話になり、ホテルのレストランで顔合わせだけを行いました。
形式にとらわれず、でも礼儀と感謝の気持ちは忘れずに。
それだけで、親たちは笑顔で迎えてくれました。
顔合わせが入籍ギリギリになったときの対処法
本当は早めにやりたかった。
でも現実は、なかなかうまくいかないこともあります。
実際、私たちは顔合わせの場所を決めるのも遅れてしまい、結果的に入籍の直前でようやく両家が顔を合わせることになりました。
そのとき私が感じたのは、「遅れてしまったことを責めないで、今できるベストを尽くすことが大事」だということです。
親には正直に、「日程が合わなくて遅くなってしまってごめんなさい」と一言添えました。
そして、レストランの予約、席順、話の流れなどをできる限り丁寧に準備し、事前に彼とも何度も打ち合わせをして、当日を迎えました。
ギリギリでも、気持ちが伝わればちゃんと喜んでもらえます。
大切なのは、遅れたことよりも「誠意」と「準備の姿勢」なんだと思います。
事前の段取りで安心感は格段に変わる
顔合わせをスムーズに進めるには、事前に確認しておくべきことがいくつかあります。
開催場所、会費の分担、親の希望、当日の進行役、食事の内容、手土産の準備など、どれも細かいようでいて、当日を和やかに過ごすためには欠かせないポイントです。
両家での価値観の違いが浮き彫りになりやすい場面でもあるので、ふたりでしっかりと事前に擦り合わせをしておくと安心です。
私たちは、ホテルのレストランを予約して、窓際の落ち着いた席を選びました。
進行もある程度シナリオを組んでおいて、
「まず彼から挨拶→私が両親紹介→乾杯→食事しながら歓談」
という流れを決めておいたことで、変な沈黙もなく、和やかに過ごせました。
顔合わせは“ふたりの家族”になる最初の扉
どんなに形式がシンプルでも、顔合わせという時間は「ただの挨拶の場」ではありません。
そこには、ふたりが「家族」になる最初の一歩が詰まっています。
親の緊張や期待、不安もきっとあるはずです。
でも、ふたりでしっかり準備して、笑顔でその場に立てれば、それだけで親は安心してくれます。
形式や完璧さにとらわれなくて大丈夫。
「今日はお互いの家族として、はじめましてを伝える日」そんな気持ちで向き合えば、きっとあたたかくて優しい時間になります。
入籍日はどう決める?縁起と実用のバランス
「結婚記念日って、入籍日になるんだよね?」
プロポーズのあとの結婚準備を進めていく中で、かなり早い段階で出てくる話題がこの“入籍日”の決定です。
でも、いざ「いつにする?」と聞かれても、意外と決められないものなんですよね。
私自身、カレンダーとにらめっこしながら、何度も「これでいいのかな?」と悩みました。
- 大安?
- ふたりの記念日?
- 語呂合わせ?
- それとも都合のいい平日?
だからこそ、大切に選びたいし、でも現実的な事情も無視できない。
この中見出しでは、入籍日を決める際に考えておきたいポイントと、私が実際に選んだ理由、そして入籍手続きに向けた注意点も交えて詳しくお伝えしていきますね。
人気の日取りにはどんな傾向がある?
多くのカップルが入籍日に選ぶのは、以下のような「覚えやすくて、意味のある日」です。
- 交際記念日
- お互い、もしくはどちらかの誕生日
- 「大安」「友引」などお日柄の良い日
- 縁起が良いとされる語呂合わせ(11月22日=いい夫婦の日など)
私の知り合いは「7月7日の七夕に入籍して、毎年ロマンチックな気分になれるよ」と笑って話してくれました。
素敵ですよね。
ただ、人気の日にこだわりすぎると、スケジュールの調整や書類の準備に追われてバタバタすることもあります。
縁起も大切だけど、心の余裕を持てる“ふたりらしい日”を選ぶことが一番だと私は思っています。
私が「式当日」に入籍した理由
私はというと、結婚式当日を入籍日にしました。
これにはちゃんと理由があります。
うちの夫は、記念日をびっくりするくらい覚えられないタイプで(笑)誕生日も交際記念日も、3年連続で忘れられました。
「これはもう、入籍日と結婚式の日を一緒にしないと、確実に覚えてもらえないぞ」と思って、迷いなく式当日を選びました。
結果としては大正解。
いまでも「〇〇年目の結婚記念日だね」とふたりでお祝いできています。
実用性重視の選び方ではあるけれど、「忘れない」というのは、意外と大事な要素です。
気をつけたいのは「書類の準備」と「提出タイミング」
入籍日に向けて大切なのは、「気持ち」だけではありません。
現実問題として、必要な書類や手続きの準備がきちんと整っていなければ、希望の日に受理されない可能性もあります。
- 婚姻届(記入済み+証人2名の署名)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 印鑑(旧姓のもの)
平日の日中であれば問題ありませんが、土日祝や夜間に提出したい場合は「時間外受付」になるため、書類に不備があるとその場で修正できずに差し戻しになるケースもあります。
私は平日の朝一番で提出しました。
事前に役所に電話して、必要書類を確認しておいたおかげでスムーズに進み、「婚姻届受理証明書」もすぐに発行してもらえました。
「ふたりらしさ」を大切にしてほしい
「入籍日って、やっぱり大安がいいのかな?」「人気の日じゃないと後悔するかも」
そんなふうに悩んでしまう気持ち、すごくよくわかります。
私も一度は大安にこだわりそうになりました。
でも、入籍日に正解なんてありません。
大切なのは「ふたりが納得して選んだ日」だということ。
記念日を大切にしたい人もいれば、仕事や生活とのバランスを重視したい人もいる。
それぞれの形でいいんです。
ふたりにとって意味のある日。
思い出すと胸があたたかくなる日。
そんな入籍日を選べたなら、それはもう立派な“縁起の良い日”なのだと私は思います。
結婚式をするかしないかでスケジュールは大きく変わる
プロポーズを受けて「結婚しよう」と決まったあと、早々に話題にのぼるのが“結婚式、どうする?”問題。
この問い、思っていた以上に悩みます。
やるべきなのか、やらなくてもいいのか。
正解がないからこそ、モヤモヤした気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。
私自身、式を挙げるかどうかはすごく悩みました。
最初は「ナシ婚(結婚式なし)でもいいかもね」とふたりで話していたのに、親からの「晴れ姿は見たいなあ」という言葉に心が揺れて……
結局、小規模ながらも結婚式を挙げることにしました。
この選択がスケジュールに与える影響は、想像以上に大きかったんです。
結婚式ありの場合は準備に時間と労力が必要
結婚式を挙げると決めた場合、理想的には1年前からの準備がベスト。
式場の予約は早い者勝ちだし、人気のシーズン(春・秋)は特に早めに動かないと、希望の日時が埋まってしまいます。
しかも、準備することが本当に多いんです。
式場選びに始まり
- 衣装決め
- 招待状
- 席次表
- 引き出物
- 料理の試食
- ウェディングケーキ
- 写真撮影
- BGMの選定……
私も仕事を続けながらの準備だったので、何度も「もうやめようかな」と思いました。
でも、結婚式当日に彼と目を合わせた瞬間、「ああ、やってよかった」と心から思えたんです。
親の嬉しそうな表情や、友人たちの笑顔に囲まれて、準備の苦労が一気に報われました。
とはいえ、誰にとっても「式あり」がベストな選択とは限りません。
ふたりの事情、家族の意向、費用面、そして心の準備。
どれもが重なって初めて、“やる・やらない”の判断ができます。
結婚式なし(ナシ婚)を選ぶカップルも増えている
最近は「ナシ婚」を選ぶカップルも本当に増えています。
実際、私の周りでも5組中2~3組は式を挙げていませんでした。
ナシ婚の理由はさまざまです。
- 費用を抑えたい
- 式の準備が負担に感じる
- 派手なことが苦手
- 妊娠中、あるいは育児中で時間がない
- 家族や親しい人たちだけで、ささやかに祝いたい
ナシ婚にしたからといって、結婚の価値が薄れるわけではありません。
むしろ「ふたりにとって心地よい形を選べたこと」は、自信をもっていいと思います。
式を挙げない場合の注意点とおすすめの代替案
ただし、ナシ婚を選ぶ場合にも、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
まずは、両親への相談。
特に親世代は「結婚=結婚式」という価値観が根強いこともあり、話をせずに決めてしまうと、のちのちトラブルの火種になることがあります。
私の友人は、式を挙げないことを先に自分たちだけで決めてしまい、報告のタイミングで親に大反対されて大ゲンカになったと話していました。
結果的には、「フォトウェディングを贈り物として提案する」という形で落ち着いたそうです。
式を挙げない代わりにおすすめなのは:
- フォトウェディング(スタジオ・ロケーション撮影)
- 友人や家族とのお披露目パーティー(食事会)
- 家族旅行を兼ねた小規模セレモニー
- 新婚旅行先での記念写真・動画撮影
スケジュールに与える影響は大きい。だからこそ最初に話し合いたい
結婚式をやるかどうかで、スケジュールは大きく変わります。
「式をする」と決めれば、準備に半年~1年は見込んでおきたいところ。
一方で「ナシ婚」にすると、入籍までの期間がグッと短くなることも珍しくありません。
重要なのは、プロポーズを受けて「結婚しよう」と決まったら、なるべく早い段階でふたりの気持ちを確認し合うことです。
どんな形がいいのか、何を大切にしたいのか、そして親や周囲にはどう伝えるのか。
誰かの正解ではなく、自分たちの納得がある形こそが、一番幸せな“ふたりの結婚式”だと思います。
顔合わせが入籍ギリギリになってしまったらどうする?
本当はもっと早くやるはずだったのに、気づけば入籍まであと数週間。
そのタイミングで「そういえば、まだ顔合わせできてない……」とハッとしたときの焦り。
私も、まさにその経験をしたひとりです。
「親に申し訳ない」「順番が逆になっちゃったかも」「怒られないかな」と、頭の中はグルグル。
不安や罪悪感、プレッシャーでいっぱいになってしまったことを、今でもはっきり覚えています。
でも、そんなときこそ大切なのは、落ち着いて状況を整理し、今できるベストな対応を考えること。
完璧な段取りじゃなくても、誠意と思いやりを持って行動すれば、ちゃんと気持ちは伝わります。
なぜギリギリになってしまうのか?原因と背景を振り返る
顔合わせがギリギリになる理由は、意外とたくさんあります。
- お互いの仕事の都合や住んでいる場所が離れている
- そもそも顔合わせの段取りに不慣れで後回しになってしまった
- 結婚準備に追われて優先順位が下がってしまった……
私たちの場合も、彼が多忙な時期で休みが取れず、ようやく日程を調整できたのが入籍の3週間前。
しかも、会場探しや親の都合調整まで含めると、あっという間に時間が過ぎていきました。
けれど、ギリギリになってしまったからといって「失敗」ではありません。
そこからどう動くかが大切です。
親への気持ちは正直に。誠意が伝われば十分
まず一番に大切なのは、「遅くなってごめんなさい」と素直に伝えることです。
親も、子どもの事情はわかってくれます。
ただ「何も言われずに遅れたこと」に対して寂しさを感じる場合があるので、きちんと言葉にして説明することが誠意になります。
私は、彼の両親に「お忙しい中、ギリギリの日程になってしまい申し訳ありません。
でもどうしても一度お会いしたくて……」と手紙を添えてお願いしました。
その手紙を見て、お義母さんが「気持ちが嬉しいわ」と言ってくださり、心の緊張がふっと溶けたのを覚えています。
ギリギリでも温かい雰囲気を作るための工夫
直前の顔合わせでも、いくつかの工夫で“ちゃんと感のある”場を作ることができます。
まずは会場選び。
高級すぎず、でも少し特別感のあるレストランや個室のある和食店がおすすめです。
騒がしすぎず、落ち着いて話ができる空間を選びましょう。
次に進行内容をざっくり決めておくこと。
「まず彼が挨拶、続いて私から家族を紹介、そのあと食事、最後に記念撮影」
など、あらかじめふたりで流れを打ち合わせておくと、安心して臨めます。
そして手土産の準備。
形式にこだわらず、感謝の気持ちが伝わるように選んだお菓子や名産品を用意するだけで、印象はずっと柔らかくなります。
顔合わせは“スタート”であり“確認”でもある
顔合わせの本当の目的は、「お互いの親が初めて会い、家族としての一歩を踏み出すこと」です。
堅苦しい儀式ではなく、これから長く続くご縁の“はじめまして”の場。
入籍直前だとしても、それを大切にできれば十分です。
「今さら遅いかも」と感じる必要はありません。
私も、両家の笑顔を見ながら「ああ、ちゃんとやってよかった」と心から思えました。
バタバタだったけれど、その日を経て、家族としての距離がぐっと縮まった気がしたんです。
今だから言える、“順番よりも気持ち”の大切さ
結婚準備って、「こうしなきゃ」「これが正しい順番」と思い込んでしまいがち。
でも、すべてを完璧にこなせる人なんていません。
むしろ、予定通りにいかないことのほうが自然なのかもしれません。
大切なのは、どんなタイミングでも、相手の気持ちを大切にすること。
そして、後悔しないように「できる範囲で、できることを、心を込めてやる」こと。
顔合わせがギリギリになってしまったとき、私が自分に言い聞かせたのは、「遅くなってしまったけど、今なら間に合う。
心をこめて向き合えば、きっと大丈夫」という言葉でした。
そして本当に、それで大丈夫でした。
ふたりのペースで進めていい。けど段取りは味方になる
結婚準備って、なんとなく「こうあるべき」とか「みんなこうしてるから」という空気に流されがちじゃないですか?
SNSを開けば“理想の花嫁ルーティン”や“完璧な結婚準備スケジュール”がずらっと並んでいて、「え、私全然できてない……」と焦ってしまうこと、あると思うんです。
でもね、本当に大切なのは“ふたりの気持ちとペース”なんです。
周りのスピードに合わせなくても、決められた順番通りに進まなくても、ふたりが納得できていれば、それが一番いい形。
とはいえ、「段取り」が味方になってくれるのもまた事実。
私も結婚準備の中で何度もつまずきながら、「もっと早くやっておけばよかった」と思ったことが何度もありました。
だからこそ、“無理なく進めるための段取り”の大切さを、今ならすごく実感しています。
準備に正解はない。でも“全体の流れ”を把握するだけで心が軽くなる
最初に知っておいてほしいのは、「何をいつやるかの正解」は人によって違うということ。
でも、全体の流れをざっくり把握しておくだけで、「今、自分たちはどのあたりにいるのか」が見えるようになって、気持ちに余裕が生まれます。
↓
「親への結婚報告」
↓
「顔合わせ」
↓
「入籍日決定」
↓
「結婚式の有無の検討」
↓
「式場選び(必要なら)」
↓
「新居の準備」
↓
「手続き関係」
↓
「新婚旅行など」
ひとつひとつ、ふたりの暮らしや価値観にあわせて入れ替えてもいいんです。
私たちは、新居の準備を優先していたために、結婚式の打ち合わせがギリギリになってしまいました。
だけど、それも今となっては「私たちらしい流れだったな」と笑って話せる思い出になっています。
段取りが助けてくれる“心の余裕”
結婚の準備って、予想以上にエネルギーが必要です。
ふたりの話し合いだけじゃなくて、親との調整、書類の提出、職場への報告、引っ越しのタイミング……とにかく、人生のいろんなパーツが動くんです。
そんなとき、段取りを立てておくと「今はこれに集中すればいいんだ」と思えるようになります。
それが結果的に、気持ちの安定やストレスの軽減につながるんですよね。
私も一度、何もかもを同時に進めようとして心がいっぱいいっぱいになってしまったことがありました。
夜な夜なスマホで式場を探しながら、彼と口論になってしまった日もありました。
でも、ひとつずつやることをリストに書き出して、スケジュール帳に
「ここまでは彼」
「ここからは私」
と役割分担したことで、気持ちがぐんとラクになりました。
“ふたりで決める”ことが絆になる
結婚準備をしていくなかで、ふたりの意見がぶつかることもあると思います。
- 入籍日をどうするか
- 結婚式をするかしないか
- どこに住むのか
- 親への対応……
でも、そのすべての話し合いが“ふたりで人生をつくっていく”という体験になる。
私はそう信じています。
うちも、親への報告をいつにするかで揉めたことがあります。
彼は「もうちょっと先でいいよ」と言っていたけど、私は「親に変に思われる前に言いたい」と焦っていて……。
結局、お互いの気持ちをちゃんと話すことで、相手の背景や価値観を理解できたし、それ以降は決め事もスムーズになりました。
段取りを共有しながら、お互いの希望や不安を確認し合うことが、結婚準備において何よりの“夫婦練習”になるんだと思います。
完璧じゃなくていい。つまずいたら立ち止まっていい
「失敗したらどうしよう」「順番がズレたら怒られるかも」
そうやって心配して、身動きが取れなくなってしまうこともありますよね。
でも大丈夫。
完璧じゃなくていいんです。
段取りがズレたって、ちょっと忘れてたって、ふたりの気持ちがそこにあるなら、必ずちゃんと形になります。
私たちも顔合わせは遅れたし、婚姻届も提出前日に慌てて書きました。
でも、そういうドタバタも含めて「私たちらしいね」と笑える今があります。
焦らなくていい。
無理に詰め込まなくていい。
一歩ずつ、自分たちのペースで進めていけば、それがいちばん心に残る結婚準備になるはずです。
新婚旅行の準備は意外と後回しになりがち
「新婚旅行、どこに行きたい?」
プロポーズされたあとのウキウキの会話の中で、きっと一度は出てくるこの話題。
でも実際には、結婚準備が本格化すると、新婚旅行のことって意外と後回しになりがちなんです。
入籍日や顔合わせ、式の段取りや新居探しなど、「今すぐやらなきゃいけないこと」が山のようにある中で。
ついつい「旅行はそのあとゆっくり考えよう」となってしまうのは、本当にあるある。
私たちもまさにそうでした。
「旅行は落ち着いてからね」と話していたのに、気づいたら年末、人気シーズンの予約がほとんど埋まっていて……。
ふたりで焦りながら航空券サイトを漁った思い出があります。
新婚旅行の準備が後回しになりやすい理由とは?
結婚の準備って、実は“期限が明確なもの”から優先されがちです。
たとえば、
- 婚姻届の提出日
- 式場の予約
- 引っ越しの日程
- 会社への報告……
でも、新婚旅行って、なんとなく「いつか行ければいいよね」と後回しにされやすいんですよね。
旅行代理店に行くのも時間がかかるし、飛行機やホテルの手配は面倒だし、プランを立てる余裕もなかったりして。
結果的に、直前になって「あの場所に行きたかったのに、もう予約が取れない」「長期休暇が取れない」といった事態になることも。
理想の旅を叶えるには“少し早めの行動”がカギ
とはいえ、全部を早く決めろ!というのは現実的ではありません。
ただ、旅行に関しては“希望があるなら早めに動く”だけで、選択肢がぐんと広がるのは事実です。
特に人気のリゾート地や海外旅行、連休やハネムーンシーズンに被る時期は、半年前、場所によっては1年前からの予約が必要になることもあります。
さらに「早割」や「早期特典」などで旅行費用がかなり抑えられる場合もあるんです。
私たちは結局、オフシーズンを狙って少し遅れて旅行に行ったのですが、ちょうどそのタイミングで彼の有休が取れたこともあり、かえってのんびりした旅になりました。
結果オーライではあったけど、「行きたい場所が決まってるなら早めに予約しておいたほうが安心だったね」とふたりで何度も話しました。
ふたりの好みをすり合わせる“旅の打ち合わせ”も楽しい時間に
旅行って、ふたりの価値観が見えるイベントでもあります。
「海がいい!」
「いや、海外より国内が落ち着く」
「絶対グルメ重視」
「いやいや絶景でしょ」
……なんて、ちょっとした好みの違いが見えてくることも。
でもそのすり合わせも、結婚生活の準備期間として大切なプロセス。
旅行プランを一緒に考えること自体が、ふたりの絆を深めてくれます。
私は、彼と夜な夜な「旅のしおり作戦会議」をしていました。
インスタやブログを見ながら、「このお店行きたい!」「ここでプロっぽい写真撮ろう!」と盛り上がったあの時間も、今では大切な思い出です。
直前でもできる“新婚旅行らしさ”の工夫とは?
準備が遅れてしまっても、新婚旅行らしい雰囲気を出す工夫はたくさんあります。
たとえば、旅先でちょっと特別なディナーを予約したり、ふたりの名前入りのアイテムを用意したり。
ホテルに「ハネムーンです」と伝えれば、ウェルカムドリンクやサプライズ演出をしてくれるところもあります。
さらに、式のあとすぐに旅行に行けなくても、数ヶ月後に「後撮り旅行」や「記念月旅行」としてあらためて行くカップルも増えています。
「今すぐじゃなくても、ふたりで行きたいときに行けばいいよね」という柔軟な発想が、かえって気楽で楽しめることもあるのです。
焦らなくて大丈夫。ふたりの気持ちに正直な旅であればそれでいい
新婚旅行=絶対このタイミングで行かなきゃ!ではありません。
他人と比べる必要も、完璧なプランじゃなきゃいけない理由もないんです。
結婚という人生の節目に、「ふたりで特別な時間を過ごしたい」という気持ちがあれば、それがもう“最高の新婚旅行”になります。
「スケジュールが合わないからまだ行けてない」というカップルも、「あえて時期をずらして楽しむ」という選択肢があっていい。
焦らなくても大丈夫。
あなたたちらしい旅のカタチを、ゆっくりと見つけていけばいいのです。
いよいよ入籍!手続きと注意点
長いようであっという間だったプロポーズからの準備期間。
いよいよ「入籍」の日が近づいてくると、嬉しさと同時にじわじわと緊張もこみ上げてきますよね。
私も、婚姻届を手に役所へ向かう途中、「本当にこれで大丈夫かな?何か忘れてないかな?」と、何度も確認しながらドキドキしていたのを覚えています。
ふたりの人生がひとつに重なる、大切な第一歩。
だからこそ、心穏やかにその日を迎えるためにも、入籍手続きの流れと注意点はしっかり押さえておきたいところです。
婚姻届の提出は「書いて出すだけ」じゃない!
「婚姻届って、紙に書いて出せば終わりでしょ?」と思っている方、少なくないかもしれません。
でも実は、必要な書類や注意点がいくつかあって、事前にきちんと準備しておかないと、せっかくの記念日に「受理されなかった…」なんて残念なことになりかねません。
婚姻届と一緒に提出が必要なものは、以下のとおりです(※自治体によって細かい違いがあります):
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 本籍地以外の役所で提出する場合は戸籍謄本
- 証人(満20歳以上の2名)の署名と押印
- 印鑑(旧姓のもの)
なので、その場で不備を指摘されても訂正ができません。
私の知人は、夜間に提出して不備が見つかり、入籍日を翌日にずらすことになってしまったことがありました。
提出予定の自治体に事前に確認の電話を入れるだけでも、安心感がまるで違いますよ。
証人は誰にお願いする?気をつけたいマナーと配慮
婚姻届には、ふたり以外に“証人”が必要です。
これは、ふたりの結婚の意思を確認してくれる存在で、法的にも重要なサイン。
私たちは、彼の姉と私の親友にお願いしましたが、誰に頼むかは意外と迷いますよね。
親にお願いする人もいれば、兄弟姉妹、親しい友人や職場の上司にお願いする方もいます。
ただし、誰に頼む場合でも、事前に丁寧にお願いをすること、婚姻届に記入・押印してもらう日程を余裕を持って設定することが大切です。
急ぎで証人欄を書いてもらう必要が出てきて、相手に負担をかけてしまうケースもあるので、入籍日が決まったら早めにお願いしておきましょう。
「記念日」にするなら、計画的な提出を!
入籍日は、ふたりにとって一生の記念日になる特別な日。
だからこそ、「どうしてもこの日付にしたい!」という思いがある人も多いはず。
交際記念日や誕生日、「大安」「いい夫婦の日」などの縁起の良い日を選ぶカップルも少なくありません。
ただし、先ほども触れたように、記念日にこだわるなら提出の“時間帯”や“受付体制”にも要注意です。
どうしてもこの日に提出したい場合は、開庁時間内(平日9:00~17:00など)に提出できるよう調整しておくと安心です。
また、特に混雑しやすい日(11月22日など)は提出待ちが長くなることもあるため、余裕を持って行動しましょう。
受理されたら安心…ではなく、次にやるべきことがたくさん!
婚姻届が無事に受理されると、ほっとひと安心。
でも実は、そこからが“本当の意味での結婚生活のスタート”です。
姓が変わる場合には、以下のような変更手続きが必要になります:
- 健康保険証の名義変更
- 銀行口座、クレジットカードの氏名変更
- 免許証やマイナンバーカードの変更手続き
- パスポートや車検証などの名義変更
- 携帯電話やネット通販サイトの情報更新 など
手続きのリストをスマホにまとめておくと、あとでラクになりますよ。
不安なときは、役所に聞いてOK!ひとりで抱え込まなくて大丈夫
入籍の手続きって、一生に一度だからこそ“慣れていないのが当たり前”です。
でも、不安や疑問が出てきたときに「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮する必要はまったくありません。
役所の窓口の方は、毎日のように婚姻届を扱っています。
私も何度か役所に電話をしましたが、どの担当者さんもとても親切に教えてくれました。
わからないことは、早めに確認する。
それが安心につながるし、入籍日当日を笑顔で迎えることにもつながります。
ふたりの“はじまりの日”を、丁寧に迎えるために
入籍は、ふたりの人生がひとつに重なる瞬間。
手続きと聞くとなんだか事務的に感じてしまうかもしれませんが、その1枚の婚姻届には、ふたりのこれまでとこれからの想いが詰まっています。
- 記念日にするかどうか
- どこで提出するか
- 誰に証人を頼むか……
完璧じゃなくてもいい。
書類に少し手間取っても、写真を撮り忘れても、それも全部が大切な思い出。
ふたりらしいペースで、あなたたちだけの“入籍のかたち”を大切に迎えてくださいね。
ナシ婚でも忘れちゃいけない4つのこと
結婚式を挙げない「ナシ婚」という選択は、いまや珍しいものではありません。
むしろ、私のまわりでも「式を挙げなかった」という夫婦は年々増えていますし、それぞれが自分たちらしい形で幸せな家庭を築いています。
「結婚=盛大な式」というのは、もしかしたら親世代までの常識なのかもしれません。
でも今は、結婚式をしない分、新生活の準備や将来のためにお金を使いたい、という考え方もとても現実的で素敵な選択肢だと私は思っています。
ただ、ナシ婚を選ぶ場合でも「何もしなくてOK」ではなく、気持ちや関係性の面で大切にしておきたいことがあるんです。
ここでは、ナシ婚でも後悔しないために、忘れずに意識しておきたい4つのポイントをお伝えします。
① 親への相談は、決定前にしっかりと
「式はしないよ」と決めたら、すぐに親へ報告…ではなく、できれば“相談”という形で早めに伝えることをおすすめします。
私の友人は、事後報告で「ナシ婚にしたよ」と伝えたことで、親御さんから「せめて一言、相談してくれてもよかったのに…」と寂しそうに言われてしまったそうです。
式を楽しみにしていた親世代にとって、報告ではなく相談という“ワンクッション”があるだけで、気持ちの整理がずいぶん違うものです。
「お金の面で現実的に難しい」「目立つのが苦手」「今の状況では準備に時間をかけられない」
そうした理由をきちんと伝えれば、多くの親はちゃんと理解してくれます。
② 式の代わりに“形として残すこと”を考えてみて
ナシ婚でも、「なにかしら記念になることをしたい」と思う気持ちは、きっとどこかにあるはずです。
それを無理に押し込める必要はありません。
実際、ナシ婚を選んだカップルの中には、
- フォトウェディング(洋装・和装)
- 親しい人を集めた食事会(1.5次会)
- 旅行先でのセルフ撮影や記念ディナー
私たちも、式はしなかったけれど、お気に入りのドレスを着て写真スタジオでフォトウェディングをしました。
最初は恥ずかしかったけど、撮ってよかったです。
いま、その写真は寝室に飾ってあって、見るたびに「このときの気持ち、忘れないようにしよう」と思えるんです。
③ 結婚祝いのお返し(内祝い)はきちんと丁寧に
結婚式をしないと、「お祝いをもらう場」があいまいになりがちですが、ナシ婚でもお祝いをいただいたら、内祝いを贈るのがマナーです。
とくに式がない分、内祝いを通じて「感謝の気持ちをきちんと形にして伝える」ことが、相手との関係性をより大切にすることにもつながります。
私の周囲では、「ナシ婚だからお返しは気軽にでいいよね」と思っていた人が、のちに「ちょっと失礼だったかも…」と後悔していました。
相場としては、いただいた金額の半額を目安に、1ヶ月以内を目途に送るのが基本です。
そこに手書きのメッセージや、ふたりの写真を添えたポストカードを同封すると、より気持ちが伝わります。
④ 結婚報告は“言葉で届けること”を忘れずに
式を挙げない場合、「結婚したことをどうやって周りに伝えたらいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
そんなときにおすすめなのが、結婚報告ハガキや、新住所のお知らせと一緒にメッセージを添えることです。
「SNSに投稿したからそれで十分」と思うかもしれませんが、親戚や年配の方など、SNSを使っていない人にはきちんとお知らせしておくと、あとから気まずくならずに済みます。
私も、地元の友人に結婚の報告が漏れていたことで、「なんで黙ってたの~!」とちょっと寂しそうに言われてしまったことがありました。
直接会えないからこそ、言葉にして伝えることは、思っている以上に大切なコミュニケーションなんですよね。
ナシ婚は、自由でスマートな選択のようでいて、実は「だからこそ丁寧にしたいこと」がたくさんあります。
大切なのは、“式をしないこと”を決めるだけで終わらせず、「ふたりの結婚をどう祝うか、どう伝えるか」を考えること。
形がシンプルだからこそ、気持ちの部分に真心を込めて。
あなたたちらしい“節目の迎え方”を、ぜひ大切にしてあげてくださいね。
入籍後に必要な名義変更リスト
入籍が無事に終わってホッとしたのも束の間、そこから始まるのが“怒涛の名義変更ラッシュ”。
特に名字が変わる側は、思った以上にやることが多くて、「まだ終わってないの?」「またこの書類いるの!?」と心の中で何度も叫ぶことになるかもしれません(笑)
でも大丈夫。
順番に、ひとつずつ、できるところから対応していけば、ちゃんと終わります。
私も最初は「なんかめんどくさそう…」と気が重かったけれど、リストを作って“見える化”したことで、スムーズに進めることができました。
ここでは、入籍後に必要となる主な名義変更の項目と、その注意点をわかりやすくまとめていきますね。
まず最初にやるべき“公的書類”の名義変更
名義変更は、まず身分証明書類など“基礎となるもの”から変更するのが鉄則です。
以下のような公的書類は、他の手続きのときに必要になるので、早めに済ませましょう。
運転免許証
警察署や運転免許センターで変更可能。
新しい姓を証明する書類(婚姻届受理証明書や新しい住民票など)が必要です。
マイナンバーカード(通知カード)
市区町村の役所で変更手続きが必要。
つい忘れがちなので注意。
健康保険証
勤務先の会社経由で変更、または国保の場合は役所へ。
病院にかかる予定がある場合はとくに早めに。
パスポート
海外旅行を予定しているなら、すぐに対応を。
戸籍謄本などが必要になるので、時間と費用に余裕を持って。
私の場合、まず免許証を変更しておいたことで、銀行やクレカの変更手続きがすごくスムーズに進みました。
「とりあえずこれを最初にやっておけば安心」という“軸”になるんですよね。
金融関係の変更は“連鎖型”で一気に進めよう
次に着手したいのが、銀行口座やクレジットカード、各種支払い関係の名義変更です。
これらは身分証明書や印鑑が必要になることも多いので、公的書類の変更が終わってからがスムーズです。
銀行口座
窓口での手続きが多く、本人確認書類と通帳、印鑑、新姓の確認書類が必要。
クレジットカード:多くはウェブサイトや郵送で変更可能。
カード会社によっては再発行になることも。
証券口座・保険・年金
名前と住所の変更が必要。
放置すると将来的にトラブルの原因に。
住宅ローン・奨学金など、借入関係の契約情報も変更忘れに注意。
私が便利だったのは、変更した銀行口座に紐づけている「電気・ガス・水道」「スマホ代」「ネット通販」などの引き落とし先も一緒に見直したことです。
この機会に“生活の中のお金の流れ”を整理することができて、家計管理がグンとラクになりました。
地味だけど忘れやすい“暮らしの名義変更”
名義変更と聞くと、つい「公的な書類」や「銀行関係」ばかりに目が行きがちですが、実は日常の中にも“名前が変わると面倒になるもの”がたくさんあるんです。
- 携帯電話・インターネットの契約名義
- サブスク系サービス(Netflix、Amazon、楽天、各種アプリ)
- 定期券や交通系ICカード(Suica、PASMOなど)
- 病院の診察券
- 職場のメールアドレスや名刺など
- 宅配業者の登録情報やネット通販アカウント
まとめて見直しておくと、あとからのモヤモヤが減ります。
すべてを完璧にやろうとしなくていい。優先順位が大事
名義変更って、やり始めると「あれもこれもやらなきゃ!」と焦ってしまいがち。
でも、すべてを一度に完璧に終わらせようとしなくて大丈夫です。
「今日は免許証だけ」「来週は銀行と保険」など、1日1タスクでも充分。
大事なのは、ひとつひとつを丁寧に、確実に進めていくことです。
私はノートにチェックリストを作って、完了したら赤ペンで丸をつけていました。
進捗が目に見えるだけで、気持ちに余裕が持てたし、ちょっとした達成感も味わえましたよ。
名義変更は“ふたりの暮らしを整える時間”でもある
名義変更って、どこか“面倒な義務”のように感じがちですが、実はこれって、ふたりの暮らしをかたちにしていく時間でもあるんですよね。
書類を出したり、窓口に行ったり、メールでやり取りしたり……
日常に追われていく中で、「ああ、結婚ってこうして“現実になっていくんだな”」と実感できる、大切なプロセスだったと私は感じています。
だからこそ、焦らなくて大丈夫。
ゆっくりでもいいから、ひとつずつ。
ふたりで確認しながら進めていけば、それで十分なんです。
自分たちらしい形で、後悔のない結婚を
プロポーズのあと、結婚に向けて歩み出すふたり。
でもその道のりには、正解もマニュアルもありません。
私自身、結婚準備を進める中で何度も迷いました。
式をするかしないか、入籍日はどうするか、両親への対応、新婚旅行のタイミング、引っ越しの段取り……
一つひとつに「これでいいのかな?」と自信が持てなくなったり、他のカップルと比べて落ち込んだりする瞬間が、たくさんありました。
でも今振り返って思うのは、「誰かと同じじゃなくてよかった」ということです。
完璧じゃなくていい。“わたしたちらしさ”がいちばんの正解
SNSでは、きらびやかな結婚式や完璧な段取りがたくさん流れてきますよね。
見るたびに「自分はちゃんとできていないかも」と不安になってしまう気持ちも、とてもよくわかります。
でも、ふたりにしかわからないペースや事情、価値観があるように、結婚の形もふたりだけのもの。
誰かの「普通」や「正解」に合わせなくてもいいんです。
私たちは顔合わせが遅れてしまったし、結婚式もシンプルな形だったけれど、それでも心から幸せだと思える日々を送れています。
“ふたりで決めてきたこと”そのものが、なによりも意味のある軌跡になるんですよね。
後悔を減らすコツは、“気持ち”を置いてきぼりにしないこと
結婚準備で後悔している人の多くが口にするのが、「もっと自分たちの気持ちを大切にすればよかった」という言葉。
逆に言えば、自分たちの“こうしたい”を大事にすることが、後悔を防ぐ一番のカギなんです。
「本当はドレスを着たかった」
「もっと親と向き合えばよかった」
「焦って決めすぎた」
そんな気持ちを抱えたまま時間だけが過ぎていくのは、きっともったいないですよね。
ふたりで何度でも話し合っていい。
立ち止まって、迷って、また決め直したっていい。
大切なのは、“選ぶこと”じゃなくて、“納得すること”なのだと思います。
あなたの“これから”を応援しています
この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっと誰かのために、そして自分のために、丁寧に未来を考えている優しい方だと思います。
悩みながらでも進もうとしている、その姿勢こそが、すでに幸せのスタートラインに立っている証です。
プロポーズから入籍までの道のりは、決して一直線じゃありません。
でも、だからこそ、ひとつひとつをふたりで乗り越えていく過程が、これからの人生の土台になってくれるはず。
どんな形の結婚でもいい。
大切なのは、ふたりが笑顔で「これでよかった」と思えるかどうか。
どうか、あなたたちらしい、あたたかくて後悔のない結婚になりますように。
心から応援しています。