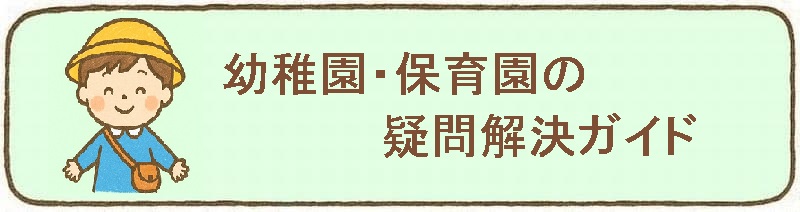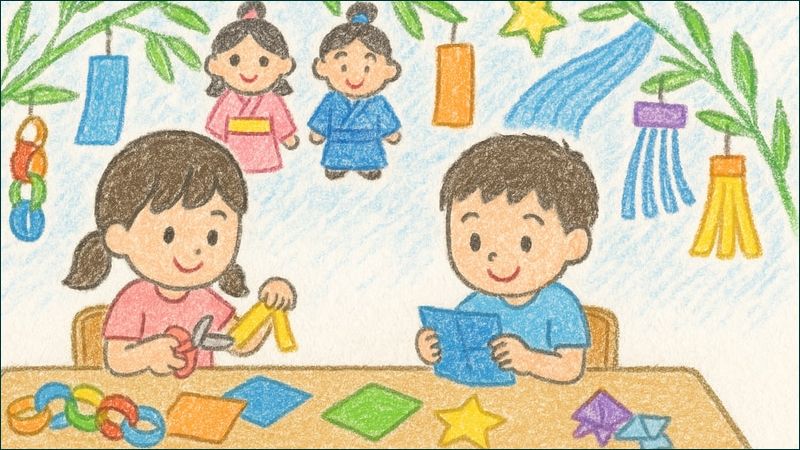
七夕といえば、夜空に願いを込めて飾りを作る、年に一度のロマンチックで心温まる季節のイベントですよね。
特に保育園では、七夕をきっかけに子どもたちと季節を感じたり、日本の伝統行事に親しんだりする大切な時間にもなっています。
そんな中で、みんなで一緒に折り紙を使って七夕飾りを作るのは、子どもにとっても先生にとっても、とても思い出深い経験になるんです。
この記事では、折り紙を使って保育園でも簡単に作れる七夕飾りのアイデアをたっぷりご紹介していきます。
小さなお子さんでも楽しみながら取り組めるような工夫や、教室での飾り方のコツ、準備のポイントまで、幅広く取り上げていますので、「何を準備すればいいかな?」「どんな折り紙飾りなら子どもが楽しめるかな?」と迷っている先生や保護者の方にも、きっと役立てていただける内容になっていますよ。
工作が初めての子どもでも安心して取り組めるように、折り方の簡単さや材料の選び方にも触れながら、わかりやすくやさしい言葉でお届けしていきます。
ぜひ、今年の七夕準備に役立ててくださいね。
保育園で七夕飾りを折り紙で作るメリットとは?
子どもと一緒に楽しめる行事として人気
七夕は、子どもたちにとっても先生にとっても、わくわくするイベントです。
願いごとを書いた短冊を飾るだけじゃなくて、自分の手で飾りを作ることで、より思い入れのある特別な時間になりますし、子どもたちの個性も輝きますよね。
折り紙を使えば、色とりどりの紙が変身していく楽しさを体験できて、創造力も自然と育ちます。
また、飾りを作る過程で「どんな形にしようかな」「この色にしてみようかな」と考える時間も、子どもたちにとっては大切な学びの時間なんです。
先生や友達と話しながら進めていくことで、コミュニケーションの力や協調性も育ちます。
完成した飾りを教室に飾れば、空間全体がぐっと華やかになって、子どもたちも「みんなで作ったんだ!」という喜びと達成感を感じることができます。
教室の雰囲気もパッと明るくなって、七夕の季節をより楽しく、心に残るものにしてくれますよ。
集中力や指先の発達にも効果的
折り紙は、ただ楽しいだけじゃなくて、手や指をたくさん使うことで、指先の細かな動きや感覚を育てるのにもぴったりなんです。
特に保育園の年齢の子どもたちは、まだ手先の発達途中にあるので、こうした折る・つまむ・貼るといった一連の作業は、成長にとってとても良い刺激になりますよ。
さらに、折り紙を使って「形が変わっていく様子」を楽しむことで、図形や色への興味が自然と芽生えてきます。
「この形は星に似てるね!」「こっちの色のほうが明るいね」といった気づきが、感性や観察力にもつながっていくんです。
色の組み合わせを考えるときには、創造力もぐんぐん育まれます。
完成した飾りで子どもの達成感も育てる
「自分で作れた!」という経験は、子どもにとってとても大きな喜びです。
時間をかけてがんばったものが形になることで、満足感や達成感が自然と育ちますし、「もっと作ってみたい!」というやる気にもつながります。
先生やおうちの人に「すごいね!」とほめられることで、自信にもつながっていきます。
また、みんなで一緒に飾ったときに「これは〇〇ちゃんが作ったのだよ」と紹介されたりすると、子ども自身が自分の存在を認められたように感じられて、心の安定にもつながります。
保育園の行事として七夕飾りを作る時間は、そんな心の成長にもつながる貴重なひとときなんですね。
保育園でも簡単に作れる!七夕折り紙飾りのおすすめアイデア
年少さんでも作れる!織姫と彦星
織姫と彦星の折り紙は、七夕を象徴するキャラクターとしてとても人気です。
作り方はとってもシンプルで、顔の部分は白い紙を丸く切ってペンで表情を描くだけでもかわいくなります。
目や口を自由に描いてあげることで、子どもたちそれぞれの個性がしっかり出せるのも楽しいポイントなんです。
体の部分は折り紙をそのまま使って着物のように折っていくだけ。
色は自由に選べるので、「織姫はピンクがいい!」「彦星は水色が好き!」といった風に、好きな色で組み合わせられます。
模様のある折り紙を使うと、より本格的な雰囲気になりますよ。
また、できあがった織姫と彦星は、紙皿や台紙に貼ってストーリー仕立てにするのもおすすめです。
背景に星を散りばめて天の川を描いたり、短冊と一緒に飾ってあげると、世界観が広がってさらに楽しい七夕飾りになりますよ。
飾りに映える!天の川や星の折り紙
星型の折り紙は見た目も華やかで、飾るだけで一気に七夕らしさが演出できる素敵なアイテムです。
天の川のように横に並べて吊るすととてもキレイで、子どもたちの目を引く装飾になりますよ。
色を工夫するとさらに魅力的になり、金や銀の折り紙を使えばキラキラして夜空の雰囲気がぐんとアップします。
透明の糸や糸付きのテープを使って吊るすと、まるで星が浮かんでいるように見えて、飾り全体の完成度も高く見えるんです。
また、星の折り紙はさまざまな大きさで作れるのもポイント。
大きい星は教室の目立つ場所に、小さい星は短冊の周りに飾るなど、工夫しだいでいろいろな場面で活躍してくれます。
少し難しい形でも、先生がゆっくり見本を見せてあげたり、一緒に折ってあげたりすれば、年中さんや年長さんでもしっかりチャレンジできますし、完成したときの満足感も大きいですよ。
カラフルで人気!ちょうちん飾りの折り方
折り紙を折って切るだけで作れるちょうちん飾りは、保育園の七夕行事でもとっても人気のあるアイテムです。
作り方はとてもシンプルで、まず折り紙を半分に折って、端を少し残してハサミで均等に切り込みを入れていきます。
それをくるっと丸めて貼り合わせれば、あっという間に完成。
工程がわかりやすく、道具も少ないので準備も楽なんです。
色とりどりの折り紙で作ることで、教室全体が一気にパッと明るくなり、七夕らしいにぎやかで楽しい雰囲気になります。
色の組み合わせを考えながら作るのも、子どもたちにとっては楽しみのひとつ。
「赤と黄色で元気な感じにしたい!」「水色と白で夜空みたいにしたい!」と、創造力もぐんぐん育まれます。
さらに、ちょうちん飾りは縦にも横にも飾れるので、壁や天井、廊下などいろいろな場所で使いやすいのも魅力。
子どもたちも「もっと作りたい!」と夢中になる飾りですよ。
切って貼るだけ!すだれ・輪つなぎもおすすめ
小さな子でも取り組みやすいのが、輪つなぎやすだれ飾りです。
折り紙を細長く切ってノリでつなげるだけだから、ハサミや複雑な折り方がまだ難しい年少さんでも楽しみながら取り組めます。
輪つなぎは、同じパターンの繰り返しなので達成感を感じやすく、「つなげていく」過程がとても楽しいんです。
自分で作った長い飾りが教室に飾られると、子どもたちもとっても誇らしげになりますよ。
すだれ飾りは、折り紙を細長く重ねて貼るだけで、風に揺れるようなデザインになるので、見た目も爽やかでおすすめです。
これらの飾りは材料も少なくてすむうえ、たくさん作っても時間がかからないので、大人数のクラスでも取り入れやすいですよ。
色の組み合わせ次第で雰囲気ががらっと変わるので、飾る場所に合わせてアレンジしてみてくださいね。
七夕飾りを折り紙で作るための準備と進め方のコツ
使いやすい折り紙サイズや種類とは?
保育園で七夕飾りを作るときに使う折り紙のサイズとして、15cm四方の一般的なサイズがとても扱いやすくておすすめです。
小さすぎると折るのが難しくなったり、飾ったときに目立たなかったりしますし、大きすぎると手が小さな子どもにとっては扱いにくく、作業しづらくなってしまいます。
15cmというサイズは、子どもが自分の手でしっかり折れるちょうどよい大きさなんですね。
また、折り紙の種類を工夫することで、飾りの雰囲気がぐっと華やかになります。
たとえば、伝統的な和柄の折り紙は、七夕という行事の和の雰囲気にもぴったり。
キラキラ光るホログラム折り紙を取り入れると、夜空に輝く星のような印象になってとても素敵です。
パステルカラーやグラデーションの折り紙を使うと、やさしい雰囲気に仕上がるので、年少さんの作品にもぴったりですよ。
色や柄のバリエーションをいろいろそろえておくと、子どもたちも「この色がいい!」「この柄かわいい!」と、自分で選ぶ楽しみが広がります。
自分の選んだ折り紙で作ることで、作品への愛着もわいて、よりやる気を持って取り組めるようになりますよ。
ハサミを使うか使わないかの判断基準
年少さんなどまだ年齢が小さい子どもたちには、ハサミを使わずに作れる飾りを選んであげると安心です。
折り紙を折るだけで作れる飾りなら、道具を使う不安もなく、気軽に楽しむことができます。
ただ、年中さん・年長さんになると、徐々にハサミの使い方にも慣れてきますし、簡単な切り込みを入れる作業に挑戦してみることで、工作の幅も広がります。
先生がそばについてサポートしてあげながら、少しずつハサミを使う経験を取り入れていくといいですね。
もちろん、子どもの発達段階や性格に合わせて、「今日は折るだけにしよう」「チャレンジしたい子にはハサミを使わせてみよう」と柔軟に対応することも大切です。
安全第一を心がけながら、その子にとってちょうどいい難易度の活動を選んでいけると、無理なく楽しく進められますよ。
大人数でもスムーズに進めるには?
保育園では一度にたくさんの子どもと一緒に作業をすることになるので、事前の準備がとても大切です。
まずは、先生が見本を用意しておくことで、子どもたちは完成形のイメージがつかみやすくなり、「これを作るんだ!」というやる気にもつながります。
見本は大きめに作って掲示しておくと、離れた場所からでも見やすくなりますよ。
加えて、手順カードや図解の説明を用意しておくと、先生が一人ひとりに説明しなくても子ども自身で流れを確認しながら進めやすくなります。
イラスト入りの手順カードを掲示したり、机ごとにセットしておくと、視覚的にも理解しやすくなっておすすめです。
また、折り紙やノリ、はさみなどの道具はあらかじめ人数分をそろえ、テーブルごとに分けておくと混雑やトラブルも少なくなります。
特にハサミを使う場合は、安全に使えるようにルールを決めておくと安心です。
素材も、折り紙をあらかじめ折る段階まで準備しておいたり、切る作業がある場合は先生が事前に切っておくなど、年齢に合わせて対応すると作業がスムーズに進みますよ。
作った七夕飾りをきれいに飾る方法とアイデア
教室や廊下に吊るすなら?バランス良く見せるコツ
いろんな飾りを一緒に飾るときは、全体の色のバランスや飾りの大きさ、配置を考えながら吊るすことで、よりまとまりのある美しい七夕飾りになります。
例えば、明るい色と落ち着いた色を交互に配置したり、同じ色が続かないように並べると、にぎやかすぎず整った印象になります。
また、大きな飾りは下の方に配置し、小さな飾りを上の方に吊るすと、全体のシルエットが三角形になって自然に引き締まって見えるんです。
これはツリーのような効果で、安定感があり視線の流れもスムーズになりますよ。
飾る高さも重要で、子どもたちの目線に合わせて低めに飾ると、自分たちが作ったものをすぐに見られて嬉しくなります。
反対に、少し高い位置には目立つ飾りを配置することで、空間全体の印象を華やかにすることもできます。
天井や窓枠、廊下の壁など、飾る場所によって工夫のしがいがありますので、場所に合わせて最適な飾り方を考えるのも楽しいですよ。
笹がないときの代用方法もご紹介
本物の笹が手に入らないときは、手軽に手作りできる代用品を使って、素敵な七夕飾りスペースを作ることができます。
たとえば、緑の画用紙を笹の葉の形に切って、壁に何枚も貼っていくだけでも、立派な笹の雰囲気が出せますよ。
紙ストローや割りばし、ラップの芯などを束ねて茎のようにすれば、立体感のある笹飾りができあがります。
特に紙ストローは軽くて扱いやすいので、子どもと一緒に作っても安全です。
束ねるときはマスキングテープや色テープを巻くと、茎の部分も可愛らしくデコレーションできます。
また、布やフェルト素材を使って笹を作ると、壁に貼ったときに柔らかな印象になっておすすめです。
笹の代用品を用意することで、飾りの自由度が高まり、笹がなくても素敵な七夕空間を演出することができますよ。
写真映えする飾りつけで思い出に残そう
せっかく作った飾りは、写真に残しておくことでその日の思い出を形に残すことができますし、あとから見返したときに「このとき頑張って作ったね」と話題にもなって楽しいですよね。
特に子どもたちの笑顔や飾りの工夫がよく見えるようにするためには、撮影のときの背景や光の入り方も少し意識すると、より素敵な一枚になりますよ。
飾る場所や高さを工夫して、子どもたちの顔と飾りが一緒に写るようにすると、より臨場感が出て「その場の空気」が伝わる写真になります。
たとえば、飾りの中に立って写真を撮るフォトスポットを用意するのもおすすめです。
子どもたちも「写真撮って!」と自らポーズを取ってくれるようになりますよ。
また、短冊を並べる専用のコーナーを作ると、願いごとの文字や飾りも一緒に写すことができて、七夕らしい雰囲気がより一層引き立ちます。
カラフルな背景布や、星のガーランドなどを飾っておけば、撮影時にも映える空間になりますので、保護者の方にも喜ばれること間違いなしです。
まとめ|保育園でも楽しめる簡単な七夕折り紙飾りで思い出をつくろう
保育園での七夕は、子どもたちの成長を感じられる素敵な行事です。
願いごとを込めた短冊を飾るだけでなく、折り紙を使って自分たちの手で飾りを作る体験は、子どもたちにとって特別で思い出深い時間になります。
日々の生活の中ではなかなか体験できない日本の伝統文化に親しみながら、季節の移り変わりを感じられる貴重なチャンスでもあります。
折り紙で作る飾りは、材料も手に入りやすく、道具も少なくてすむので準備がしやすいのも嬉しいポイント。
見た目にもかわいくて、教室や廊下に飾ると一気に七夕ムードが高まります。
子どもたち自身が「これを作ったよ!」と誇らしげに話す姿も微笑ましく、大人にとっても喜びを感じられるひとときになりますね。
簡単なものから少しチャレンジが必要な飾りまで、子どもたちの年齢やスキルに合わせて選べば、無理なく楽しく取り組めます。
年少さんには切って貼るだけの飾りを、年中・年長さんには少し工程のある折り紙工作を…と工夫して取り入れることで、全員が満足できる活動になりますよ。
手作りの飾りには、一つひとつに子どもたちの想いや努力が込められています。
今年の七夕も、そんな温かみのある飾りで教室を彩って、子どもたちの心に残る素敵な思い出をたくさん作っていってくださいね。