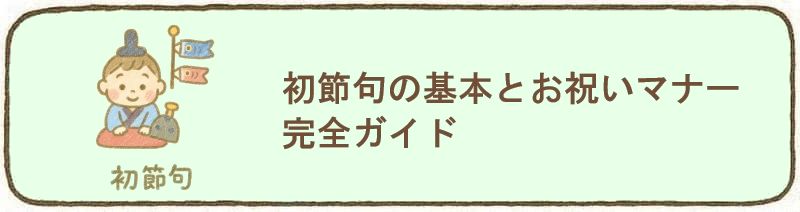初節句を迎えるにあたって、女の子の家庭で必ず話題にあがるのが「雛人形って誰が買うの?」という疑問です。
昔ながらの風習では母方の実家が贈るのが一般的とされていますが、最近では地域差や家庭の考え方の違いもあって、そのルールは一概には言えません。
共働きが当たり前になった今の時代、夫婦で購入するケースや、両家で費用を出し合うスタイルも増えてきています。
しかし、誰が買うかをあらかじめ確認しないまま時期が近づいてしまうと、
「準備が間に合わない」
「両家から2つ届いた」
など、思わぬトラブルの原因になることも。
相手に失礼なく、かつ円満に雛人形の購入について確認するためには、伝え方やタイミングに気をつけることがとても大切です。
この記事では、「雛人形は誰が買うのが正解なのか?」という基本から。
親族との関係を悪くしないための確認方法、トラブルを避ける伝え方の工夫まで、初節句を安心して迎えるための実践的なポイントをご紹介します。
雛人形は誰が買うもの?まずは基本を知っておこう
初節句が近づくと、雛人形をどうするかで頭を悩ませる家庭は少なくありません。
特に初めての子どもとなると、何をどこまで準備すればいいのかもよくわからず、「雛人形って、そもそも誰が買うべきなの?」という疑問にぶつかる方も多いんです。
実はこの「誰が買うか」問題は、家庭や地域によって慣習が違っていたりして、意外と曖昧なままになっていることが少なくありません。
さらに、ショッピングモールやデパートに雛人形の特設コーナーが並び始めると、「うちもそろそろ準備しないと」と焦る気持ちになりがちです。
でも誰も話題に出してくれないと、余計にどうしていいか分からなくなってしまいますよね。
伝統的には「女方の実家」が購入する風習
昔からの風習では、女の子の初節句に贈る雛人形は、奥さんの実家、つまり母方の祖父母が用意するのが一般的とされてきました。
これは「嫁いだ娘に、孫の健やかな成長を願って人形を贈る」という意味が込められていて、昔ながらの家族のあり方が反映された風習なんですね。
とくに、昔は三世代同居や、親戚づきあいが密だったこともあって、こうしたしきたりは地域の年配の方から自然と教えられることが多かったようです。
「ひな人形は嫁ぎ先ではなく、実家が贈るもの」という考え方が浸透していた時代背景もあります。
ただ、現代では家族の形も変化していて、核家族で暮らしている人も多いですし、そもそもこの風習自体を知らないという若い世代も少なくないんです。
実際は地域差や家庭の方針によってさまざま
とはいえ、この風習は地域によってかなり違いがあるのが実情です。
たとえば関西と関東でも雛人形に関する考え方が異なることがあり、「父方の実家が用意するのが当たり前」とされる地域もあります。
また、家同士の関係性や家計の状況によって、最初から「両家で費用を出し合う」という前提で話が進むこともあります。
さらに、結婚してからの時間が長かったり、すでにお祝いの風習がはっきりしている家庭であれば問題は起きにくいですが。
初めての子どもで両家とも「何をすればいいのか分からない」となっていると、ややこしい空気になってしまうことも。
そういったときに、「うちはどうするか」ということを早めに確認し合うことがとても大切になってきます。
雛人形に限らず、こうした季節の行事では“正解”が一つではないことがほとんどなので、周りの常識や昔のしきたりにとらわれすぎず、自分たちの生活に合ったやり方を話し合う姿勢が大切です。
最近は「自分たちで買う」家庭も増えている
最近では、夫婦で自由に選んで購入するスタイルをとるご家庭がとても増えています。
共働きで家計をしっかり支えている夫婦も多いですし、「せっかく飾るものだから、自分たちの気に入ったものを選びたい」と考えるのも自然な流れです。
お祝いの場では祖父母に「選んだ雛人形を見せる」という形にして、「こんな風に選んだよ」と報告するだけでも、とても喜ばれることがあります。
また、実際には買うのは自分たちでも、お祝いとして祖父母からお祝い金をいただいたり、別の贈り物をもらうなど、いろんなサポートの形があるんですね。
さらに、近年はミニマル志向や収納スペースの都合で、小さめの雛人形やケース入りの飾りを選ぶ人も多く、それに合わせて「購入は自分たち、気持ちは両親から」というスタイルも定着しつつあります。
トラブルを防ぐために事前確認は必須!
「うちは母方の実家が買ってくれるだろう」と思い込んでいたら、当の実家はまったくそのつもりがなかった…なんてこともあります。
こうした思い込みは、意外とどの家庭でも起こりがちな落とし穴です。
とくに初めての子どもで、初めての初節句となると、経験もなく「どこが何を用意するのか」がはっきりしないまま時間だけが過ぎてしまいがち。
その結果、いざというときに雛人形が手配できていなかったり、急いで選ぶことになって満足のいかないものになってしまったりすることも。
また、せっかくのお祝いなのに
「間に合わなかった」
「準備不足だった」
と感じてしまうと、親としてもなんだか後悔の残る行事になってしまいます。
それだけでなく、
「どうして声をかけてくれなかったのかな?」
「まさか何も考えてないってこと?」
と、義実家との関係にも微妙な空気が流れてしまうこともあるんです。
準備が遅れたことで気まずい雰囲気になってしまうと、その後のやりとりにも影響が出てしまいかねません。
何も言わずに待つのはNG!お互いに誤解のもと
「言わなくても分かるはず」「常識でしょ」と思ってしまいがちですが、こういうイベントほど、お互いに認識のズレが出やすいんです。
とくに今は、昔ながらの風習を知らないご家庭も多いので、何も確認せずにいると「えっ?雛人形って必要なの?」といった温度差が生まれることも。
また、言わずに黙っていると「向こうも何も言ってこないし、うちで準備しなくていいのかな?」というように、お互いが様子見をしているだけ…という状況になりがち。
結果的に、誰も動かないまま気がつけば時期を逃してしまった、なんてことにもなりかねません。
だからこそ、早めに軽く話題に出してみたり、「そろそろ雛人形のことも考えたいね」と夫婦で話すところから始めてみるのがいいですね。
「両家から2つ届いた!」などの実例も
なかには、母方・父方の両方がそれぞれ気を利かせて、まったく同じタイミングで雛人形を用意してしまったというケースも実際にあるんです。
贈る側としては「何かしてあげたい」という純粋な気持ちからの行動なのですが、受け取る側としては、
「えっ、まさか2セット?」
「どっちを飾ればいいの…?」
と戸惑ってしまうことも。
さらにそれがサプライズだった場合。
「あちらのご両親も雛人形を用意してくれてるなんて知らなかった!」と驚きながらも、どう対応すればよいのか分からず、内心焦ってしまうなんてこともありますよね。
特に限られたスペースに2つの雛人形を飾るのが難しい場合は、なおさら気まずく感じてしまうものです。
こんな事態を避けるためにも、事前に「準備について確認しておこう」と一言相談しておくだけで、誤解や気まずさはかなり防げるはずです。
後から金銭トラブルに発展するケースもある
「こっちはこんなに出したのに」「あっちは何もしてくれなかった」など、初節句が終わった後に、思わぬ金銭的なトラブルが起こってしまうケースも少なくありません。
お祝いの場面で、あえて金額を口に出さないことが多い分、気づかぬうちに不満がたまってしまうこともあるんです。
たとえば、片方の祖父母が数十万円の立派な雛人形を購入したのに、もう一方がまったく関与していなかった場合、「なんでうちだけ…?」という気持ちになるのも無理はありません。
もちろん、お祝いに金額の多い少ないは本来問題ではありませんが、やはり「お互いの気持ちが見える」ような工夫が必要です。
そうならないためにも、雛人形の費用についてはあらかじめ「どういう形にする?」と話しておくのがベスト。
完全に折半にする場合でも、「気持ちとしていくらくらい出そうか」などの目安をすり合わせておくと、あとあと揉める心配がぐっと減りますよ。
もめずに確認するためのおすすめの伝え方
「じゃあ、誰が買うのかはっきり聞いちゃえばいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、言い方やタイミングを間違えると、かえって関係がこじれてしまうこともあります。
お祝いごとは「気持ち」で動いている部分が多いので、踏み込み方によっては相手にプレッシャーを与えたり、「あてにされている」と感じさせてしまうこともあるからです。
自然な形で確認するには、やっぱり相手が受け取りやすい雰囲気づくりが大切。
なるべく軽やかに、でもきちんと気持ちが伝わるような聞き方を工夫してみるといいですね。
妻から実家に「相談」の形で聞いてもらう
一般的には母方の実家が用意するケースが多いので、奥さんから自分の実家に「初節句ってどう準備したらいいの?」と相談してもらうのが自然な流れです。
ストレートに「買ってくれるの?」と聞くのではなく、「どうやって準備するものなのかな?」と、まずは教えてもらう姿勢で尋ねてみるのがポイントです。
そうすれば、相手の考えや地域の風習も聞けますし、その流れで「雛人形って、そちらで考えてるの?」と柔らかく確認できるようになります。
また、「自分たちもこういうのが気になっていて…」と候補を見せながら話せば、話題が前向きに広がって、スムーズに次のステップへ進めることが多いですよ。
さらに、こうした会話を通じて「買うつもりはなかったけど、一緒に見に行ってみようか」と話が膨らんでいくこともあります。
逆に「今は難しいから自分たちで選んでね」と正直に話してくれるケースもあります。
どちらにしても、角を立てずにスッキリと状況を把握できるという点で、この方法はとてもおすすめです。
「誰が買うか」ではなく「どう準備するか」を聞く
いきなり「雛人形はそっちで買ってくれるの?」と聞いてしまうと、相手に負担をかける印象になってしまうことがあります。
そんなときは、「うちの初節句って、どう準備したらいいのかな?」という聞き方に変えてみると、相手も構えずに受け入れやすくなりますよ。
こういった聞き方なら、相手に「買ってほしい」と直接言っているようには聞こえず、「一緒に考えたい」という前向きなニュアンスが伝わります。
加えて、「どんな流れでお祝いするのがいいのかな?」など、行事そのものへの関心を見せることで、自然と雛人形の話題にも入っていきやすくなるでしょう。
また、会話の中で「最近は両家で相談して決めることも多いみたいだよ」などと話を広げてみるのもおすすめです。
誰が買うかということに焦点を当てずに、あくまで「みんなでどう祝うか」という視点を大切にすると、気持ちよくやりとりできます。
写真撮影など“行事の相談”をきっかけに話すのも◎
初節句の記念写真の相談を口実にして、両家に集まってもらうのもおすすめの方法です。
たとえば「みんなで写真を撮りたいと思ってるんだけど、日程いつがいいかな?」と声をかけるところから始めてみましょう。
「せっかくだから、写真だけじゃなくて、雛人形も見に行ってみたいと思ってて…」というように、自然な流れで雛人形の話題に持っていくことができます。
実際に一緒に人形店やデパートに足を運ぶことになれば、どんな雛人形がいいかを相談しながら選ぶことができて。
贈る側にとっても「一緒に選んだ」という実感が得られるので満足度が高くなる傾向にあります。
また、そういった場をきっかけに
「うちはこれにしようかな」
「予算的にこれくらいで考えてるんだけどどう思う?」
といった形で、負担の分担や購入時期についても具体的に話し合えるようになります。
行事を通して家族の絆を深めるチャンスにもなりますし、ぜひ前向きに活用してみてくださいね。
こんな聞き方はNG!相手を不快にさせないために
確認すること自体はとても大切ですが、伝え方を間違えると相手に不快な思いをさせたり、余計な摩擦が生まれてしまうこともあるんです。
特に初節句のような家族イベントでは、「どのように伝えるか」が、雰囲気を左右する大きなカギになります。
相手との信頼関係を保ちつつ、前向きな話し合いに持ち込むには、言葉の選び方やタイミング、さらには話し方のトーンまで細かく気をつけたいところ。
ちょっとした一言でも、聞く側の受け取り方次第では「押しつけられた」と感じてしまうことがあるからです。
また、義実家との関係がまだ浅い場合などは、余計に緊張が走る場面でもあるので、失言を避けるためにも慎重に言葉を選びたいものです。
では、具体的にどんな言い方がNGなのか、特に注意したいポイントを見ていきましょう。
「常識でしょ?」という言い方は禁物
「女方の実家が買うのが当たり前だよね」
「それが常識でしょ」
といったような決めつけの表現は、たとえ事実であったとしても、言われた側にとっては強いプレッシャーになります。
家庭ごとに育ってきた背景や価値観が異なるので、自分の当たり前が相手の当たり前とは限りません。
こうした一方的な言い方は、相手に「押しつけられている」と感じさせてしまい、「じゃあ、そうしなきゃいけないの?」と不快感を与える原因になってしまうことも。
本来、お祝いごとは「気持ち」で動くもの。
相手の気持ちを尊重しながら「うちはこう聞いたことがあるけど、どうなんだろう?」といったように、やわらかく話題を振ってみることが、良好な関係を保つコツです。
男方の親が先に口出しするのは避ける
奥さんの実家がまだ何も言ってきていない段階で、旦那さん側。
つまり男方の実家が「ひな人形はどうするの?」と先に話を切り出してしまうと、思いのほか角が立ってしまうことがあります。
本来、ひな人形は「母方の実家から贈るもの」という風習がある地域も多です。
なので、その前提がある中で男方が先に意見を言ってしまうと、「うちが買うものなのに、どうしてそっちが先に決めようとしてるの?」と、相手に不快な印象を与えてしまう可能性があるんですね。
たとえ悪気がなくても、「向こうが用意する気がなさそうだから…」と心配しての発言だったとしても、こういったタイミングや順序を誤ると、相手のプライドを傷つけることにもつながりかねません。
なので、まずは奥さんからご実家にやんわりと相談してもらうのが、最も穏やかで自然なアプローチといえるでしょう。
プレッシャーをかけるような聞き方はトラブルのもと
「そろそろ買ってもらわないと困るんだけど」なんて、催促とも取れるような強い言い方をしてしまうと、せっかくのお祝いムードも一気に冷めてしまいます。
特に年配の方は「そんなに言われるなら、もういいわ」と気分を害してしまうこともあるので、言い方には十分な注意が必要です。
あくまで、相談という形を大切にして。
「雛人形って、どうしたらいいか一度話せたら安心なんだけど」といったように、協力をお願いするような柔らかい言葉に置き換えるだけで、相手の受け取り方はぐっと変わってきますよ。
また、「どんな雛人形がいいのか一緒に見に行けたら嬉しいな」など、楽しみを共有するニュアンスを含めると、会話のトーンも明るくなって、トラブルの火種を避けることができます。
雛人形の費用分担はどうする?最近の傾向と工夫
雛人形は決して安いものではありません。
高価なものだと数十万円を超えることもあり、なかなか気軽には手が出せない買い物です。
だからこそ、最近では家庭ごとにいろいろな工夫を凝らしながら、費用分担の方法を考えるケースが増えているんです。
特に共働き家庭や、両家ともにある程度距離のある関係性の場合などは、
「誰がいくら負担するのか」
「どのくらいの価格帯のものを選ぶのか」
といった点を、あらかじめ話し合っておくことがとても大切になります。
無理のない範囲で、気持ちよく用意できる方法を選ぶのが、後々のトラブル回避にもつながりますよ。
両家折半や小さめの人形を選ぶ家庭も
「高価な人形じゃなくても、気持ちが大事」と考えて、コンパクトな雛人形を両家で折半して購入するスタイルも人気です。
特に最近では、住宅の間取りや収納スペースの問題もあって、小さめで省スペースなデザインの雛人形を選ぶ家庭が増えています。
このタイプの人形は、飾る・片づけるといった手間も少なく、忙しい家庭にもぴったり。
見た目も華やかでおしゃれなものが多く、価格も数万円台から選べるので、両家で相談しながらちょうどいいものを選びやすいんです。
また、
「子どもが成長しても飾りやすいサイズ感」
「次のきょうだいにも使えるように」
といった実用性を重視して選ぶご家庭もあり、そうした観点から小さめの人形に注目が集まっています。
自分たちで選び、後から援助を受ける方法もある
「自分たちで気に入ったものを選びたい」というご夫婦は、先に購入してから、あとでご両親にお祝いとして金銭援助してもらうという形もありです。
スムーズに準備が進められますし、両家のバランスもとりやすいですよ。
「写真だけ」や「レンタル」という選択肢も視野に
どうしても予算やスペースの問題で雛人形の購入が難しい場合は、記念写真だけで済ませる、期間限定で飾れるレンタルサービスを利用する、という方法もあります。
無理なく楽しく初節句を祝うために、柔軟な選択肢を持つことも大切ですね。