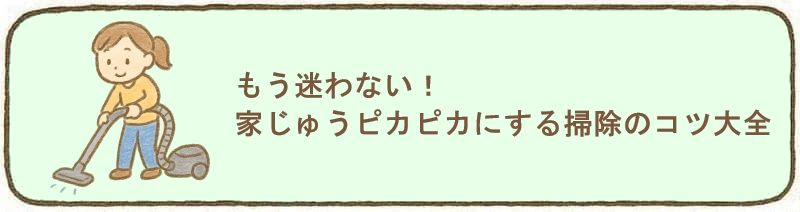「お墓参り」というと、春と秋の彼岸の7日間と盆というイメージがあって「年末になったから墓参りをしよう」と思われる方は、少ないのではないでしょうか。
年末には、家の大掃除は必ず行うという人は多いでしょうが、お墓の大掃除はどうされていますか?
「今まで、年末に墓掃除をされたことがない方」
「えっ、墓掃除するの~!と思われた方」
ここはひとつ、考え方を変えてみてはいかがでしょう。
年末年始といえば、普段なかなか会えない家族が集まれる、一年のうちでも貴重な時期でもありますよね。
その貴重な団欒(だんらん)の時間を、ちょっとだけご先祖様のためのお墓参りと、お墓の大掃除に当ててみるのもいいのではないのでしょうか?
年末には墓掃除をしないとダメなの?
年末に限らず、墓掃除は墓参りのときにしてあげると、ご先祖様も喜ばれますし、掃除をした私たちもすがすがしい気持ちになれますね!
ですが何かと忙しい年末です。「家の大掃除もまだまだ残っているのに、さらに墓掃除まで…」そんな声が聞こえてきそうですね
もしも年末が無理なら、年始にお参りするのも一手ですよ。
家族が集まったときに、みんなでワイワイ言いながら仲良く協力しあいながら墓掃除をすると、ご先祖様も安心されますよ。
「ひとりで墓掃除をするよりも、みんなですると早く終わることができて時短にもなるかも?」なんて事を思っても、罰当たりなんかじゃないですよね~。
墓参りにダメな日ってあるの?
墓参りにやお墓の大掃除をするにあたって、気をつけたほうがいい日にちがあるのでしょうか?
私が以前、お寺の住職さんから言われたのは「思ったときが吉日で、墓参りにダメな日はないですよ」ということです。
ですが「ついで参り」はよくないようですよ。
「●●に行ったついでに墓参りでも」といったように、何かのついでに墓参りをすることは、ご先祖様に対して失礼にあたるのでやめたほうが良さそうですね。
できれば墓参りや掃除を避けたほうがいい日
12月29日は「にじゅうく」と読めることから、不幸が重なるということで、できれば避けたほうがいいとされています。
12月31日は「一夜飾り」と言って「葬儀のときの祭壇」をイメージすることから、お参りを避ける風習のところもあるようです。
なので、年配者に聞いてみて、お墓のある地域の習わしがあれば、それに従っておくのが無難ですね。
基本、「何かのついでのお参り」でなければ、いつお参りしても大丈夫ですよ。
お墓の掃除の仕方 墓掃除で気をつけることは?
墓掃除というと「墓石に水をかけてゴシゴシ…」といったイメージでしょうか。
家の掃除の基本は「上から下に」ですから、やっぱりお墓の掃除も、まずは高いところからですよね?
でもちょっと待ってください!
お墓の掃除は足元からきれいにしていくべし
お墓の掃除をする場合には、まずは足元からきれいにしていきましょう。
なぜか?といいますと、お墓の周りには草が生えてはいませんか?
この草を最初に抜いておかないと、お墓の掃除をしているうちに、どんどん足元がベチャベチャにぬかるんで、草とりが大変になるからです。
抜いた草をゴミ袋に集めるときも、泥だらけの草や枯葉よりも、乾いたものの方が集めやすいですよね
墓石はゴシゴシこするばからず
墓石は、ゴシゴシとこすらずに、タオルで拭きましょう
墓石をたわしなどでゴシゴシこすると、墓石に傷がついてしまいます。
墓石って、意外とデリケートでやわらかいのです!石なのに…。
墓石が一度傷がついてしまうと、汚れが墓石の傷口から中にどんどん入り込むようになってきてしまいますよ。
そうすると、墓石の劣化が早くなってしまうんです。
なので、墓石に傷をつけないように。基本は、やわらかいタオルで拭くようにするのがおすすめです。
年末のお墓の大掃除についてのまとめ
年末のお墓参りと墓掃除について、お話ししてきました。
墓参りや墓掃除は、いつ行っても良いということですが、やっぱりご先祖様を思う気持ちが一番です。
今年の年末は、家族みんなが集まる機会に、みんなで協力しあってお墓の大掃除をしてみてはいかがですか?
ご先祖様あっての私たちですから、感謝の気持ちを忘れないようにする、いいきっかけにもなりますよ。