 冠婚葬祭
冠婚葬祭 初盆は家族だけで大丈夫?親戚への連絡・準備・お供え対応まで完全ガイド
初盆を家族だけで行いたい。そう思うことに、引け目や遠慮を感じる必要はありません。世の中の空気が大きく変わったこの数年で、人との付き合い方や行事の意味について、私たちの価値観も静かに変化してきました。以前は「みんなを呼んで盛大に」とするのが当...
 冠婚葬祭
冠婚葬祭 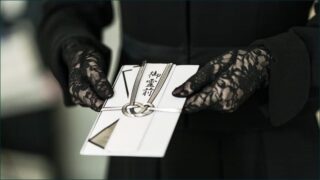 冠婚葬祭
冠婚葬祭 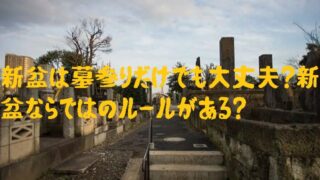 冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭 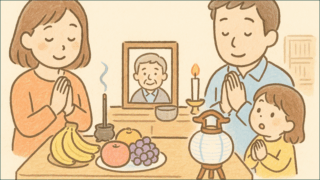 冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭  冠婚葬祭
冠婚葬祭