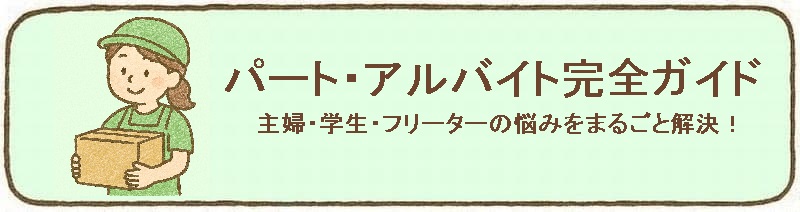パートとして働いてると、理不尽に感じることってありますよね。
その最たるものの一つが「仕事の内容」です。
社員に比べて、圧倒的に安い給料で働いていて、福利厚生だって全然違うのに。
それなのに、社員と全く同じような仕事をさせられたり、下手をすると社員以上の仕事量をさせられるような、そんな職場も少なくないですもんね。
では実際に「パートと正社員の仕事の違い」はないんでしょうか?
その答えは「正社員とパートに仕事の違いはない」ということになります。
そこでこの記事では
- そもそもパートと社員って仕事に違いがない理由は?
- 給料は安いのに社員並みの仕事をしてるのって理不尽?
パートと社員って仕事の違いはないって本当?その理由は?
一般的に、パートは社員よりも給料は安いし、福利厚生もちゃんとしてもらえていないことが多いですよね。
っていうか、社員よりも給料をたくさんもらってる「スーパーパート」なんて聞いたこともないし、そんな人がいるのかも定かじゃないですけど。
そんな風に、社員よりも低待遇で働いてるパートと、パートよりもいいお給料で福利厚生もちゃんとしてもらってる社員。
仕事内容って
「社員がやるべきこと」
「パートがやるべきこと」
みたいに、何か切り分け的なものってないんでしょうか?
パートと社員の違い!パートってそもそも何なの?
「安い給料で、社員と同じように働かされてる」ってついつい思っちゃうけど、そもそも”パート”って何なんでしょう?
このパートっていうのは、パートタイムを省略して呼んでるもので、「短時間労働者」のことを指します。
その会社で正規の労働時間として決められてる時間よりも、短い日数・時間で働く雇用形態のことなんですね。
逆に正社員は「フルタイム」で、会社で定められてる雇用時間通りに働かなくちゃいけません。
例えば正社員の所定の雇用時間が
「週5日、1日8時間」
だったとしたら、パートは
「週3日、1日5時間」
っていう感じです。
パートの場合は、働く日数や時間の調整がしやすいので、主婦や学生が普段の空いてる時間を有効活用して働くのにとっても適した雇用形態なんですよね。
パートと社員の違い!パートでも仕事は社員と同じことなのは普通なの?
パートっていうのは、あくまでも「働く日や時間」が、会社の規定通りでなくても、ある程度自由がききやすい働き方っていうことです。
なので実は
- パート契約だから、この仕事を
- この仕事は社員にやってもらうべき
なので、パートの場合は、仕事をする時間は社員の人より短くなるだけで、仕事内容は社員の人と同じであっても何か問題があったりする訳じゃないんですよね。
パートと社員の違い!パートなのに社員以上に仕事をしてるのってどうなの?
パートと社員に仕事の違いはないとは言っても、例えば
- 昼休み前に「〇〇さん、この仕事を急ぎでお願いしたいんだけど」って言われて、昼休み返上で仕事を頑張ってるのに、社員の人達は普通にお昼を食べに行ってたり
- 頼まれた仕事が多くってバタバタしてるのに、社員の人はしょっちゅうタバコを吸いに行ってなかなか帰ってこない
- 仕事内容も社員と同じようなことをさせられて、仕事量は社員の人以上にやってる。
- なのに、パートっていうだけで安い給料で働かされて、時給もなかなか上がらない。
パートと社員の違い!パートだってもっと大切にしてほしい!!
今の時代では、社員の人でもリストラがあったりして、決して安泰(あんたい)じゃないのはわかっているつもりです。
でも社員の人には
「パートはどうせ、いつか居なくなっちゃうんだから」
みたいな、
「せっかくお金を出してきてもらってるんだから、働いてもらわなきゃ損」
的な感じで、酷使しまくるのはどうなんでしょうね。
でもパートだって一人の人間です。
当然、感情だってありますよ。
忙しそうにアタフタしてるところに
「何か手伝えることがありますか?」
なんて言われたら、そりゃぁ嬉しいですよね。
急ぎの仕事を頼まれて何とか頑張って終わらせた後なんかに
「お疲れさま!ちょっと休憩してきてもいいよ^^」
のひと言でもあっていいんじゃないでしょうかね。
そんな風に私は思うわけですよ。
パートと社員の違いは責任の違いっていうのは本当なの?
社員とパートの違いという話になると、よく
「給料や福利厚生」
っていうのとは別に
「責任の違い」
っていう人がいますよね。
確かに、仕事でなにかトラブルがあった時に、最終的に責任をとるのは社員の人だったり、役付きの課長さんや部長さんだったりすることがありますよね。
まぁ役職がついてるような課長さんとか部長さんは、実際そういった「部下の尻ぬぐい」が仕事の1つでもあったりするんだろうけど。
でも、普通の社員の人たちって
「あんたは本当にそこまでちゃんと責任感持って仕事してる?」
って思わず突っ込みたくなる人もいないですか?
ちなみに私は、別に仕事をするときに「どうせパートだから」って思って、責任感もなく中途半端な仕事をしたりしていないですからね。
だからといって、じゃぁ何か私が失敗したりトラブった時に、一緒に働いてる一般社員の人が責任をとってくれるかっていうと、そんなこと今まで1度もなかったです。
なので、パートと社員の違いに何があるっていうときに
「仕事に対して責任があるかないかの違い」
って言われると、少しカチンときちゃう私がいます。
「おぃおぃ。それ違うんじゃない?」って喉まで出かかったことも何度もあります。
そんなとき、いまではネットでお仕事なんていうこともできる時代です。
こちらのクラウドワークスさんでは、パソコンやスマホでできるいろんなお仕事を募集しているので、覗いてみるだけでも
「何か自分にできそうなお仕事ないかなぁ」
「これなら私にもできそう」
なんてイメージしてみるだけでも楽しいですよ^^
![]() 「日本最大級のオンラインお仕事マッチングサイト!クラウドワークス」の詳しい情報を見てみる
「日本最大級のオンラインお仕事マッチングサイト!クラウドワークス」の詳しい情報を見てみる
![]()
フルパートと正社員の違いは何?
パートは「パートタイム=短時間労働者」ということはお話ししました。
パートの中には「フルパート」と呼ばれる働き方をしている人がおられるのをご存知でしょうか。
「パート」と「フルパート」の違いは、ずばり「勤務時間」です。
会社で決められている労働時間(例えば、“1週間あたり40時間”など)と同じだけ勤務することができるのが「フルパート」です。
そうでない場合が、一般的な「パート」です。
ということで、フルパートは正社員と同じように勤務するのですが、この違いは何かと言うと、「契約の違い」なんです。
端的に言うと、
- 正社員よりも給料が低かったり
- 福利厚生がなかったり
私はかつて銀行で正行員として働いていた経験があるのですが。
その当時一緒に勤めていたパートさんの中にも、週に3日程度出勤して夕方4時に仕事を終える「一般的なパートさん」・
そして、毎日出勤して夕方5時まで仕事をしている「フルパートさん」がいました。
私の経験からいくと、フルパートさんは毎日出勤するけど残業は基本的にゼロでした。
当時は勤めだして日が浅かったですが、そんな私の意識からも「残業をさせてしまってはいけない」と思っていました。
特に上司からそのように指示があったわけではありませんが、パートさんの対しては「時間になったのでもう上がってくださいね」と言うのが常でした。
パートと正社員の仕事内容に違いはないというのは前述しましたが、フルパートになると、ますます正社員との違いが薄れてきてしまいます。
雇用されている会社によって違うと思いますが、パートの強みである、
- 短時間労働である
- 責任が正社員より軽い(…はず)
なので、同じように働いているのに福利厚生もなくて、辛い思いをされることがあるかもしれません。
例えば、正社員に向けたステップとして、フルパートになっているのであれば良いですが。
そうでないので、あれば働き方を見直した方が良いかもしれませんね。
フルタイムパートっておかしい?!社員と比べると働き損って本当なの?
長い間、
- パート(非正規社員)や正社員などの雇用形態によって待遇が違う
- フルタイムパートは働き損なのでは
このような待遇差を禁じる「同一労働同一賃金」を定めた「働き方改革関連法案」というものが、実は2020年に大企業向けに施行されています。
そして、2021年4月には中小企業にも完全施行されました。
この「同一労働同一賃金」。
言葉をそのまま読むと「同じ仕事をしたら同じだけの給料がもらえるという法律かな?」と思ってしまいますが、実は少し違います。
フルタイムパート(=非正規社員)と正社員とはある程度の待遇差をつけることは認めつつも、「不合理な差」をつけることを禁じているのです。
待遇に差がある場合
- 会社に説明を求めることができたり
- 労働局が解決手続きを行ってくれたりする
この法律が完全施行されたとは言え、今は施行されて間がありませんし、企業の対応もまだ進んでいないのが現状だそうです。
「不合理な差」がある状態でのフルタイムパートは、正社員に比べると働き損のところがあるかもしれません。
もし、働き損だと感じることがあれば、それは前述した法律に則って会社に説明を求めたり、然るべき機関に訴えることも可能です。
ただ、この法律があるからこそ、「賃金を正社員と同じだけ払うので、正社員と同じ責任の仕事をしてほしい」と言われることもあるかもしれません。
そうなってくると、「パートとして気楽に働きたい」と思っている場合はプレッシャーですよね。
これは私の個人的な意見ですが、最終的に働き損だと感じるかどうかは、雇用されている会社や職場環境によって違うのではないかなと思います。
「パートであることをきちんと正社員が理解し、責任の重すぎる業務を外したり残業を絶対にさせない」などの環境が整っていれば、それは働き損には感じないかもしれません。
とにかく、理不尽に「働き損だ」と感じることがないようにする法律がある、ということは知っておいてくださいね。
フルタイムパートと正社員!いったいどちらが得なの?
「フルタイムパートと正社員のどちらが得か」と言われると、なかなか即答はできません。
得というのも、
- 賃金面の得
- 時間面の得
- 責任面の得
賃金面の得かどうかというのは、
「扶養の範囲内で働きたいのか」
「バリバリと働きたいのか」
というところで違ってきます。
ずっと扶養内で働けていても、週に1日出勤日を増やしてしまって扶養から外れてしまうと。
その結果、社会保険料や税金を払わないといけないことになり、結果的に収入が減ってしまうこともあります。
- あくまでも「パート」として扱ってもらえ
- 毎日勤務する必要があったとしても、残業が一切ない
これは時間的な得、と言えると思います。
そしてこれも、あくまでも「パート」としてきちんと扱ってもらえた場合ですが、「仕事を辞めるときも(言い方は悪いですが)後腐れなく辞めることが可能」ということがあります
この場合は「責任面の得」、かなと思います。
ご自身の収入面や生活スタイルによって、勤務時間を増やしても正社員ではなくあくまでも「パート」という立場を選ばれる人もいると思います。
雇用されている会社の実情を見て、どのような選択がベストなのかを探っていくことができれば良いですね。
パートに求めすぎ任せすぎな職場ってどうなの?職場を変えるべき?
パートといっても、仕事ができる人もいればできない人もいて本当に様々ですよね。
でも、これは正直なところ正社員でも同じだと思います。
企業側からしても、できる人に仕事を任せたい!と思うのは普通の考えです。
例えば、仕事ができるパートと仕事ができない正社員がいたら、どちらに仕事を頼みたいのか。
じっくりと考えてみると、なんとなく答えはみえてきてしまいますね。
だけど、パートで働いている人には、それぞれ様々な理由がありますよね。
主婦のパートであれば、旦那さんの扶養内で働きたいとか、家庭に重きを置きたいという方が多いです。
そのような方に、正社員と同じような仕事をさせるのは、あまり良くないと思います。
主婦のパートであれば残業はできないですし、そもそも残業をさせる前提というのはよくないですよね。
パートとなると勤務時間も正社員に比べると短いです。
それなのに正社員と同じ責任感のある仕事をさせようというのは賛成できません!
もし、パートに頼りすぎているという企業があるなら、どんな理由でも改善していってほしいですね。
そしてこれは、主婦のパートだけに言えることではないです。
もしかしたら、前職でいろいろとあったり、やむを得ない理由でパートを希望する人もいるかもしれません。
家庭の事情などもありますし、それは他人がどうこう言えることではないですよね。
パートという雇用形態を希望している場合は、それぞれ理由があります。
あくまでもパートという立ち位置でできる仕事を任せるのが理想的ですね。
もしも、パートなのに正社員と同じ働き方を強要されたり。
仕事内容が辛いとか残業を強いられるという場合は、職場を変えるのもありです。
職場環境について相談をしてみて、改善されないのであれば他を探しましょう!
パートと正社員の違いのまとめ
パートと社員、雇用形態の違いはあるけど、実際にやってる仕事に違いがない…っていうか。
パートの方が忙しいってどうなのよ?っていうことについて、ご紹介してきました。
同じように思っている人が、少しでも同感してくれると嬉しいです。
そして、あなたのこれからの働き方の参考にしてもらえると、嬉しく思います。