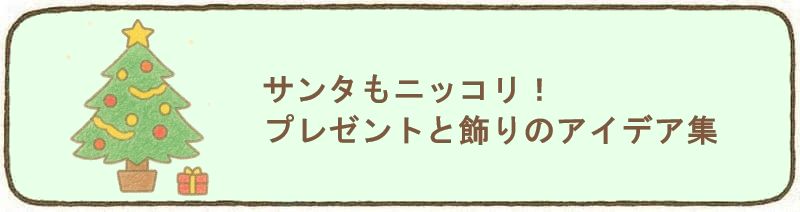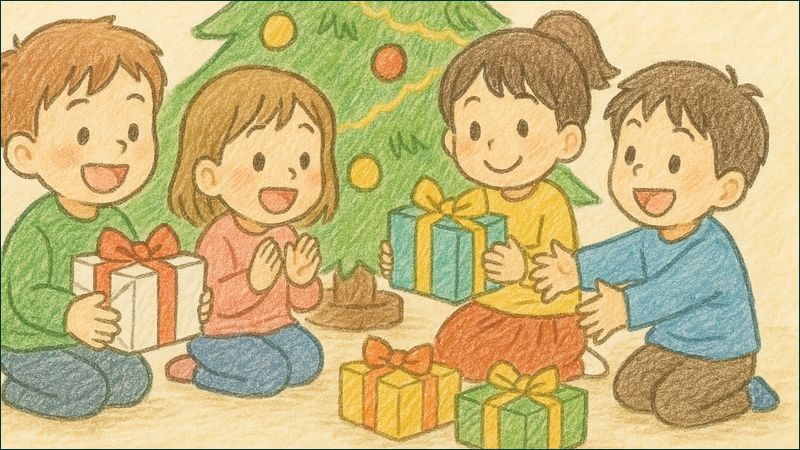
子どもが集まるクリスマス会で定番となっている「プレゼント交換」。
でも、ただ順番に渡すだけでは、あっという間に終わってしまって盛り上がらなかった…そんな経験はありませんか?
特に未就学児や小学生の子どもたちは、プレゼントをもらうこと自体が楽しみではあるものの、
「どれがもらえるかわからないワクワク」
「ゲームで勝ち取るドキドキ」
があることで、より一層イベントが思い出深いものになります。
この記事では、子どもたちが本当に楽しめる、ゲーム感覚で盛り上がるプレゼント交換のやり方をたっぷりご紹介します。
準備も簡単で、おうちでも実践しやすいアイデアばかりなので、保護者の方や主催者の方も安心して取り入れられますよ。
定番のくじ引きから、宝探し・風船ダーツなど、笑顔と歓声があふれる楽しい方法をまとめているので、「今年はもっと楽しくしたい!」という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
子どもとのクリスマス会で悩んだ「プレゼント交換、どうしよう?」
ただ渡すだけじゃ物足りない!
子どもが集まるクリスマス会といえば、やっぱり目玉はプレゼント交換ですよね。
でも、「ただ渡すだけじゃ味気ないな…」と感じたことはありませんか?
特に小さな子どもたちは、プレゼントを手渡しでもらったとしても、その時間が一瞬で終わってしまうと、あっという間に飽きてしまうこともあります。
実際に「えっ、もう終わり?」という声が聞こえてくると、主催する側としても少し物足りなさを感じてしまいますよね。
せっかくの楽しいイベントだからこそ、プレゼント交換もひと工夫あると、子どもたちの記憶に残る特別な時間になります。
ほんのちょっとゲーム性を加えるだけで、笑い声が増えたり、子どもたちがキラキラした目でプレゼントを待つようになったり、いつもより盛り上がった空気になるんです。
大がかりな準備をしなくても、簡単な道具やルールで十分楽しめます。
親としても「これなら自分でもできそう!」と思えるような工夫があると、取り入れやすいですよね。
子どもが飽きずに盛り上がる方法は?
盛り上げるコツは、“わかりやすいルール”と“ドキドキ感”の組み合わせです。
たとえば、勝負に勝った人が好きなプレゼントを選べるルールや、音楽に合わせてプレゼントを回していく方法など、シンプルなのに子どもたちが夢中になる要素がたくさんあります。
また、「何が出てくるかわからない」というワクワク感は、子どもたちにとっては最高のスパイス。
予想外の展開やちょっとしたサプライズがあるだけで、笑顔があふれる時間になりますよ。
次からは、そんなワクワク感たっぷりの定番スタイルや、ひと工夫でさらに盛り上がるアイデアをたっぷりご紹介していきます。
プレゼント交換の基本スタイルをおさらい
定番は「番号くじ」や「ランダム配布」
一番手軽でよく使われる方法といえば、くじで番号を引いて、その番号がついたプレゼントを受け取るというやり方です。
この方法なら、子どもたちが順番を守って受け取ることができるし、誰がどのプレゼントをもらうか最後まで分からないので、公平性もばっちりです。
何よりも、準備がとっても簡単なので、忙しい保護者や初めての主催でもすぐに取り入れやすいのが嬉しいですね。
ほかにも、プレゼントをテーブルの上に並べておいて、「順番に選んでいく」という方法もあります。
たとえば、あらかじめ番号札を配っておいて、その順番で選んでもらえばケンカにもなりにくく、スムーズに進行できます。
中には見た目から何が入っているのか予想して選ぶ子もいて、プレゼント選びの瞬間にもドキドキが詰まっています。
こうした方法は、参加人数が少なめな場合や、落ち着いて進めたいときにも向いています。
ちょっとした説明だけでできるので、年齢の低い子どもでも参加しやすいのもポイントですね。
でも子供にはもっと楽しい仕掛けを!
とはいえ、ただ番号を引いて終わり…というのは、ちょっと味気ないかもしれません。
特に元気いっぱいの子どもたちは、もっと体を動かしたり、想像したりするような“遊び”の要素があるほうが盛り上がるんです。
ゲーム感覚のプレゼント交換は、ただの贈り物を「イベント」に変えてくれます。
プレゼントをもらうまでの過程にワクワクや笑いが詰まっていると、それだけで会全体の雰囲気がぐっと明るくなりますよ。
次の章では、そんなドキドキ感や笑いを取り入れた、子どもたちに大人気の交換アイデアをたっぷりご紹介しますね。
子どもがワクワクする!ゲーム感覚のプレゼント交換アイデア
①じゃんけん大会で勝ち取るプレゼント
シンプルだけど毎回盛り上がるのが、じゃんけん大会を取り入れたプレゼント交換。
みんなで輪になって一斉にじゃんけんをして、勝ち残った子から順番にプレゼントを選んでいくスタイルです。
特別な準備はほとんど必要ないので、忙しいママやパパも当日その場で気軽に始められるのが魅力なんですよね。
しかも、じゃんけんというルールなら、小さな子どもでもすぐに理解できて公平に楽しめます。
「次は勝てるかな?」とドキドキする気持ちや、勝ったときのうれしさがプレゼントをもらう喜びと重なって、子どもたちのテンションも一気にアップします。
さらに、プレゼントの中身を事前に包装して見えないようにしておくと、「どれにしようかな?」という選ぶ時間もまた楽しい瞬間に。
ラッピングの大きさや形をじっくり観察しながら選ぶ姿も、見ていて微笑ましいものですよ。
②お部屋を使った宝探しゲーム
お部屋を使った宝探しゲームは、ちょっとした工夫でクリスマス会をアドベンチャーに変えてくれる遊びです。
とはいえ、実際にプレゼントそのものを隠すとなると、スペース的に難しいこともありますよね。
そんなときにおすすめなのが、「プレゼント番号が書かれた紙」を隠して探してもらうスタイルです。
紙を小さく折っておけば、家具のすき間やカーテンの裏など、いろんなところに隠すことができるので、広いスペースがなくても問題ありません。
さらに、いくつか「ダミー番号」や「ハズレ」の紙を混ぜておくと、子どもたちは「当たりを見つけたい!」と夢中になって探してくれます。
子どもたちが紙を見つけたときの「やったー!」という笑顔や、「これ違ったー!」という声も、会場を盛り上げる大事なエッセンスになります。
番号とプレゼントを結びつけておけば、公平さも保てて安心。
見つけた瞬間のワクワク感をプレゼントの開封まで引っ張れるので、イベントとしての満足感も高まりますよ。
③紐を引いて運試し!ひもくじゲーム
このひもくじゲームは、ちょっとした仕掛けで子どもたちのテンションをグンと上げてくれるアイデアです。
まず、すべてのプレゼントに長い紐を一本ずつ結びつけて、見えないように布や段ボールなどで隠しておきます。
プレゼントと紐の接続部分がわからないようにしておくのがポイントで、何がどこにつながっているのかを子どもが予測できない状態にすることで、ドキドキ感がアップします。
子どもたちは順番に好きな紐を1本選んで引っ張るだけですが、その瞬間にプレゼントがスルスルと姿を現すのがとっても楽しいんです。
「えーっ!これだったの!?」「やったー!」という歓声があがり、プレゼントが出てくるタイミングに会場が一気に盛り上がります。
このゲームの良さは、見た目以上に直感的で小さな子でもルールがすぐに理解できることと、ほとんど準備物がいらないことです。
紐がない場合は毛糸やリボンなどでも代用できますし、プレゼントが軽めなら紙袋でもOK。
紐を迷路のように絡ませたり、紐の数を増やしてダミーを入れてみたりと、アレンジの幅も広がります。
引っ張る前の真剣な表情と、引いたあとの笑顔が見られるこのゲーム。
ちょっとしたサプライズ感を加えたいときには、ぴったりの交換方法ですよ!
④目隠しで選ぶサンタ袋ゲーム
サンタ袋ゲームは、クリスマスらしい雰囲気を演出しながら、子どもたちにドキドキのプレゼント選びを体験してもらえる人気の方法です。
大きな袋や箱に全員分のプレゼントを入れて、順番に目隠しをした子どもが袋の中に手を入れ、手探りでひとつ選ぶというシンプルなルールです。
このときのポイントは「手の感触で選ぶ」というところ。
袋の中にはさまざまな形・大きさ・重さのプレゼントが入っているため、子どもたちは
「これ柔らかい!ぬいぐるみかも?」
「ちょっと軽いけど大丈夫かな?」
と、想像を巡らせながら選ぶのがとっても楽しいんです。
さらに盛り上がりをプラスしたい場合は、いくつかのダミー(空き箱やお菓子の空き袋など)を混ぜておくのもおすすめです。
「あれ?これは…何も入ってない?」というリアクションが出ることで、周りの子どもたちも大笑い。
選んだあとの開封タイムも一緒に楽しめる構成にしておくと、最後までワクワクが続きます。
袋の中が丸見えにならないように、布で口を縛ったり、手元だけ差し込める段ボールを使ったりすると、雰囲気も出て秘密感がアップします。
目隠しはバンダナやアイマスクなどでOK。
人数が多い場合は2袋用意して、左右に分かれて同時進行にするのも良いですね。
プレゼントの選び方にドキドキが詰まっているこのゲーム。
中身がわからないからこそ広がる子どもたちの想像力と、リアルな反応が会場の空気をさらに盛り上げてくれますよ!
⑤パーン!風船ダーツチャレンジ
風船の中にプレゼント番号が書かれた紙を入れて、それを的あてゲームのように割ってもらうこのアイデアは、視覚的にも音的にも盛り上がる楽しい方法です。
風船をカラフルに飾ったり、壁に貼り付けたり、箱に入れて積み重ねたりと、見た目のインパクトもばっちり。
風船を並べた時点で、子どもたちの目はキラキラ輝きはじめます。
割るときには、安全面に配慮して針ではなく、割りばしの先に粘土をつけた「安全ダーツ」を使うのもおすすめです。
的を狙って「パーン!」と風船が割れる瞬間には、会場中が一気に盛り上がります。
出てきた紙には、プレゼントの番号が書かれており、その番号のプレゼントをもらえるというルールにしておけば、子どもたちも納得して楽しめますよ。
風船の中に「当たり」や「ハズレ」の紙を入れると、ゲーム性がさらにアップします。
「再チャレンジ」や「友達と交代」などのミッションを書いておくのもおもしろく、会話や笑いが広がります。
また、風船をプレゼントの数より多めに用意しておくことで、外れ風船を作ることができ、よりドキドキ感を演出できます。
ちょっとした工夫で、プレゼント交換がアトラクションのように感じられるこの方法。
道具の準備さえできれば、大人数でも一気に盛り上がるので、子どもたちの思い出に残ること間違いなしです!
みんな一緒に楽しめるプレゼント交換方法もおすすめ
⑥音楽に合わせてプレゼントリレー
音楽を使ったプレゼントリレーは、シンプルだけどとっても盛り上がる定番の交換方法です。
やり方は簡単で、子どもたちが輪になって、自分が用意したプレゼントを持ちながら、音楽に合わせて隣の子にプレゼントをどんどん回していきます。
音楽が流れている間はテンポよくまわし続け、曲がピタッと止まったその瞬間、手元にあるプレゼントが自分のものになります。
この方法のいいところは、ゲーム性がありながらも全員が一斉に参加できる点。
体を使って動くので自然とリズムに乗れて、会場全体が一体感のある雰囲気になります。
また、曲のスピードや長さを工夫することで、ゲームの難易度や盛り上がり度合いも調整できますよ。
さらに、「音楽係」を保護者や少し年上の子どもが担当するなど、役割をつけることで子どもたちにとっても特別な体験になります。
途中で音楽のジャンルを変えたり、リズムに合わせてスピードアップしてみたりするのも楽しい演出です。
「このタイミングで止まったら誰のがくるかな?」とワクワクしながら見守る様子は、大人も一緒に楽しめる光景になります。
⑦ビンゴ形式でワクワクを共有
ビンゴゲームを取り入れたプレゼント交換も、根強い人気のある方法です。
あらかじめビンゴカードを配っておいて、数字が読み上げられるたびに「リーチ!」「ビンゴ!」と声が飛び交う場面は、子どもたちにとっても大きな楽しみ。
ビンゴになった順番で、好きなプレゼントを選べるルールにすると、ゲーム性もあって盛り上がります。
ただし、普通のビンゴだと時間がかかってしまいがちなので、工夫が必要です。
たとえば、すぐにビンゴしやすいようにマスを少なくした「ミニビンゴカード」を使ったり、列ではなく「3つそろえばOK!」など、独自のルールに変更するのもアリです。
また、あらかじめプレゼントに番号を振っておいて、ビンゴになった人がその番号を引いてプレゼントをもらう方法もおすすめ。
中身が見えないように包装しておけば、開けるまでのお楽しみ要素も加わって、最後までワクワクが続きます。
テンポよく進めるためには、数字を読み上げるスピードも重要。
リズムよく進行することで、子どもたちの集中力も切れずに楽しく参加できます。
ビンゴは遊び慣れている子どもも多いので、ルールがすぐに伝わるのも安心ポイントですね。
やってみたら微妙だった?避けたい交換方法とその理由
時間がかかる方法はNGになりがち
ビンゴやボードゲームなど、勝敗が決まるまでに時間がかかるものは、子どもたちが飽きてしまうこともあります。
特に小さな子どもは、じっと座って待つ時間が長くなると集中力が途切れやすく、ゲームそのものに対する興味がなくなってしまうこともあるんですね。
また、「いつ順番が回ってくるの?」「まだ終わらないの?」といった声が出始めると、せっかくの楽しいイベントが少しずつトーンダウンしてしまうことも。
だからこそ、テンポよく進められる仕掛けを事前に考えておくのがポイントです。
たとえば、全員同時に参加できるタイプのゲームや、時間制限のある簡単なクイズ、すぐに結果が出るじゃんけん方式などは、短時間でも盛り上がるのでおすすめです。
途中で集中力が切れそうなときは、手遊びやダンスなどを挟むと気分転換にもなります。
また、司会進行を担当する大人がテンポよく、かつ楽しく声がけをすることで、雰囲気を保ちやすくなります。
子どもが主役のイベントでは「待たせすぎない」「飽きさせない」が大事なキーワードになりますよ。
プレゼント選びで子どものテンションが変わる?
見た目で「当たり」「ハズレ」がはっきりわかってしまうと、もらったときの喜びに差が出てしまい。
せっかくの楽しいプレゼント交換がちょっとした残念な気持ちで終わってしまうこともあります。
特に子どもは正直なので、「あっちの方がよかった~!」と無意識に言ってしまうことも。
そうなると、せっかく準備した保護者や贈った側もなんだか気まずくなってしまいますよね。
そうしたトラブルを避けるためにも、事前のプレゼント選びには少し気を配るのがおすすめです。
たとえば、参加者から少額の会費を集めて、代表の保護者が中身のバランスを考えて一括購入する方法があります。
こうすると、プレゼントの見た目や価格に大きな差が出にくく、子ども同士の不公平感も防げます。
また、男女どちらでも使いやすいキャラクターグッズや、誰でも楽しめる文房具、パズルやシールなどの定番アイテムは万能です。
さらに、プレゼントを同じ大きさの袋や箱に入れて、中身が見えないように統一するだけでも、当たりはずれの印象を和らげることができます。
ちょっとした心配りで、プレゼント交換が「楽しかった!」という印象で終われるようになりますよ。
子どもが喜ぶプレゼント交換のコツまとめ
ルールはシンプル&スピーディーに
子どもにとって大切なのは、分かりやすくてテンポのいい進行です。
複雑な説明が必要なルールよりも、見たまま・感じたままにすぐ動けるような直感的な遊びの方が、ぐっと引き込まれて楽しんでくれます。
たとえば、「音楽が止まったらプレゼントを持っている人がもらえる」や「じゃんけんで勝ったら順番を決められる」など、説明が数秒で終わる内容なら安心して始められます。
ゲームの開始からプレゼントをもらうまでの流れも、なるべくスムーズに進行できると子どもたちの集中力も続きやすいですよね。
途中で戸惑うことがないように、ゲームを始める前には簡単なデモンストレーションをしたり、大人が1人ついて進行を補助したりするとより安心です。
テンポよく進めることで、子どもたちの「もう一回やりたい!」という声も増えて、プレゼント交換が思い出深い時間になります。
プレゼント内容にも気を配ろう
プレゼント交換の場面では、交換したあとでその場ですぐに開封するというケースがとても多いです。
だからこそ、中身の選び方にはちょっとした気配りが大切です。
たとえば、誰がもらっても嬉しくなるような文房具やシール、キャラクターグッズ、お菓子セットなど、年齢や性別を問わず楽しめるアイテムを選ぶのがポイントです。
プレゼントに偏りがあると、「これがいい!」「あれが当たりだ!」という空気が生まれてしまい、もらった子のテンションにも影響します。
もし可能であれば、予算やジャンルを事前に話し合っておいたり、会費制にして中身のバランスを調整できるようにすると安心ですね。
子どもたちがニコニコしながら開ける姿を見られたら、準備した大人としても大満足です!
みんなが笑顔になる仕掛けを意識しよう
ちょっとしたゲーム性やドキドキ感があるだけで、プレゼント交換は一気に特別なイベントになります。
たとえば、「どれがもらえるか分からない」ドキドキ感や、「くじ引きやゲームで勝って選べる」ワクワク感を取り入れると、子どもたちのテンションも自然と上がります。
また、全員が主役になれるような進行方法にすると、「みんなで楽しめた!」という気持ちが残ります。
順位や勝敗がはっきりしすぎないゲームにしたり、ちょっとしたおまけ景品を用意しておいて“参加賞”として配るのもおすすめです。
ゲームの流れの中で自然と笑いが生まれたり、「なにが当たるかな?」というワクワクを感じられたら、それだけでプレゼント交換は大成功。
子どもたちの「また来年もやりたい!」という一言が、その日の思い出を最高のものにしてくれますよ。