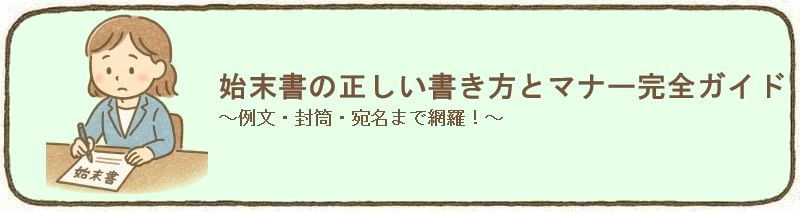「まさか自分が始末書を書くことになるなんて」
そう感じたあの日の私は、手の震えが止まらず、心臓がバクバクしていました。
頭では反省していても、いざ文字にしようとすると、何を書けばいいのかまるで分からなくなってしまって。
「正直に書いたら怒られる?でも嘘を書いても見抜かれる?」そんな不安でいっぱいでした。
でも、だからこそ伝えたいんです。
始末書を書くことは、怒られるためじゃなくて、ちゃんと反省して、これからをどう変えていくかを自分の言葉で伝えるための機会なんだってこと。
始末書には、会社ごとのルールがあったり、決まった様式があったりもします。
だからまずは、提出前に上司や人事に確認をとることも忘れないでほしい。
この記事では、無断欠勤や遅刻など、どうしても書かざるを得ないときに、どんなふうに始末書を書けばよいか、気をつけるべきポイントや例文を交えて丁寧に解説しています。
書き方に迷っているあなたが、少しでも安心して一歩を踏み出せるように、心を込めてお届けします。
どうか、責めすぎないでください。
大丈夫、立て直すチャンスはここから始まります。
始末書と顛末書の違い、ちゃんとわかってる?
正直に言うと、私も最初は違いなんて気にしたことすらありませんでした。
「何かあったら反省文みたいなの書くんでしょ?」くらいの感覚でいたんです。
でもある日、上司にこう言われました。
「今回のは顛末書じゃなくて始末書ね」って。
そのとき私は思わず「え?なにが違うんですか?」って聞き返してしまったんですよね。
実はこのふたつ、似ているようで大きな違いがあるんです。
そしてその違いを知らずに書いてしまうと、相手の受け取り方も大きく変わってしまいます。
顛末書は「事実の報告」、始末書は「謝罪と反省」
顛末書というのは、問題が発生したときに
- 「何が起きたのか」
- 「なぜ起きたのか」
- 「これからどうするか」
つまり顛末書は、ミスやトラブルが「どうやって発生したのか」を冷静に説明するための報告書なんですね。
一方で、始末書はもっと個人の責任にフォーカスが当たります。
自分がしたことに対して
- どれだけ反省しているか
- どう謝罪するか
- 再発防止策をどう考えているか
たとえば、会社でシステムトラブルが起きたとします。
その原因が外部委託先の操作ミスで、あなたが直接の当事者でないなら顛末書で足ります。
でも、あなた自身がそのミスの当事者だったり、無断欠勤や遅刻など明らかなルール違反をしてしまったときには、始末書が必要になります。
始末書は「懲戒処分」にも関係する文書
ちょっと怖い話に聞こえるかもしれませんが、始末書というのは会社によっては人事評価や懲戒処分の判断材料になることもあります。
だからこそ、言葉を選ぶ必要があるし、事実をねじ曲げたり適当に書くことは絶対に避けなければなりません。
特にYMYLに配慮する観点からも、「これを書けば処分されない」「この通りに書けば評価が下がらない」といった断定的な表現は避けたほうが良いです。
あくまで始末書は「反省の気持ちを自分の言葉で伝えるもの」であり、処分の有無や軽重を決めるのは会社側の判断に委ねられています。
でもだからこそ、ちゃんと誠意を込めて書いたものは、少なからず相手の心に届きます。
評価や処分のことばかりにとらわれるよりも、自分自身のこれからの信頼をどう取り戻していくか、そこに気持ちを向けて書いていくことが大切なんだと私は思います。
「どっちを書けばいいかわからない」ときはどうする?
始末書なのか顛末書なのか、自分で判断がつかないときってありますよね。
私も過去に「これは謝罪も含めたほうがいいのかな……?」って悩んだことがあります。
そんなときは、迷わず上司や人事担当に確認するのが一番です。
独断で書いてしまって、あとから「これは違うよ」と突き返されるよりも、事前に方向性を確認しておくほうがスムーズです。
ちなみに私がそうやって相談したとき、上司は「始末書でお願いね。
ただ、そんなに堅苦しくならなくていいから、ちゃんと反省してる気持ちが伝われば大丈夫だよ」と言ってくれました。
あの言葉に、どれだけ救われたことか……。
形式よりも大切なのは「誠実さ」
始末書を書くときに意識してほしいのは、形式の整った美しい文章よりも、「本当に申し訳なかった」という気持ちが相手に伝わることです。
ビジネスマナーとしての基本は押さえつつも、表面的な言葉より、自分の中の“悔しさ”や“情けなさ”をきちんと自覚して書く。
それこそが、あなたの信頼を取り戻す第一歩になるんです。
会社に遅刻したとき、どこまで書く?どう書く?
「たった一度の寝坊で、始末書……?」
そんなふうに思ってしまったこと、ありませんか?私もあります。
前の日に少し夜更かししただけのつもりだったのに、アラームを止めた記憶すらなくて。
目が覚めたら始業時間を過ぎていて、心臓が一気に冷たくなるような、あの感覚。
「どうしよう」って、何度も時計を見ながら呆然としました。
でも現実は待ってくれないんですよね。
会社ではあなたの到着を待ってくれている人がいて、スケジュールが動いていて、そしてあなたがそこに“いなかった”という事実だけが残る。
その結果が始末書の提出、ということもあるのです。
言い訳じゃなく、事実と誠意を書く
遅刻の理由がたとえ正当だったとしても、始末書は言い訳を書く場ではありません。
これが一番つらいところかもしれませんが、「自分の気持ち」と「相手の目線」は、必ずしも一致しないんですよね。
「体調が悪かった」
「前日帰宅が遅くなった」
「どうしても子どもが泣き止まなくて」
私たちには、それぞれの事情があるし、どれも本当につらかった。
でも始末書で必要なのは、“その出来事がなぜ起きたのか”という事実と、
“それに対してどのように責任を感じ、どんな対策をとるか”という誠意なんです。
始末書に書くべき基本の要素とは?
遅刻に関する始末書を書くときに、基本として押さえておきたいのは以下の4点です。
- 遅刻した日付と時間、具体的な内容(例:9時始業に対して9時40分に出社)
- 遅刻の原因となった事情や背景
- 遅刻により発生した影響と、それに対する謝罪の言葉
- 今後、同じことを繰り返さないための改善策や決意表明
でも大丈夫。
この4つのポイントを
- 事実を包み隠さず伝える
- 心から謝る
- もう二度と繰り返さないと誓う
「謝罪」の重みを、あなどらないで
私は以前、謝罪文に「申し訳ございませんでした」と形式的に書いたことがあります。
でもそのときの上司の言葉が今でも忘れられません。
「謝るって、こんなに軽くていいの?」
その一言が胸に刺さって、自分がどれだけ“カタチだけ”で書いていたかを思い知らされたんです。
謝罪の言葉は、ただ並べればいいものじゃない。
そこにちゃんと“気持ち”がこもっているかどうか。
それは読む人に必ず伝わってしまうんだと、身をもって学びました。
「何度目か」の遅刻なら、書き方にも注意を
一度きりの遅刻で始末書、というのはそこまで多くはありません。
多くの場合は、
- 繰り返し遅刻している
- 重要な会議に遅れた
- 上司の指導後にまたやってしまった
このときに大事なのは、「前回と同じことを繰り返してしまった」という事実とどう向き合うかです。
「気をつけます」だけでは足りません。
具体的にどう生活リズムを見直すか、どう環境を変えるか、自分自身で立てたルールや工夫を言葉にして伝えることが大切です。
提出はすばやく、誠実に
そして、書き終えた始末書はできるだけ早く提出しましょう。
「何を書けばいいか悩んでいた」と後回しにしてしまうと、謝罪のタイミングを逃してしまいます。
理想としては、当日中、遅くとも翌日、難しくても3日以内が目安です。
「すみません、まだ気持ちの整理がつかなくて」
その気持ちもすごく分かります。
でも、誠実に伝えようとする姿勢があれば、完璧でなくても大丈夫です。
テンプレより、自分の言葉で
ネットにはいろんなテンプレートがありますし、「コピペで済ませたい」という気持ちになるのも無理はありません。
でも、読んでいるのはあなたの上司であり、同じ職場で顔を合わせる人です。
だからこそ、「あなた自身の言葉」で綴ることが、なによりの誠意になるんです。
完璧な文章じゃなくてもいい。
少し拙くてもいい。
自分の心で書いた言葉は、ちゃんと相手の心に届きます。
失敗しない始末書の書き方!遅刻をしてしまった時の例文一覧!
「例文を見たら、すぐ書けると思ってたのに、ペンが全然進まない」
私はそんなふうに、始末書の前で何度も手を止めました。
言葉にしようとするたびに、心の中にある申し訳なさや悔しさがこみあげてきて、
それを“適切な表現”にするって、想像以上にむずかしかったんです。
だからこそ、例文は大きな助けになります。
でも、ただ“当てはめて終わり”ではなくて、あくまでベースとして使うことが大切です。
自分自身の言葉を足して、気持ちを込めて、世界にひとつだけの始末書に仕上げてくださいね。
例文①:繰り返し遅刻してしまった場合
自己管理が行き届かず、社会人としての自覚に欠けた行動だったと深く反省しております。
本来、周囲に良い影響を与えるべき立場でありながら、むしろ現場の士気を下げてしまったことを重く受け止めています。
今後は生活習慣を見直し、体調管理と時間管理により一層の注意を払うことで、信頼の回復に努めてまいります。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
このように、繰り返し遅刻してしまった場合は「一度の不注意」では済まされません。
「なぜ改善できなかったのか」を自分なりに分析し、どこをどう変えるかを具体的に書くことが大切です。
上司が知りたいのは、あなたが本当に変わろうとしているかどうか、ただそれだけなんです。
例文②:飲みすぎて遅刻・欠勤してしまった場合
社会人としてあるまじき行動だったと痛感しており、深く反省しております。
連絡もできず、皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。
今後は酒量を控え、常に体調を万全に保てるよう努め、二度と同じ過ちを繰り返さぬよう徹底してまいります。
このタイプのミスは、とくに信頼を大きく損なってしまうことがあります。
だからこそ、「甘かった自分」と真剣に向き合う覚悟を文章ににじませてください。
飲みすぎたことそのものよりも、「責任ある行動ができなかったこと」に謝る必要があります。
例文③:一度注意されたのに再び遅刻した場合
自分自身の認識の甘さ、反省の浅さを痛感しております。
指導してくださった上司の信頼を裏切る形になり、本当に申し訳なく思っております。
今後は生活の見直しだけでなく、再発防止策をノートに記録しながら意識的に行動を変えてまいります。
同じことを繰り返さぬよう、自分を律し、職務に対して誠実に向き合う所存です。
過去に一度でも指導を受けたことがあるなら、それ以降は“猶予期間”ではありません。
「それでもまたやってしまった」ときには、前回よりも踏み込んだ反省と対策が求められます。
嘘や取り繕いは必要ありません。
その代わり、心の底からの謝罪と、今後の“本気”を見せていきましょう。
例文④:連絡できなかった体調不良のケース
回復後も謝罪のタイミングを逃してしまい、連絡が遅れたことを心よりお詫び申し上げます。
結果として皆さまに不安とご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。
今後は緊急連絡体制を整え、体調が悪くとも必ず何らかの方法で連絡を取れるよう事前に準備してまいります。
体調不良は誰にでも起こり得ます。
でも「連絡ができなかった」「その後も何も言わなかった」という事実は、信頼を大きく揺るがすものになります。
こういうときこそ、「誠意」と「対応力」が問われるんです。
体調不良は仕方ない。
でも連絡や報告の仕方は、自分の判断で変えられます。
例文は“道しるべ”、あなたの言葉がいちばん強い
ここで紹介した例文は、あくまでも“道しるべ”です。
テンプレートのとおりに書いて終わりではなくて、そこにあなたの気持ちを添えることが何よりも大切です。
「この文のように書けば許してもらえるかな」じゃなくて、「この文に、今の私の想いを込めて伝えよう」と思ってもらえたら、それだけで素敵な始末書になります。
誠実に、丁寧に、自分と向き合いながら。
そうして書いた言葉は、きっと相手にも届きます。
まとめ
始末書を書くという経験は、多くの人にとって心が折れそうになる出来事かもしれません。
私自身、机の前で何度も深呼吸を繰り返しながら、反省の言葉をどう綴ればいいのか分からずに悩んだことがあります。
でもそんなとき、ふと思ったんです。
「これは自分の失敗を清算するための罰ではなく、もう一度信頼を取り戻すための機会なのかもしれない」って。
確かに、遅刻や無断欠勤は社会人として許されない行動です。
けれど、大切なのは“過ちをどう受け止めて、どう変わっていくのか”。
その姿勢こそが、職場での評価を決めていく本当の鍵になります。
始末書を書くときは、ただ形だけを整えるのではなく、自分の中にある悔しさや反省の気持ちを、言葉にして届けるつもりで書いてみてください。
たとえ不器用でも、誠実な言葉には必ず力があります。
そして書き終えたとき、少しでも気持ちが前を向いているなら、それが何よりの回復への一歩です。
大丈夫、ちゃんと向き合おうとしているあなたの姿勢は、きっと伝わります。