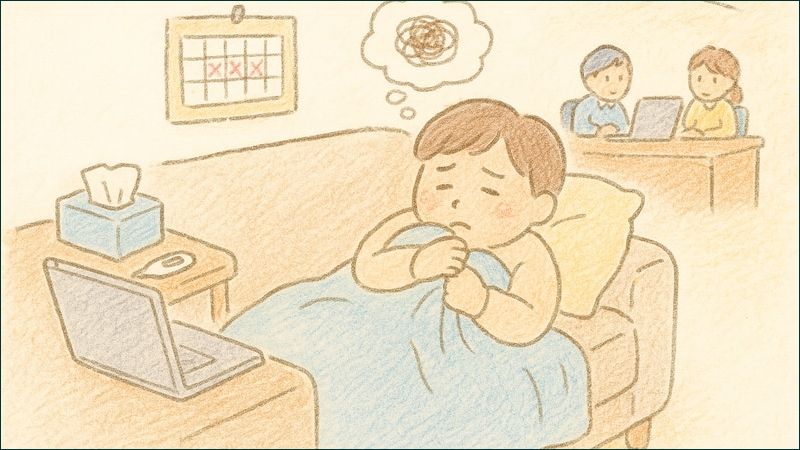
突然の病気やケガで会社を休まなければならなくなったとき、ふと頭に浮かぶのが「病気休暇制度」ではないでしょうか。
日ごろ元気に働いているとあまり意識しないかもしれませんが、いざというときに会社を休める制度があると心強いですよね。
実際、私も体調を崩して仕事を休まざるを得なかった経験があり、そのときに病気休暇制度のありがたみを身にしみて感じました。
でも正直なところ、制度があるとはいえ、実際に使ってみると「想像していたよりもずっと大変だったな…」というのが本音です。
たとえば、思っていたほど給料がもらえなかったり、復職後に職場でなんとなく気まずさを感じたり、仕事の遅れを取り戻すプレッシャーがあったり。
さらには同僚に負担をかけたことへの申し訳なさや、自分の評価への不安もあって、心の面でもなかなかしんどかったです。
病気休暇は、一見すると「安心して休める便利な制度」のように思われがちですが、実際にはその裏にいろんな現実や課題も隠れています。
働く側にも、制度を整える企業側にも、それぞれにとっての負担や悩みがあるからこそ、あらかじめそうしたデメリットについて知っておくことはとっても大切なんです。
この記事では、病気休暇制度の基本的な仕組みから始まり、実際に使ったときに感じる不便さや困りごと、企業側の立場から見た課題、そして万が一のときに備えて何を確認しておくといいのかなど、できるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
病気休暇の基本制度とは?法定外休暇の仕組み
そもそも病気休暇ってどんな制度?
病気やケガで働けなくなったときに、会社を休んでしっかり治療に専念できるのが「病気休暇」という制度です。
突然体調を崩して仕事に行けなくなったとき、この制度があるかないかで精神的な安心感がまるで違ってきます。
出勤しなくてもいい期間が設けられていることで、無理せずに心と体を休めることができるのは大きなメリットですよね。
体調が万全でない状態で無理して働き続けるより、しっかりと静養した方が長い目で見てもプラスになると実感しています。
実際、私の知人もインフルエンザで1週間ほど寝込んでいたときにこの制度に助けられたと言っていました。
その間、職場に迷惑はかけたものの「制度があったから安心して休めた」と言っていたのが印象に残っています。
病気休暇は法定外休暇!会社ごとにルールが違う
この病気休暇制度、なんとなく法律で決められているもののように思われがちですが、実はそうではないんです。
法律で取得が義務付けられている「法定休暇」とは違って、病気休暇は会社が自主的に用意している「法定外休暇」にあたります。
だからこそ、制度の内容や適用の条件は、会社ごとにかなり差があるんですね。
たとえば、ある会社では病気休暇の間も一部給料が支払われるところもあれば、別の会社ではまったく無給になるケースもあります。
また、何日まで取得できるのか、何回まで取得可能かなどの細かい規定もそれぞれ違っていて、実際に使う前に就業規則などを確認しておかないと「こんなはずじゃなかった…」ということになりかねません。
公務員と民間での違いも要チェック
公務員と民間企業の間でも、この病気休暇制度には大きな違いがあります。
公務員の場合は制度としてきちんと整備されていて、たとえば90日間の病気休暇を取得したあと、さらに「病気休職」という形で最長3年まで休むことができるケースもあります。
そのうち一定期間は給料の8割が支給されたりと、手厚い保障が受けられるんですね。
一方で民間企業では、病気休暇の制度がそもそもなかったり、有給休暇でまかなうように求められることもあります。
仮に病気休暇があったとしても、日数が短かったり、給料がまったく出ないこともあるので、公務員に比べるとどうしても制度面では差が出てしまうのが現状です。
このように、病気休暇は企業ごとに大きく異なるうえ、公務員か民間かでも待遇に大きな違いがあります。
だからこそ、自分の職場の制度をしっかり確認しておくことがとても大切なんです。
病気休暇の個人側デメリットとは?
給料が出ない場合がある
私自身、急な入院で1ヶ月間病気休暇を取ったことがあるんですが、その月の給料はゼロでした。
普段はあまり気にしていなかった通帳の残高を見て、急に現実に引き戻されたというか、言葉にならない焦りを感じたのを今でも覚えています。
「えっ、これで家賃も払えるかな…」と不安になってしまって、すぐに家計簿を見直したほどです。
たとえ制度があっても、会社によっては病気休暇中の給与が支給されないケースがあるんですね。
もちろん有給休暇が残っていれば充てることもできたかもしれませんが、私の場合はすでにほとんど使い切っていたので、完全に無給状態でした。
それに加えて、傷病手当金の申請もしたんですが、実際に振り込まれるまでに少し時間がかかってしまって、その間の生活費のやりくりにかなり苦労しました。
毎月の収入が当たり前だと思っていた自分にとっては、とても大きな気づきになった出来事でした。
復職後の負担が大きいケースも
休んでいた間の仕事がたまっていて、復帰後はその対応に追われました。
職場に戻ったその日から、デスクの上には山積みの書類、パソコンには未読メールが何十件も。
まさに「待ってました!」と言わんばかりの仕事の山に、正直ちょっとめまいがしました。
それでも「休ませてもらった分、頑張らなきゃ」という気持ちもあって、つい無理をしてしまったんですよね。
体はまだ本調子ではなかったのに、毎日遅くまで残業したり、土日に自宅で片づけたりと、リズムを取り戻すのにかなり時間がかかりました。
しかも、仕事をお願いしていた同僚たちにも申し訳なくて、なるべく自分で何でも片付けようと気を張っていたら、今度は精神的にもしんどくなってしまって。
病気から復帰したはずなのに、また別の疲れがたまっていくような感覚でした。
「病気休暇が終われば元通り」とはなかなかいかないのが現実なんだなと実感しましたし、だからこそ、復職後のケアや周囲の理解って本当に大事なんだなと改めて感じました。
ボーナス査定に響く可能性あり
ボーナスの査定期間に重なると、出勤日数が少なくなってしまって、その分評価に影響が出ることがあります。
実際、私の会社では「査定期間中に所定日数以上出勤していないと満額は出さない」という明確なルールがありました。
私は1ヶ月間の病気休暇を取ったことで出勤日数がギリギリになってしまい、結果的に支給額が減らされてしまいました。
それまで頑張ってきたことや、休んだのがやむを得ない事情であることは理解されていても、制度上どうしようもないということもあるんですね。
「あれだけ頑張ったのに…」とちょっと切ない気持ちになったのを覚えています。
だからこそ、自分がどの時期にどれくらい出勤しているか、あらかじめ把握しておくのも大事だと感じました。
「周囲に申し訳ない」気持ちの負担
仕事を代わってくれた同僚に対して、感謝の気持ちと申し訳なさの両方が押し寄せてきました。
特に忙しい時期に入院してしまったので、「あの人たち、本当に大変だっただろうな…」と気になって仕方がありませんでした。
復帰したときは、みんな温かく迎えてくれましたが、それでも「本当にごめんね」という思いが拭えなくて、お礼の意味も込めて菓子折りを持参しました。
「気にしないで」と笑ってくれた同僚の言葉に、ホッとしたと同時に、もっと感謝を伝えなきゃな…と心から思いました。
病気休暇って、自分の身体を休める時間でもあるけれど、実は心の葛藤も少なくないなと感じましたね。
企業側のデメリットや負担とは?
他の社員へのしわ寄せが発生する
誰かが病気休暇に入ると、その分の業務を他のメンバーでカバーしなければならなくなるため、どうしても周囲の社員の負担が増えてしまいます。
特に、少人数の職場や繁忙期の場合は、ひとり抜けるだけでも業務の流れに大きな影響が出ることがあるんですよね。
自分の仕事をこなしながら、さらに休んだ人の分まで引き受けることになると、心身ともにかなりのストレスを感じる人も多いです。
また、急な休みによってスケジュールが狂ってしまい、納期の調整やお客様への対応にも影響が出ることもあります。
これが連鎖的に他の部署にまで波及するケースもあるので、全体の業務効率に悪影響が出てしまうことも少なくありません。
人員補充や業務調整のコスト
人手が足りない状態が長引くと、企業側としてはどうにかして穴を埋めなければならなくなります。
たとえば、派遣スタッフやアルバイトを急きょ雇うとなると、採用コストや教育コストが発生しますし、短期間で即戦力として機能してもらうのも簡単なことではありません。
さらに、既存のスタッフのシフトを変更したり、他部署から応援を呼んだりといった調整も必要になるので、管理職や人事担当者の負担も増してしまいます。
業務内容を見直したり優先順位を変える必要があることもあり、会社全体としての生産性が一時的に落ちるリスクもあるんです。
制度設計にコストと手間がかかる
病気休暇制度を導入・維持していくためには、それなりに手間もコストもかかります。
まずは就業規則や労務関係のルールを見直す必要があり、法務や人事部門が細かい制度設計を行わなければなりません。
また、社員への周知や研修、必要に応じた相談窓口の整備など、実際に運用するための準備も欠かせません。
制度があるだけでは意味がなく、実際に社員が使いやすいように整備していく必要があるんですね。
こうした背景から、病気休暇制度は企業にとってもメリットだけではなく、運営側としての努力やコストが求められるものなんです。
給与が出ないときは?傷病手当金を活用しよう
傷病手当金とは?条件と申請の流れ
病気休暇中に給料が出ない場合は、「傷病手当金」を申請することで収入をある程度カバーすることができます。
これは健康保険に加入している人が対象の制度で、働けない間の生活を少しでも安定させるために用意されているんですね。
実際、私も病気休暇を取って給料が出なかったときにこの制度の存在を知り、助けられた経験があります。
傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、会社からの給与が出ない場合でも、一定額が支給されるという安心感はとても大きかったです。
制度の内容を事前に知っておけば、収入が途絶えたときにも慌てずに対応できますよ。
1日あたりいくら支給されるの?
支給される手当金の金額は、基本的に日給の3分の2が目安です。
たとえば月給30万円の人であれば、1日あたりおよそ6,667円が支給される計算になります。
もちろんこれはあくまで目安で、実際には直近の報酬から平均額を出して算出される仕組みになっているんですね。
ちなみに、ボーナスは含まれず、通常の給与部分だけが基準になります。
少し細かい話にはなりますが、「標準報酬月額」という計算ベースがあって、それを30で割ってから3分の2を掛ける、という計算式になります。
これを知っておくだけでも、どれくらい支給されるかの予測が立てやすくなります。
支給までのタイムラグにも注意
ただし、傷病手当金は申請したらすぐに支給されるわけではありません。
私が申請したときは、申請から振り込みまでに3~4週間ほどかかりました。
申請書類の記入や提出も必要ですし、会社や医療機関に記入してもらう部分もあるため、準備にも少し時間がかかります。
その間、貯金がないと本当に不安になってしまいます。
なので、病気休暇を取る可能性がある人は、万が一に備えて少しでも生活費を確保しておくことをおすすめします。
また、申請書類の記入ミスなどがあると、さらに支給が遅れることもあるので、提出前にはしっかりとチェックしておくと安心ですよ。
こういったタイムラグがあることを想定して、事前に制度の仕組みを理解しておくと、いざというときにスムーズに対応できますし、精神的にもゆとりが持てます。
病気休暇で評価やキャリアに影響する?
ボーナスや昇進の評価に関わる?
病気休暇を取ったことで、ボーナスや昇進に響いてしまうのでは…と不安になることもありますよね。
特に評価基準が数値化されていたり、出勤日数がボーナス査定や昇進条件に組み込まれているような会社では、「今回の病気で自分のキャリアに影響が出るかも…」と心配になるのも無理はありません。
実際、勤務実績が少ないとマイナスに捉えられる会社もあり、「体調不良が自己管理の甘さとみなされたらどうしよう」と感じてしまう人もいます。
とくに自分自身が真面目で責任感が強いタイプだと、余計にその不安が大きくなるようです。
休暇取得が理由で肩身が狭くなる?
「長く休んで申し訳ないな…」という気持ちは、私自身も経験があります。
周りが忙しく働いているなか、自分だけが長く席を外していたという事実に、なぜか罪悪感のようなものがついてまわるんですよね。
復帰した初日は、オフィスの空気がちょっとよそよそしく感じてしまったほどです。
特に人手が足りない部署だったり、みんなが自分の穴をカバーしてくれていた場合は、なおさら気をつかう場面が増えます。
たとえ誰も責めていなくても、自分の中に「迷惑をかけたかも…」という意識があるだけで、自然と肩身が狭くなってしまうものです。
復帰後しばらくは、自分のペースを取り戻すのにも気を張り続けてしまい、疲れを感じやすくなることもあるので、無理せず周囲の声に耳を傾けてみることも大切だなと思いました。
企業文化によって受け取り方が変わる
病気休暇への理解度は、ほんとうに会社の雰囲気や文化によって大きく違います。
ある会社では「健康第一だから遠慮なく休んでね」と言ってくれる一方で、別の会社では「体調管理も仕事のうち」なんて雰囲気が暗黙のうちに漂っていたりもします。
制度そのものが整っていても、実際に使いづらいと感じてしまうのは、そういった空気感が大きく影響しているんですね。
「制度はあるけど使いにくい」と感じている社員が多い職場では、制度が機能していないも同然です。
だからこそ、自分の会社がどんなスタンスで病気休暇を捉えているのか、周囲の先輩や同僚の様子を見ておくことも大切ですし、できれば日頃からオープンに相談できる関係性を築いておくと、いざというときにずいぶん気がラクになりますよ。
事前に確認したい!就業規則と社内制度
自分の会社に病気休暇制度はある?
そもそも自分の勤務先に病気休暇の制度があるのか、まずはしっかり確認しておきましょう。
制度があると思っていたら、実はなかった…というケースも意外と少なくありません。
特に中小企業などでは、制度自体が整備されていなかったり、「うちは有給休暇を使って対応してね」というスタンスのところもあります。
私の友人も、体調を崩して数日休むことになったときに「病気休暇はないから有給で処理して」と言われて戸惑っていました。
制度の有無はもちろんですが、どんな条件で使えるのか、手続きの流れはどうなっているのかなど、細かい部分まで確認しておくと安心です。
実際に病気になってから焦って調べるのでは遅いので、元気なうちに備えておくのがおすすめですよ。
休暇中の待遇は就業規則で要チェック
病気休暇中の給料やボーナスの扱いは、就業規則にきちんと明記されているはずです。
たとえば「病気休暇中は無給」「ボーナス査定に影響あり」といった内容が記載されていることもあるので、見落とさないようにしましょう。
就業規則というと堅苦しい印象があるかもしれませんが、自分の権利や待遇に関わる大事な情報がたくさん詰まっています。
中には、「一定期間以上の出勤がなければ賞与支給対象外になる」といった条件がある場合もあるので、しっかり読んでおくと損をせずに済みます。
また、会社によっては休暇中の手続きや必要書類についても細かくルールが決まっていることがあります。
確認しておくことで、急な体調不良にも落ち着いて対応できますよ。
休職期間や復職支援の体制も確認を
病気休暇が長引いた場合、「休職」という扱いに切り替わることがあります。
そうなると就業規則や労務上の手続きも変わってくるので、そのタイミングや条件についても事前に知っておくと安心です。
たとえば、何日以上の欠勤で休職扱いになるのか、休職期間は最長でどのくらいまで認められるのか、そしてその間の給与や保険の取り扱いはどうなるのかなど、会社ごとにルールが違うことが多いんです。
また、復職の際にどんなサポートが受けられるのかも要チェックです。
面談があるのか、勤務時間の調整ができるのか、段階的な復帰が認められるのかなど、復帰後の負担を減らす工夫が整っている会社もあれば、まったくそういった制度がないところもあります。
もし不安な点がある場合は、早めに人事や上司に相談してみると良いでしょう。
きちんとしたサポートがあると、安心して治療と復帰に向き合うことができますよ。
病気休暇制度は上手に使えば安心材料にも
制度があるだけで安心感がある
いざというときに頼れる制度があると思うだけで、働く上での安心感が本当に違ってきますよね。
「何かあっても大丈夫」という気持ちがあると、日々の業務にも余裕が出てくるものです。
たとえば、少し体調が悪くなったときも「無理せず休める環境がある」と思えるだけで、ストレスが軽減されますし、体調を崩す前の段階でケアする意識も高まります。
しかも、同僚や家族のことを考えたときにも、制度が整っている職場にいるというだけで安心できますよね。
「自分が倒れたら周りに迷惑が…」と常に不安を抱えていると、かえって体調にも悪影響が出てしまいます。
働く人の心と体を守るために必要な制度
心身の健康を守るには、無理をせずにきちんと休むことがとても大切です。
頑張ることはもちろん素晴らしいことですが、それと同じくらい「ちゃんと休む」ことも立派な自己管理のひとつなんです。
病気休暇制度があることで、「休むことに罪悪感を持たなくていい」環境が生まれます。
私も以前、休むことに対してすごく後ろめたさを感じていたんですが、病気休暇を活用する中で「しっかり治すことも仕事のうち」と考えられるようになりました。
それによって、気持ちがすごく軽くなりましたし、結果的に元気に働き続けられています。
「損をしない」ために知っておくべきこと
制度の内容を知らなかったばかりに損をしてしまう…そんなもったいないことは避けたいですよね。
たとえば、病気休暇中にもらえる傷病手当金の存在を知らなかったせいで申請しなかったり、ボーナスの査定期間を把握しておらず減額されてしまったり。
これって、ほんの少し事前に調べておけば防げることなんですよ。
だからこそ、「今は大丈夫だから…」と先送りにせず、自分の会社のルールや制度については一度しっかり確認しておくことをおすすめします。
ちょっとした知識の差が、大きな安心感につながるんです。
まとめ

病気休暇制度には、安心して休めるメリットがある一方で、収入の減少や復職後のプレッシャーといったデメリットもつきものです。
私自身も体調を崩して仕事を休んだとき、制度に救われた部分がある反面、「こんなに大変なんだ…」と感じる場面もたくさんありました。
たとえば、給料が思っていたよりも減ってしまって生活費のやりくりに苦労したり、復帰後にたまった仕事を片付けるのに時間がかかったり。
周囲に申し訳ない気持ちが強くなって、仕事に戻ってからもなかなか気持ちが休まらなかったんです。
でも、同時に「制度がなかったらどうなっていたんだろう」と思うと、やっぱりありがたかったとも感じています。
だからこそ、「いざ」というときに慌てないためには、普段から自分の会社の制度をしっかり理解しておくことがとても大切です。
「病気休暇があるって聞いたことはあるけど、内容まではよく知らない」という人は多いと思いますが、就業規則を読んでみたり、総務や人事に確認したりして、制度の中身を把握しておくだけでもいざというときの安心感が違ってきますよ。
また、自分が使うときだけでなく、同僚や家族が体調を崩したときにも、制度について知っていればサポートしやすくなります。
特に、申請のタイミングや必要書類などは事前にわかっていれば、いざというときに慌てずに済みますよね。
病気やケガは誰にでも起こりうることですし、いつどんなタイミングでやってくるかは分かりません。
お互いに無理をしすぎず、自分の体と心のサインに気づいてあげること。
そして、必要なときには遠慮せずに制度を活用して、しっかりと回復することが、長く健康的に働き続けるためには欠かせないことだと思います。
もし少しでも不安を感じたら、今このタイミングで会社の制度を確認しておくといいですよ。
未来の自分のために、ちょっとした準備をしておくだけでも気持ちが軽くなります。